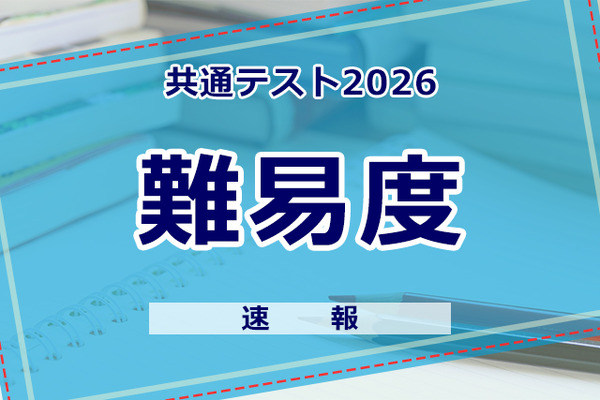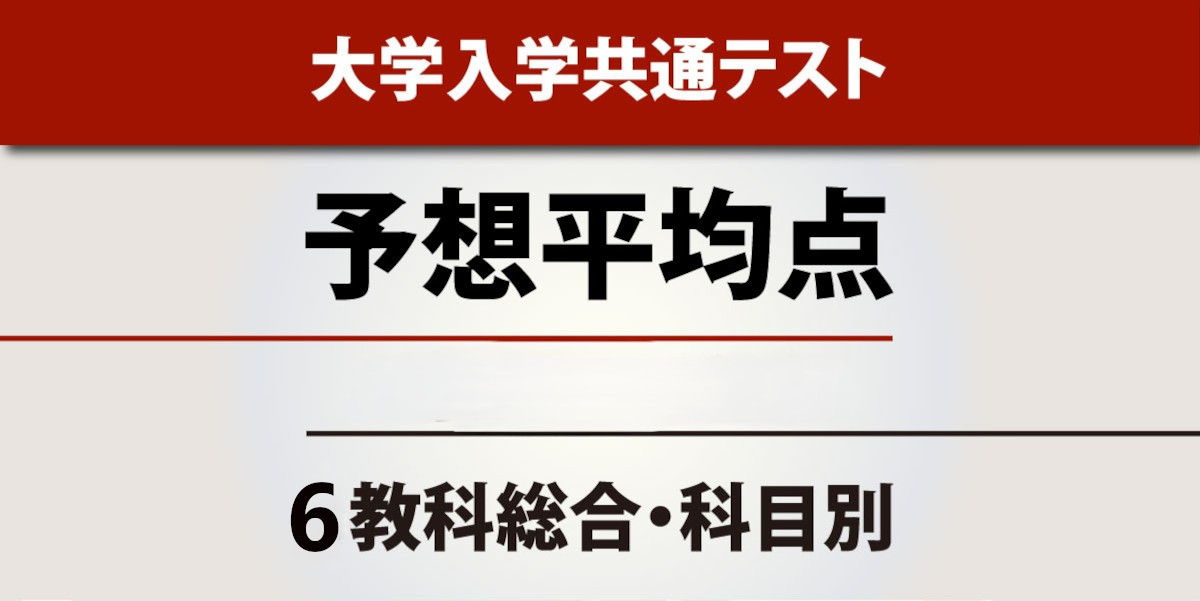金融政策、上下のリスクに「最も中立的な位置」に調整必要=内田日銀副総裁

[高知市 23日 ロイター] - 日銀の内田真一副総裁は23日、各国の通商政策やその影響を巡る不確実性が「極めて大きい」との認識を示した上で、こうした局面での金融政策は経済・物価の安定の観点から「上振れ・下振れ双方向のリスクに対して最も中立的な立ち位置に調整していく必要がある」と述べた。
高知県金融経済懇談会であいさつした。トランプ米大統領が日米関税交渉の合意を発表した直後のタイミングでの実施となった。
内田副総裁は、日銀が描く経済・物価のメインシナリオが実現していけば「経済・物価情勢の改善に応じて、引き続き政策金利を引き上げ、金融緩和の度合いを調整していくことになる」として、利上げの継続方針を示す一方で、その見通しが実現していくか予断を持たずに判断していくと述べた。
通商政策に関する各国の交渉の帰すうに加え、そのもとで内外の経済・物価や国際金融資本市場がどういう方向に向かうのか「現在までの各国の経済データからはっきりとは分からない」と話した。その上で「不確実性は極めて高く、内外経済は大きな岐路にあるように思える」とした。
各国間の関税交渉がある程度進展するという前提に立つのであれば、仮に輸出企業の収益が相応に下押しされたとしても、企業部門全体としては高水準の収益が維持されるとし、今後も人手不足感が強い状況が続くと見込まれるため、「近年の積極的な賃金・価格設定行動の流れは途切れないというのがメインシナリオ」だとした。
ただ、関税政策の負のインパクトが予想以上に大きくなったり、長引いたりした場合には、ここ数年の賃上げの流れが弱まることが懸念されるとした。「世界経済や国際金融資本市場の動きを巡る不確実性が極めて大きいことを踏まえると、わが国経済・物価に対するこうしたダウンサイドリスクを注視していく必要がある」と語った。
米国動向については「今後数カ月の消費者物価と労働市場の動向は、米国経済やFRB(米連邦準備理事会)の政策運営をみる上で重要であり、それは為替市場をはじめとした国際金融資本市場にも影響を与える」と述べた。
<消費者物価「私どもの予想より強め」>
内田副総裁は物価について、米国の高関税政策が経済下押しを通じて物価の押し下げリスクとなる一方で、食料品価格を中心にコストプッシュ面からの押し上げ圧力がかかっていると指摘。双方の動きが、企業の賃金・価格設定行動などを通じて先行きの物価見通しにどのような影響を及ぼすか、注目していくと述べた。
その一方で今年度入り後、値上げの動きがコメ以外の食料品にも広がっており「消費者物価は私どもや市場の予想よりも強めで推移している」と指摘。少なくとも食料品について、企業の価格設定行動が「従来の考え方から有意に変化している」と述べた。中長期的な予想物価上昇率は直接観察することが難しい指標だが、「ここ数年は大きな変革期にある」との認識の下、企業行動の変化などを丁寧に把握していきたいと話した。
日銀は6月に2026年度の国債買い入れ減額計画を決めた。内田副総裁は、減額のペースを落とす理由として「急激な金利の変動による景気・物価への悪影響」を挙げ、「当然のことながら財政に対する配慮ではない」と述べた。
私たちの行動規範:トムソン・ロイター「信頼の原則」, opens new tab