忙しい人に読んでもらえる文章術 ハーバードの行動科学者が説く6つの原則
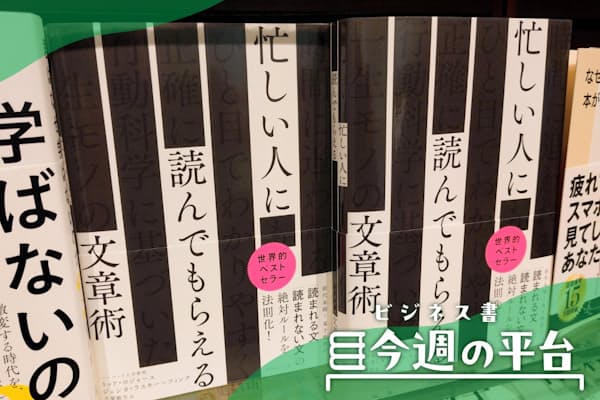
入り口近くのメインの平台に2列に並べて面陳列する(丸善日本橋店)
本はリスキリングの手がかりになる。NIKKEIリスキリングでは、ビジネス街の書店をめぐりながら、その時々のその街の売れ筋本をウオッチし、本探し・本選びの材料を提供していく。
今回は、2〜3カ月に一度訪れている準定点観測書店の丸善日本橋店だ。ビジネス書の売れゆきは、天気の悪い日が多かった割には好調だという。そんな中、書店員が注目するのは、行動科学の知見を生かし、忙しい人に読んでもらえる効果的な文章術を6つの原則にまとめた本だった。
原則はどんな場面で使い回せる
その本はトッド・ロジャース、ジェシカ・ラスキー=フィンク『忙しい人に読んでもらえる文章術』(千葉敏生訳、ダイヤモンド社)。ロジャース氏は米ハーバード大学教授を務める行動科学者。共著者のラスキー=フィンク氏もハーバード・ケネディ・スクールに拠点を置く研究機関のリサーチ・ディレクターで行動科学に基づく研究に従事する。
ロジャース氏は忙しい有権者の心に刺さる文章の書き方について、10年にわたり科学的に研究してきたという。忙しい家庭に向けた文章の書き方もラスキー=フィンク氏と共同で研究してきた。その過程で「効率的な文章を書くための原則はほぼどんな場面でも使い回しが効くのに、あまり理解が進んでいない」と、日々痛感するようになったと語る。
そこで書かれたのが本書だ。「本書を読めばきっと、日常生活で役立つ文章術と、その根底にある納得の科学が学べる」というのが「はじめに」にある売り文句だ。
全体は3つのパートに分かれる。パート1は「読み手を理解する」、パート2は「6つの原則」、パート3は「原則を実践する」だ。
「忙しい読み手のための文章」の書き方を理解するには、まず「忙しい読み手の脳のなかで何が起きているのか」を理解することが先決と説く。処理しきれないほどの膨大な情報に接すると、重要な情報のみ脳のフィルターを通過させる「選択的注意機能」が働いて、脳は情報を取捨選択してしまう。そして脳は意外なほど疲れやすい。
パート1は、このように行動科学の知見や実験を紹介しながら、「脳のなか」を解説していく。これをベースに書き方の原則を提示する本論へと入っていく。
「少ないほどよい」「読みやすくする」…
「少ないほどよい」「読みやすくする」「見やすくする」「書式を生かす」「読むべき理由を示す」「行動しやすくする」――これが6つの原則だ。それぞれの原則は2〜6のより細かいルールにかみ砕いて解説されている。
例えば「少ないほどよい」なら、①「言葉」を減らす②「内容」を減らす③「依頼の数」を減らす――の3つ、「読むべき理由を示す」なら①読み手にとっての「読む価値」を強調する②「どういう人に読んでほしいか」を強調する――の2つ、といった具合だ。
パート3は「6つの原則を実行に移すのに役立つツールや戦術」を紹介する。「言いたいことが『たくさん』あるときは?」「『多様な相手』に向けたメッセージを書くときの注意点は?」……このような質問に答える「FAQコーナー」だ。
「今は少し落ち着いてきたが、9月初めに入荷してしばらくは毎週ベスト10圏内の売れゆきだった」と、ビジネス書を担当する石田健さんは話す。翻訳書の文章術が売れるのは珍しい。行動科学との組み合わせが読者に刺さった様子だ。
メールやSNS(交流サイト)から、企業から消費者への告知、様々な手続きの説明など、文章で伝えるべきことは山ほどある。どうすれば読ませて読み手を動かすことができるかは、人工知能(AI)時代になっても人間の書き手の役割なのかもしれない。
『すごい習慣大百科』が2位
それではランキングを見ていこう。今回は10月9〜15日のビジネス・経済書のベスト5を紹介する。
1位は、富裕層が注目する希少ダイヤモンドの資産価値を宝石商が解説した本だ。2位は、本欄7月の記事〈「すごい習慣」で仕事や人生を変える 科学的根拠に基づく小さなメソッドの大百科〉で紹介したスキル本。息の長い売れ筋になってきた。3位は元手ゼロから純資産を4億円まで増やした投資術を明かすマネー本。6月に〈本を読む人はうまくいく 「移動」の次に見つけた人生を成功に導く法則〉で紹介した自己啓発本が4位に入った。5位は「管理職は罰ゲーム」時代の管理職育成術を説いた本だった。紹介した『忙しい人に読んでもらえる文章術』はランク外だった。
(水柿武志)



