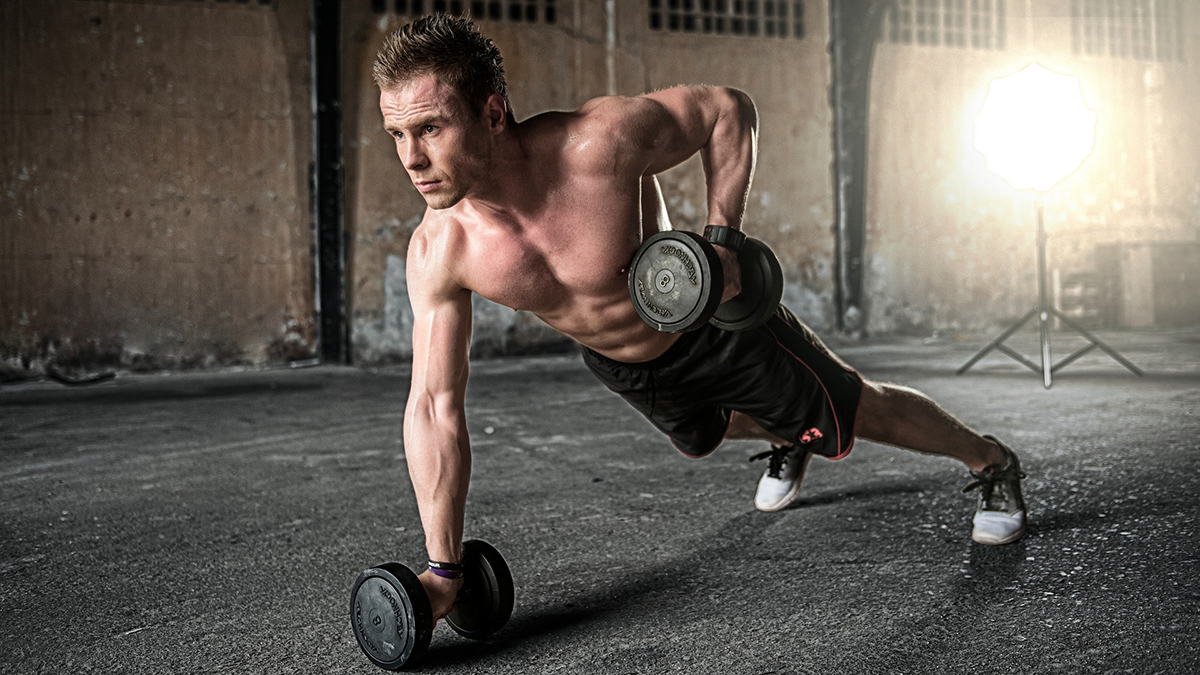心理師がバリ島シャーマンに話を聞いた|バリヒンドゥーの教えと仏教との共通点(ヨガジャーナルオンライン)

インドネシアのバリ島。他のインドネシアの島々はイスラム教を信行する一方で、バリ島だけがバリ・ヒンドゥー教を信行している。今回は、筆者がバリのヒンドゥー教寺院を訪れた際の体験を紹介したい。 〈画像〉心理師がバリ島シャーマンに話を聞いた|バリヒンドゥーの教えと仏教との共通点 ■バリ島に息づく祈り 朝のバリ島では、花の香りと線香の煙がゆるやかに空にのぼっていく。寺院、家の門の前、スーパーのレジ横とあらゆる場所にチャナンと呼ばれる小さな花籠が供えられ、祈りが日常に溶け込んでいる。チャナンは「美しくありますように」という意味で、一日の平和を祈るものだ。バリ島で信仰されるバリ・ヒンドゥー教は、インドのヒンドゥー教を基盤にしながらも、古くからのアニミズムや祖霊信仰が融合した独自の宗教。人間だけでなく、木々や石、風、川、すべての自然に神聖な力が宿ると考えられている。朝、昼、夕方と一日に三回の祈りを捧げ、祈りは生活のリズムそのものであり、人々の心を支えるための“習慣”として息づいている。 ■バリアンと呼ばれるシャーマン 島のあちこちには「バリアン」と呼ばれるシャーマンがいる。薬草を扱う人、祈りや占いを通して相談に乗る人、儀式を司る人。村の人々にとって、バリアンは医師でもあり、カウンセラーでもあり、占い師でもある。悩みや病を「心身のバランスの乱れ」としてとらえ、薬草、祈り、マッサージ、霊的対話などを組み合わせて整えていく。バリ島の文化では、“こころの治癒”が信仰と深く結びついていることを感じた。 ■聖地での浄化の儀式 シャーマンとのセッションのために訪れたのは、ウブド近郊の「Beji Griya Park Waterfall Temple」。聖なる滝と洞窟があるこの寺院で、まずはお清めの儀式を受けた。寺院のさまざまな祠にチャナンを供え、聖水で頭や顔を洗い、ココナッツ水を頭から注がれ、滝の前で声を出して叫ぶ。普段の生活では味わえない、力強い体験。この浄化の時間は、人々の心を整え、次に訪れるセッションへの扉を開く鍵なのかもしれない。 ■バリアンとの対話 浄化が終わると、ひとりずつ名前を呼ばれる。「バレ」と呼ばれる東屋のような建物に案内されると、白い衣をまとったシャーマンが静かに座っていた。いくつかセッションのメニューがあり、オープンオーラを選んでみた。シャーマンは、私の目をじっと見つめ、「まずはネガティブなものを出し、あなたの中をきれいにしてからでないと、良いものは入ってこない。」と言った。 セッションのあと、私は尋ねた。「毎日、何かすべきことはありますか?」彼は少し笑って答えた。「朝起きたら感謝すること。どんな自分でも許すこと。そして自分自身をハグして“愛している”と言うこと。」それは特別な修行ではなく、コンパッションにあふれた日常の祈りだった。 ■セルフコンパッションとの共鳴 シャーマンの語る「許し」と「愛」は、まさにセルフコンパッション。自分への思いやりの実践そのものだった。苦しみや不完全さを否定せず、そのまま受け入れる優しさ。それは「セルフケア」の核心であり、同時に仏教の慈悲の教えとも深く重なる。バリ・ヒンドゥー教と仏教との共通点が興味深い。ウブド近郊の古代遺跡「ゴアガジャ寺院」には、同じ敷地内にヒンドゥー寺院と仏教寺院が存在する。両者の信仰が自然に共存していること自体が、この島の精神性を象徴しているように思う。 セルフケアとは、結局のところ「つながりを取り戻す」営みなのだろう。自分と他者、自分と自然、そして自分自身との。そのつながりを少しずつ結び直しながら、人はまた生きる力を取り戻していく。寺院からの帰り道、夕暮れの光が、棚田に張られた水面を黄金色に染めていた。風が渡るたびに、水鏡のような田んぼがゆらぎ、空の色をやさしく映している。シャーマンの言葉を思い出した。 「どんな自分でも、許して、愛してあげて。」 ライター/石上友梨(臨床心理士、公認心理師)
石上友梨