釘を刺しても燃えないリチウムイオン電池を開発
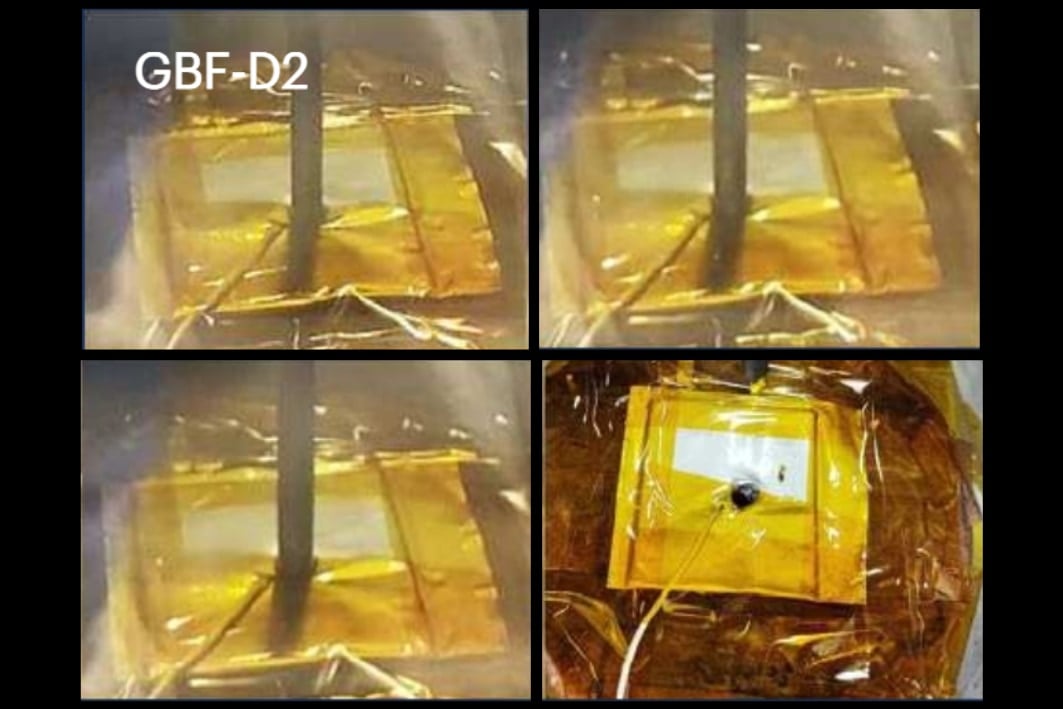
「スマホのバッテリーに穴が空いたら…?」
そんな想像をするだけでもゾッとしてしまいます。
ですが、実際にはリチウムイオン電池が原因の火災事故が近年急増しています。
東京消防庁の発表によれば、令和5年に起きたリチウムイオン電池関連の火災は167件(東京消防庁公表資料、2024年7月12日)と過去最多を記録しました。
スマートフォンやパソコン、電気自動車など、身近で当たり前に使われているはずの電池が、実は私たちの生活を脅かす存在になっているわけです。
しかし、ここで疑問が生まれます。
これほど多くの研究者や企業が「安全な電池」を目指して取り組んできたにもかかわらず、なぜまだリチウムイオン電池は燃えてしまうのでしょうか?
実は、これまでにもリチウムイオン電池を安全にするための数多くの工夫が試みられてきました。
たとえば電池の中に燃えにくい添加剤を混ぜたり、燃えにくい性質をもった溶媒を使った「難燃電解液」を採用したりする方法です。
ところが、残念ながらそうした「燃えにくいはず」の電解液でも完全な安全化にはつながりませんでした。
実際、難燃性をうたった特殊な電解液でも、内部でショート(短絡)が起きた場合には短時間で激しく高温に達することが報告されています。
結局のところ、熱暴走と呼ばれる危険な現象を完全には抑えきれないのです。
こうなると、リチウムイオン電池の中で何が起きているのかをもう少し詳しく見ていく必要があります。
そもそも、リチウムイオン電池の中では何が起きているのでしょうか。
電池の中には「電解液(でんかいえき)」と呼ばれる液体が入っています。
この液体の中をリチウムイオンが移動することで電気が生み出される仕組みです。
しかし、この電解液には問題がありました。
従来型の電解液には可燃性の有機溶媒(燃えやすい性質をもつ液体)が使われているのです。
こうした可燃性の液体が熱で蒸発し、気体となって発火や爆発を引き起こします。
また、電池を繰り返し充電すると、負極側にはデンドライト(金属の細い結晶)などが成長し、短絡の一因となることがあります。
これが電池内部の仕切り膜を突き破って正極まで到達すると、内部でショート(短絡)が起きます。
そのショートによって発生する急激な発熱が、電解液に引火し、大きな事故につながるのです。
ここで先ほど述べた「難燃電解液」が登場しますが、じつは難燃化してもこうした内部短絡そのものは防げず、電解液の燃焼性を多少抑える程度にしかなりませんでした。
つまり、根本的な安全化には不十分だったのです。
そんな中、近年になって注目されたのが、「イオン会合(イオンかいごう)」という現象です。
そしてもしかしたら、こちらの現象を解決した方が、発火防止に役に立つのではと考えられ始めています。
イオン会合とは、プラスの電気を帯びたリチウムイオンとマイナスの電気を帯びた陰イオン(アニオン)が、電解液の中でお互いに強く引きつけ合い、しっかりと「ペア(対)」になっている状態のことです。
これをイメージとして「分子同士の握手」と表現することもできます。
イオン同士ががっちりと手を組むことで、電池内部の電極表面には「SEI(固体電解質中間相)」と呼ばれる安定した膜が形成されやすくなります。
この膜がきちんとできることで、電池は長い間使い続けても性能が落ちにくくなり、長寿命化を実現しやすくなるのです。
ところが、今回の研究チームはここに新たな疑問を投げかけました。
「イオンがあまりにも強く握手しすぎると、逆に発熱しやすくなって危険ではないか?」ということです。
つまり、イオン会合によって分解反応を起こすためのエネルギーの壁が低くなり、比較的低い温度でも急激な熱反応(熱暴走)が起きやすくなってしまう可能性が指摘されたのです。
電池の性能を高めるために役立つはずの「イオン同士の握手」が、安全面では逆効果になってしまう——。
これが従来の電池開発では解決できなかった「安全性」と「寿命」という二律背反(トレードオフ)の壁だったのです。
では、どうすればこの矛盾を解決できるでしょうか?
研究チームはここで一歩踏み込んで考えました。
イオン同士の握手を状況に応じて「切り替える」ことができれば、この矛盾を解消できるのではないか、という発想です。
つまり、通常時(低温)ではイオン同士がしっかり握手して長寿命化に貢献し、異常時(高温)にはその握手をサッとほどいてしまえば、安全性も確保できるのではないかと考えたのです。
「そんな都合のいい話が本当に可能だろうか?」——これが今回の研究の核心的な問いかけとなったのです。



