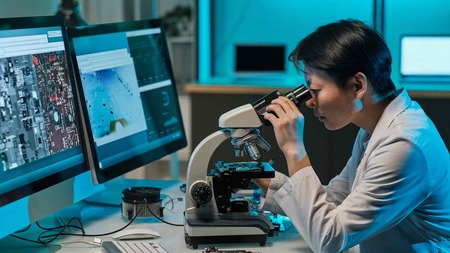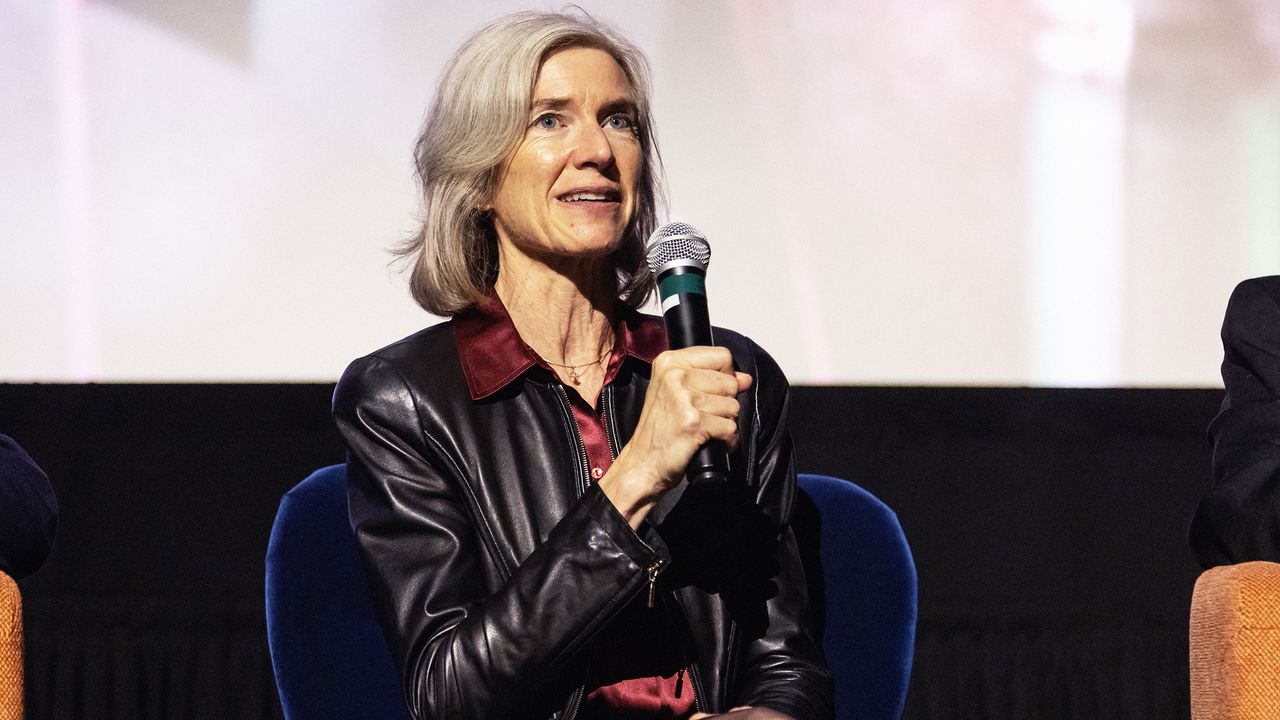「スマホを取りに行こうとしたのに、スマホを忘れた」よくある"うっかりミス"が起きる認知心理学的理由 人間は「システム1」と「システム2」の思考回路を持っている

スウェラーはこうした脳のワーキングメモリーの特性を踏まえて、学習の効率を最大化するために、学習者の認知負荷を最小化することが重要だと提唱しました。情報を処理する認知リソースもワーキングメモリーも限られているので私たちの脳は複雑なことを覚えたり、同時にいろいろ考えたりするのには向いていないのです。
みなさんが、大量の情報に接したときに、「こんなの覚えられない」「理解できない」と感じてしまうのはみなさんが悪いのではなく、人間の脳がそうできているのです。どのような職業に就いても、新しい情報を学んで、それを適用したり、使ったりしなければいけませんが、人間の認知のリソースは限られています。
とはいえ、新しく提示された情報すべてを学んだり、すべてを適用したりすることは簡単ではありませんし、現実的でもありません。大事なところだけを覚えたり、体系化して覚えたり、できる限り認知負荷を減らすことが重要になります。認知負荷を減らすために人は、無意識に工夫して覚えようとすることもあります。企業の研修や教育プログラムはこの認知負荷理論を活用しているケースが非常に多いです。
写真=iStock.com/kazuma seki
※写真はイメージです
人間が瞬時に記憶・認識できるのは7つまで
人の認知リソースの限界を示した研究がジョージ・A・ミラーのマジカルナンバー7±2の法則です。彼が1956年に発表した論文(“The Magical Number Seven, Plusor Minus Two”)は記憶の研究ではとても有名です。人間が短期記憶(ワーキングメモリー)に一度に保持できる情報の単位(チャンク)の数が7±2であると主張しています。
彼は人間が瞬時に記憶、認識できるのは7つ(個人差を含めると7プラスマイナス2)が限度だと突き止めました。ですから、私たちは7(厳密には5~9)の容量を超えてしまうと、脳の構造上、覚えたり、認識したりするのが一気に難しくなる傾向があります。人間の認知リソースの限界を示す内容であり、認知の経済性が情報を整理し効率的に処理する際にどのように影響を与えるかを示しています。
この法則のわかりやすい例が電話番号です。人がパッと言われて、一時的に覚えられる量は電話番号の長さくらいが限界だからです。たとえば、みなさんが外出中に電話番号も登録できず、メモすることもできない状態で、誰かに電話をかけなくてはいけないとします。そうした状態で、電話番号は人に教えてもらって、復唱して覚えていられるギリギリの長さなのです。
Page 2
彼は人間の意思決定において「限定合理性」という概念を提唱しました。これは、人間が意思決定を行う際に、すべての情報を完全には処理できず、限られた認知リソースの中で最適な選択をしようとするという考え方です。人間の認知能力が限られているため、完全に合理的な決定を下すことはできず、代わりに「満足できる」「後悔しない」決定を目指すと主張しました。
この研究は、経済学、心理学、人工知能の分野に広く影響を与え、認知の経済性に関する理解を深める基盤となっています。
ダニエル・カーネマンとエイモス・トヴェルスキーの「プロスペクト理論」も認知の経済性を語る上で欠かせません。彼らは特にシステム1の役割を強調して、人々がどのようにして認知リソースを節約しながら、リスクに対して非対称的な反応を示すかを説明しています。
非対称というのは利益と損失の感じ方が異なるという意味です。つまり、人々は、得られる利益よりも損失を過剰に避けようとする傾向があり、これが認知の経済性とも関連しています。この理論は行動経済学の基盤となり、認知バイアスや意思決定プロセスにおける認知の経済性の理解に大きく寄与しています。
脳には「ワーキングメモリー」にあたる領域がある
なぜシステム1で人が判断してしまうかに関してはジョン・スウェラー(1988年)の「認知負荷理論」も有名です。
私たちの脳には、パソコンでいうところのワーキングメモリー(情報を一時的に保ちながら操作するための領域)があります。たとえば、「寝室にスマートフォンを忘れたから取ってこよう」という行為は、このワーキングメモリーに入れられて、一時記憶として保存されます。しかし、寝室に行ったときに、ちょうどインターフォンが鳴って荷物が届いたのであわてて玄関に行くと、「スマホを取ってこよう」という最初の記憶が「インターフォンが鳴ったので対応する」という記憶に上書きされる形で消されてしまいます。
そして、しばらくしてから「あれ、何をしようとしていたのだっけ……スマホを忘れた!」となります。これはワーキングメモリーの容量が限られているために、あれもこれもと同時にやろうとすると起こる現象です。
写真=iStock.com/Farknot_Architect
※写真はイメージです
Page 3
「携帯番号は11桁だし、少し、長くない?」と思われた人もいるかもしれません。確かに、携帯電話の番号は、090-○○○○-△×△×のように11桁あります。7+2を超えています。
栗山直子『世界は認知バイアスが動かしている』(SBクリエイティブ)
ただ、これはミラーが提唱した情報の単位(チャンク)と関係しています。090、080、070は、基本的に携帯番号の最初にくる3桁です。誰にも共通する数字で変化はありません。おそらく、日本に住んでいれば、「そういうものだ」と誰もが苦も無く認識できるはずです。チャンクの数え方は情報のまとまりの単位なので、この090を1チャンクと考えます。その後の8桁の数字は1個ずつがバラバラのランダムな数字なので、1個の数字を1チャンクと数えます。そう考えると携帯電話の番号は9チャンクになります。
このように、無秩序に並んでいる場合瞬間的に記憶できる数字は平均7つまでとされ、脳の情報処理能力の限界を示すといわれています。実際、記憶術では何の意味も持たない数字の羅列でも、7桁ずつ区切れば覚えやすくなるともいわれています。
マジカルナンバー7±2の法則は情報処理の理論や教育心理学においても広く引用されており、認知の経済性に関する基礎的な理論になっています。こうした「認知の経済性」により、私たちは必要があっても熟慮ができない場面があり、主にシステム1の思考によって誤った判断に導かれてしまう可能性もあるのです。
- 東京科学大学リベラルアーツ研究教育院/環境・社会理工学院 講師専門は認知心理学、教育心理学、教育工学。青山学院大学文学部教育学科卒業、東京工業大学 大学院社会理工学研究科 人間行動システム専攻修士課程、同大学大学院同研究科 博士課程修了。博士(学術)。日本学術振興会特別研究員PDを経て、東京工業大学 大学院社会理工学研究科人間行動システム専攻助手。その後、同大学同研究科助教、改組により同大学リベラルアーツ研究教育院/環境・社会理工学院 助教、講師を経て、現職。2016年文部大臣表彰科学技術賞(理解増進部門)受賞。認知バイアスも含む人間の柔軟な思考、主に推論・問題解決に関心があり人の思考に関係する研究に従事。現在は論理的思考を育成するための研究を進めている。日本心理学会、認知科学会等会員。日本認知科学会をはじめ、海外のCognitive Science関連の学会で発表を多数行っている。