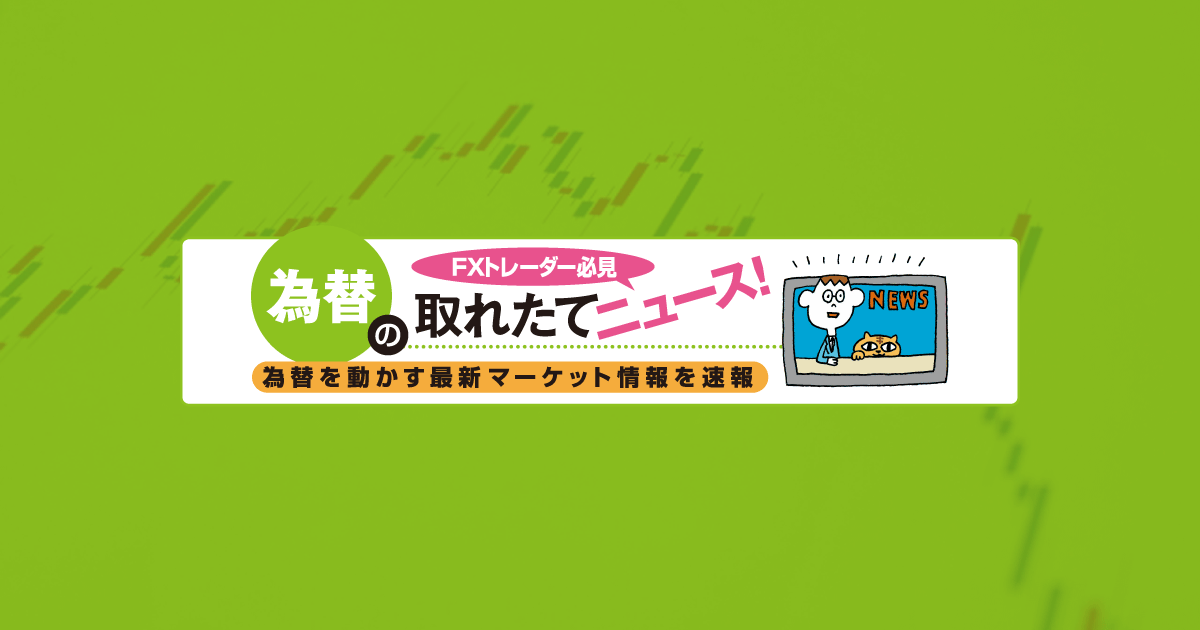「配当ファクター」が日本株市場で存在感、関税懸念の逃避マネー吸収

日本株市場で配当に注目した投資戦略のパフォーマンスが高まっている。トランプ米政権下でマクロ経済の先行き不透明感が強まる中、安定したリターンを求める投資家が高配当銘柄に資金を振り向けているためだ。
ブルームバーグのデータによると、高配当銘柄を買って低配当銘柄を売る投資戦略は、過去1年で11%超のリターンを達成している。これは株式の特性に焦点を当てた12のファクター投資で最高のパフォーマンスだ。バリュー(割安)や過去のトレンドに基づくモメンタム、ボラティリティーの低さなどに着目した戦略を大きく上回る。
持続性への懸念から自社株買いの株価押し上げ効果が弱まる中、配当を安定的に実施し株主還元強化に長期的に取り組む企業への相対的な評価が高まっている。配当金の再投資による株高の好循環も期待できるとあって、トランプ米大統領の関税発言を巡って市場の動揺が続く最近はとりわけ、確実性の高い好材料として投資家に安心感をもたらした。
ブルームバーグのデータでは、アセットマネジメントOneが運用する上場投資信託(ETF)の「One ETF 高配当日本株」もトランプ氏の大統領選勝利以降のトータルリターンが1%と、東証株価指数(TOPIX)の同0.8%を上回っている。
アイザワ証券投資顧問部の三井郁男ファンドマネジャーは、資本効率を意識する流れにあって、配当性向や株主資本配当率(DOE)を導入して株主還元が一過性ではないことを示せる企業が評価される傾向があると話す。外部環境が不安定な中、決算や増配の発表後は悪材料が出る可能性が低いことも買いやすい理由だと言う。
東京ガスは1月31日、累進配当の継続を前提に増配の検討を進めると発表し、同日の株価が7%上昇した。SUBARU(スバル)も7日、総還元性向の引き上げや新たなDOE方針を示したことで株価が急騰した。
アイザワ証券の三井氏は、配当ファクターの有効性には季節的な要因もあるとみている。日本企業の多くが決算期末を迎える3月の配当権利落ち日を前に、例年12月から2月にかけてファクター効果が強くなる傾向があると指摘。そのため、3月に近づくと一転して高配当銘柄には利益確定売りが増え、この傾向は弱まるとの見方を示した。
とはいえ、資本効率改善は今や国内企業が中長期にわたって取り組んでいくトレンドでもある。T&Dアセットマネジメントの浪岡宏チーフ・ストラテジストは、関税政策などの不透明感が続く中、配当は投資家が「安心してリスクを取る一つの戦略」になると分析。「機関投資家だけでなく、個人投資家も着目するだろう」と述べた。