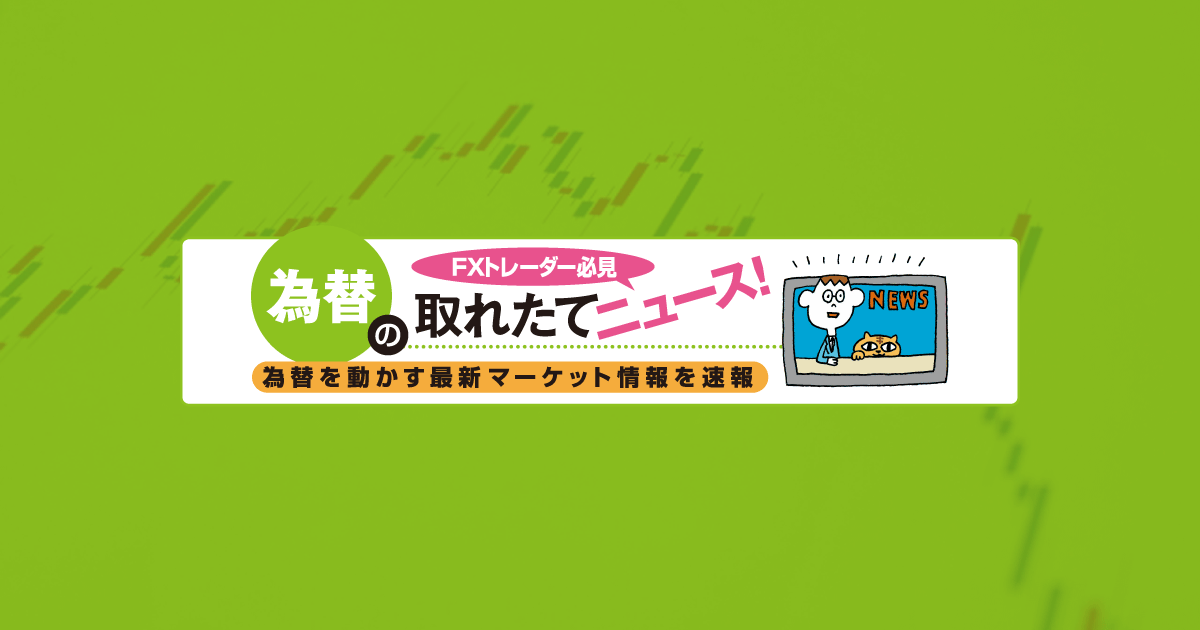常陽銀常務「国債への本格投資はまだ先」、政策金利1.5%程度にも備え

めぶきフィナンシャルグループ(FG)傘下の常陽銀行はさらなる金利上昇を見据え、国債投資は当面、様子見姿勢を続ける。外国債券への投資については、米利下げに減速感が出ていることから、変動金利の割合を維持する方針だ。
市場部門を担当する鳥羽吉嗣常務執行役員がブルームバーグとのインタビューで語った。国債投資で慎重姿勢を続ける理由として、日本銀行が今後も利上げを続ける可能性を挙げた。7月の利上げで当面打ち止めをメインシナリオに置きつつも、サブシナリオとして3年程度かけて政策金利を1.5%程度まで引き上げることを想定して運用しているという。
地方銀行は長期金利の指標である10年物国債の主な買い手。長年の低金利を背景に運用に占める国債投資の比率を減らしてきたが、新発10年債利回りが21日に一時1.455%と約15年ぶりの高水準になる中、本格的な投資再開の動向には市場関係者の関心も高い。三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)などは昨年、国債への本格的な投資を開始する目線として利回りが1.2%以上としていた。
鳥羽氏は「金利の絶対水準がもう一段上がってきたら国債を買おうかと思っている」としながらも、本格的な国債投資という意味では、4月から始まるめぶきFGの3カ年の次期中期経営計画の「後ろの方だ」との見通しを示した。
めぶきFGは資産規模で国内4位の地銀グループ。常陽銀単体の昨年12月末時点での有価証券運用残高は約2兆7000億円。そのうち、国内債券が約1兆5800億円、外債が約5000億円となっている。
鳥羽氏によると同行は金利上昇に備え、円債のデュレーションを近年落としてきた。足元では年限が5年から7年の政府保証債や住宅金融支援機構のRMBS(住宅ローン債権担保証券)などを段階的に買っている。また、固定金利と変動金利を交換するアセットスワップを使い円債の2割程度を変動金利化しているという。
FRBが利下げしない可能性も
米連邦準備制度理事会(FRB)の政策見通しとしては、年内2回の利下げを予想の中心としつつも、利下げしない場合も念頭に置いている。2022年に始まった米国の利上げを契機に外貨調達コストが急激に上昇したことを受け、常陽銀は外債投資における変動金利の比率を高めてきた。足元では6割程度に上る。
外債の変動金利資産には約1800億円の残高があるローン担保証券(CLO)も含む。スプレッドの状況にもよるが、基本的にはCLOへの新規投資を続ける方針だ。
また、政策保有株の売却でリスクアセットが削減されるため、純投資としての国内株式やプライベートエクイティー(PE、未公開株)の比率を徐々に増やしていく方針も明らかにした。金利や株との相関が低い資産として、米国の大企業の売掛債権を裏付けとした証券化商品に投資するファンドにも資金を振り向ける。
つくば市に市場部門の拠点
茨城県を本拠地とする常陽銀の本店は水戸市にあるが、鳥羽氏率いる市場部門が拠点を構えるのは同県つくば市。地銀の市場部門が本店や東京以外にあるのは珍しい。きっかけは東京・八重洲の再開発に伴い、市場部門が入居していたビルが解体されたことだ。新型コロナウイルス禍でのリモート勤務の経験も後押しとなり、21年につくば市の自社ビルに市場部門に所属する約50人が移った。
つくば市に拠点を移した利点の一つは、都内に比べて広いオフィススペースを確保できたことだ。運用を手掛ける「フロント」と決済関係などを担う「バック」の業務を行う部署が同じフロアに移ることができ、意思疎通が容易になったという。
ただ、東京に比べて不利な面もある。キャリア採用に力を入れる中、市場部門での中途採用の実績はまだない。東京を中心に転職先を探している人材にとって同行は対象から外れてしまうといい、通勤に便利なつくばエクスプレスやJR常磐線の沿線などに住む人材をターゲットとした採用活動を展開している。