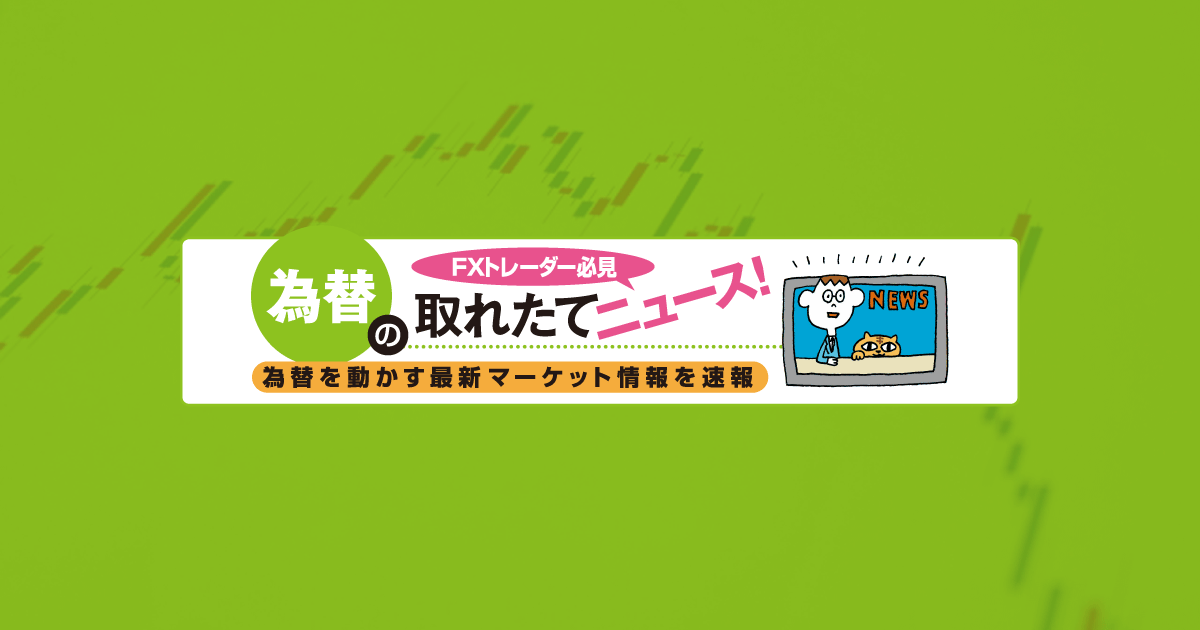【日本市況】債券上昇、米金利低下と5年債入札を無難通過-円は堅調

14日の日本市場では債券の先物や超長期債が上昇。米国長期金利の大幅低下や5年利付国債入札を無難にこなしたことで買いが優勢となった。円は一時152円台半ばに上昇、株式は下落した。
13日の米10年国債利回りは前日比9ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低い4.53%程度になった。労働省が発表した1月の生産者物価指数(PPI)は、金融当局が重視する個人消費支出(PCE)価格指数に反映される項目が落ち着きを示し、インフレが緩和されるとの見方から債券が買われた。トランプ米大統領が貿易相手国に同水準の関税を課す相互関税の即時発動を見送ったことも買いにつながった。
14日の5年利付国債入札は無難に終えた。SMBC日興証券の奥村任シニア金利ストラテジストは、「日本銀行の利上げの織り込みが進み金利上昇に一服感が出ており、債券を買い戻す動きが広がった。表面利率が1%に到達したことも買い戻しを促した」と述べた。
国内債券・株式・為替相場の動き-午後3時30分時点- 長期国債先物3月物の終値は前日比2銭高の139円70銭
- 新発10年債利回りは横ばいの1.35%
- 東証株価指数(TOPIX)の終値は前日比0.2%安の2759.21
- 日経平均株価は0.8%安の3万9149円43銭
- 円相場は対ドルでニューヨーク終値比0.1%高の152円64銭
債券
債券は先物や超長期債が上昇。財務省が実施した5年利付国債入札は無難な結果となった。一方、日銀のターミナルレート(政策金利の最終到達点)を織り込む流れが継続し、2年や5年など中期債は上値が重かった。
野村証券の宍戸知暁シニア金利ストラテジストは、5年債入札は午前に先回り買いが入った割に無難だったとし、総じて好調と指摘。ただ、「もともと好調でも相場の上値は重いとみられていた上、ターミナルレート期待が下がることもない」ため、買い進みにくいとの見方を示した。
入札結果によると、最低落札価格は100円5銭と市場予想と一致、小さいと好調を示すテール(落札価格の最低と平均の差)は3銭と、前回の1銭からやや拡大した。投資家需要の強弱を反映する応札倍率は3.52倍と、前回の3.82倍から低下した。
新発国債利回り(午後3時時点)
2年債 5年債 10年債 20年債 30年債 40年債 0.795% 1.005% 1.350% 2.010% 2.315% 2.640% 前日比 +0.5bp +0.5bp 変わらず -0.5bp -0.5bp -1.5bp株式
東京株式相場は下落。為替市場で再び円高が進み、企業業績に対する楽観的な見方がやや後退した。非鉄金属など素材関連や商社、医薬品、機械が安い。
為替相場が円高に動いたため、海外株高が日本にはあまり波及しなかったと、しんきんアセットマネジメント投信の藤原直樹シニアファンドマネジャーは述べた。日経平均はこの1週間ほどでかなり戻したため、利益確定の売りが出ていると指摘した。
為替
東京外国為替市場の円相場は一時1ドル=152円台半ばに上昇。米国の長期金利低下や米関税に対する懸念が和らいだことを背景に円買いの流れが続いた。
SBIリクイディティ・マーケットの上田真理人金融市場調査部長は、今週は米消費者物価指数(CPI)の上振れに対する相場の反応が過剰となり、「円が売られ過ぎた部分の巻き戻しが続いているのではないか」との見方を示した。
三井住友信託銀行米州部マーケットビジネスユニットの山本威調査役(ニューヨーク在勤)は、米相互関税の発動が4月以降の見通しとなったことについて、「カナダやメキシコと同様、本当に発動するかどうかは交渉次第との印象を受け、懸念がやや和らいだ」と話した。
この記事は一部にブルームバーグ・オートメーションを利用しています。