AIは人を「愚か」にするのか? 研究でわかった依存の「代償」
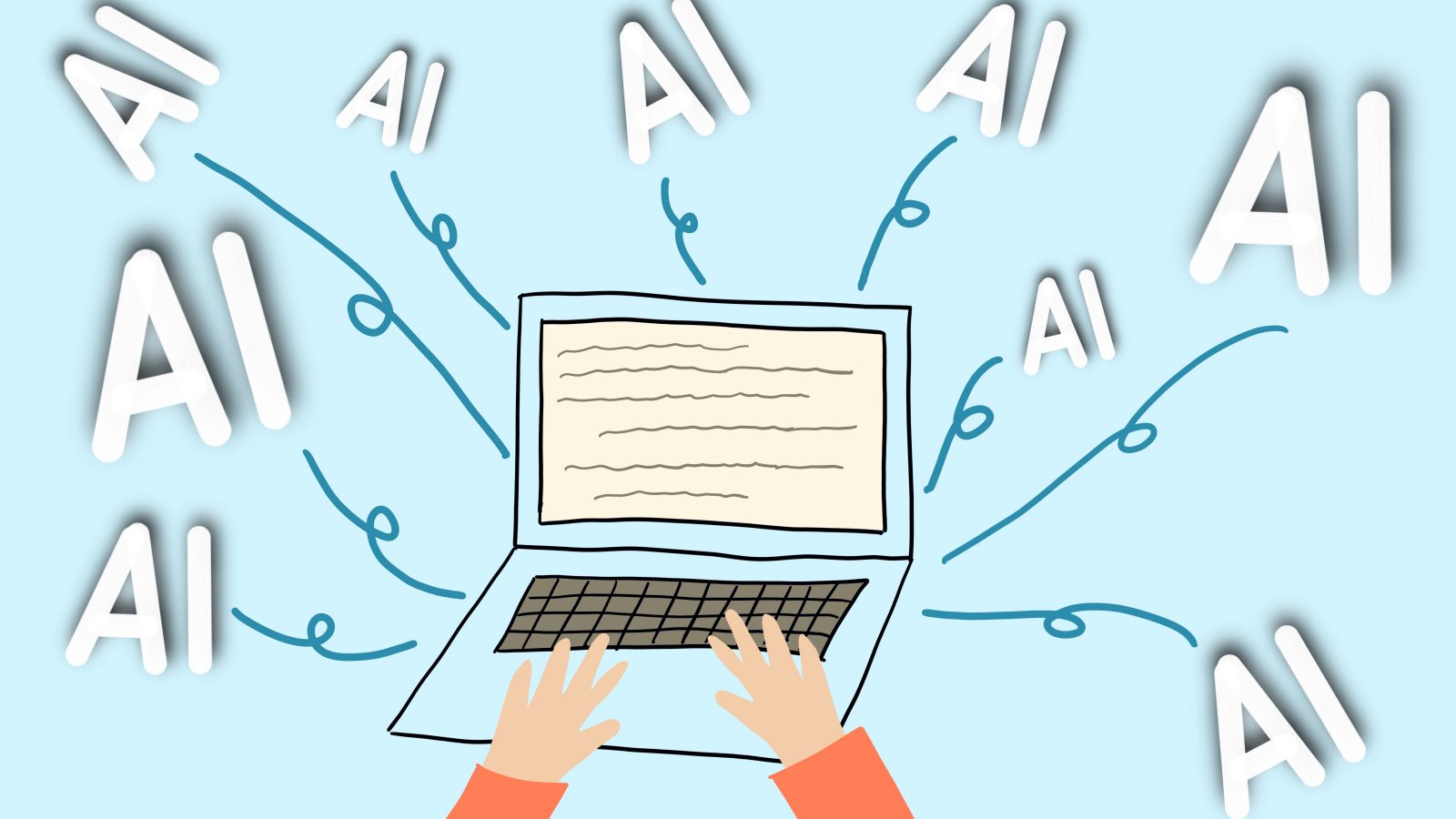
SCIENCE
6min2025.8.27
脳の“怠け癖”を助長するかも…
AIに「頼りすぎる」のは良くないことなのか Photo: Ekaterina Goncharova / Getty Images
Text by The Economist
生成AIの能力は日進月歩で、学業や仕事の現場でも、それに頼っている人がたくさんいる。だが、思考をAIに任せきりにしたら、人間の能力が低下するのではないだろうか──。
欧米の大学入学のための統一テストを受けたことがある人なら誰でも知っているように、壮大なテーマのエッセイを20分以内に書き上げるには、かなりの思考力を要する。そんな課題に取り組むとき、人工知能(AI)を自由に使えれば、精神的負担は確実に軽減される。
しかし、米マサチューセッツ工科大学(MIT)による最近の研究が示唆するように、この手助けには「代償」が伴うかもしれない。
研究では、ChatGPTを使ってエッセイを書いた学生と、自力で書いた学生の両方の頭に脳波計を装着し、作業中の脳の活動を測定した。こうした問いはいまに始まったことではなく、パソコンや計算機やタイプライターの登場時にも投げかけられた、おなじみのものだ。ただ、生成AIは「思考」全般を担うという意味でこれまでと性質が異なる。最新研究は何を語っているのか、英誌「エコノミスト」がまとめている。
その結果、AIを使った学生たちは一様に、「創造的機能」や「注意力」に関連する脳の領域の神経活動が著しく低かった。さらに、自分が書いたばかりの文章から一部を正確に再現することも、より困難に感じていた。
この結果は、AIを創造的な作業や学習に使うことの潜在的な悪影響を調べた近年の研究の一部だ。こうした研究は増えており、それらは重要な問いを投げかける。
生成AIによって得られる目覚ましい短期的なメリットは、隠れた長期的なデメリットを生むのではないか? MITの研究は、AIの使用と批判的思考(クリティカル・シンキング)の関係に関する、他の2つの注目すべき研究結果を補強するものだ。
1つ目の研究は、マイクロソフトリサーチの研究者たちによるものだ。研究に参加したのは、少なくとも週に1回は生成AIを使うナレッジワーカー(知識労働者)319人。参加者たちはAIの手を借りて、「長文の書類の要約」から「販売キャンペーンの企画」まで900件以上のタスクに取り組んでいると回答した。
参加者たち自身の評価によると、批判的思考を要するタスクはこのうち555件にすぎない。たとえば、AIが生成した内容をクライアントに渡す前に注意深く確認する作業や、AIが出した最初の回答が不適切だった場合に、プロンプト(AIに出す指示)を修正する作業がそれに当たる。
それ以外のタスクは特に思考力を要するものではないと、参加者たちは判断した。
調査では、参加者の過半数が、ChatGPT 、グーグルのGemini、マイクロソフトのCopilotなどの生成AIツールを使うと、使わないときに比べてタスクの遂行に要する認知的努力は「少ない」または「大幅に少ない」と回答した。
もう1つの研究は、SBSスイス・ビジネススクールのマイケル・ゲルリッヒ教授によるものだ。
彼は英国で研究に参加した666人に、AIをどのくらい使い、どの程度信頼しているかを尋ねたうえで、広く使用されている批判的思考力の評価基準に基づいた一連の質問をおこなった。
その結果、AIを頻繁に使う参加者の批判的思考力のスコアは一様に低かった。
この研究の発表後、ゲルリッヒは高校や大学の教員など、数百人から連絡を受けたという。彼らは生徒たちの間で広がるAIの使用をめぐる問題に直面しており、この研究結果は「まさに自分たちの経験を裏付けていると、彼らには感じられたのです」とゲルリッヒは述べる。 AIが長期的に人々の脳を鈍らせ、弱らせるかどうかは、まだ明確にはわかっていない。
上記3つの研究を実施した全員が、AIの頻繁な使用と、思考力の弱体化の因果関係を決定づけるには、さらなる研究が必要だと強調する。
たとえばゲルリッヒの研究では、批判的思考力が高い人は、たんにAIに頼ることが少ない可能性がある。またMITの研究は参加者が54人と少なく、検証したのは、エッセイを書くという1つの限定的なタスクだけだった。
さらに、生成AIツールは、他の多くのテクノロジー同様、人々の精神的負担を軽減することを明らかな目的としている。
すでに紀元前5世紀には、ソクラテスが、「書くことは記憶するための薬ではなく、思い出すための薬だ」とぼやいたと引用されている。計算機は、レジ係が勘定を計算する手間を省き、ナビゲーションアプリは、地図を読む手間を省いてくれる。
でもだからといって、「人間の能力が低下している」と言う人はほとんどいないだろう。
思考する作業を機械に任せることで、脳本来の思考力が変わることを示す証拠はほとんどないと、ウォータールー大学の心理学教授エヴァン・リスコは指摘する。
彼は同僚のサム・ギルバートとともに、「認知的オフロード(認知的負荷の軽減)」という用語を作り出した。これは頭を使う難しいタスクや面倒なタスクを、外部の補助ツールに任せる行為を説明するために用いられる。
懸念されるのは、リスコが言うように、生成AIは、「より複雑なプロセスのオフロード」も可能にする点だ。応用範囲が狭い「暗算」をオフロードするのと、文章を書いたり、問題を解決したりする「思考プロセス」をオフロードするのは同じではない。
一度、脳がオフロードすることに味をしめてしまうと、その癖をやめさせるのは難しくなる可能性がある。「認知的手抜き」として知られる、問題解決のいちばん楽な方法を探そうとする傾向は、ゲルリッヒが「フィードバック・ループ」と呼ぶ現象を生じさせかねない。
AIに頼る者は、批判的思考を難しく感じて、その脳が手を抜く可能性があり、それがさらなるオフロードにつながる、ということだ。
ゲルリッヒの研究に参加したあるAIのヘビーユーザーは、こう嘆く。「あまりにもAIに頼りすぎているので、ある種の問題については、AIなしで解決する方法がわからない気がします」 多くの企業が、AIを広く導入することで生産性が上がることを期待している。だが、そこには驚くべき事実が隠されているかもしれない。
「長期にわたる批判的思考の劣化は、競争力を削ぐことになるかもしれません」とノースイースタン大学の経営学教授バーバラ・ラーソンは言う。
残り: 1780文字 / 全文 : 4726文字



