半導体内の「電子スピン波」を自由に制御。東北大学などの研究(石田雅彦)
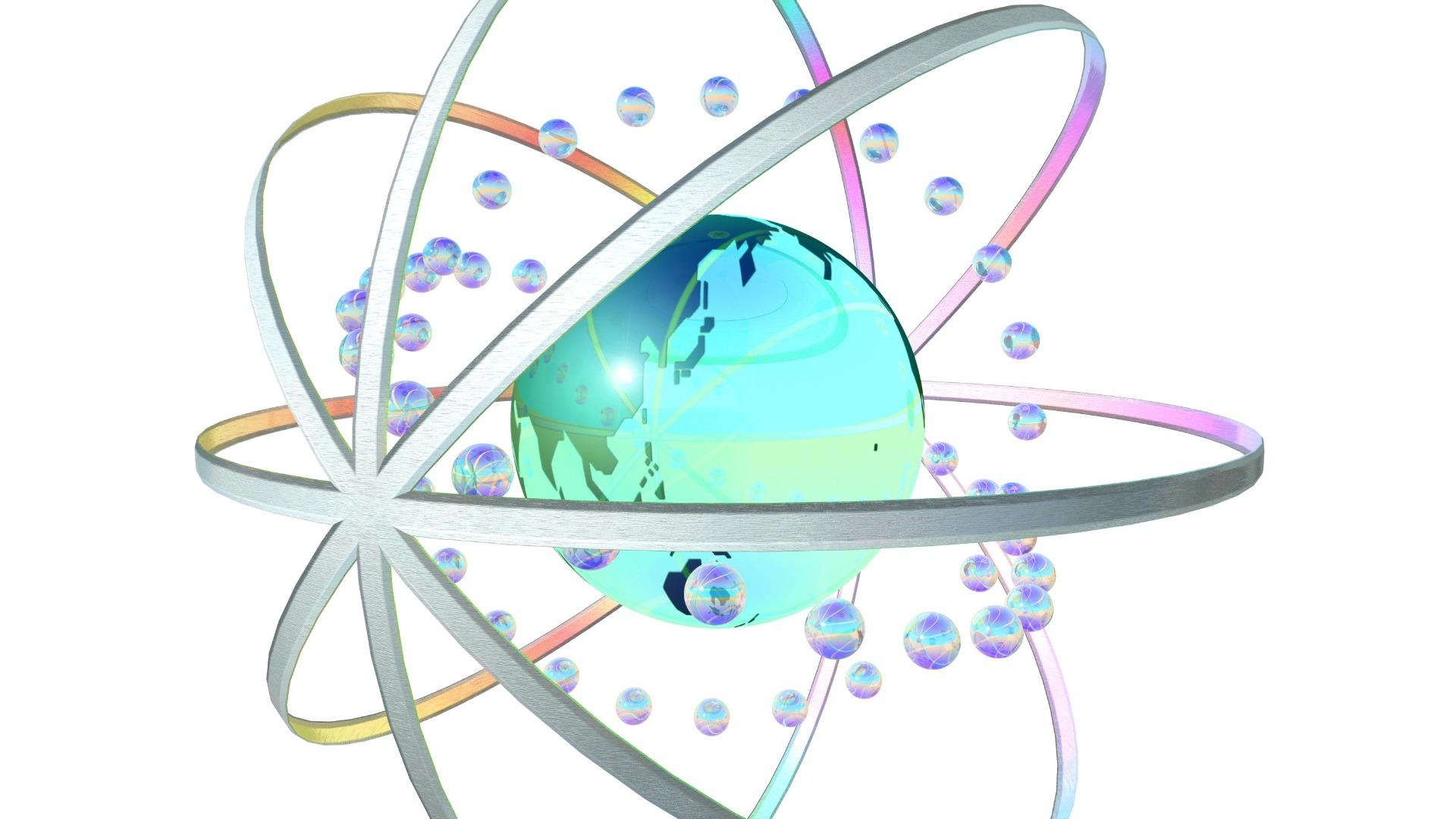
電子デバイスの低電力化や高効率化などに欠かせない電子スピン波を自由に制御する技術を東北大学などの研究グループが開発した。量子コンピュータなどへの応用の可能性もある技術だ。
電子スピンとは
電子スピンという量子力学の言葉があるが、半導体などの電子デバイスの開発にとって重要な技術分野だ。電子は、原子の周りを衛星のように軌道を描いて回転する極微小粒子で、原子同士を結びつけて分子を作るなどする。
電子は最も小さな磁石と考えられ、電子スピンはかなりざっくり言えば、電子による磁場と軌道運動が量子化された力のいわばベクトル(スピン角運動量)のことだ(※1)。電子のスピンには上向きと下向きがあり、多くの原子で軌道の電子は上向きと下向きがバランスを取って中性になっている。
また、特定のスピン軌道の相互作用にキラリティ(鏡像)などの条件がそろうと、スピンのらせん構造が形成され、波のように扱うことができ、それを電子スピン波という。この電子が持つ電気的な性質(電荷)と磁気的性質(電子スピン波)を利用するデバイス開発などを目的とした技術をスピントロニクスという(※2)。
中でも電子スピン波を正確に制御できれば、電子デバイスを大幅に低電力化させたり、新たな高効率・高機能な電子デバイスを開発したりすることが可能となる。そして、半導体の中にも電子スピン波があり、このスピン状態を精密に制御することは次世代のスピントロニクス・デバイスの開発にとって不可欠な技術とされる。
特に、半導体の中でスピンのらせん構造として電子スピン波が長時間、維持させる永久スピン旋回(Persistent Spin Helix、PSH)という状態は、MRAM(磁気ランダムアクセスメモリ)といった記憶メモリやクラウドなどの情報ストレージやCPUなどの演算デバイスの基盤技術で注目されているが、従来の電子スピン波の生成技術では波数(単位長さに含まれる波の数)の柔軟な制御ができないという制約があった。
電子スピン波の自由な制御に成功
東北大学などの研究グループ(※3)は、プログラム可能な空間光変調器を用いた構造化光を利用し、ガリウム・ヒ素(GaAs)/アルミニウム・ガリウム・ヒ素(AlGaAs)の量子井戸中に任意の電子スピン波を直接転写することに成功したと米国物理学会の学術誌に発表した(※4)。
空間光変調器(Spatial Light Modulator、SLM)とは光の振幅、位相、偏光といった空間的な分布を電気的に制御するデバイスで、構造化光というのはこの光の振幅、位相、偏光が制御された特殊な光のことだという。電子のスピン状態は、光の偏光(光の電場の振動方向が特定方向へそろう状態)に反映されるため、こうした技術を用いた。
また、量子井戸というのは、電子の動きや正孔(ホール)を特定の2次元の平面に閉じ込め、自由に動ける空間が制御された構造のことだ。ガリウム・ヒ素などの半導体材料では、量子井戸構造がナノ・スケールで存在するため、スピン研究の観察ではよく使われる。
同研究グループは、空間光変調器に周期的な位相変調信号を入力することで、空間的に45度直線偏光→左回り円偏光、→マイナス45度直線偏光→右回り円偏光が繰り返し配置された変更パターンを生成した。その後、空間光変調器によってプログラムされたこの周期的な偏光パターンをガリウム・ヒ素/アルミニウム・ガリウム・ヒ素量子井戸に照射し、周期構造を持つ電子スピン波を光励起した。
こうして生成された電子スピン波の状態は、ポンプ・プローブカー回転顕微鏡という技術を用い、そのスピン偏極をマッピングすることで確認した。これらの手法により、電子スピン波の波数、周期、空間構造を自由に制御することを実証したという。
電子スピン波の観察。空間光変調器の円偏光状態(上)とポンプ・プローブカー回転顕微鏡による信号の空間マップ(下)。東北大学のリリースより同研究グループによれば、今回の成果により電子スピン波を利用した情報処理技術の高度化に貢献するだけでなく、磁気デバイスの高効率化を目的とした磁性薄膜への応用、モリブデンやタングステンなどの偏移金属を使った新素材やペロブスカイト半導体の二次元物質への材料展開、ホログラフィック・イメージングとの組み合わせによる光情報技術、電子スピン波を利用した新たな情報演算技術の開発などが期待できるという。
※1:Norbert Straumann, "On Wolfgang Pauli's most important contributions to physics" History and Philosophy of Physics, doi.org/10.48550/arXiv.physics/0010003, 2, October, 2000
※2:Supriyo Datta, Biswajit Das, "Electronic analog of the electro-pitic modulator" Applied Physics Letters, Vol.56, Issue7, 12, February, 1990
※:東北大学大学院工学研究科の菊池奎斗大学院生、石原淳助教、山本壮太特任助教、好田誠教授(兼 量子科学技術研究開発機構 量子機能創製研究センター プロジェクトリーダー)、筑波大学数理物質系の大野裕三教授、東京理科大学先進工学部物理工学科の宮島顕祐教授ら
※:Keito Kikuchi, et al., "Direct imprinting of arbitrary spin helices using programmable structured light in a semiconductor two-dimensional electron gas" Physical Review Applied, Vol.23, 044017, 7, April, 2025



