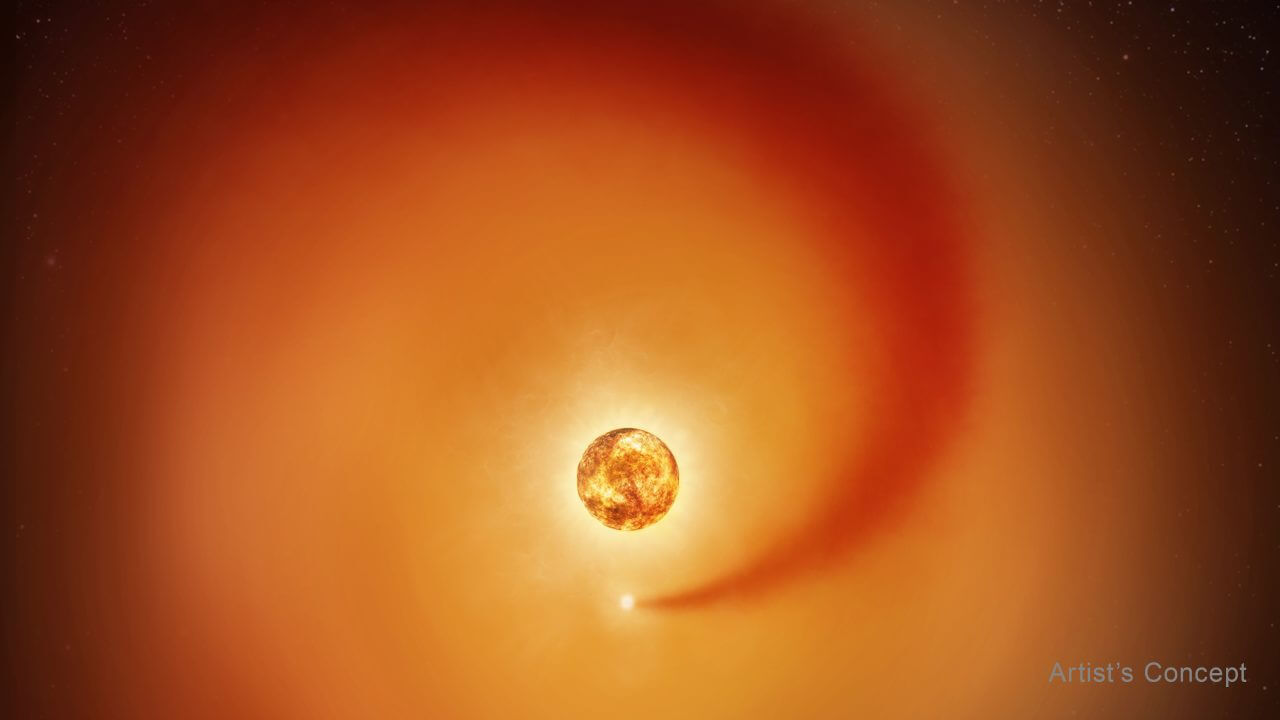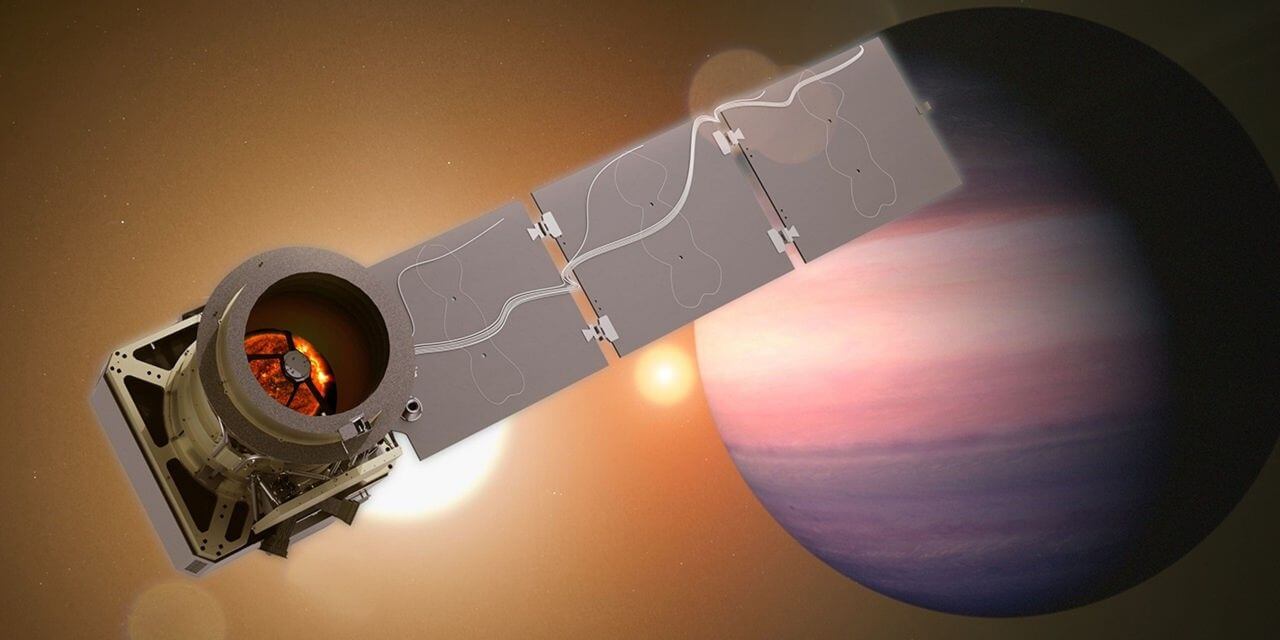宇宙で咲き誇る「花」って何だろう?

ISSの日本実験棟「きぼう」では植物が宇宙空間でどんな反応をするのか研究されています。
でも、宇宙には本物の植物以外にも「開花している花」があるってご存知でしょうか。
実は日本の人工衛星には「ひまわり」や「さくら」など、花の名前が付けられたものが数多く存在します。
なんかロマンを感じないですか?
なぜ花の名前が付けられるのか?
親しみやすさを持ってもらうためと、「宇宙に花開け」という願いが込められているから。
最初に花の名前がつけられた人工衛星は、1975年に打ち上げられた技術試験衛星「きく」。正式には「技術試験衛星1号(ETS-1)」という名前があるんですが、「きく」のほうが愛着が湧きますよね。
以降、気象衛星「ひまわり」や通信衛星「さくら」など、花の名前が付けられるように。これらの愛称は、人工衛星の特徴をよく表しているんですよ。
代表的な「花」衛星たち
ひまわり
1977年に初号機が打ち上げられた日本の気象衛星シリーズ。東アジア・西太平洋地域の気象観測を行ない、天気予報や災害対策に貢献しています。
Image: JAXA静止気象衛星「ひまわり」天気予報画面の下とかに「ひまわりで観測」とか書かれているので、馴染みの名前かもしれませんね。
さくら
日本の通信衛星シリーズで、国内外の通信インフラを支えています。
Image: JAXA通信衛星2号-a(CS-2a)「さくら2号-a」(種子島宇宙センター)ゆり
日本の放送衛星シリーズで、全国へのテレビ放送の普及に寄与しています。
Image: JAXA放送衛星2号「ゆり2号-a」(BS-2a) 1984年1月23日16時58分に、種子島宇宙センターからN-IIロケット5号機を打ち上げました。日本初の静止実用放送衛星あじさい
測地実験衛星で、地球の形状や重力場の測定に活用されています。
もも
海洋観測衛星で、海洋現象や資源の監視を行なっています。
日本の人工衛星の名前は分かりやすい
宇宙とか人工衛星とかって難しい印象があるし、まぁ、実際のところ複雑なことをやっているんですが、だからこそわかりやすくてミッションを連想しやすい名前がついているんです。
花の名前以外にも、自然や神話、天体、動物をモチーフにした名前もあるんですよ。
ちなみに、私が個人的に好きなのは「つばめ(SLATS)」(2019年にミッション終了)。
Image: JAXA種子島宇宙センターで公開された超低高度衛星技術試験機「つばめ」(SLATS)これは超低高度衛星技術試験機です。こんなに漢字が並んでいると一気に難しく感じてしまいますが、つばめの生態を少しでも知っていたら何をする人工衛星か予測できるはず。
ほら、つばめって地面スレスレをスーッと飛ぶじゃないですか。あれは雨の前に空気が湿気を帯びると虫が地面の近くに集まってくるから効率よく餌を得るために低い場所を飛ぶんですよね。
つまり「つばめ」は「超低い高さを飛ぶテスト衛星」です。覚えやすいし、連想できると思います。そして、「低く飛ぶためにはどんな技術が必要になるの? どこが技術を持っているの? 」ってところにも興味が湧いたら知的好奇心や探究心も大きく花開いていきそう。
ま、そこからは専門的な分野になっていっちゃうんですけどね(難しいったらありゃしない)。
Source: Jaxa