NVIDIAファンCEO流型破り経営 社員3万人でも現場指示
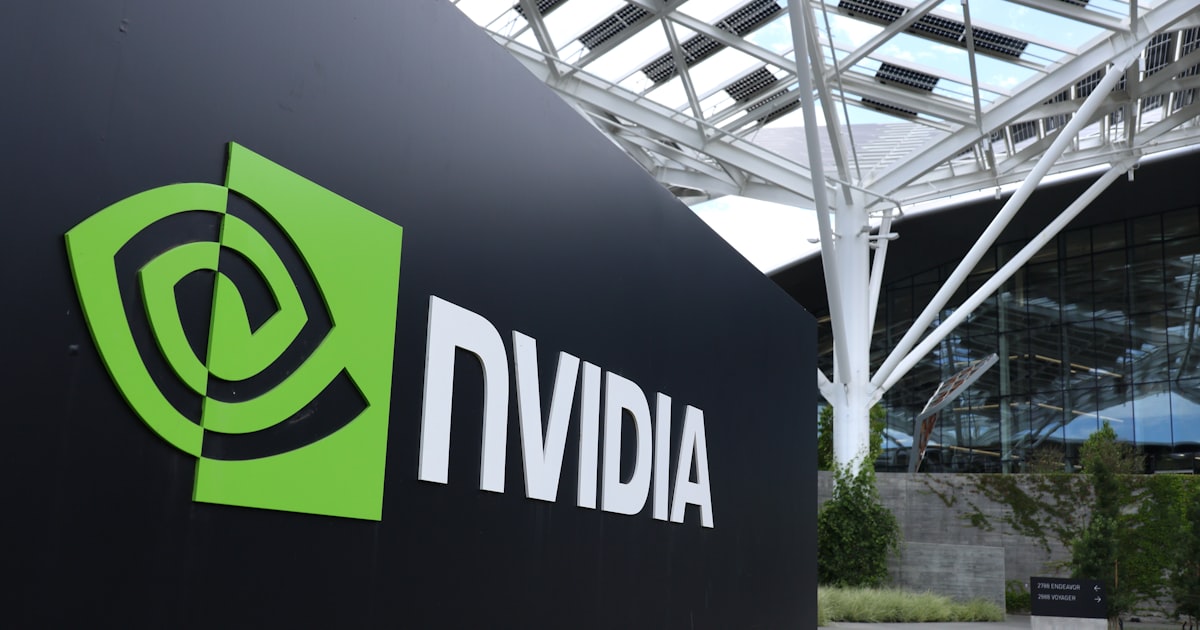
2時間前から長い行列ができた会場は超満員。時の人が壇上に姿を見せた瞬間、一斉にフラッシュがたかれシャッター音が鳴り響いた。なじみの黒い革ジャンに身を包んだジェンスン・ファン最高経営責任者(CEO)が2024年11月、6年ぶりに日本のイベントに登壇した。
「今、私たちはAI(人工知能)革命の始まりにいる」。決まり文句で口火を切ったファン氏は、AI向け半導体で市場を席巻するGPU(画像処理半導体)の驚異的な性能と、AIの未来について冗舌に語った。
早口でまくし立てる強い個性とテクノロジーへの深い造詣。創業者兼CEOであるファン氏は、社員の誰もが「絶対的な存在」と認めるカリスマだ。ファン氏なくしてエヌビディアという企業は語れない。
「ジェンスンは我々全員を導く星明かりだ」。同社でロボットなどを担当するディープゥ・タッラ副社長はそのリーダー性を強調する。
エヌビディアがAI向け半導体市場で「無双」状態にある理由も、ファン氏によるところが大きい。
台湾生まれのファン氏は幼少期に渡米し、大学卒業後に米半導体大手アドバンスト・マイクロ・デバイス(AMD)などで経験を積んだ。エヌビディアの創業は1993年。祖業はゲーム用の半導体で、当時から異色のビジネスを展開し、その一つが、半導体領域での水平分業モデルの採用だった。
90年代の半導体の主流は、設計と製造の両方を手掛ける垂直統合型。だが、エヌビディアは98年に台湾積体電路製造(TSMC)と提携し、製造を同社に委託した。自らはGPUの開発・設計だけを担うファブレス企業となり、これがメーカーでありながら営業利益率が60%超の高収益体質につながった。
製造は水平分業だが、顧客との接点は垂直統合した点もユニークだ。2006年、エヌビディア製GPUの計算速度を最大化させるソフトウエア開発環境「CUDA(クーダ)」を発表。GPUの能力を最も発揮できる環境を自ら用意した。開発者や研究者はGPUをより高速で動かすために一斉にCUDAの利用を開始。半導体というハードウエアだけでなく、ソフトでも覇権を握る布石を打ったわけだ。
学生時代からCUDAを利用する開発者は就職後も慣れ親しんだCUDAを使いたがる。ただし、CUDAはエヌビディア製GPUに特化した開発環境で、それ以外の半導体を動かすことはできない。
これが、ハードの参入障壁を高めることにつながった。競合がエヌビディア製GPUに匹敵する性能を持つ半導体を開発したとしても、CUDAで動かせないので開発者は敬遠する可能性が高いからだ。ソフトとハードの双方で高い壁を築いたことで、GPUの市場での評価を盤石なものにした。
企業や消費者に対する「共通の基盤」であるプラットフォームを握ることは、現代のビジネス戦略の王道の一つとなっている。米マイクロソフトや米グーグルといった巨大IT(情報技術)企業が、ソフト領域で実権を握っているのがその象徴だ。
エヌビディアは、さらに上を行く。プラットフォーム論の世界的第一人者で米マサチューセッツ工科大学経営大学院のマイケル・クスマノ教授は「エヌビディアはソフトとハードの両面で市場を支配している。これは非常にまれな現象だ」と分析する。
例えばパソコン市場では、基本ソフト(OS)「ウィンドウズ」を提供するマイクロソフトと、パソコン向けCPU(中央演算処理装置)を手掛ける米インテルが、1990年代から「ウィンテル時代」を築いた。「今のエヌビディアは、この2社のピーク時の力を1社に結集したような存在だ」(クスマノ教授)
今やAI需要を一手に引き受ける世界最大の半導体メーカーとなったエヌビディア。ファン氏はここに至る過程でどう意思決定し、どう会社を動かしてきたのか。
鍵となるのは、従業員数3万人超の巨大企業としては極めて異例となるフラットな組織構造だ。
最大の特徴は、CEO直属の最高幹部の人数にある。「私の直下には60人の幹部がいる」。2024年11月に東京都内で日系メディアの合同取材に応じたファン氏は、日経ビジネスの質問にこう答えた。
マネジメント論の定石では、企業の最高幹部は最大でも10人までとされる。「60人は聞いたこともない数字。エヌビディアの組織で最もユニークな部分だろう」。企業の人事制度に詳しい京都大学経営管理大学院特命教授の鵜沢慎一郎氏はこう指摘する。
なぜ60人も幹部が必要なのか。ファン氏は「情報の価値を失わないために、組織をフラットにする必要があるから」と説明する。
従来のピラミッド型の組織構造では、最高幹部の下に5〜10人の本部長クラス、その下にそれぞれ部長クラスなどと続き、数万人の企業だと10〜11層の階層構造を持つことも珍しくない。だが、上層に位置する幹部の数を多くすればするほど、そのピラミッドは低くなる。エヌビディアは同規模の企業と比較して「階層を3〜4層削減している」(ファン氏)
情報の流通性を高めるもう一つのルールが、幹部と1対1の会議をしないことだ。ファン氏は、1人の幹部だけが知っておくべき情報などないし、CEOからのフィードバックは他の幹部も同様に聞くべきだ、と考える。「私がほとんどの時間を費やしているのは、考えることと考えを口に出して表現すること。そしてそれをみんなに聞いてもらうことだ」(ファン氏)
1対1の打ち合わせが禁止されているのはファン氏と幹部の間のみ。ミドルマネジメント層での運用は各幹部に委ねられている。
エヌビディア日本代表兼米国本社副社長の大崎真孝氏は「彼と同じであろうと心掛けているのは、常に現場の近くにいようとする点だ」と自身の経営手法を語る。
米国でマーケティングを担当する社員は、ある日突然、ファン氏から直接メールの返信が届いて驚いた。進めていた大型イベントに関するキャンペーン施策について、「もっと具体的に教えてほしい」と書かれた1行の短いメールだった。常に現場を見ることがファン氏の流儀の一つだ。
ファン氏は創業から30年以上たった今も、現場に直接指示を下すプレーヤーなのだ。ただ、数年前に同社を退職したエンジニアは「悪く言えば、現場の箸の上げ下げまで口を挟むマイクロマネジメント」と苦言を呈する。確かに大企業のマネジメント論では異端だ。
「創業者モード」か「マネジャーモード」か――。米シリコンバレーで2024年9月、こんな議論が巻き起こった。米エアビーアンドビーの共同創業者兼CEO、ブライアン・チェスキー氏が投資家向けイベントで「従来の常識は間違っている」と発言したのがきっかけだ。
創業者モードとは、まだ社員も少ない段階で、経営者自らがプレーヤーとして何でもこなす様を指す。ある程度の成長が視野に入ったら創業者は権限を幹部に委譲し、経営に特化するマネジャーモードに移行すべきだという考え方が根強く、チェスキー氏はこれを「従来の常識」と呼んだ。起業家に対して「いつまで創業者モードでいるのか」と質問することは、その起業家をやゆするものなわけだ。
チェスキー氏も、エアビーアンドビーが成長するにつれてマネジャーモードに移行すべきだとの助言にいったんは従ったが「結果は惨憺(さんたん)たるものだった」とし、創業者モードに戻ったという。自ら現場を指示する方法は「うまくいっている」と説明した。
同様にファン氏も、「30年たった今も創業者モードのまま。その先見性を最大限に生かす組織構造がうまく機能している」と京都大学の鵜沢氏は指摘する。
(日経BPシリコンバレー支局 島津翔)
[日経ビジネス電子版 2024年12月13日の記事を再構成]
週刊経済誌「日経ビジネス」と「日経ビジネス電子版」の記事をスマートフォン、タブレット、パソコンでお読みいただけます。日経読者なら割引料金でご利用いただけます。
詳細・お申し込みはこちらhttps://info.nikkei.com/nb/subscription-nk/


