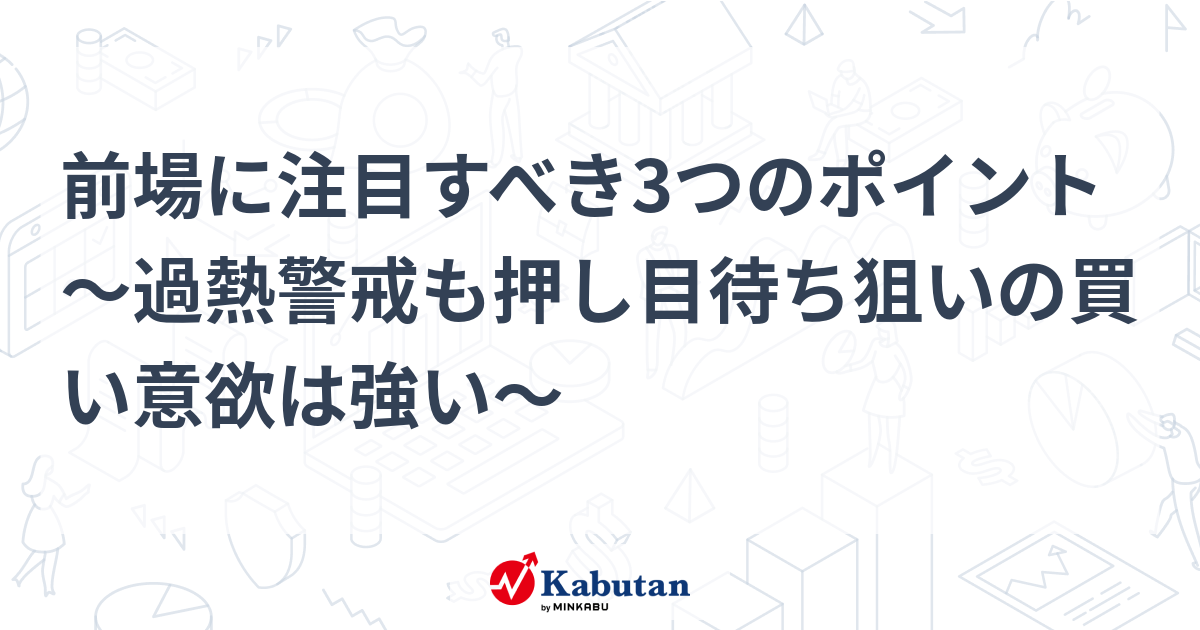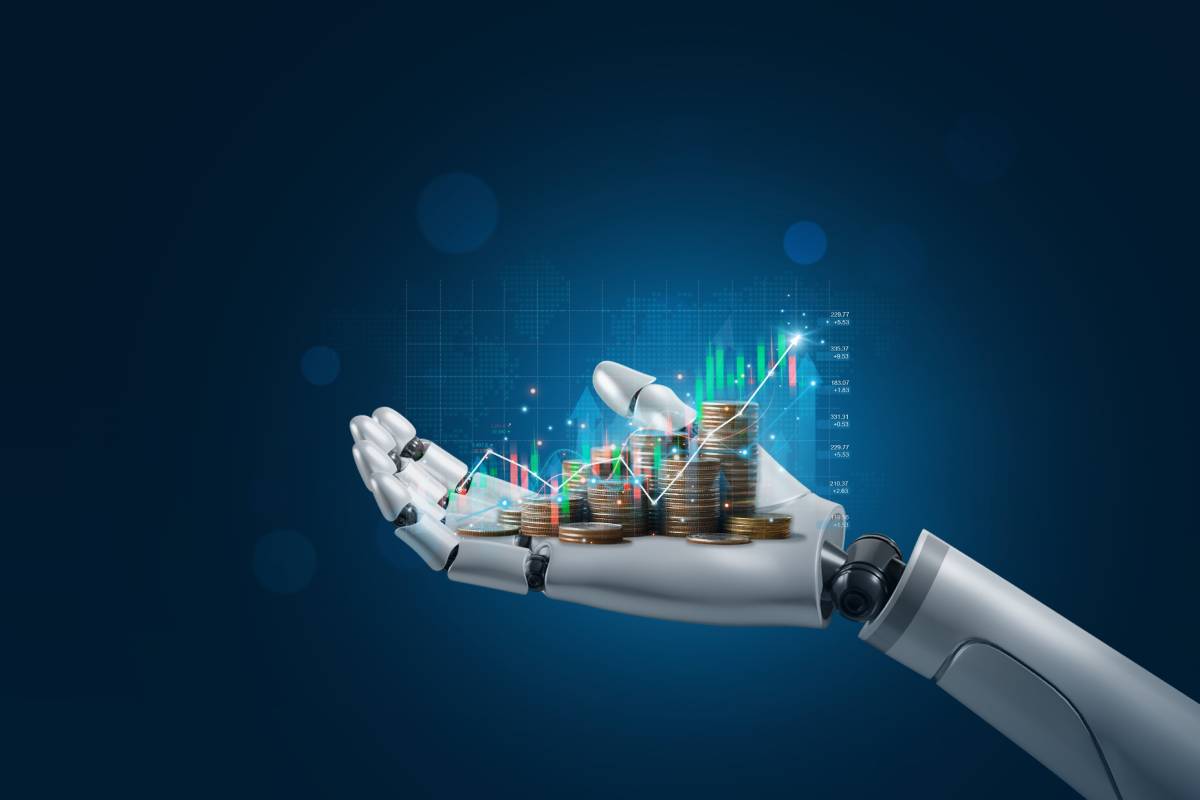円トレーダーの姿勢に変化、日銀利上げで国内指標への感応度高まる

日本銀行によるさらなる利上げへの期待が高まる中、円トレーダーの日本の経済指標に対する注目度が高まっている。
日銀が大規模緩和を続けていた10年間、トレーダーらは経済指標が何を示そうと緩和策の維持をほとんど疑わず、日本の指標は無視して問題ないと考えていた。そうした考え方が昨年3月のマイナス金利解除以降、変化している。
ブルームバーグが分析したデータによると、5日の毎月勤労統計調査の発表後5分間にドル・円相場は0.11%変動し、2017年以来最大の反応を示した。17日の昨年10-12月期国内総生産(GDP)速報値では発表から5分間で0.18%と16年以降で2番目に大きな変動を見せた。
動きそのものはまだ限定的だが、米国の金利動向や経済指標でドル・円相場が動くことに慣れていた市場参加者の姿勢は明らかに変化している。その背景には、日銀がさらなる利上げを示唆する一方で、米連邦準備制度理事会(FRB)が昨年後半の連続利下げの後、様子見に転じていることがある。
バークレイズ証券のチーフ為替ストラテジスト、門田真一郎氏は、日本の経済指標が市場を動かすことはなかったが、最近はより大きな影響力を持つようになったと指摘。「おそらく日銀がより大きな推進力となっているためだ」と話す。
国内経済指標に対する円相場の感応度の高まりは、円高がさらに進む余地があることを意味しているかもしれない。最近の良好な指標は日銀が利上げを続ける根拠になっており、海外投資家や日本の外国為替証拠金取引(FX)トレーダーが円売りポジションの削減に動いて円の上昇が加速する可能性を高める。
米商品先物取引委員会(CFTC)のデータでは、ヘッジファンドによる円の売り越しが減少する一方、アセットマネジャーは21年以来最大の円の買い越しとなっていた。一方、ブルームバーグの分析によると、日本のFX投資家は2月に円売りポジションを約7割増やしたと推計される。こうした他通貨との金利差に着目して構築されたポジションが解消されれば、円高が勢いづきかねない。
出所:ブルームバーグ、金融先物取引業協会、東京金融取引所、米商品先物取引委員会
2月に発表された国内指標では、名目賃金が約30年ぶりの高い伸びとなり、GDPは予想を上回るプラス成長となった。28日発表の2月の東京都区部消費者物価指数(CPI)は日銀の利上げ路線の支援材料になると予想されており、通貨オプションの指標(リスクリバーサル)は市場が向こう1カ月で円高が進むとみていることを示唆している。
関連記事:ドル・円の1カ月物ボラティリティー、6週間ぶり高水準に接近 (1)
マネックス証券の債券・為替トレーダー、相馬勉氏は、マーケットは「円高方向の材料を探してる」と指摘する。
もっとも、オーバーナイト・インデックス・スワップ(OIS)市場が年内に確実視する日銀の追加利上げは1回のみで、日米の大きな金利差は引き続き円の重しとなる。円高の進行は利上げ時期の判断で日銀に柔軟性を与えることにもつながる。
出所: ブルームバーグ、シティグループ、国際決済銀行(BIS)
JPモルガンは予想外の経済指標が円相場に与える影響について、過去2年間において賃金関連指標のサプライズが最も説明力があったと分析する。日銀が賃金上昇のモメンタムとそれが企業の価格設定行動に与える影響に注目していることを強調しているためだ。
棚瀬順哉、斉藤郁恵両ストラテジストはリポートで、円はインフレや政策金利期待にはまだあまり反応していないが、「いずれ正常化するだろう」と予想。円が追加利上げ期待の高まりをあまり織り込んでいないことを踏まえると、今後物価指標に対する感応度が高まれば、「インフレが予想比上振れた際の円の上昇は比較的大きなものになる可能性がある」と指摘している。