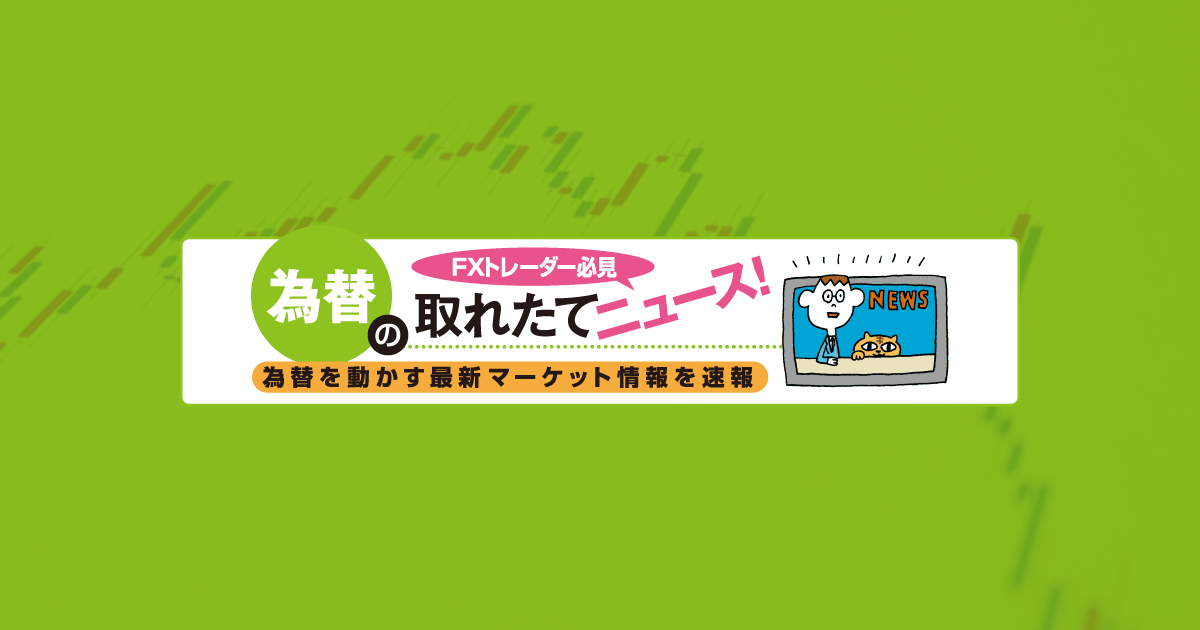福岡発の「ヤバい小型スーパー」が東京に進出…「カツ重343円」だけじゃない"儲けのカラクリ"を徹底解説 「スーパー」→「コンビニ」の次の革命が始まった

福岡発の小型スーパー「トライアルGO」が11月7日、東京に初出店した。日本工業大学大学院技術経営研究科の田中道昭教授は「見た目は普通の小型スーパーだが、商品管理、価格変更、補充までがデジタルで同期し、人が少なくても店舗が止まらない仕組みが成立している。わずか50坪ほどの店舗が、日本の流通の常識を根底から揺るがせている」という――。
プレスリリースより
2025年11月7日、午前7時。東京・西荻窪。通勤客が足早に行き交う駅前の一角に、異様な熱気が漂っていた。
その中心にあるのは、たった50坪ほどの小さな店――トライアルGO。
開店と同時に人がなだれ込み、棚に並ぶ343円のロースカツ重や199円のたまごサンドを手に取る。
「できたてです」 「値引きしました」
自動アナウンスが流れ、天井には複数のカメラが並ぶ。棚はデジタルディスプレイで価格が自動更新され、レジはセルフの顔認証決済。24時間を少人数で回せるように設計された“省人化ストア”だ。
店内の24時間稼働、オペレーションを支えるのはテクノロジー。商品管理、価格変更、補充までがデジタルで同期し、人が少なくても店舗が止まらない仕組みが成立している。
わずか50坪ほどのこの店舗が、日本の流通の常識を根底から揺るがせている。
トライアルホールディングス。九州を地盤に350店舗超を展開するディスカウントの雄が、「時間を制御するRetail Tech」として都心に殴り込んだ。
真の標的は、イオンではなく「業界全体」
テクノロジーやAIで在庫を管理し、販売速度に応じて価格を変動させ、できたて商品を1時間以内に陳列する――。この“時間制御小売”がもたらすインパクトは、既存プレイヤーの想像を超えている。
・ドラッグストアは「ついで買い」を誘うが、トライアルGOは「出来たてを短時間で買える」動機を生みだす。
つまり、これは単なる新規出店ではない。“価格競争”から“時間競争”への歴史的転換点である。
世間は「トライアルGO vs. まいばすけっと」と捉えがちだ。だが、トライアルGOの戦いのスケールはもっと大きい。その照準の先には、日本の小売全体がある。
トライアルが挑むのは、「日次で動く経営」そのものだ。スーパー、コンビニ、ドラッグストア――。どの業態も日々の販売データを翌日に反映させる“後追い経営”で動いてきた。そこにトライアルGOは、「分時経営」という概念を持ち込んだ。
・その情報が瞬時にPOSに反映され、即座に本部と共有される。
これまで時間がかかっていた在庫や値引きの判断が、データとテクノロジーで短時間に完了する小売。この「時間OS」(Operating System=基本ソフト)の登場により、業界の競争構造は一変した。
Page 2
この2つのOSの衝突が示しているのは、小売業が「モノを売る産業」から「時間と生活を設計する産業」へ変わるということだ。
トライアルGOが分時単位で供給を制御することで、消費者は“待たない・探さない”購買を体験する。まいばすけっとが生活単位で秩序を保つことで、消費者は“考えなくても済む”日常を得る。
AIと人間、スピードと秩序。そのどちらが優位になるかではなく、どちらが顧客の時間をより美しく使わせるかが鍵だ。
これからの小売の勝者は、「何を売るか」ではなく、「どの時間を売るか」で決まる。
トライアルGOの首都圏一号店は、小さく見える。だが、そのインパクトは巨大だ。それはまいばすけっとだけでなく、コンビニ、スーパー、ドラッグストア――あらゆる小売企業を巻き込む“リテールOS戦争”の導火線である。
2025年、日本の流通は「時間」と「生活」の総力戦に突入した。どちらのOSが人々の暮らしをより滑らかに動かすか。その勝負が、この国の経済構造そのものを変えていく。
これは静かな競争ではない。いま始まったのは、流通のアルゴリズムそのものを奪い合う激戦である。
写真=iStock.com/metamorworks
※写真はイメージです
近い店ではなく、「常駐する店」
第2章:まいばすけっととは何か――“生活OS”を体現する都市の小売
早朝、出勤前に立ち寄る人。夜10時、帰宅途中に牛乳を買う人。どの時間帯にも、「まいばすけっと」は灯をともしている。
それは巨大でも華やかでもない。むしろ、無音で都市の「すき間」を埋めている。しかしその静けさの中で、人々の生活リズムを精密に再現している。
都市生活において最も価値があるのは「時間」ではない。それは、“時間の使い方を決める秩序”だ。まいばすけっとは、その秩序をつくっている。つまり、人間の生活アルゴリズムを掌握したリテールOSである。
徒歩5分圏にほぼ必ずと言ってよいほど存在する「まいばすけっと」。“人口1万人に1店舗”級というドミナントは、物理的距離の近さではなく、心理的距離の支配を意味する。
顧客はあえて「行こう」と思わない。対象顧客には、“いつもの帰り道にある”という無意識の立地が、生活ループに組み込まれている。
まいばすけっとの株主でもあるイオンリテールの幹部は、「まいばすけっとは、買い物という行為そのものを“生活の自動動作”に変えた」と見ているようだ。
立地ではなく、「習慣の座標」を占有する。この“常駐戦略”こそ、まいばすけっとが都市で築いた最大の参入障壁だ。
Page 3
迎え撃つのは、都心で圧倒的な存在感を誇る都市型小型スーパーのまいばすけっとだ。東京・神奈川・千葉・埼玉で約1200店舗。駅前でも商店街でも住宅街でも、「必ずある」店。
まいばすけっとは、“近さ”を武器に「生活のOS」を構築してきた。イオンのプライベートブランド「トップバリュ」の安定供給、秩序化されたオペレーション、そして“変わらない今日”を保証する信頼。
彼らの経営は人間的で、アナログだが極めて洗練されている。都市生活者のリズム――朝はパンと牛乳、夜は弁当と惣菜――をアルゴリズムのように再現する。AIではなく、人間の習慣がシステムを動かし、それに合わせて売場が積み上げられる仕組みと言える。
まいばすけっとの強さは、「人間の生活を最適化するリテールOS」にある。トライアルGOの“時間革命”に対し、まいばすけっとは“生活の秩序”で応じる。
写真=iStock.com/winhorse
※写真はイメージです
コンビニ・スーパー・ドラッグストアを巻き込む波
トライアルGOが仕掛けたのは、「業態の再定義」だ。この動きが、既存の全プレイヤーを巻き込むのは時間の問題である。
・ドラッグストアは、購買データとAIを掛け合わせた“生活提案”の領域で競争に巻き込まれる。
トライアルGOの「時間OS」は、これら全ての業態境界を溶かしていく。もはや「コンビニ」「スーパー」「ドラッグストア」という分類自体が意味を失い、“時間をどこまで制御できるか”が新しい業界基準になる。
いま、流通業界で起きているのは「店の数」でも「安さ」でもなく、“OSの競争”である。
トライアルGOはAIやテクノロジーで時間を制御する「時間OS」。まいばすけっとは生活習慣を最適化する「生活OS」。
そして、そのOS戦争の余波が、セブン‐イレブンやローソン、イトーヨーカドー、ライフ、マツキヨ、ウエルシアにまで波及する。
“時間”と“生活”のどちらの軸で顧客を掴むか。これこそ、次の10年の流通業を左右する決定的な分水嶺になる。
Page 4
店に入ると、照明はやや控えめで、BGMもない。棚は常に同じ配置、価格はほとんど動かない。商品の並びは季節が変わっても大きくは変化しない。その“変わらなさ”が、都市生活者にとっての安心を生む。
だがこの安定は、惰性ではなく戦略だ。まいばすけっとは、徹底したマニュアル経営でこの「日常の再現性」を実現している。
青果のカット角度、惣菜の陳列順、レジオペレーションの秒数――すべてがデータ化され、標準化されている。
「AIではなく、人間による秩序の最適化」
これが、まいばすけっとの“人間中心型DX”である。
テクノロジーが人を代替するのではなく、人間のリズムを忠実に再現する“アナログ型のアルゴリズム”なのだ。
プライベートブランド「トップバリュ」の本質
まいばすけっとの棚を見渡すと、「トップバリュ」商品が大きな割合を占める。弁当、惣菜、パン、乳製品――。それは単なるPBではない。“生活の定数”である。
どの店舗でも、どの時間帯でも、同じ価格、同じ品質。それが顧客にとっての「再現性の安心」をつくる。「この商品がここにあるはず」という期待を裏切らない。
まいばすけっとは、「トップバリュ」を使って“日常のプログラム”を維持している。「トップバリュ」はブランドではなく、生活の信号なのだ。
表面的にはテクノロジーを感じさせないが、実際のまいばすけっとは、イオングループの中でもデータ活用が進んだ業態の一つだ。
WAON・iAEONなどのIDデータに基づき、店舗別に購買時間・商品カテゴリー・来店頻度を解析。補充や値引きのタイミングもデータに基づいて設計されており、現場のスタッフはそのオペレーションをマニュアル通りに再現する。
AIと人間が分業するのではなく、データとマニュアルを掛け合わせることで「人間中心の精密機械」をつくり上げた。
都市生活者のリズムは、分単位ではなく「習慣単位」で動く。トライアルGOが時間を制御するなら、まいばすけっとは習慣を制御する。この差が、両者の本質的なOSの違いである。