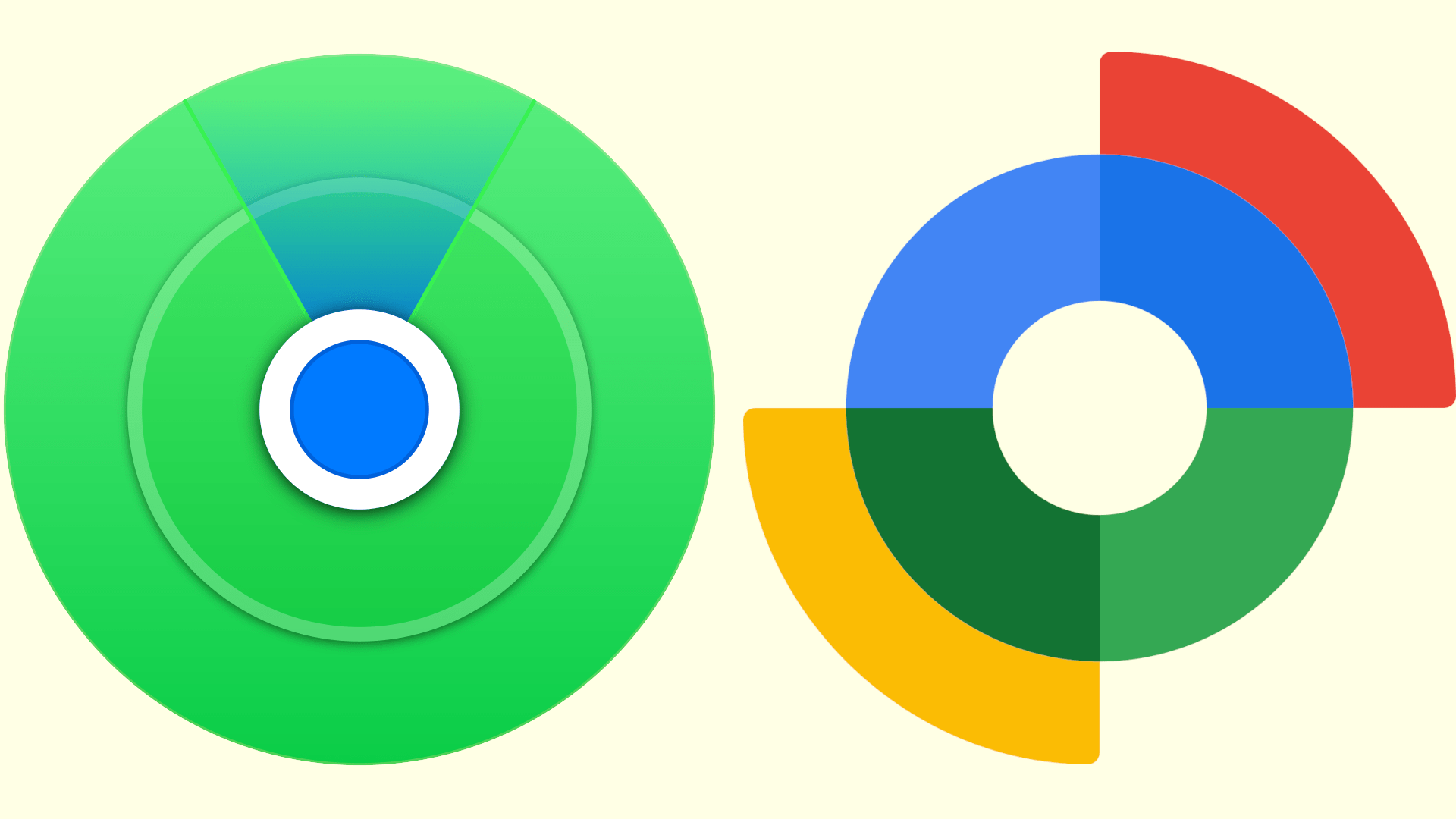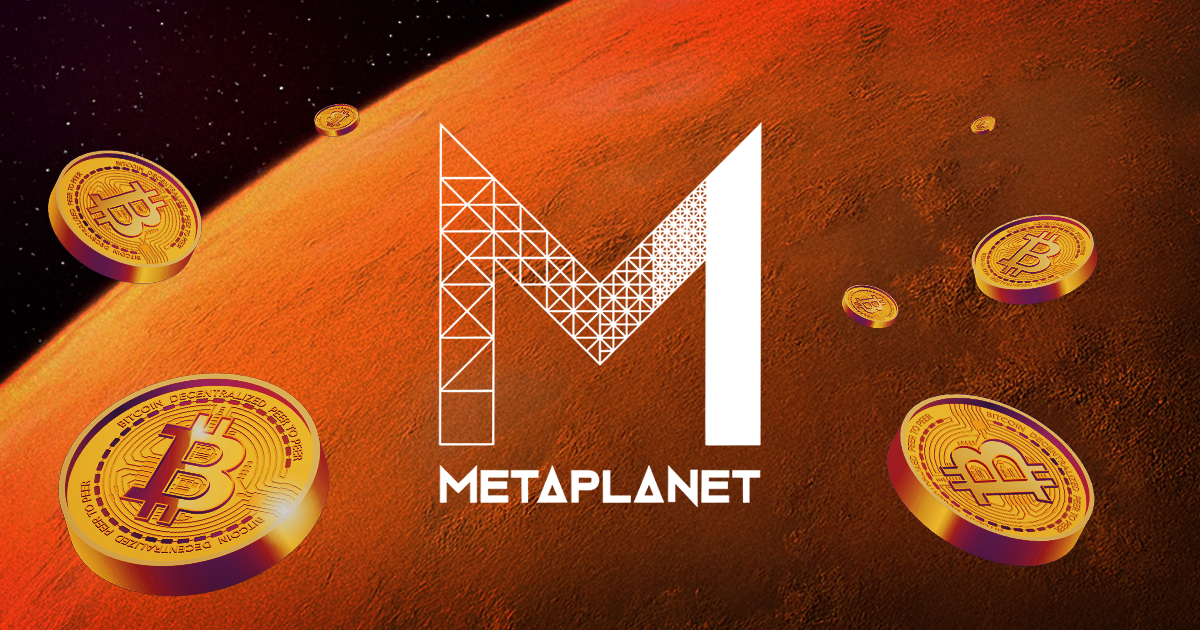スティーブ・ジョブズが語る「本当の知能」と、それを高める方法(ライフハッカー・ジャパン)
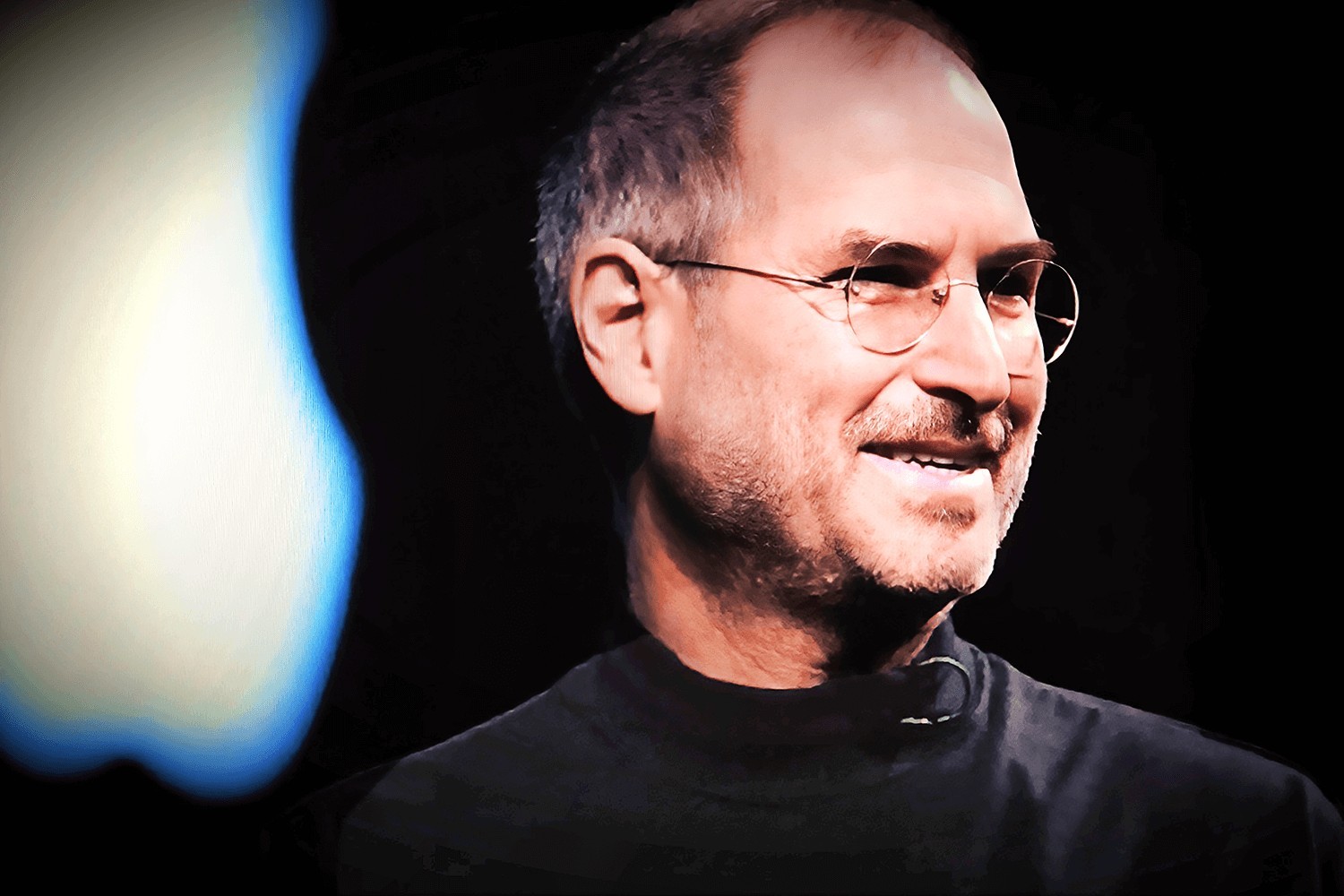
高い知能の持ち主は、ひとりで時間を過ごすことを非常に好む傾向があると、研究では示されています。 また、知能が高ければ高いほど、「自分はパターンを見抜いたり結果を予測したりする能力が高い」と信じがちだという研究結果もありますが、実際には自分が思っているほどその能力が高いわけではないこともまた、研究で示されています(自分の能力を過大評価してしまうダニング=クルーガー効果です)。 では、現代の偉人たちは「知能」というものをどのように捉えているのでしょう?
ジェフ・ベゾスは、「自分の考えを自ら変えることへの意欲こそが、知能の高さを測る最善の尺度だ」と述べています。 一方、スティーブ・ジョブズは異なる見解をもっており、知能の高さについて次のように述べていました。 知能の多くは記憶によるものです。しかし、知能のなかには、ズームアウトする(全体のなかで捉える)能力もあります。 たとえば街中にいるとしましょう。高いビルの80階に行けば、街の全体像を見ることができるでしょう。けれども、A地点からB地点までたどり着く方法を見つけようと、ばかばかしいほど小さな地図を読もうとする人もいます。一方のあなたは、全体をひと目で見渡すことができるのに。 一目瞭然の結びつきを見つけられるのは、全体像が見えているからなのです。 ジョブズにとっての知能とは、物事を結びつける力、他人がまだつなげていない点と点を結びつけることなのです。
詳しく見ていきましょう。心理学では、知能を8種類に分ける概念もありますが、ここでは、知能を2つに分けた概念に焦点を絞っていきます。 「結晶性知能(Crystallized intelligence)」は蓄積された知識、つまり、事実や数値のことです。結晶性知能が高い人は勉強が良くできます。いわゆる「ブック・スマート」と呼ばれる人たちです。 とはいえ、高度な教育を受けていても、本当の意味で必ずしも賢いとは言えない人がいます。そこで登場するのが「流動性知能(fluid intelligence)」です。 流動性知能は、新しい情報を学んで記憶し、それを使って問題を解決したり、新しいスキルを習得したりする能力を指します。すでに頭にある記憶を呼び起こして、新しい知識をもとにその記憶を修正する能力です。 流動性知能が高い人は、「ストリート・スマート」と呼ばれる人たちです。 ブック・スマートはたくさんいますし、ストリート・スマートもたくさんいます。けれども、両方を兼ね備えた人はそれほどいません。
Page 2
その理由として少なくとも言えるのは、結晶性知能を高めるプロセスと流動性知能を高めるプロセスは、根本的に異なる傾向があるということです。 特定のテーマやスキルについてもっと学ぼうとする場合、そのプロセスはいたってシンプルです。学びたい事柄を掘り下げれば掘り下げるほど、知識は増えていくでしょう。 これに対して、流動性知能を高めたい場合は、もっとハードルが上がります。何かを深く掘り下げたあとに、新しいことに取り組むという行為を何度も繰り返さなくてはならないからです。 なぜかというと、新しいことを学ぼうとすると、しばらくの間は大脳皮質の厚みが増し、大脳皮質の活動が活発化します。これはどちらも、神経細胞の結合と、習得した専門知識が増えたという証しです。 しかし、学習を開始して数週間が過ぎると、大脳皮質の厚みが減り、大脳皮質の活動も弱くなって、最終的には基準のレベルまで戻ってしまいます。 知識も、やれることも、間違いなく増えてはいきますが、その知識やスキルをいったん獲得し、理解してしまうと、脳は前ほど熱心に働く必要がなくなるのです。 だからこそ、流動性知能を高めてその水準を維持するためには、新しい経験を重ねていくしか方法はありません。 新しいことを学び、新しいことに挑戦し、絶えず自分を試し続けるしかないのです。職場でも、家でも。どこでも。 新しい経験を重ねてください。そうすれば、新しい情報やスキルが絶えず自分に流れ込むことでメリットを得られるばかりか、脳の「厚みが増した」状態が保たれ、新しい神経回路が形成され続けるでしょう。 ひいては、学び、知能を高め続けることが容易になります。
こうした話は最終的に、ジョブズが知能について語った言葉につながっていきます。 革新的なつながりを生み出し、2つの経験を結びつけようとするなら、ほかの人と同じ量の経験を積むだけでは不十分です。他人と同じなら、みんなと同じつながりしか生み出せず、革新的なものはつくり出せません。だからこそ、異なる経験を積む必要があるのです。 高い知能の持ち主についてのストーリーをあれこれ耳にするでしょう。しかし、そこから得るべきは、そうした人たちが多種多様な経験を積んでいたということです。 そして彼らは、問題を解決したり、独自の方法で窮地を切り抜けたりする際に、そうした経験を生かしていたということです。 知識が増えれば増えるほど、経験の幅が広がれば広がるほど、連合学習(associative learning)の威力を活用することができます。 連合学習とは、一見すると無関係に思える物事同士の関係を見抜き、「新しいこと」と「自分がすでに持っている知識」を関連付けるプロセスです。 簡単に言えば、「わかったぞ。『これ』は『あれ』のようなものだ」と言ったとき、あなたは連合学習を活用しています。「ちょっと待てよ。『これ』を『あれ』に応用できるかもしれない」と考えたとき、あなたは自分が学んだことを生かして、賢いつながりを生み出しているのです。