【毎日書評】論理的思考問題はこう解く。「嘘つきだらけの会議」で、たった1人の正直者を探し出すには?
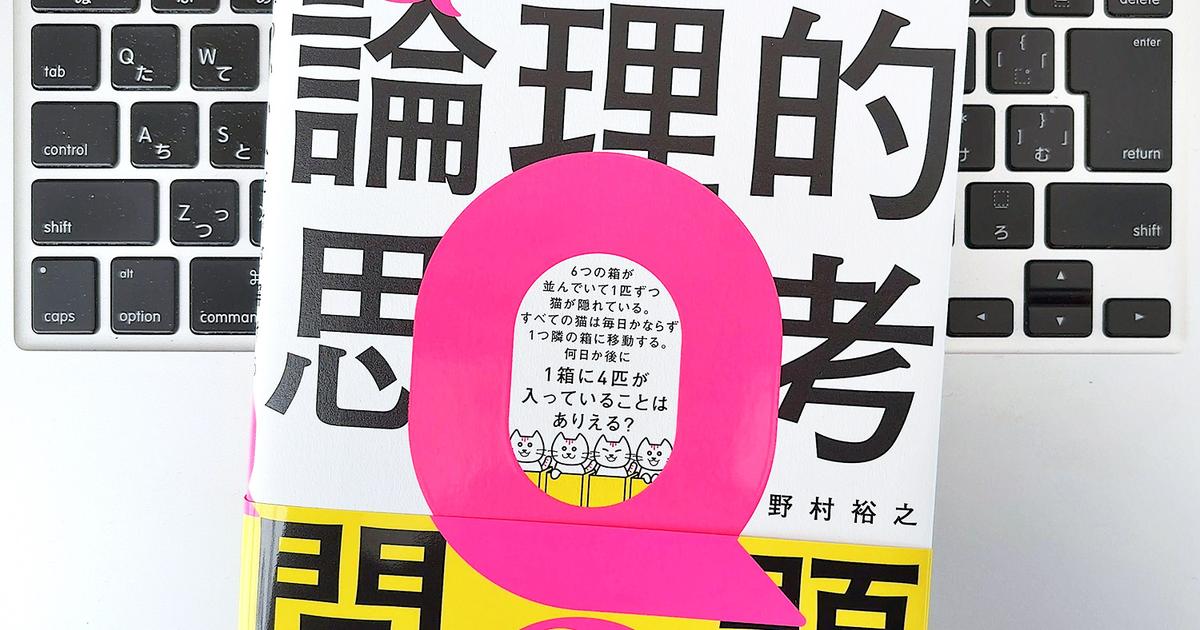
論理的思考問題とは、「特別な知識を必要とせず、問題文を読んで論理的に考えれば答えが導ける」もの。
そんな論理的思考問題を集めた『もっと!! 頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』(野村裕之 著、ダイヤモンド社)は、前著『頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』に続く新刊です。
タイトルにある「もっと!!」とは「もっと難しい」ということではなく、「もっとおもしろい」という意味だそう。もちろん前著で落選したネタを集めた「ボツ作」ではなく、世界中の文献やデータベースをあたり、新たにおもしろそうな問題を収集したものなのだとか。
その数は5000問以上に及び、そこから厳選した珠玉の問題を紹介しているのです。
問題の選定基準も前作と同じです。難しい計算や知識が必要なものや、パズルのような問題は紹介していません。「汎用性の高い思考力」、つまり「考え方の型」が身につく問題を中心に紹介しています。(「はじめに」より)
前作と同じように、簡単な問題からはじまって、次第に難しくなっていく構成。①論理的思考、②批判思考、③水平思考、④俯瞰思考、⑤多面的思考と、5つの能力が問われる論理的思考問題が紹介されているため、さまざまな思考法を身につけることができそうです。
きょうは第1章「論理的思考」のなかから、「少ない手がかりから真実を導けるか?」を抜き出してみたいと思います。
少ない情報から手がかりを得て真実を見抜く、それが論理的思考。では、わかっている事実がたったひとつだけだったとしたら? そのことに関連して紹介されているのが以下の問題です。
Q:ある会議で、参加者全員が他の全員に向かって「あなたたちは全員嘘つきだ」と言ったそう。では、この会議に正直者は何人出席しているでしょうか? なお全員、嘘つきか正直者のどちらかだそうです。
[解説]全員が自分以外の全員に向かって「嘘つきだ!」と言っている会議、地獄すぎますね……。と思っていたら、参加者のなかに正直者は何人いるか……? だいたいこういうときって「〇〇と言っている人が△人」とか、人数に関するヒントがあるものですが、この問題では皆無ですね……。これだけの情報で、本当に解けるんでしょうか?(32ページより)
明らかに手がかりの少なすぎる問題ですね。(31ページより)
ひとつずつ、可能性を決していく
が、確実にいえることがひとつだけあるようです。「『参加者全員が嘘つき』という可能性はない」ということ。もし参加者全員が嘘つきだったとしたら、「あなたたちは全員嘘つきだ」という発言は“真実”を述べていることになってしまうからです。
それでは嘘つきが真実を話していることになるため、矛盾が生じるのです。(32ページより)
もし正直者が1人なら
かくして「1人は正直者がいる」ということがわかったわけですが、その人数に関するヒントはありません。だとすれば、「もし正直者がひとりいたら?」と仮定して、とりあえず考えを進めてみることにしましょう。
ではまず、もし正直者が1人いたとしたら。
この1人を、仮にAとしましょう。
A以外の人たちは、全員嘘つきです。
その嘘つきの人たちが「あなたたちは全員嘘つきだ」と言っている。
でも実際には、Aという正直者が1人いる。
よって嘘つきの人たちの発言は、ちゃんと「嘘」になっています。
一方で、正直者であるAも「あなたたちは全員嘘つきだ」と言っている。
実際にA以外は全員嘘つきなので、この発言にも問題はないですね。(33ページより)
したがって、「正直者が1人」というパターンは、ありえそうだとわかります。(32ページより)
では、正直者が2人なら?
次に考えるのは、「正直者が2人いたとしたら」というケース。その2人を、それぞれA、Bとしましょう。
この場合、A、B以外の人たちはすべて嘘つきだということになります。その嘘つきの人たちが、「あなたたちは全員嘘つきだ」と言っているわけです。ところが実際にはA、Bと正直者が2人いるので、嘘つきの人たちの発言はちゃんと「嘘」になっています。
一方、正直者のAが「あなたたちは全員嘘つきだ」と言うと、正直者Bも嘘つきということになってしまいます。それでは、正直者であるAが嘘をついたことになるため、このパターンは成立しないのです。
これは、正直者が3人いる場合も同じ。自分以外にも正直者がいる場合、正直者の「あなたたちは全員嘘つきだ」という発言は真実ではなくなってしまうからです。(33ページより)
正解:正直者は1人だけ
自分以外の全員が嘘つきであるときのみ、正直者は「あなたたちは全員嘘つきだ」と言えます。
つまり、正直者は1人しか存在できません。(34ページより)
こんなに短い問題文でも、ちょっと考えさせられるのがおもしろいところ。ぱっと見では「具体的な人数もわからないし、答えられるわけがない」と思いがちかもしれませんが、仮定して考えてみればちゃんと答えが出るわけです。
そういう意味でこれは、思考することをすぐに放棄せず、ちゃんと考えてみることの大切さを教えてくれる問題だと著者は述べています。(34ページより)
著者が望んでいるのは、紹介されている問題について悩み、楽しんでもらうことだそう。「ちゃんと考える力」を向上させるために、チャレンジしてみるのもいいかもしれません。
>>Kindle Unlimited、500万冊以上が楽しめる読み放題を体験!
作家、書評家、音楽評論家。1962年東京都生まれ。広告代理店勤務時代に音楽ライターとなり、音楽雑誌の編集長を経て独立。「ライフハッカー・ジャパン」で書評連載を担当するようになって以降、大量の本をすばやく読む方法を発見。年間700冊以上の読書量を誇る。「東洋経済オンライン」「ニューズウィーク日本版」「サライ.jp」などのサイトでも書評を執筆するほか、「文春オンライン」「qobuz」などにもエッセイを寄稿。著書に『遅読家のための読書術』(ダイヤモンド社、のちにPHP文庫)、『書評の仕事』(ワニブックスPLUS新書)など多数。最新刊は『現代人のための読書入門 本を読むとはどういうことか』(光文社新書)。@innamix/X
Source: ダイヤモンド社



