本当の“賢さ”って? AIの時代こそ子どもに身につけさせるべき、教育のプロたちが「学力よりも重視する能力」
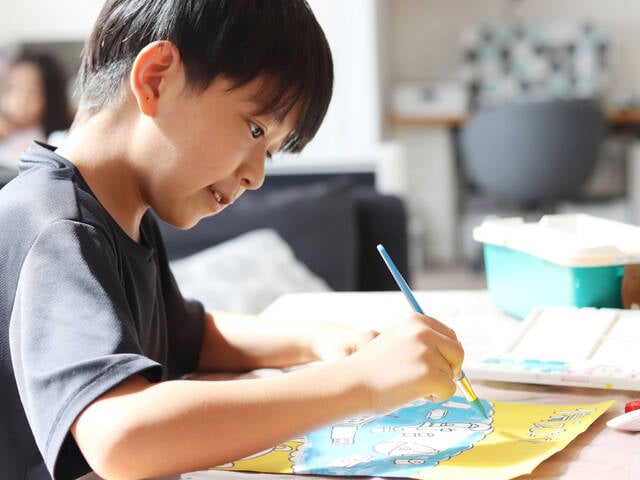
2023年に入り、対話型AIサービス「ChatGPT」が世の中に大きな衝撃を与えてからもAI技術の進歩は止まることなく、私たちの想像を超えるスピードで進化を続けています。 必ずやってくるAI時代に向けて、どんなふうに子育てを考えていけばいいのか。保護者の皆さんから、そんなニュアンスの相談を受けることも増えてきました。これまで「良い」とされてきた進学の仕方の意味合いが変わってくるのではないか。10年後、20年後には評価される能力がガラリと変わってしまうのではないか。先行きが見えないだけにぼんやりとした不安が広がります。 例えば、最近も医療の分野でX線やMRIなどの医用画像をAIで解析して診断に役立てる、画像診断支援AIの利用が拡大しているというニュースがありました。2019年に大腸を対象とした画像診断支援AIが実用化されて以来、現在では、肺や胃、咽頭、乳房、骨、目、脳などの画像診断に活用されているそうです。 こうした画像診断支援AIが腫瘍などの異常を検知する精度は、すでに人間の医師を上回っていて、膨大な過去のデータから瞬時に類似の症例を検索するなど、認知能力に優れたAIが特性を発揮。その結果を踏まえて、最終的な判断は医師が行うという、人間とAIの協働が始まっている……のだとか。こうした変化は医療分野に限らず、多くの業界で起きていて、AIの発展についてはいわゆる「シンギュラリティ(AIが人間の知能を超える転換点)」をめぐる議論も活発化しています。 AIは人間を超えるのか、それとも超えることはないのか。この問いに対する明確な答えは、まだ出ていません。現時点のあなたの考えはどうでしょうか? 子どもたちが大人になる頃、AIは脅威になっているのか、社会を支える協働のパートナーになっているのか。 私自身は、そもそも人間を超えるという定義自体が曖昧だと捉えています。子どもたちの将来を考えるときに大切なのは、どの部分でAIが人間を超え、どの部分では超えられないのかを具体的に考えていくことではないでしょうか。 データ処理や計算、パターン認識といった認知能力の面では、すでにAIが人間を上回っている分野が多く、大学入試の数学の試験では高校生の受験生よりもAIのほうが平均的に高得点を出しているという研究データもあります。 しかし、AIには決定的に欠けている部分があります。それは「肉体」と「感情」です。 カメラと画像処理技術の発達によって、人間の表情や体温、血圧の変化などから相手の感情を予測するAIはすでに存在していますが、それでも心の機微までは察することができません。目の前の人の機嫌がいいのか、悪いのか。悩み事があるのか、そうでもないのか。いいことがあったのか、どうなのか。AI自身が温かみのある触れ合いや他者への共感、喜びや悲しみといった感情そのものを持つことはないはずです。 ここにAIと協働する将来を考えるときの大きなヒントがあります。 例えば、私たちの学童保育の現場にAIロボットが子どもたちの遊び相手として導入されたとしましょう。最初は大人気になると思いますが、すぐに飽きられてしまう様子が容易に想像できます。なぜなら、子どもたちが求めているのは、一緒に喜んでくれたり、笑ってくれたり、時にはってくれたり、一人ひとりの気持ちをみ取ろうとしながら適切な対応をしてくれる遊び相手だからです。 また、スポーツの世界を見ても同じことが言えます。AIロボットは人間のアスリート以上の身体能力を発揮できるかもしれません。でも、私たちが観戦者として心を揺さぶられるのは、限界に挑戦する人間の姿であり、障がいを乗り越えて輝くパラアスリートの活躍です。eスポーツにワクワクするのも、競技者が人間だからこそではないでしょうか。 そこに人間ならではの価値があるのです。 近年の学習指導要領でも「非認知能力」の育成が重視されています。これは予期せぬ変化が起きるVUCA〈変動性(Volatility)、不確実性(Uncertainty)、複雑性(Complexity)、曖昧性(Ambiguity)の頭文字をとった用語で、未来が予測しにくい状況を指す〉の時代に対応するため、自ら考え行動する力、数値化できない、目に見えない人間らしい力を高めていくことが、子どもたちの将来に必要となるからです。 恋をすること、家族を持つこと、他者と深くつながること。こうした幸せも、人間にしか味わえません。だからこそ、これからのAI時代を生きる子どもたちには、人間らしい感性や創造性、コミュニケーション能力を磨いていってもらいたい。非認知能力の重要性はこの先ますます増していき、人間力はその子が自分らしい人生を切り開いていくための土台となるのです。 次回は、教育の世界で非認知能力が注目されるようになったきっかけについてご紹介します。
株式会社東急キッズベースキャンプ代表取締役社長。一般社団法人キッズコーチ協会代表理事。1965年東京都目黒区生まれ。中央大学卒業。輸入雑貨事業や自然食事業等を経て、2003年株式会社エムアウトに入社。心理学に関わる事業開発を経験し、「小1の壁」の問題解決と非認知能力の教育を志し、2006年キッズベースキャンプを創業。民間学童保育のパイオニアとして業界を牽引。2008年12月には東急グループ入りし、東急グループの子育て支援事業の中核企業としての展開を開始。一般社団法人民間学童保育協会、東京都学童保育協会で理事を務める。保育士資格保有。
with online



