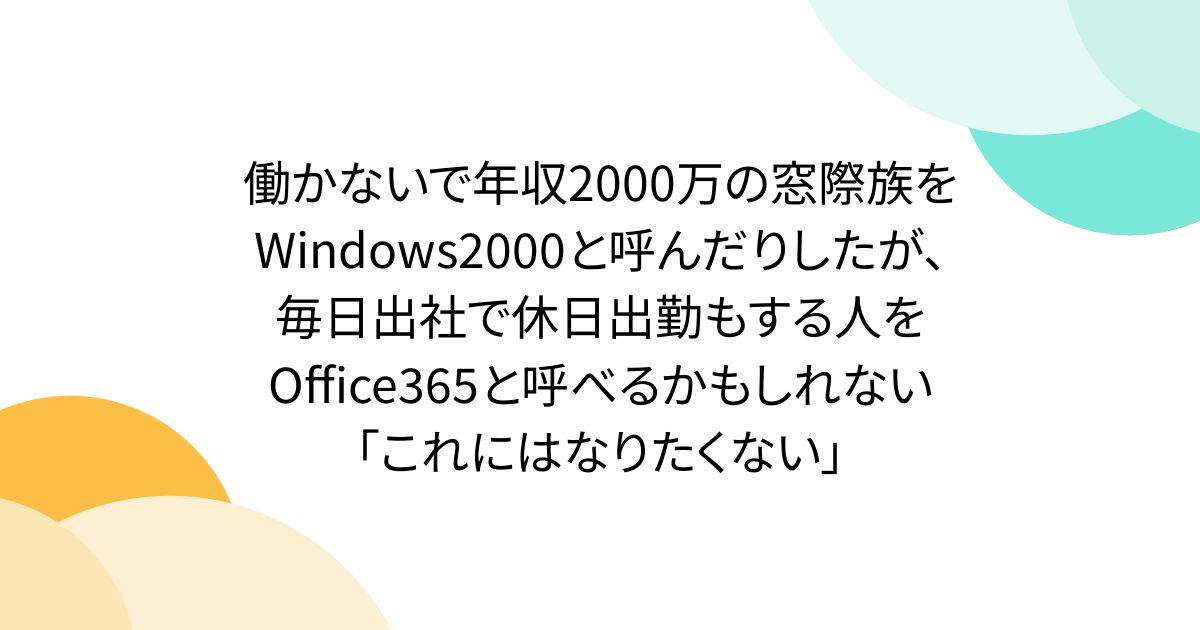Windows 95がもたらしたものとは何か?改めて30年前を振り返る(前編)
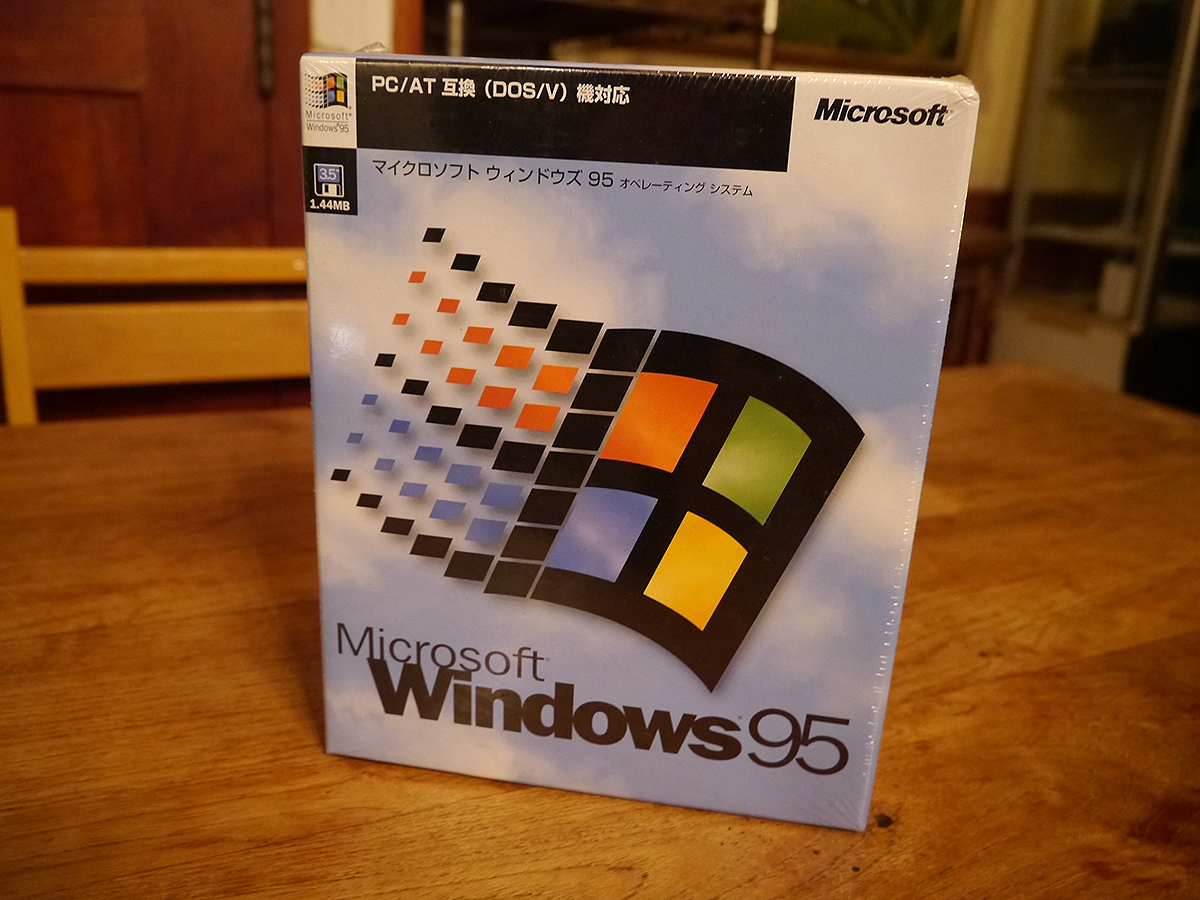
1995年11月23日、日本でWindows 95が発売された。今から30年前のことになるが、1995年を振り返るTV番組などには、秋葉原での深夜発売の様子が紹介されるなど、大きなインパクトを与える出来事となっている。
PCの世界においても、PCに関連するマーケティング施策がマスマーケティングへと転換したのがWindows 95であり、技術面、施策面から見ても大きな転換点となっている。
今回、さまざまな関係者に改めて取材を行ない、Windows 95発売前後を振り返ってみる。
Windows 95の発売時を振り返る前提として、当時のPC市場を振り返ってみたい。
電子情報技術産業協会の統計によれば、1994年度(1994年4月~1995年3月)の国内のPC出荷台数は334万8,000台。1993年度は対前年同期比26%増、1994年度には29%増と大きく伸張している時期だった。
「大きく伸張しているPC市場の勢いを落とすな!」――当時のマイクロソフト日本法人の社長だった成毛真氏から、そうハッパをかけられたと話すのは、Windows 95のプロダクトマーケティングチームの一員だった御代茂樹氏。
「米国ではWindows 3.1のあとに、1993年11月にWindows 3.11というバージョンが発売されている。日本でも発売するか、否かという議論があったが、発売せずにWindows 95まで待つという選択肢がとられた。Windows 95の発売までの期間が長くなることから、盛り上がっている勢いを消すなという檄だった」。
市場の盛り上がりに拍車をかけるために、プロダクトマーケティングチームが実施したのが雑誌との連携だった。現在のようにインターネットが普及していない時代である。雑誌に付録ソフトをつけることで、PCユーザーにWindowsの存在をアピールすることを狙ったのだ。
この雑誌への付録ソフトについては、雑誌側でも歓迎の声があがった。当時、IDGで「Computer World」「Windows World」の2誌の編集長だった松浦義幹氏は、「Windows Worldを刊行したのは、確か1995年の4月だったと記憶している。Windowsというタイトルの雑誌は、アスキー、ソフトバンクが出版していたものに続き3誌目となった。当時は付録のCD-ROMに入れたソフトの内容によって売れ行きが左右されるような時代だった」と当時を振り返る。
後日譚となるが、Windowsを冠した雑誌発行が3番目となったことに反省した松浦氏は、法人向けWindowsである「Windows NT」を雑誌タイトルに入れた「Windows NT World」を他社に先んじて刊行した。「Windows NTに関してはその後他社から雑誌が刊行され、先行する立場となることができた」という。
各社が率先して新しい雑誌を刊行する――これは当時、雑誌が大きな影響力と勢いを持っていたことを示すエピソードだといえる。
また、松浦氏は、「Windowsの勢いを感じたのは、雑誌とともにイベント開催時だった」とも話す。当時IDGでは雑誌や書籍事業とともに、イベント事業を展開していた。アップルのイベントとして有名な「MacWorld Expo」もIDGが開催したイベントだ。
Windowsの盛り上がりを受け、松浦氏は「WindowsWorld Expo」を日本で開催する。「最初の開催は、Windows 95の前、Windows 3.1発売後だった。これが大変盛り上がり、多くの来場者を集めた。開催したのは幕張メッセだったが、1つのホールへの入場者数が当時の最高記録となったほど盛り上がった。これは間違いなくWindows 95は成功するだろうと推測できた」。
この成功を受け、IDGではそれまで雑誌をユーザーへの直販するというモデルを、Windows Worldでは書店販売することに変更した。
「システムの安定という意味でも、Windows 95登場を待っていたユーザーは多かったのではないか」と話すのはWindows 95のプロダクトマーケティング部門の責任者だった佐藤一志氏。
「Windows 3.1は、MS-DOS上でWindowsを動かさなければいけなかったために、コンフィグ設定をしなければならない。拡張メモリも必要となる。CPU側はIntelから32bit CPUが出てきていたのにもかかわらず、Windows 3.1は32bit対応していない。それに対し、Windows 95はネイティブで32bitに対応し、拡張メモリの必要がない。安定して動作するWindowsとして期待するユーザーも多かったのではないか」。
こうしたユーザーの期待を受け、開発にあたるマイクロソフト日本法人は急ピッチで開発を進めていた。Microsoftは、Windows 95で開発体制を変更している。世界各国版をMicrosoft本社で一緒に開発する体制へと変更している。
Windows 3.1までは米国本社で米国版完成後、日本語版の開発が行なわれるスタイルだった。そのため、米国では1992年5月にリリースされたWindows 3.1の日本語版は、それから1年後の1993年5月と1年遅れで発売された。Windows 95に関しては、米国での発売から90日で発売することが明言された。この開発スケジュールに合わせた発売を行なうために開発チームは必死で開発を進めていった。
ちなみに、日本語版はPC/ATアーキテクチャのものと、NECのPC-9800アーキテクチャのものと2種類が開発された。日本では、当初は各メーカーが独自アーキテクチャのPCを発売していたが、PC/ATアーキテクチャのPC上で特別なハードウェアを必要とせず日本語が動作するDOS/Vが発表されて以降、独自アーキテクチャからPC/ATアーキテクチャの、通称「DOS/V PC」へと切り替えるPCメーカーが続出した。
Windows 95が発売になる頃には、NEC以外のメーカーはDOS/V PCを販売。NECのみがPC-9800という独自アーキテクチャのPCを販売していたが、一時期は5割以上という高いシェアを確保していたために、PC-9800版のWindows 95の開発が行なわれたのだ。
今回、当時のマイクロソフト関係者に取材を行なっていると、当時、NECでPC事業に携わっていた幹部の名前が出てきた。マイクロソフトとNECのスタッフが密接に連携し、ビジネスを行なっていた証左だといえる。
当時のNECの勢いを感じさせる資料がPC Watchで大河原克行氏が連載した「ニュースリリースで振り返る、時代を築いたPCたち」の中に残っている。この連載の中の【Microsoft編 Windows 3.0~95】の中に掲載されている、NECが1995年11月21日に発表したニュースリリースである。
この中に次のような説明がある。
「NECでは、Windows 95の先進性、重要性に早くから注目し、日本のユーザーがいち早く利用できるようマイクロソフトとの共同開発に取り組みました。そのため、日本語化の仕様検討が始まった2年半前から開発に参画してまいりました。この結果、英語版出荷から約3カ月で日本語対応NEC版の出荷を実現しました」。
これを読むと、Windows 95に対するNECの強い自負を感じさせる。
日本語版開発とともに、日本では周辺機器メーカーやソフトメーカーとの連携協議も進められていた。
Windows 95以前は、周辺機器のデバイスドライバは各周辺機器メーカーが独自に開発していたのだが、Windows 95からはMicrosoft自身がデバイスドライバを開発することになった。それまでとは大きくルールが異なる仕様変更となることから、周辺機器メーカーへの協力呼びかけが行なわれたのだ。
「大きな変更となるので、日本の周辺機器メーカーさんに対しては、マイクロソフト自身がWindows 95パッケージを積極的に販売し、対応周辺機器の売上増にもつながるためと説明し、アメリカではこれだけ実績も出ていますといったことを示しながら、納得し、協力してもらうためのお願いをしていった」とWindows 95のプロダクトマーケティング部門の責任者だった佐藤一志氏は振り返る。
佐藤氏はWindows 95のプロダクトマーケティング部門の責任者であると同時に、「Office 95」のプロダクトマーケティング責任者を兼務していた。現在であれば、WindowsとOfficeの責任者を兼務するというのは考えられないことだ。当時はどうだったのだろうか?
「今でも覚えているが、ビル・ゲイツが日本に来た際、成毛さんが、『彼はWindows 95とOfficeの2つのプロダクトマーケティング責任者だ』と紹介したら、『クレイジーだ!』という答えが返ってきた」と佐藤氏は笑いながら振り返った。
当時、日本ではそこまでOfficeが大きなプロダクトになっていなかったこと、佐藤氏が成毛氏からの信頼が厚かったことから、両製品のプロダクトマーケティング責任者を兼務することになったのかもしれない。
OfficeはWindows 95以前から発売されていたものの、現在のように定番ソフトとして定着しているとはいえない状況だった。特に「Word」の使い勝手が悪いという声が多くあがっていたことから、佐藤氏は日本では定番ワープロソフトだった「一太郎」を開発するジャストシステムへと交渉に訪れたことがあったという。
「当時の開発部門の責任者だった浮川初子さん、福良伴昭さんに会って、ATOKをOffice用IMEとしてバンドルさせてくれないか?という交渉をしたこともあった。残念ながら、当時の社長だった浮川和宣さんに却下されてしまったが」。
こうした交渉を行ないながら、Windows 95と同時にOffice 95の発売準備が進められた。
「成毛さんから、OfficeはWindows 95の何割くらいの販売率を目指すのか?と訊かれ、3割くらいかと答えたところ、少なすぎる!と厳しいことばをもらった覚えがある」と佐藤氏は苦笑いする。通常であればOSの3割というのは決して少なくない割合な気もするが、Office 95はもっと高い目標を目指すべき、大きな製品だという認識があったということだろう。
日本語版の開発が進むと同時に、マーケティングや宣伝のための活動も行なわれていった。
米国ではローリングストーンズの「スタート・ミー・アップ」を使ったTVコマーシャルが放映された。スタート・ミー・アップは、1981年にリリースされた曲で、STARTボタンが1つの特徴となっているWindows 95と合わせて採用したのではないかと思われる。
このCMの日本版も製作された。Windows 95のプロダクトマーケティングに所属していた御代茂樹氏は、「米国で流れていたCMの映像をそのまま使うのではなく、日本人を起用した、日本の映像を使いたいと考えた」と話す。当時のCMを見ると、その言葉通り、日本のオフィスで仕事をする人や子ども達などの映像が使われている。
米国では1995年8月24日、Windows 95が発売され、日本と同様、深夜発売も行なわれた。当時開催されたプレスツアーに参加し、米国での深夜発売、さらに発売イベントにも参加したのが、「山田祥平のRe:config.sys」を連載している山田祥平氏だ。
山田氏は、「ワシントン州のカークランドにあったComp USAでの深夜発売に参加した。日本同様、発売は盛り上がった。おそらく、日本での深夜発売はこの時の米国の深夜発売を参考にしたところがあったのではないか」と振り返る。
発売当日の様子などは、山田氏は自身の連載で複数回紹介している。
2004年5月21日の回では、Windows 95の発売当日の米国の新聞にAppleが出した全面広告を紹介している。今ではあまりピンとこないが、GUIを搭載したOS同士の競争という側面があったからこそ、AppleはWindowsを皮肉るような広告を出したのだろう。
日本での発売は、米国から遅れること90日後、1995年11月23日発売と決まった。
「日本での新作ソフト発売は金曜日というのが通例だったが、イベント開催などを考慮し、11月23日、木曜日とすることとなった」と話すのは、当時マイクロソフトの営業部門に所属していた小川秀人氏。11月23日は祝日で休日となるため、深夜発売を行なっても翌日が休日で、深夜販売に参加してもらうにも負担が少ない。さらに、23日の昼間に販促イベントを行なうにあたっても参加してもらいやすい。
ちなみに、Windows 95の深夜発売は、「マイクロソフトが実施した」と紹介されることが多いが、実際には店舗側が実施したものだ。小川氏は、「店舗側から深夜発売を実施したいという声があがり、マイクロソフトは店舗が実施する深夜発売を支援するという立場だった」と説明する。
当時、マイクロソフトで広報やPRを担当していた江崎真理子氏は、「我々(マイクロソフト)自身が開催したのは、発売日の昼間から秋葉原で開催したイベントだった」と話す。
「Windows 95をアピールするためのイベントは、当初は国技館で開催できないかなど検討したが、当時は駐車場に使っていた広いスペースがあり、PCとも関連が深い秋葉原で開催することが決まった」という。
店舗主導で始まったWindows 95深夜発売は、どれくらいの参加者があるのか、どんなイベントになるのかなど誰にも分からない状況だった。
「当時、夜になると開いているお店も少なく、人がほとんどいなくなる秋葉原だが、どんどん人が降りてくるという報告が入った」とプロダクトマーケティング部門の御代氏は話す。誰も予想もしていなかった盛り上がりとなったWindows 95の深夜発売が始まった。