脂肪肝・脂肪肝炎の名称が変更に やせ型女性も更年期以降は注意
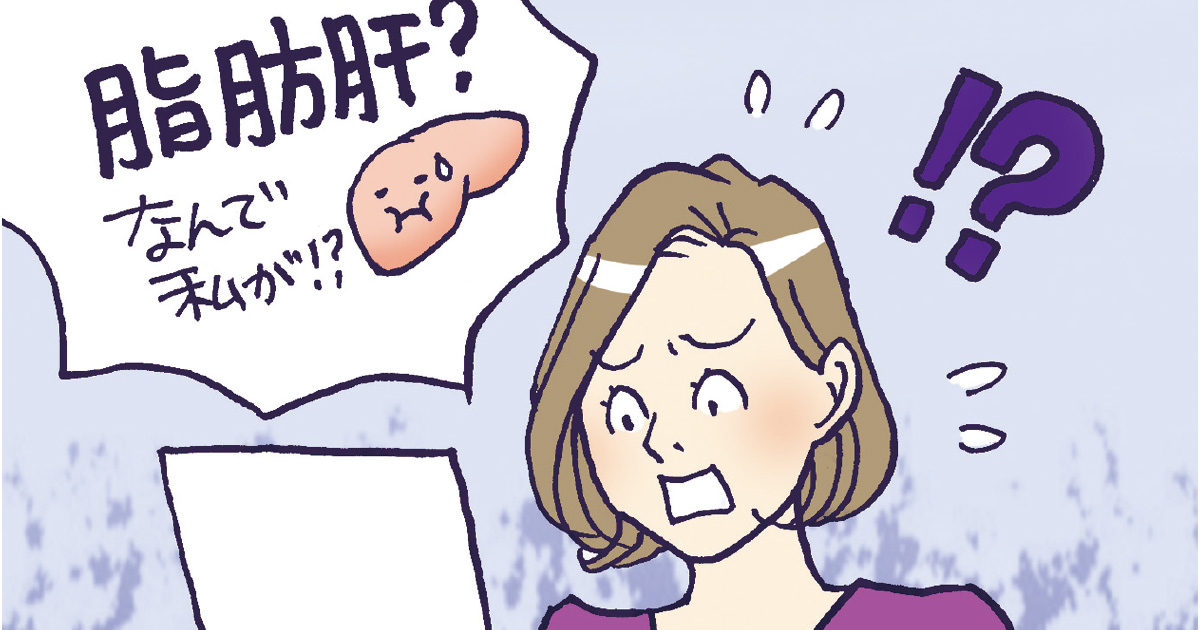
中高年の男性に多いと思われがちな脂肪肝。実は女性の場合も更年期以降に増えやすく、一見普通体形でも若いころにやせ型だったという人も脂肪肝になるリスクがあるようです。脂肪肝になりやすいタイプやその影響について見ていきましょう。また、国内では2024年に発表になった脂肪性肝疾患の新名称についても紹介します。
(イラスト:進藤やす子)
Check! こんな人は脂肪肝になりやすいかも
脂肪肝のほとんどは悪い生活習慣によるもので、大きく肥満を背景とする代謝異常と多飲酒の2つの要因がある。前者は今の体重よりも若いころからの“増え幅”が問題。太っていなくても高血糖などメタボを指摘されたら要注意。
肝臓には脂肪がたまりやすい
脂肪肝とは肝臓に脂肪がたまりすぎた状態のこと。肝臓は右のわき腹に位置する体内最大の臓器で約3000億個もの肝細胞で成り立っている。その働きは主に「栄養の代謝」「胆汁の生成」「毒素の解毒」で、私たちが生きていくには欠かせない臓器だ。
肝臓は体内最大の臓器。肝細胞から酵素が分泌され「栄養の代謝」「胆汁の生成」「毒素の解毒」という3つの重要な働きを担う。余ったエネルギーが中性脂肪として肝臓に一時的に蓄えられ、必要に応じて放出されるが、中性脂肪が増えすぎると脂肪肝に。(イラスト:PIXTA)
私たちが食事でとった栄養は主に肝臓で代謝されエネルギーが作られるが、作るエネルギーが消費する分よりも多い場合はその余剰分が中性脂肪に変換されて肝臓に一時的に蓄えられ、必要に応じて放出される。中性脂肪が肝細胞全体の20~30%を超えた状態になると脂肪肝と診断され、その理由のほとんどは生活習慣が背景に。その内訳は大きく「アルコールによるもの」と「肥満を背景とした代謝異常によるもの」「両方混在しているもの」に分けられる。
-
- 正しい知識で熱中症を防ぐ! 水分補給の仕方は? 危険な場合は?
-
毎年、夏の時期が訪れると、過酷な暑さと共に増えるのが熱中症だ。高温多湿になると、体内の水分が失われて脱水症が起こりやすくなり、脱水症は熱中症を引き起こす。夏は命を守る戦いの季節。今回は熱中症を防ぐための基本的な知識から対策まで紹介する。
-
- 糖尿病になるまでの「3ステップ」 その対策はどうすればいい?
-
日本に約550万人の患者がいると言われている糖尿病。自分は大丈夫だろうかと気になる人もいるのではないか。その糖尿病に関するトピックとして、「体の血糖コントロールの仕組み」「糖尿病のタイプ」や「血糖値が上がりにくい食べ方」「予防・対策のための運動」について見ていく。
-
- 誰もがなる「白内障」、失明原因1位「緑内障」 早期発見のカギ
-
年を重ねたら誰もが必ずなる病気で、眼鏡をかけても矯正できない白内障。日本人の中途失明原因の1位であり、40歳以上の20人に1人がかかるという緑内障。視機能低下を進ませるこれら2つは、一体どうしたら早期発見でき、どんな治療をするのでしょうか。過去の人気記事を基に、多くの人が直面する白内障・緑内障との付き合い方を見ていきましょう。
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 2
働く女性にとって、自分の体調管理は仕事と同じくらい大切です。日経ヘルスにて好評連載中の「女性のお悩み相談室」から、女性特有の病気について、予防法や対処法を学びましょう。今日も輝くあなたの「転ばぬ先の杖」になること請け合いです!
有料会員になると、鍵つき記事が全て読める&医療専門家に電話相談や名医紹介も!
-
- 正しい知識で熱中症を防ぐ! 水分補給の仕方は? 危険な場合は?
-
毎年、夏の時期が訪れると、過酷な暑さと共に増えるのが熱中症だ。高温多湿になると、体内の水分が失われて脱水症が起こりやすくなり、脱水症は熱中症を引き起こす。夏は命を守る戦いの季節。今回は熱中症を防ぐための基本的な知識から対策まで紹介する。
-
- 糖尿病になるまでの「3ステップ」 その対策はどうすればいい?
-
日本に約550万人の患者がいると言われている糖尿病。自分は大丈夫だろうかと気になる人もいるのではないか。その糖尿病に関するトピックとして、「体の血糖コントロールの仕組み」「糖尿病のタイプ」や「血糖値が上がりにくい食べ方」「予防・対策のための運動」について見ていく。
-
- 誰もがなる「白内障」、失明原因1位「緑内障」 早期発見のカギ
-
年を重ねたら誰もが必ずなる病気で、眼鏡をかけても矯正できない白内障。日本人の中途失明原因の1位であり、40歳以上の20人に1人がかかるという緑内障。視機能低下を進ませるこれら2つは、一体どうしたら早期発見でき、どんな治療をするのでしょうか。過去の人気記事を基に、多くの人が直面する白内障・緑内障との付き合い方を見ていきましょう。
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 3
働く女性にとって、自分の体調管理は仕事と同じくらい大切です。日経ヘルスにて好評連載中の「女性のお悩み相談室」から、女性特有の病気について、予防法や対処法を学びましょう。今日も輝くあなたの「転ばぬ先の杖」になること請け合いです!
有料会員になると、鍵つき記事が全て読める&医療専門家に電話相談や名医紹介も!
-
- 正しい知識で熱中症を防ぐ! 水分補給の仕方は? 危険な場合は?
-
毎年、夏の時期が訪れると、過酷な暑さと共に増えるのが熱中症だ。高温多湿になると、体内の水分が失われて脱水症が起こりやすくなり、脱水症は熱中症を引き起こす。夏は命を守る戦いの季節。今回は熱中症を防ぐための基本的な知識から対策まで紹介する。
-
- 糖尿病になるまでの「3ステップ」 その対策はどうすればいい?
-
日本に約550万人の患者がいると言われている糖尿病。自分は大丈夫だろうかと気になる人もいるのではないか。その糖尿病に関するトピックとして、「体の血糖コントロールの仕組み」「糖尿病のタイプ」や「血糖値が上がりにくい食べ方」「予防・対策のための運動」について見ていく。
-
- 誰もがなる「白内障」、失明原因1位「緑内障」 早期発見のカギ
-
年を重ねたら誰もが必ずなる病気で、眼鏡をかけても矯正できない白内障。日本人の中途失明原因の1位であり、40歳以上の20人に1人がかかるという緑内障。視機能低下を進ませるこれら2つは、一体どうしたら早期発見でき、どんな治療をするのでしょうか。過去の人気記事を基に、多くの人が直面する白内障・緑内障との付き合い方を見ていきましょう。
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 4
健康・医療に関するホット・トピックスをお伝えします。
有料会員になると、鍵つき記事が全て読める&医療専門家に電話相談や名医紹介も!
-
- 正しい知識で熱中症を防ぐ! 水分補給の仕方は? 危険な場合は?
-
毎年、夏の時期が訪れると、過酷な暑さと共に増えるのが熱中症だ。高温多湿になると、体内の水分が失われて脱水症が起こりやすくなり、脱水症は熱中症を引き起こす。夏は命を守る戦いの季節。今回は熱中症を防ぐための基本的な知識から対策まで紹介する。
-
- 糖尿病になるまでの「3ステップ」 その対策はどうすればいい?
-
日本に約550万人の患者がいると言われている糖尿病。自分は大丈夫だろうかと気になる人もいるのではないか。その糖尿病に関するトピックとして、「体の血糖コントロールの仕組み」「糖尿病のタイプ」や「血糖値が上がりにくい食べ方」「予防・対策のための運動」について見ていく。
-
- 誰もがなる「白内障」、失明原因1位「緑内障」 早期発見のカギ
-
年を重ねたら誰もが必ずなる病気で、眼鏡をかけても矯正できない白内障。日本人の中途失明原因の1位であり、40歳以上の20人に1人がかかるという緑内障。視機能低下を進ませるこれら2つは、一体どうしたら早期発見でき、どんな治療をするのでしょうか。過去の人気記事を基に、多くの人が直面する白内障・緑内障との付き合い方を見ていきましょう。
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 5
人生100年時代といわれる昨今、年齢を重ねても生涯現役で仕事をしたり、自立した生活を送ったりするためには、身体活動の基盤となる「筋肉」を維持することが欠かせない。特に、加齢によって衰えやすい筋肉は、意識的に鍛える必要がある。本特集では、「いくつになっても動けるカラダ」をつくるうえで必要な衰えやすい部位の筋力トレーニングを紹介する。
町田修一(まちだ しゅういち)氏 順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科 教授
有料会員になると、鍵つき記事が全て読める&医療専門家に電話相談や名医紹介も!
-
- 正しい知識で熱中症を防ぐ! 水分補給の仕方は? 危険な場合は?
-
毎年、夏の時期が訪れると、過酷な暑さと共に増えるのが熱中症だ。高温多湿になると、体内の水分が失われて脱水症が起こりやすくなり、脱水症は熱中症を引き起こす。夏は命を守る戦いの季節。今回は熱中症を防ぐための基本的な知識から対策まで紹介する。
-
- 糖尿病になるまでの「3ステップ」 その対策はどうすればいい?
-
日本に約550万人の患者がいると言われている糖尿病。自分は大丈夫だろうかと気になる人もいるのではないか。その糖尿病に関するトピックとして、「体の血糖コントロールの仕組み」「糖尿病のタイプ」や「血糖値が上がりにくい食べ方」「予防・対策のための運動」について見ていく。
-
- 誰もがなる「白内障」、失明原因1位「緑内障」 早期発見のカギ
-
年を重ねたら誰もが必ずなる病気で、眼鏡をかけても矯正できない白内障。日本人の中途失明原因の1位であり、40歳以上の20人に1人がかかるという緑内障。視機能低下を進ませるこれら2つは、一体どうしたら早期発見でき、どんな治療をするのでしょうか。過去の人気記事を基に、多くの人が直面する白内障・緑内障との付き合い方を見ていきましょう。
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 6
「腰が痛い…。腰痛とはかれこれ十数年の付き合いです」――。腰を押さえながら、腰痛の悩みを吐露する人は少なくない。痛みが生じ、仕事や生活に支障が出ている人もいる。「どうにかしたい!」というのが、腰痛持ちの共通した願いだろう。そこで本特集は、そんな腰痛を「どうにかする」方法を紹介していく。解説してくれるのは、「腰痛には必ず原因があり、治せます」と心強い言葉をくれる徳島大学病院病院長・徳島大学大学院医歯薬学研究部運動機能外科学教授の西良浩一氏だ。放っておくと危険な腰痛、痛みの原因を特定するセルフ診断、主な8つの腰痛の特徴や治療法、腰痛を自分で治す運動療法などを学び、腰痛対策を万全にしよう。
西良浩一(さいりょう こういち)氏 徳島大学病院 病院長、徳島大学大学院医歯薬学研究部運動機能外科学 教授
有料会員になると、鍵つき記事が全て読める&医療専門家に電話相談や名医紹介も!
-
- 正しい知識で熱中症を防ぐ! 水分補給の仕方は? 危険な場合は?
-
毎年、夏の時期が訪れると、過酷な暑さと共に増えるのが熱中症だ。高温多湿になると、体内の水分が失われて脱水症が起こりやすくなり、脱水症は熱中症を引き起こす。夏は命を守る戦いの季節。今回は熱中症を防ぐための基本的な知識から対策まで紹介する。
-
- 糖尿病になるまでの「3ステップ」 その対策はどうすればいい?
-
日本に約550万人の患者がいると言われている糖尿病。自分は大丈夫だろうかと気になる人もいるのではないか。その糖尿病に関するトピックとして、「体の血糖コントロールの仕組み」「糖尿病のタイプ」や「血糖値が上がりにくい食べ方」「予防・対策のための運動」について見ていく。
-
- 誰もがなる「白内障」、失明原因1位「緑内障」 早期発見のカギ
-
年を重ねたら誰もが必ずなる病気で、眼鏡をかけても矯正できない白内障。日本人の中途失明原因の1位であり、40歳以上の20人に1人がかかるという緑内障。視機能低下を進ませるこれら2つは、一体どうしたら早期発見でき、どんな治療をするのでしょうか。過去の人気記事を基に、多くの人が直面する白内障・緑内障との付き合い方を見ていきましょう。
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 7
日経Goodayでは日々、新しい健康・医療情報をお届けしています。その中で、読者のみなさまが今、最も気になっているテーマ、例えば、「大腸がん」「脂肪肝」「痛風・尿酸値」「男性ホルモン」などに関する多数の記事の“エッセンス”をすばやく知りたい――。そんなニーズにお答えする新サービスを開始します。
それが「テーマ別特集」です。毎月、読者のみなさまの関心が高かったテーマをチョイスし、特に好評だった記事のポイントを編集部でピックアップしてお届けします。そのテーマ、ジャンルについて知っておくべきことが、この記事を読むだけですべて把握できます。さらに、そのテーマに関する記事一覧もご用意しました。ご活用ください。
有料会員になると、鍵つき記事が全て読める&医療専門家に電話相談や名医紹介も!
-
- 正しい知識で熱中症を防ぐ! 水分補給の仕方は? 危険な場合は?
-
毎年、夏の時期が訪れると、過酷な暑さと共に増えるのが熱中症だ。高温多湿になると、体内の水分が失われて脱水症が起こりやすくなり、脱水症は熱中症を引き起こす。夏は命を守る戦いの季節。今回は熱中症を防ぐための基本的な知識から対策まで紹介する。
-
- 糖尿病になるまでの「3ステップ」 その対策はどうすればいい?
-
日本に約550万人の患者がいると言われている糖尿病。自分は大丈夫だろうかと気になる人もいるのではないか。その糖尿病に関するトピックとして、「体の血糖コントロールの仕組み」「糖尿病のタイプ」や「血糖値が上がりにくい食べ方」「予防・対策のための運動」について見ていく。
-
- 誰もがなる「白内障」、失明原因1位「緑内障」 早期発見のカギ
-
年を重ねたら誰もが必ずなる病気で、眼鏡をかけても矯正できない白内障。日本人の中途失明原因の1位であり、40歳以上の20人に1人がかかるという緑内障。視機能低下を進ませるこれら2つは、一体どうしたら早期発見でき、どんな治療をするのでしょうか。過去の人気記事を基に、多くの人が直面する白内障・緑内障との付き合い方を見ていきましょう。
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 8
生活習慣病の中でも日本に約550万人の患者がいると言われている糖尿病。失明、心臓病、腎不全、足の切断といった重篤な症状につながることがあるため、自分は大丈夫だろうかと気になる人もいるのではないか。今回、その糖尿病に関するトピックとして、「体の血糖コントロールの仕組み」「糖尿病のタイプ」や「血糖値が上がりにくい食べ方」「予防・対策のための運動」について見ていく。
テーマ別特集「糖尿病」 この記事の主な内容 内臓脂肪が増えるとインスリンが効きにくくなる 糖尿病には3つのステップがある 普通に1人前を食べただけなのに、食べ過ぎに? 血糖値を上げにくくする食べ方のコツ 糖尿病など生活習慣病の予防・対策にウォーキング! まずは、糖尿病の指標となる血糖値(*1)とそのコントロールの仕組みについて、大阪大学大学院医学系研究科 公衆衛生学 特任准教授の野口緑氏に聞いた。内臓脂肪が増えるとインスリンが効きにくくなる
私たちの体の血糖コントロールの仕組みはどうなっているのだろうか。すい臓のβ細胞から分泌されるインスリンは「血糖値を下げるホルモン」というイメージがあるかもしれないが、このインスリンは脳に必要なブドウ糖を維持するため、「血糖をコントロールするためのホルモン」だ。食事をしていない就寝中などは、血糖が下がってくるが、そのような時には肝臓に蓄えておいたブドウ糖の塊(グリコーゲン)を分解して血液中に放出して、血糖値を一定にしておくのもインスリンの仕事なのだ。
したがって、食事をとっていない時間帯も含めて1日中一定量が分泌されている。これを「基礎分泌」という。一方、食事で血糖値が上がったときは大量のインスリンが分泌されて、余分な糖を肝臓や脂肪細胞などに取り込むように働き、血糖値を下げる。この時のインスリン分泌は「追加分泌」と呼ばれている。
大量に分泌されたインスリンは、血液中の糖を中性脂肪に置き換えて脂肪細胞に取り込む。体重が増えて太る人は、インスリンがすごく出ているということ。ところが、メタボになって内臓脂肪が増えると、脂肪細胞から分泌されるTNF-αなどの悪玉サイトカイン(生理活性物質)によって、インスリン作用が落ちる状態(インスリン抵抗性)が生じる。
すると、十分なインスリンは出ているのに、血糖値を下げるため、さらにインスリン分泌をしようとする。その結果、血糖はどんどん脂肪細胞に取り込まれ、結果としてより内臓脂肪が蓄積するという悪循環に陥るという。これを長期間にわたって繰り返していると、そのうちに、すい臓のβ細胞が疲弊して、インスリン分泌のタイミングが遅れるようになるとともに、分泌量も減っていくのだ。
-
- 正しい知識で熱中症を防ぐ! 水分補給の仕方は? 危険な場合は?
-
毎年、夏の時期が訪れると、過酷な暑さと共に増えるのが熱中症だ。高温多湿になると、体内の水分が失われて脱水症が起こりやすくなり、脱水症は熱中症を引き起こす。夏は命を守る戦いの季節。今回は熱中症を防ぐための基本的な知識から対策まで紹介する。
-
- 糖尿病になるまでの「3ステップ」 その対策はどうすればいい?
-
日本に約550万人の患者がいると言われている糖尿病。自分は大丈夫だろうかと気になる人もいるのではないか。その糖尿病に関するトピックとして、「体の血糖コントロールの仕組み」「糖尿病のタイプ」や「血糖値が上がりにくい食べ方」「予防・対策のための運動」について見ていく。
-
- 誰もがなる「白内障」、失明原因1位「緑内障」 早期発見のカギ
-
年を重ねたら誰もが必ずなる病気で、眼鏡をかけても矯正できない白内障。日本人の中途失明原因の1位であり、40歳以上の20人に1人がかかるという緑内障。視機能低下を進ませるこれら2つは、一体どうしたら早期発見でき、どんな治療をするのでしょうか。過去の人気記事を基に、多くの人が直面する白内障・緑内障との付き合い方を見ていきましょう。
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 9
日経Goodayでは日々、新しい健康・医療情報をお届けしています。その中で、読者のみなさまが今、最も気になっているテーマ、例えば、「大腸がん」「脂肪肝」「痛風・尿酸値」「男性ホルモン」などに関する多数の記事の“エッセンス”をすばやく知りたい――。そんなニーズにお答えする新サービスを開始します。
それが「テーマ別特集」です。毎月、読者のみなさまの関心が高かったテーマをチョイスし、特に好評だった記事のポイントを編集部でピックアップしてお届けします。そのテーマ、ジャンルについて知っておくべきことが、この記事を読むだけですべて把握できます。さらに、そのテーマに関する記事一覧もご用意しました。ご活用ください。
有料会員になると、鍵つき記事が全て読める&医療専門家に電話相談や名医紹介も!
-
- 正しい知識で熱中症を防ぐ! 水分補給の仕方は? 危険な場合は?
-
毎年、夏の時期が訪れると、過酷な暑さと共に増えるのが熱中症だ。高温多湿になると、体内の水分が失われて脱水症が起こりやすくなり、脱水症は熱中症を引き起こす。夏は命を守る戦いの季節。今回は熱中症を防ぐための基本的な知識から対策まで紹介する。
-
- 糖尿病になるまでの「3ステップ」 その対策はどうすればいい?
-
日本に約550万人の患者がいると言われている糖尿病。自分は大丈夫だろうかと気になる人もいるのではないか。その糖尿病に関するトピックとして、「体の血糖コントロールの仕組み」「糖尿病のタイプ」や「血糖値が上がりにくい食べ方」「予防・対策のための運動」について見ていく。
-
- 誰もがなる「白内障」、失明原因1位「緑内障」 早期発見のカギ
-
年を重ねたら誰もが必ずなる病気で、眼鏡をかけても矯正できない白内障。日本人の中途失明原因の1位であり、40歳以上の20人に1人がかかるという緑内障。視機能低下を進ませるこれら2つは、一体どうしたら早期発見でき、どんな治療をするのでしょうか。過去の人気記事を基に、多くの人が直面する白内障・緑内障との付き合い方を見ていきましょう。
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 10
毎年、夏の時期が訪れると、過酷な暑さと共に増えるのが熱中症だ。高温多湿になると、体内の水分が失われて脱水症が起こりやすくなり、脱水症は熱中症を引き起こす。夏は命を守る戦いの季節。今回は熱中症を防ぐための基本的な知識から対策まで紹介する。
テーマ別特集「熱中症」 この記事の主な内容 熱中症の初期段階は脱水症から始まる 適切な水分補給のタイミングは? あなたの1日に必要な水分量は? 日常の水分補給にカフェイン飲料はOK? 夏の飲み会に熱中症リスクが潜む 朝食を抜くと、脱水リスクが高まる 早めに気づきたい、脱水症・熱中症の症状は? 救急搬送の判断基準は? 高齢者は早めに救急要請熱中症の初期段階は脱水症から始まる
熱中症とは蒸し暑い環境にいることで起こる様々な体の異常を総称したものだ。恒温動物である人間は、蒸し暑い環境下に置かれると、血管を広げて体の表面に温かい血液を移動させたり、発汗によって熱を放散したりして、体温を一定に保とうとする。こうした働きに欠かせないのが体の水分だ。体温調節をしているうちに体の水分が失われていき、「脱水症」の状態になる。これが熱中症の始まりに当たる。
では、体の水分がどれぐらい失われると「脱水症」と定義されるのだろうか。熱中症・脱水症対策に詳しい済生会横浜市東部病院患者支援センター長の谷口英喜氏は、以下のように話す。
「成人では体重の約60%が水分で占められています。水分が3~5%失われると軽度の脱水症、6~9%で中度、10%以上だと重度の脱水症となります。重度の脱水症まで進むと、体の外に熱を逃がせなくなり、熱がこもって体温がどんどん上昇する異常高体温の状態になります」
つまり、熱中症の初期段階は脱水症から始まり、脱水症が進むにつれて高温環境によって異常高体温を伴い、重症の熱中症に至ってしまうというわけだ。そうなる前に適切な水分補給が必要になる。
適切な水分補給のタイミングは?
「夏はこまめな水分補給を」とは言うが、適切な水分補給のタイミングと量は意外と知られていない。谷口氏が勧めるのは「6オンス8回法」。1オンス=約30mLなので、6オンスは約180mL、コップに軽く1杯分の量。1回約180mLの水分を、1日8回補給するのが「6オンス8回法」だ。
朝・昼・晩の食事の際に水分補給するだけでなく、それぞれの食事の間にも水分をとることが大切だ。食事以外に2時間おきに水分補給するのが理想。お勧めのタイミングは、起床後、1日3回の食事時、食事と食事の間、お風呂に入る前、寝る前の計8回。一気に飲むのではなく、点滴のように少しずつ飲むことが大切だ。「一気に飲むと、脳が“体に水分が十分足りている”と判断して尿として排出してしまう。脳に気づかれないよう、少しずつ飲むのがコツです」(谷口氏)
水分補給のタイミング
基本の水分補給は、1回あたりコップ1杯。起床後、1日3回の食事時、食事と食事の間、お風呂に入る前、寝る前の計8回がお勧めだ。(使用イラスト:PIXTA)
高齢者は喉の渇きを感じにくくなるため、喉が渇いてから飲むのではなく、薬のように時間を決めて飲むのがポイントだ。夜間頻尿を気にして寝る前の水分を控えがちだが、全く飲まないのは危険だ。「寝る前の水分補給は150mL程度にとどめ、カフェインの含まれていない常温か、やや温かい飲み物を5分ほどかけて飲みましょう。可能なら夜中に目が覚めたときにも再度水分補給を。トイレが近くなる場合は、寝る前に飲む量を50mLずつ減らして様子を見るとよいでしょう」(谷口氏)
-
- 正しい知識で熱中症を防ぐ! 水分補給の仕方は? 危険な場合は?
-
毎年、夏の時期が訪れると、過酷な暑さと共に増えるのが熱中症だ。高温多湿になると、体内の水分が失われて脱水症が起こりやすくなり、脱水症は熱中症を引き起こす。夏は命を守る戦いの季節。今回は熱中症を防ぐための基本的な知識から対策まで紹介する。
-
- 糖尿病になるまでの「3ステップ」 その対策はどうすればいい?
-
日本に約550万人の患者がいると言われている糖尿病。自分は大丈夫だろうかと気になる人もいるのではないか。その糖尿病に関するトピックとして、「体の血糖コントロールの仕組み」「糖尿病のタイプ」や「血糖値が上がりにくい食べ方」「予防・対策のための運動」について見ていく。
-
- 誰もがなる「白内障」、失明原因1位「緑内障」 早期発見のカギ
-
年を重ねたら誰もが必ずなる病気で、眼鏡をかけても矯正できない白内障。日本人の中途失明原因の1位であり、40歳以上の20人に1人がかかるという緑内障。視機能低下を進ませるこれら2つは、一体どうしたら早期発見でき、どんな治療をするのでしょうか。過去の人気記事を基に、多くの人が直面する白内障・緑内障との付き合い方を見ていきましょう。
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 11
中高年の男性に多いと思われがちな脂肪肝。実は女性の場合も更年期以降に増えやすく、一見普通体形でも若いころにやせ型だったという人も脂肪肝になるリスクがあるようです。脂肪肝になりやすいタイプやその影響について見ていきましょう。また、国内では2024年に発表になった脂肪性肝疾患の新名称についても紹介します。
(イラスト:進藤やす子)
Check! こんな人は脂肪肝になりやすいかも
脂肪肝のほとんどは悪い生活習慣によるもので、大きく肥満を背景とする代謝異常と多飲酒の2つの要因がある。前者は今の体重よりも若いころからの“増え幅”が問題。太っていなくても高血糖などメタボを指摘されたら要注意。
肝臓には脂肪がたまりやすい
脂肪肝とは肝臓に脂肪がたまりすぎた状態のこと。肝臓は右のわき腹に位置する体内最大の臓器で約3000億個もの肝細胞で成り立っている。その働きは主に「栄養の代謝」「胆汁の生成」「毒素の解毒」で、私たちが生きていくには欠かせない臓器だ。
肝臓は体内最大の臓器。肝細胞から酵素が分泌され「栄養の代謝」「胆汁の生成」「毒素の解毒」という3つの重要な働きを担う。余ったエネルギーが中性脂肪として肝臓に一時的に蓄えられ、必要に応じて放出されるが、中性脂肪が増えすぎると脂肪肝に。(イラスト:PIXTA)
私たちが食事でとった栄養は主に肝臓で代謝されエネルギーが作られるが、作るエネルギーが消費する分よりも多い場合はその余剰分が中性脂肪に変換されて肝臓に一時的に蓄えられ、必要に応じて放出される。中性脂肪が肝細胞全体の20~30%を超えた状態になると脂肪肝と診断され、その理由のほとんどは生活習慣が背景に。その内訳は大きく「アルコールによるもの」と「肥満を背景とした代謝異常によるもの」「両方混在しているもの」に分けられる。
-
- 正しい知識で熱中症を防ぐ! 水分補給の仕方は? 危険な場合は?
-
毎年、夏の時期が訪れると、過酷な暑さと共に増えるのが熱中症だ。高温多湿になると、体内の水分が失われて脱水症が起こりやすくなり、脱水症は熱中症を引き起こす。夏は命を守る戦いの季節。今回は熱中症を防ぐための基本的な知識から対策まで紹介する。
-
- 糖尿病になるまでの「3ステップ」 その対策はどうすればいい?
-
日本に約550万人の患者がいると言われている糖尿病。自分は大丈夫だろうかと気になる人もいるのではないか。その糖尿病に関するトピックとして、「体の血糖コントロールの仕組み」「糖尿病のタイプ」や「血糖値が上がりにくい食べ方」「予防・対策のための運動」について見ていく。
-
- 誰もがなる「白内障」、失明原因1位「緑内障」 早期発見のカギ
-
年を重ねたら誰もが必ずなる病気で、眼鏡をかけても矯正できない白内障。日本人の中途失明原因の1位であり、40歳以上の20人に1人がかかるという緑内障。視機能低下を進ませるこれら2つは、一体どうしたら早期発見でき、どんな治療をするのでしょうか。過去の人気記事を基に、多くの人が直面する白内障・緑内障との付き合い方を見ていきましょう。
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 12
大阪・関西万博が始まった。大阪市の夢洲(ゆめしま)で、2025年10月13日まで開催されている。「いのち輝く未来社会のデザイン」がテーマだが、その「いのち」にはもちろん健康や医療なども関連してくる。ここでは、出展パビリオンの中から「健康」に関する見どころを紹介しよう。
大屋根リングと公式キャラクターの「ミャクミャク」が出迎える。(写真:菅野勝男)
大阪・関西万博が開幕しました。今回の万博では、ギネスに認定された(*1)巨大な木造建築物「大屋根リング」が話題になっていますが、それだけではありません。じつは、医療や健康に関する最先端の情報が集まっています。健康に関するパビリオンもあるのでここで紹介しましょう。
多少のネタばれもありますので、万博に行く予定の方は、記事後半はご覧にならないようにお願いいたします。
*1 「最大の木造建築物」として、2025年3月4日にギネス世界記録に認定された EXPO2025公式ホームページ「大屋根リング」参照
大阪ヘルスケアパビリオンの外観。(写真:菅野勝男)
まずは、大阪ヘルスケアパビリオンを紹介します。オール大阪の知恵とアイデアを集結させたパビリオンで、「REBORN(リボーン:生まれ変わり)」がテーマだとのこと。はたして、何が「生まれ変わり」なのでしょう? パビリオンには「リボーン体験ルート」があるので、そちらをのぞいてみました(*2)。
*2 ペースメーカー等医用電気機器を利用している人は体験できない。また、体調不良の人、光・音の刺激に過敏な人などは一部のコンテンツは利用できない。
-
- 正しい知識で熱中症を防ぐ! 水分補給の仕方は? 危険な場合は?
-
毎年、夏の時期が訪れると、過酷な暑さと共に増えるのが熱中症だ。高温多湿になると、体内の水分が失われて脱水症が起こりやすくなり、脱水症は熱中症を引き起こす。夏は命を守る戦いの季節。今回は熱中症を防ぐための基本的な知識から対策まで紹介する。
-
- 糖尿病になるまでの「3ステップ」 その対策はどうすればいい?
-
日本に約550万人の患者がいると言われている糖尿病。自分は大丈夫だろうかと気になる人もいるのではないか。その糖尿病に関するトピックとして、「体の血糖コントロールの仕組み」「糖尿病のタイプ」や「血糖値が上がりにくい食べ方」「予防・対策のための運動」について見ていく。
-
- 誰もがなる「白内障」、失明原因1位「緑内障」 早期発見のカギ
-
年を重ねたら誰もが必ずなる病気で、眼鏡をかけても矯正できない白内障。日本人の中途失明原因の1位であり、40歳以上の20人に1人がかかるという緑内障。視機能低下を進ませるこれら2つは、一体どうしたら早期発見でき、どんな治療をするのでしょうか。過去の人気記事を基に、多くの人が直面する白内障・緑内障との付き合い方を見ていきましょう。
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 13
健康・医療に関するホット・トピックスをお伝えします。
有料会員になると、鍵つき記事が全て読める&医療専門家に電話相談や名医紹介も!
-
- 正しい知識で熱中症を防ぐ! 水分補給の仕方は? 危険な場合は?
-
毎年、夏の時期が訪れると、過酷な暑さと共に増えるのが熱中症だ。高温多湿になると、体内の水分が失われて脱水症が起こりやすくなり、脱水症は熱中症を引き起こす。夏は命を守る戦いの季節。今回は熱中症を防ぐための基本的な知識から対策まで紹介する。
-
- 糖尿病になるまでの「3ステップ」 その対策はどうすればいい?
-
日本に約550万人の患者がいると言われている糖尿病。自分は大丈夫だろうかと気になる人もいるのではないか。その糖尿病に関するトピックとして、「体の血糖コントロールの仕組み」「糖尿病のタイプ」や「血糖値が上がりにくい食べ方」「予防・対策のための運動」について見ていく。
-
- 誰もがなる「白内障」、失明原因1位「緑内障」 早期発見のカギ
-
年を重ねたら誰もが必ずなる病気で、眼鏡をかけても矯正できない白内障。日本人の中途失明原因の1位であり、40歳以上の20人に1人がかかるという緑内障。視機能低下を進ませるこれら2つは、一体どうしたら早期発見でき、どんな治療をするのでしょうか。過去の人気記事を基に、多くの人が直面する白内障・緑内障との付き合い方を見ていきましょう。
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 14
日経Goodayではこれまでに数多くのエクササイズを記事で紹介してきました。そうした中、「エクササイズの部分だけをまとめて見たい」「画面やプリントアウトを見ながらエクササイズしたい」といった声を多数いただきました。そこで、過去に好評だった記事の中からエクササイズだけを抜き出し、より見やすい形にまとめました。パソコンやスマートフォンの画面で見ながら、あるいはプリントアウトしたものを壁に貼って見ながら、気になるエクササイズをより快適に実践してください。
有料会員になると、鍵つき記事が全て読める&医療専門家に電話相談や名医紹介も!
-
- 正しい知識で熱中症を防ぐ! 水分補給の仕方は? 危険な場合は?
-
毎年、夏の時期が訪れると、過酷な暑さと共に増えるのが熱中症だ。高温多湿になると、体内の水分が失われて脱水症が起こりやすくなり、脱水症は熱中症を引き起こす。夏は命を守る戦いの季節。今回は熱中症を防ぐための基本的な知識から対策まで紹介する。
-
- 糖尿病になるまでの「3ステップ」 その対策はどうすればいい?
-
日本に約550万人の患者がいると言われている糖尿病。自分は大丈夫だろうかと気になる人もいるのではないか。その糖尿病に関するトピックとして、「体の血糖コントロールの仕組み」「糖尿病のタイプ」や「血糖値が上がりにくい食べ方」「予防・対策のための運動」について見ていく。
-
- 誰もがなる「白内障」、失明原因1位「緑内障」 早期発見のカギ
-
年を重ねたら誰もが必ずなる病気で、眼鏡をかけても矯正できない白内障。日本人の中途失明原因の1位であり、40歳以上の20人に1人がかかるという緑内障。視機能低下を進ませるこれら2つは、一体どうしたら早期発見でき、どんな治療をするのでしょうか。過去の人気記事を基に、多くの人が直面する白内障・緑内障との付き合い方を見ていきましょう。
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 15
人生も半ばを過ぎると、老化と無縁ではいられない。少しでも老化を遅らせ、健康寿命を延ばしたいというのは誰しも願うことだろう。近年では老化研究が急速に進み、老化を進める要因も明らかになってきた。今、その中で注目されているのが「糖化」だ。糖化は、見た目の老化はもちろん、血管や内臓、骨、関節などの機能低下、糖尿病、認知症など多くの病気のリスクも高める。では、糖化を防ぎ“老けない”ために何を実践すればいいのだろうか。本特集では、糖化の最新事情とその対策を、糖化研究の専門家である同志社大学生命医科学部アンチエイジングリサーチセンター教授の米井嘉一氏に聞いていく。
米井嘉一(よねい よしかず)氏 同志社大学生命医科学部アンチエイジングリサーチセンター 教授
有料会員になると、鍵つき記事が全て読める&医療専門家に電話相談や名医紹介も!
-
- 正しい知識で熱中症を防ぐ! 水分補給の仕方は? 危険な場合は?
-
毎年、夏の時期が訪れると、過酷な暑さと共に増えるのが熱中症だ。高温多湿になると、体内の水分が失われて脱水症が起こりやすくなり、脱水症は熱中症を引き起こす。夏は命を守る戦いの季節。今回は熱中症を防ぐための基本的な知識から対策まで紹介する。
-
- 糖尿病になるまでの「3ステップ」 その対策はどうすればいい?
-
日本に約550万人の患者がいると言われている糖尿病。自分は大丈夫だろうかと気になる人もいるのではないか。その糖尿病に関するトピックとして、「体の血糖コントロールの仕組み」「糖尿病のタイプ」や「血糖値が上がりにくい食べ方」「予防・対策のための運動」について見ていく。
-
- 誰もがなる「白内障」、失明原因1位「緑内障」 早期発見のカギ
-
年を重ねたら誰もが必ずなる病気で、眼鏡をかけても矯正できない白内障。日本人の中途失明原因の1位であり、40歳以上の20人に1人がかかるという緑内障。視機能低下を進ませるこれら2つは、一体どうしたら早期発見でき、どんな治療をするのでしょうか。過去の人気記事を基に、多くの人が直面する白内障・緑内障との付き合い方を見ていきましょう。
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 16
老化を進める「糖化」への対策を解説する本特集。食事のルールを解説した前回に続き、今回は糖化とお酒、そしてタバコ、運動や睡眠などの関係を取り上げる。実は飲酒も糖化を進める大きな要因だ。しかし、糖化リスクが比較的低いお酒もあるという。それはどのお酒だろうか。また、糖化対策としての運動は、「運動するタイミング」にコツがあるという。糖化を遠ざけつつお酒を楽しむための注意点や、運動、睡眠を見直すポイントを見ていこう。
飲酒と「糖化」の危険な関係
老化を進める「糖化」のリスクとその対策を紹介する本特集。最終回となる今回は、糖化を抑える上で知っておきたい、お酒との付き合い方や、運動や睡眠など糖化リスクを遠ざけるためにやるべきことを紹介していこう。
(写真はイメージ:PIXTA)
糖化とは、体の中のたんぱく質が、食事から摂取した糖質と結びついて劣化していく反応のこと。体は主にたんぱく質で構成されているため、糖化が進めば体の老化が進んでしまう。第1回で紹介したように、糖化の主犯は糖から発生するアルデヒドだが、アルデヒドは脂質のとり過ぎでも発生する。つまり、糖質と脂質の両方を抑える対策が求められる。しかし、アルデヒドを生む要因は他にもある。忘れてはならないのがアルコール、つまりお酒だ。
糖化研究の第一人者とされる同志社大学生命医科学部アンチエイジングリサーチセンター教授の米井嘉一氏は、「アルコールが体内で分解される過程で生じるアセトアルデヒドも、たんぱく質と結びついて糖化を進めます。飲酒も糖化を進める大きな要因なのです」と話す。
日経Goodayではこれまで飲酒と健康に関する記事を何度も取り上げており、「アルデヒド」はアルコール(エタノール)が分解されて生成する物質だとご存じの人もいるだろう。エタノールは、肝臓内でまずアルコール脱水素酵素(ADH1B)によりアセトアルデヒドに変換され、その後、アルデヒド脱水素酵素(ALDH2)により酢酸に変換され、最終的に水と二酸化炭素となって呼気や尿、汗などから排出される。このように、アルコールが体内で代謝される過程でアセトアルデヒドが生成されるわけだ。
アルコールが体内で代謝される仕組み
アルコールは胃や小腸から吸収され、肝臓で「アセトアルデヒド」に分解。アルデヒド脱水素酵素(ALDH2)の作用で酢酸に変換され、最終的には水と二酸化炭素となって呼気や尿、汗などから排出される。これとは別に、MEOS(ミクロゾームエタノール酸化系)という酵素による代謝経路もある。
アルデヒドの仲間は毒性が強い。お酒を飲んで顔が赤くなったり、二日酔いで頭痛や吐き気を催したりするのもアセトアルデヒドの作用だ。それだけでなく、糖化反応を進める元凶の1つでもある。
実際、飲む頻度が高い人ほど、糖化によって生じる終末糖化産物(AGEs:Advanced Glycation End Products)が体内に多く蓄積することが確認されている。同志社大学のアンチエイジングリサーチセンター/糖化ストレス研究センターで日本人244人の生活習慣とAGEs量の関係を解析したところ、飲酒頻度が週4日以上のグループは、週3日以下のグループに比べてAGEsの蓄積量が高かった。
AGEsの蓄積と飲酒習慣の関係
日本人244人(20~59歳)の生活習慣(飲酒など)と右上腕内側部における皮膚中蛍光性AGEs量の関係を解析した。その結果、週に4日以上飲酒するグループは、3日以下のグループに比べてAGEsの蓄積量が多かった。グラフ内の「(16)」などの数字は該当する人数を示す。(Anti-Aging Medicine. 2012;9(6):165-173.)
-
- 正しい知識で熱中症を防ぐ! 水分補給の仕方は? 危険な場合は?
-
毎年、夏の時期が訪れると、過酷な暑さと共に増えるのが熱中症だ。高温多湿になると、体内の水分が失われて脱水症が起こりやすくなり、脱水症は熱中症を引き起こす。夏は命を守る戦いの季節。今回は熱中症を防ぐための基本的な知識から対策まで紹介する。
-
- 糖尿病になるまでの「3ステップ」 その対策はどうすればいい?
-
日本に約550万人の患者がいると言われている糖尿病。自分は大丈夫だろうかと気になる人もいるのではないか。その糖尿病に関するトピックとして、「体の血糖コントロールの仕組み」「糖尿病のタイプ」や「血糖値が上がりにくい食べ方」「予防・対策のための運動」について見ていく。
-
- 誰もがなる「白内障」、失明原因1位「緑内障」 早期発見のカギ
-
年を重ねたら誰もが必ずなる病気で、眼鏡をかけても矯正できない白内障。日本人の中途失明原因の1位であり、40歳以上の20人に1人がかかるという緑内障。視機能低下を進ませるこれら2つは、一体どうしたら早期発見でき、どんな治療をするのでしょうか。過去の人気記事を基に、多くの人が直面する白内障・緑内障との付き合い方を見ていきましょう。
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 17
人生も半ばを過ぎると、老化と無縁ではいられない。少しでも老化を遅らせ、健康寿命を延ばしたいというのは誰しも願うことだろう。近年では老化研究が急速に進み、老化を進める要因も明らかになってきた。今、その中で注目されているのが「糖化」だ。糖化は、見た目の老化はもちろん、血管や内臓、骨、関節などの機能低下、糖尿病、認知症など多くの病気のリスクも高める。では、糖化を防ぎ“老けない”ために何を実践すればいいのだろうか。本特集では、糖化の最新事情とその対策を、糖化研究の専門家である同志社大学生命医科学部アンチエイジングリサーチセンター教授の米井嘉一氏に聞いていく。
米井嘉一(よねい よしかず)氏 同志社大学生命医科学部アンチエイジングリサーチセンター 教授
有料会員になると、鍵つき記事が全て読める&医療専門家に電話相談や名医紹介も!
-
- 正しい知識で熱中症を防ぐ! 水分補給の仕方は? 危険な場合は?
-
毎年、夏の時期が訪れると、過酷な暑さと共に増えるのが熱中症だ。高温多湿になると、体内の水分が失われて脱水症が起こりやすくなり、脱水症は熱中症を引き起こす。夏は命を守る戦いの季節。今回は熱中症を防ぐための基本的な知識から対策まで紹介する。
-
- 糖尿病になるまでの「3ステップ」 その対策はどうすればいい?
-
日本に約550万人の患者がいると言われている糖尿病。自分は大丈夫だろうかと気になる人もいるのではないか。その糖尿病に関するトピックとして、「体の血糖コントロールの仕組み」「糖尿病のタイプ」や「血糖値が上がりにくい食べ方」「予防・対策のための運動」について見ていく。
-
- 誰もがなる「白内障」、失明原因1位「緑内障」 早期発見のカギ
-
年を重ねたら誰もが必ずなる病気で、眼鏡をかけても矯正できない白内障。日本人の中途失明原因の1位であり、40歳以上の20人に1人がかかるという緑内障。視機能低下を進ませるこれら2つは、一体どうしたら早期発見でき、どんな治療をするのでしょうか。過去の人気記事を基に、多くの人が直面する白内障・緑内障との付き合い方を見ていきましょう。
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 18
老化の元凶として、近年大きくクローズアップされている「糖化」。体内のたんぱく質が、食事でとった糖質と結びつき劣化する現象で、血管や内臓、皮膚、骨などの老化や、糖尿病、認知症などのさまざまな病気のリスクを高めることが分かっている。飽食の時代となった今、「糖質と脂質のとり過ぎ」により、そのリスクが顕在化するようになった。では、糖化を防ぎ、老化を遅らせるためには何をすればいいのだろうか。第2回では、糖化対策の要となる「食事のルール」を見ていこう。
糖化を防ぐために目指すべき食事とは?
近年、老化を進める大きな要因として注目されている「糖化」。糖化により、皮膚、血管、内臓、骨などの老化が進み、さらに糖尿病や認知症などのさまざまな疾患リスクも高まる。老化に完全にあらがうことはできなくとも、老化を遅らせて健康寿命を延ばしたいなら、できるだけ早く対策を打ちたい。
第1回でも紹介したように、糖化とは、食事で摂取した過剰な「糖質」が体の中の「たんぱく質」と結合する反応のこと。このため、糖化対策には糖の過剰摂取を抑えることが必須条件となる。
しかし、糖質の制限だけでは不十分だ。糖化を進める黒幕は、糖から発生するアルデヒドという有害物質で、アルデヒドは脂質のとり過ぎで脂肪がたまった状態からも生成されるからだ。糖化研究の第一人者である、同志社大学生命医科学部アンチエイジングリサーチセンター教授の米井嘉一氏は、「脂質のとり過ぎも、糖化の一因であることが近年明らかになってきました。糖質と脂質のダブルパンチで糖化が進み、病的な老化につながります」と話す。糖質だけでなく、「脂質」の摂取を控えるのが、現在の糖化対策のセオリーなのだ。
糖質・脂質の両方をとり過ぎると、ダブルパンチで糖化が加速する。(写真はイメージ:PIXTA)
糖質と脂質のいずれも減らすには、食生活の改善がカギとなる。そこで今回は、糖化を抑える食事ルールを米井氏に聞いていく。近年の研究から、糖化により体の中に生じる「終末糖化産物(AGEs:Advanced Glycation End Products)」を減らす食材の存在も分かってきたので、その具体例も最後に紹介しよう。
たんぱく質・脂質・炭水化物=2:2:6の割合に
前回紹介したように、食事で糖質をとり過ぎると、食後に血糖値が急上昇する「血糖スパイク」(食後高血糖)のリスクが高まる。このとき有害なアルデヒドも急増し(アルデヒドスパーク)、糖化を誘発する。つまり、糖質のとり過ぎを抑えることが第一の対策となる。そして脂質のとり過ぎにも注意しよう。とはいえ、糖質も脂質もいずれも生きていく上で欠かせない成分なので、極端に減らさず、過不足なく摂取することが大切だ。
生きるためのエネルギー源となる3大栄養素、たんぱく質(Protein):脂質(Fat):炭水化物(Carbohydrates)の比率をPFCバランスと呼ぶが、米井氏はこの割合を「2:2:6」とすることを勧める。例えば、1日2000kcalを摂取する場合、たんぱく質400kcal、脂質400kcal、炭水化物1200kcalの内訳にする。細かいカロリー計算までするのは大変なので、「2:2:6」になるように意識するといいだろう。
たんぱく質・脂質・炭水化物の適切な割合(PFCバランス)
なお、厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2025年版)」では、たんぱく質は14~20%、脂質は20~30%、炭水化物が50~65%(50~64歳、エネルギーに対する割合)を目標量としている。これに対し、米井氏の推奨する「2:2:6」は、この基準よりも「脂質は下限寄り」「たんぱく質は上限寄り」にするのがポイントだ。炭水化物は糖質と食物繊維からなるが、大部分を占める糖質をとり過ぎず、食物繊維をしっかりとることが大切だと米井氏は話す。
「忙しいときは、コンビニや外食で簡単に食事を済ませることも多いでしょう。そうなると炭水化物が7~8割になったり、脂質が3~4割と増えたりするなど、糖質や脂質が多く、たんぱく質が少なくなりがちです。こうした食生活が糖化を進めるのです」(米井氏)
-
- 正しい知識で熱中症を防ぐ! 水分補給の仕方は? 危険な場合は?
-
毎年、夏の時期が訪れると、過酷な暑さと共に増えるのが熱中症だ。高温多湿になると、体内の水分が失われて脱水症が起こりやすくなり、脱水症は熱中症を引き起こす。夏は命を守る戦いの季節。今回は熱中症を防ぐための基本的な知識から対策まで紹介する。
-
- 糖尿病になるまでの「3ステップ」 その対策はどうすればいい?
-
日本に約550万人の患者がいると言われている糖尿病。自分は大丈夫だろうかと気になる人もいるのではないか。その糖尿病に関するトピックとして、「体の血糖コントロールの仕組み」「糖尿病のタイプ」や「血糖値が上がりにくい食べ方」「予防・対策のための運動」について見ていく。
-
- 誰もがなる「白内障」、失明原因1位「緑内障」 早期発見のカギ
-
年を重ねたら誰もが必ずなる病気で、眼鏡をかけても矯正できない白内障。日本人の中途失明原因の1位であり、40歳以上の20人に1人がかかるという緑内障。視機能低下を進ませるこれら2つは、一体どうしたら早期発見でき、どんな治療をするのでしょうか。過去の人気記事を基に、多くの人が直面する白内障・緑内障との付き合い方を見ていきましょう。
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 19
人生も半ばを過ぎると、老化と無縁ではいられない。少しでも老化を遅らせ、健康寿命を延ばしたいというのは誰しも願うことだろう。近年では老化研究が急速に進み、老化を進める要因も明らかになってきた。今、その中で注目されているのが「糖化」だ。糖化は、見た目の老化はもちろん、血管や内臓、骨、関節などの機能低下、糖尿病、認知症など多くの病気のリスクも高める。では、糖化を防ぎ“老けない”ために何を実践すればいいのだろうか。本特集では、糖化の最新事情とその対策を、糖化研究の専門家である同志社大学生命医科学部アンチエイジングリサーチセンター教授の米井嘉一氏に聞いていく。
数ある老化対策の中で最も重視すべきは「糖化」
年を重ねると、皮膚のシミ・シワ、白髪などが目立ち始める。こうした自然な加齢現象は誰にでも起こり、避けて通るのは難しい。とはいえ、“老け方”には明らかに個人差があり、同じ年代なのに10歳若く見える人もいれば、逆に10歳老けて見える人もいる。問題は見た目だけではない。健康寿命に大きく影響するさまざまな病気の進み方にも個人差がある。同い年の友人は若々しく病気知らずなのに、自分だけ老け込んで病気がちになっていくとしたら――。こんな事態は誰だって避けたいものだ。
(写真はイメージ:PIXTA)
近年、老化研究が大幅に進み、老化を進める要因も明らかになってきている。その代表として、体内の過剰な糖が悪影響を及ぼす「糖化」や、活性酸素により起こる「酸化」、免疫の低下、心身のストレス、生活習慣などが分かっている。どれも重要な要素だが、特にクローズアップされているのが糖化だ。最近はテレビや週刊誌などでも取り上げられる機会が増えているので、聞き覚えのある人も少なくないだろう。
2025年刊行『糖と脂で体は壊れる』(池田書店)
同志社大学生命医科学部アンチエイジングリサーチセンター教授の米井嘉一氏は、「数ある老化要因の中で、最も重視するべきなのが糖化です」と言い切る。米井氏は早くから老化対策(アンチエイジング)の重要性に着目し、2000年に日本鋼管病院に日本初のアンチエイジングドックを開設した医師だ。日本抗加齢医学研究会(現・日本抗加齢医学会の前身)の立ち上げに関わり、同志社大学で糖化の観点から抗加齢医学研究に携わってきた。糖化ストレス研究会の理事長も務める中、アンチエイジングについて多くの著書も手がけている。
糖化とは、糖質がたんぱく質と結びつき、そこに熱が加わって褐色に色づく反応のこと。メイラード反応ともいう。例えば、小麦粉のでんぷんや砂糖(糖質)に卵(たんぱく質)を加えて加熱すると、キツネ色のパンケーキが焼き上がる。まさにこれが糖化反応だ。
パンケーキに限らず、こんがり焼けた料理のおいしさは誰もが知るところだが、これが体内で起こると大きな問題となる。糖化反応によって体内のたんぱく質が“焦げて”変性し、劣化してしまうからだ。下の写真は、牛の皮をブドウ糖溶液(右)と、ブドウ糖を含まない溶液(左)に数日漬け込んだもの。糖を含むというだけで組織内のたんぱく質の糖化が進み、茶褐色に変色し、弾力が失われていく。
牛皮の糖化モデル(左が糖化処理なし、右が糖化処理あり)。(写真提供:同志社大学 アンチエイジングリサーチセンター/糖化ストレス研究センター)
糖化反応が進むと、最終的に終末糖化産物(AGEs:Advanced Glycation End Products)と呼ばれる物質になる。AGEsはたんぱく質が変性した状態であり、体内の老化を進めるもとだ。
「たんぱく質は、皮膚や筋肉だけでなく、各種臓器、血管、骨などさまざまな器官の構成要素です。同様に、ホルモンや酵素、遺伝子などもたんぱく質(機能性たんぱく質)でできています。これが糖化によって焦げていくのですから、見た目が老けたり、臓器などが劣化したりして、さまざまな疾患につながるのです」(米井氏)
糖化でさまざまな病気のリスクも高まる
糖化によってリスクが高まる病気は、多岐にわたる。その1つが糖尿病。糖尿病患者の体の中では、血糖値を調節するインスリンというホルモンが効きにくいことが分かっているが、それも糖化の影響だ。「インスリンがつくられる過程で糖化を起こすため、血糖値を下げる機能が落ちると考えられます」と米井氏。
このほかにも、糖化によって血管が傷むと、動脈硬化から心筋梗塞や脳梗塞を発症しやすくなり、皮膚ではシミやシワが増える。脳では認知症、骨では骨粗しょう症、目では白内障や加齢黄斑変性など、糖化はさまざまな病気の引き金になる。さらに、免疫力の低下や慢性疲労、意欲の減退などにも影響するという。
米井氏は、近年の研究から糖化を進めるメカニズムが明らかになってきたと話す。糖質のとり過ぎが原因であることは従来から知られていたが、脂質の影響も大きいことが分かったという。米井氏は「糖質と脂質が体を壊していくのです」と警告する。本特集 第1回では米井氏への取材を基に、糖質と脂質が糖化を進め、老化につながる仕組みを解説。第2回では糖化を抑える食事のルール、第3回ではお酒との付き合い方や運動のコツなど、具体的な糖化対策を紹介しよう。
Page 20
人生100年時代といわれる昨今、年齢を重ねても生涯現役で仕事をしたり、自立した生活を送ったりするためには、身体活動の基盤となる「筋肉」を維持することが欠かせない。特に、加齢によって衰えやすい筋肉は、意識的に鍛える必要がある。本特集では、「いくつになっても動けるカラダ」をつくるうえで必要な衰えやすい部位の筋力トレーニングを紹介する。今回は、なぜ筋トレが重要なのか、特に鍛えたい「速筋」について解説する。
60歳以降は筋肉の減少が加速!
60歳以降は筋肉減少が加速する。イラストはイメージ。(イラスト:高田真弓)
「最近、少し動くだけでも疲れやすくなった」「階段の上り下りがきつく感じる」──中高年になるとそんな体の衰えを実感する人は多いだろう。その大きな要因となっているのが、加齢による筋肉量の減少と筋力の低下だ。
「よく『老いは脚から』と言われますが、下肢の筋肉は30歳を過ぎると10年ごとに約4%の割合で減少し、60歳以降はその減少率が10年ごとに約10%になるという報告があります(*1)。加齢に伴って筋肉量が減少し、筋力が低下した状態は『サルコペニア(筋肉減弱症)』と呼ばれ、何も手を打たなければ、日常生活に支障を来し、将来の要介護や寝たきりのリスクを高める可能性があります」
こう話すのは、順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科教授の町田修一氏だ。町田氏は、骨格筋(筋肉)について研究し、サルコペニアの予防・改善に向けたトレーニング法の開発や指導をしている。
60代は筋肉の減少が加速する節目となる。早々に手を打って筋肉を維持するか、放置してサルコペニアのリスクが高まるか。筋肉の衰えに待ったをかける、早めの対策が欠かせない。
現代の便利な暮らしに潜む落とし穴
筋肉量の減少は、加齢のほか、運動不足や身体活動量の低下によっても起こる。「一般的に筋肉と呼ばれる『骨格筋』は、骨に沿って付着している筋肉で、歩く、走る、立つ、座る、姿勢を保つといった動作の基盤となるものです。ひと昔前までは、日常生活の中でも自然と体を動かし、筋肉を使っていたものですが、現代社会ではその機会が少なくなっています」と、町田氏は指摘する。
例えば、生活様式の変化で、しゃがんで体を支える必要があった和式トイレは、腰かけてできる洋式トイレが主流に。ベッドで寝ていれば、毎日布団を敷いたり片付けたりする手間は不要だ。四つんばいになって雑巾がけをしなくても、立ったまま掃除機やモップをかければきれいになるし、自分は動かなくとも機械任せにできるお掃除ロボットも登場している。外出しなくても自宅にいながらネット注文で買い物もできてしまう。
お掃除ロボットの登場により、体を動かさなくてもいいように。楽になった一方で、筋肉を使うシーンが減っている。(写真:PIXTA)
仕事にしても、パソコンやテレワークの普及で座りっぱなしのデスクワークの時間が長くなりがちだ。通勤時に階段を使えば運動になると分かっていても、ついエスカレーターやエレベーターを利用してしまうという人も少なくないだろう。
現代社会は、筋肉を動かすことをサボっていても生活できてしまう。「これは生活習慣病の要因の1つであるとともに、筋肉量の減少を加速させている」と、町田氏は指摘する。
筋肉量の減少に歯止めをかけ、いくつになっても自立した生活を送るためには、「筋肉を意識的に鍛える筋力トレーニングを継続することが重要」だと、町田氏は訴える。といっても、トレーニングマシンを使うようなハードな筋トレを指しているのではない。
「自分の体重を利用する自体重トレーニングを週2回するだけでも、筋肉量を維持し強化することは可能です。QOL(生活の質)の維持や向上を目的とするなら、衰えやすい部位を重点的に鍛えるメニューの実践でも十分な効果が期待できます」(町田氏)
本特集では、「いくつになっても動けるカラダ」をつくるうえで必要な「衰えやすい部位」を重点的に鍛える筋トレを紹介する。今回は、なぜ筋トレが重要なのか、筋トレによって分泌されるホルモンの観点から見ていこう。また、特に鍛えたい「速筋」についても詳しく解説していく。
*1 J Neurol Sci. 1988 Apr; 84(2-3): 275-94.
-
- 正しい知識で熱中症を防ぐ! 水分補給の仕方は? 危険な場合は?
-
毎年、夏の時期が訪れると、過酷な暑さと共に増えるのが熱中症だ。高温多湿になると、体内の水分が失われて脱水症が起こりやすくなり、脱水症は熱中症を引き起こす。夏は命を守る戦いの季節。今回は熱中症を防ぐための基本的な知識から対策まで紹介する。
-
- 糖尿病になるまでの「3ステップ」 その対策はどうすればいい?
-
日本に約550万人の患者がいると言われている糖尿病。自分は大丈夫だろうかと気になる人もいるのではないか。その糖尿病に関するトピックとして、「体の血糖コントロールの仕組み」「糖尿病のタイプ」や「血糖値が上がりにくい食べ方」「予防・対策のための運動」について見ていく。
-
- 誰もがなる「白内障」、失明原因1位「緑内障」 早期発見のカギ
-
年を重ねたら誰もが必ずなる病気で、眼鏡をかけても矯正できない白内障。日本人の中途失明原因の1位であり、40歳以上の20人に1人がかかるという緑内障。視機能低下を進ませるこれら2つは、一体どうしたら早期発見でき、どんな治療をするのでしょうか。過去の人気記事を基に、多くの人が直面する白内障・緑内障との付き合い方を見ていきましょう。
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 21
人生100年時代といわれる昨今、年齢を重ねても生涯現役で仕事をしたり、自立した生活を送ったりするためには、身体活動の基盤となる「筋肉」を維持することが欠かせない。特に、加齢によって衰えやすい筋肉は、意識的に鍛える必要がある。本特集では、「いくつになっても動けるカラダ」をつくるうえで必要な衰えやすい部位の筋力トレーニングを紹介する。
町田修一(まちだ しゅういち)氏 順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科 教授
有料会員になると、鍵つき記事が全て読める&医療専門家に電話相談や名医紹介も!
-
- 正しい知識で熱中症を防ぐ! 水分補給の仕方は? 危険な場合は?
-
毎年、夏の時期が訪れると、過酷な暑さと共に増えるのが熱中症だ。高温多湿になると、体内の水分が失われて脱水症が起こりやすくなり、脱水症は熱中症を引き起こす。夏は命を守る戦いの季節。今回は熱中症を防ぐための基本的な知識から対策まで紹介する。
-
- 糖尿病になるまでの「3ステップ」 その対策はどうすればいい?
-
日本に約550万人の患者がいると言われている糖尿病。自分は大丈夫だろうかと気になる人もいるのではないか。その糖尿病に関するトピックとして、「体の血糖コントロールの仕組み」「糖尿病のタイプ」や「血糖値が上がりにくい食べ方」「予防・対策のための運動」について見ていく。
-
- 誰もがなる「白内障」、失明原因1位「緑内障」 早期発見のカギ
-
年を重ねたら誰もが必ずなる病気で、眼鏡をかけても矯正できない白内障。日本人の中途失明原因の1位であり、40歳以上の20人に1人がかかるという緑内障。視機能低下を進ませるこれら2つは、一体どうしたら早期発見でき、どんな治療をするのでしょうか。過去の人気記事を基に、多くの人が直面する白内障・緑内障との付き合い方を見ていきましょう。
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 22
昨夏、全国平均気温が気象庁の統計開始以降、最も高くなり、過酷な暑さが全国を襲った。気象庁は7月18日、この先の1カ月予報(7月20日~8月19日)は全国的に平年より気温が高く、猛暑になる見込みと発表。今年も、恐ろしい暑さがやってきた。
高温で高湿度になると、体内の水分が失われて脱水症が起きる。脱水症が熱中症を引き起こすのはもちろんだが、様々な恐ろしい病気を引き起こすのだ。夏は命を守る戦いの季節。暑さから命を守る術を、熱中症・脱水症対策に詳しい済生会横浜市東部病院患者支援センター長の谷口英喜氏に聞いた。また、雑貨店で売れている夏のひんやりグッズも紹介する。
谷口英喜(たにぐち ひでき)氏 済生会横浜市東部病院患者支援センター長、医学博士、麻酔科医師
有料会員になると、鍵つき記事が全て読める&医療専門家に電話相談や名医紹介も!
-
- 正しい知識で熱中症を防ぐ! 水分補給の仕方は? 危険な場合は?
-
毎年、夏の時期が訪れると、過酷な暑さと共に増えるのが熱中症だ。高温多湿になると、体内の水分が失われて脱水症が起こりやすくなり、脱水症は熱中症を引き起こす。夏は命を守る戦いの季節。今回は熱中症を防ぐための基本的な知識から対策まで紹介する。
-
- 糖尿病になるまでの「3ステップ」 その対策はどうすればいい?
-
日本に約550万人の患者がいると言われている糖尿病。自分は大丈夫だろうかと気になる人もいるのではないか。その糖尿病に関するトピックとして、「体の血糖コントロールの仕組み」「糖尿病のタイプ」や「血糖値が上がりにくい食べ方」「予防・対策のための運動」について見ていく。
-
- 誰もがなる「白内障」、失明原因1位「緑内障」 早期発見のカギ
-
年を重ねたら誰もが必ずなる病気で、眼鏡をかけても矯正できない白内障。日本人の中途失明原因の1位であり、40歳以上の20人に1人がかかるという緑内障。視機能低下を進ませるこれら2つは、一体どうしたら早期発見でき、どんな治療をするのでしょうか。過去の人気記事を基に、多くの人が直面する白内障・緑内障との付き合い方を見ていきましょう。
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 23
高齢者や子どもに限らず、健康な成人でも条件が重なれば熱中症になる可能性はある。熱中症警戒アラートが発令された日は、できる限り暑さを避けて涼しい環境で過ごすことが肝要だ。しかし、どうしても休めない仕事やリスケできない予定があれば、そうはいかない日もあるだろう。そんな日は帽子や日傘、冷却グッズなどを使い、体温が上がらないよう工夫することで暑さを和らげたい。真夏の外出時の「お出かけ七つ道具」を済生会横浜市東部病院患者支援センター長の谷口英喜氏に聞いた他、記事の後半では銀座ロフトで売れている「夏を快適に乗り切るひんやりグッズ」を紹介する。実際に編集スタッフが使ってみた使用コメントも合わせて、グッズ選びの参考にしてほしい。
熱中症から命を守るための正しい知識を紹介する本特集。
今回は、真夏の外出時の「お出かけ七つ道具」を、済生会横浜市東部病院患者支援センター長の谷口英喜氏に聞く。また、近年充実している熱中症対策グッズを紹介する。グッズは生活雑貨の専門店「銀座ロフト」の売れ筋を取材した。
まずは、「お出かけ七つ道具」から紹介しよう。うだるような暑さの日でも、外出しなければならない日はある。谷口氏が勧める真夏の外出時の「お出かけ七つ道具」は以下の通りだ。
谷口氏が勧める「お出かけ七つ道具」
- 日傘
- 帽子
- 汗拭きタオル
- 飲み物
- 経口補水パウダー
- 扇子やハンディファン
- 首を冷やすグッズ
まずは日傘から、一つずつ説明しよう。日傘を使うと使わないとでは、体が受ける輻射熱の量が大きく変わる。「日傘は、外側は紫外線や赤外線を吸収しにくい白いもので内側が黒いものを選びましょう。地表からの輻射熱の乱反射を防ぎ、熱中症予防効果が高まります」(谷口氏)。女性だけに限らず、男性も日傘を使うことを谷口氏は勧める。屋外では日陰を選んで歩くことも心がけたい。
次に紹介するのは帽子。首筋に赤外線が当たると体温が上がりやすくなる。つばの広い帽子で首筋を守ることが大切だ。
汗拭きタオルも持ち歩きたい。実は、汗には蒸発するときに熱を奪うことで体温を下げる役割がある。そう聞くと、汗を拭き取ってしまうと、体温を下げられないのでは?と思うかもしれない。だが、谷口氏は「汗は全身でかいているので、拭き取れる汗はほんの一部です。不快な汗は早めに拭き取ってできるだけ快適に過ごしましょう」と話す。汗拭きタオルとするのは乾いたタオルでもいいが、ぬれタオルもいい。ぬれたものなら水分の影響で体から熱を奪う効果がより期待できるという。清涼感が得られるメントール配合の汗拭きシートなども市販されているので、活用してもいいだろう。
脱水を防ぐ要となる飲み物も忘れてはならない。屋外に出る日は普段の500mLほど追加で水分をとりたい。「外出時は水分補給を忘れてしまいがちですが、常に水筒やペットボトルを携帯してこまめに水分をとる意識づけをしましょう」(谷口氏)
運動で汗を流す場合はスポーツドリンクが好ましいが、普段の水分補給は水やお茶、無糖の炭酸水で十分だ。熱中症対策の水分補給ではカフェイン入り飲料はNGという話をよく聞くが、実は飲み慣れていれば利尿作用は強く出ることはない。カフェイン入りの飲料でも構わないということだ。
経口補水液を携帯しておけば、万が一外出先で熱中症になったときに素早く対応できる。ドリンクタイプはかさばるので、パウダータイプやゼリータイプがお勧めだ。パウダーは水で溶かすだけでドリンクになる。谷口氏は「塩あめや梅干しでも水と併用することで代用できます。熱中症になったときは必ず塩あめまたは梅干し1個に対し、コップ1杯の水を飲みましょう」と話す。
かいた汗を蒸発させ、気化熱によって体を冷やすのに役立つのが、扇子やハンディファン。「深部体温までは下がりませんが、肌表面の温度は下げることができます。暑さを和らげて快適に過ごすのに役立つでしょう」(谷口氏)。ただし、非常に外気温が高い環境では、かえって熱い風を浴びてしまうことに留意したい。その場合はぬれたタオルなどで体を拭いてから使うとよいだろう。
首を冷やすグッズもあるといい。冷たいタオルや首回りに保冷剤を巻くようなネッククーラー(ネックリング)などのグッズがあるが、キンキンに冷えたペットボトル飲料も効果的だ。首筋や額に当てて涼を得ることができる。暑くてたまらないときは、特に首の両側、脇の下、そけい部といった太い血管が通る場所を冷やすのがポイントだ。こうした部位に当てることで効率よく体温を下げることができる。洋服の上からでは、首の両側の頸(けい)動脈を冷やすといい。
-
- 正しい知識で熱中症を防ぐ! 水分補給の仕方は? 危険な場合は?
-
毎年、夏の時期が訪れると、過酷な暑さと共に増えるのが熱中症だ。高温多湿になると、体内の水分が失われて脱水症が起こりやすくなり、脱水症は熱中症を引き起こす。夏は命を守る戦いの季節。今回は熱中症を防ぐための基本的な知識から対策まで紹介する。
-
- 糖尿病になるまでの「3ステップ」 その対策はどうすればいい?
-
日本に約550万人の患者がいると言われている糖尿病。自分は大丈夫だろうかと気になる人もいるのではないか。その糖尿病に関するトピックとして、「体の血糖コントロールの仕組み」「糖尿病のタイプ」や「血糖値が上がりにくい食べ方」「予防・対策のための運動」について見ていく。
-
- 誰もがなる「白内障」、失明原因1位「緑内障」 早期発見のカギ
-
年を重ねたら誰もが必ずなる病気で、眼鏡をかけても矯正できない白内障。日本人の中途失明原因の1位であり、40歳以上の20人に1人がかかるという緑内障。視機能低下を進ませるこれら2つは、一体どうしたら早期発見でき、どんな治療をするのでしょうか。過去の人気記事を基に、多くの人が直面する白内障・緑内障との付き合い方を見ていきましょう。
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 24
昨夏、全国平均気温が気象庁の統計開始以降、最も高くなり、過酷な暑さが全国を襲った。気象庁は7月18日、この先の1カ月予報(7月20日~8月19日)は全国的に平年より気温が高く、猛暑になる見込みと発表。今年も、恐ろしい暑さがやってきた。
高温で高湿度になると、体内の水分が失われて脱水症が起きる。脱水症が熱中症を引き起こすのはもちろんだが、様々な恐ろしい病気を引き起こすのだ。夏は命を守る戦いの季節。暑さから命を守る術を、熱中症・脱水症対策に詳しい済生会横浜市東部病院患者支援センター長の谷口英喜氏に聞いた。また、雑貨店で売れている夏のひんやりグッズも紹介する。
谷口英喜(たにぐち ひでき)氏 済生会横浜市東部病院患者支援センター長、医学博士、麻酔科医師
有料会員になると、鍵つき記事が全て読める&医療専門家に電話相談や名医紹介も!
-
- 正しい知識で熱中症を防ぐ! 水分補給の仕方は? 危険な場合は?
-
毎年、夏の時期が訪れると、過酷な暑さと共に増えるのが熱中症だ。高温多湿になると、体内の水分が失われて脱水症が起こりやすくなり、脱水症は熱中症を引き起こす。夏は命を守る戦いの季節。今回は熱中症を防ぐための基本的な知識から対策まで紹介する。
-
- 糖尿病になるまでの「3ステップ」 その対策はどうすればいい?
-
日本に約550万人の患者がいると言われている糖尿病。自分は大丈夫だろうかと気になる人もいるのではないか。その糖尿病に関するトピックとして、「体の血糖コントロールの仕組み」「糖尿病のタイプ」や「血糖値が上がりにくい食べ方」「予防・対策のための運動」について見ていく。
-
- 誰もがなる「白内障」、失明原因1位「緑内障」 早期発見のカギ
-
年を重ねたら誰もが必ずなる病気で、眼鏡をかけても矯正できない白内障。日本人の中途失明原因の1位であり、40歳以上の20人に1人がかかるという緑内障。視機能低下を進ませるこれら2つは、一体どうしたら早期発見でき、どんな治療をするのでしょうか。過去の人気記事を基に、多くの人が直面する白内障・緑内障との付き合い方を見ていきましょう。
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 25
この記事では、今知っておきたい健康や医療の知識をQ&A形式で紹介します。ぜひ今日からのセルフケアにお役立てください!
有料会員になると、鍵つき記事が全て読める&医療専門家に電話相談や名医紹介も!
-
- 正しい知識で熱中症を防ぐ! 水分補給の仕方は? 危険な場合は?
-
毎年、夏の時期が訪れると、過酷な暑さと共に増えるのが熱中症だ。高温多湿になると、体内の水分が失われて脱水症が起こりやすくなり、脱水症は熱中症を引き起こす。夏は命を守る戦いの季節。今回は熱中症を防ぐための基本的な知識から対策まで紹介する。
-
- 糖尿病になるまでの「3ステップ」 その対策はどうすればいい?
-
日本に約550万人の患者がいると言われている糖尿病。自分は大丈夫だろうかと気になる人もいるのではないか。その糖尿病に関するトピックとして、「体の血糖コントロールの仕組み」「糖尿病のタイプ」や「血糖値が上がりにくい食べ方」「予防・対策のための運動」について見ていく。
-
- 誰もがなる「白内障」、失明原因1位「緑内障」 早期発見のカギ
-
年を重ねたら誰もが必ずなる病気で、眼鏡をかけても矯正できない白内障。日本人の中途失明原因の1位であり、40歳以上の20人に1人がかかるという緑内障。視機能低下を進ませるこれら2つは、一体どうしたら早期発見でき、どんな治療をするのでしょうか。過去の人気記事を基に、多くの人が直面する白内障・緑内障との付き合い方を見ていきましょう。
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定
Page 26
この記事では、今知っておきたい健康や医療の知識をQ&A形式で紹介します。ぜひ今日からのセルフケアにお役立てください!
「ビタミン」についての問題
【質問】糖質の代謝に不可欠な補酵素として機能し、その不足がかつて国民病と言われた「脚気(かっけ)」の原因になったビタミンは次のうちどれでしょう。
- (1)ビタミンB1
- (2)ビタミンB6
- (3)ビタミンD
- (4)ビタミンE
- (5)葉酸
-
- 正しい知識で熱中症を防ぐ! 水分補給の仕方は? 危険な場合は?
-
毎年、夏の時期が訪れると、過酷な暑さと共に増えるのが熱中症だ。高温多湿になると、体内の水分が失われて脱水症が起こりやすくなり、脱水症は熱中症を引き起こす。夏は命を守る戦いの季節。今回は熱中症を防ぐための基本的な知識から対策まで紹介する。
-
- 糖尿病になるまでの「3ステップ」 その対策はどうすればいい?
-
日本に約550万人の患者がいると言われている糖尿病。自分は大丈夫だろうかと気になる人もいるのではないか。その糖尿病に関するトピックとして、「体の血糖コントロールの仕組み」「糖尿病のタイプ」や「血糖値が上がりにくい食べ方」「予防・対策のための運動」について見ていく。
-
- 誰もがなる「白内障」、失明原因1位「緑内障」 早期発見のカギ
-
年を重ねたら誰もが必ずなる病気で、眼鏡をかけても矯正できない白内障。日本人の中途失明原因の1位であり、40歳以上の20人に1人がかかるという緑内障。視機能低下を進ませるこれら2つは、一体どうしたら早期発見でき、どんな治療をするのでしょうか。過去の人気記事を基に、多くの人が直面する白内障・緑内障との付き合い方を見ていきましょう。
「日経Goodayマイドクター会員(有料)」に会員登録すると...
- 1オリジナルの鍵つき記事がすべて読める!
- 2医療専門家に電話相談できる!(24時間365日)
- 3信頼できる名医の受診をサポート!※連続して180日以上ご利用の方限定



