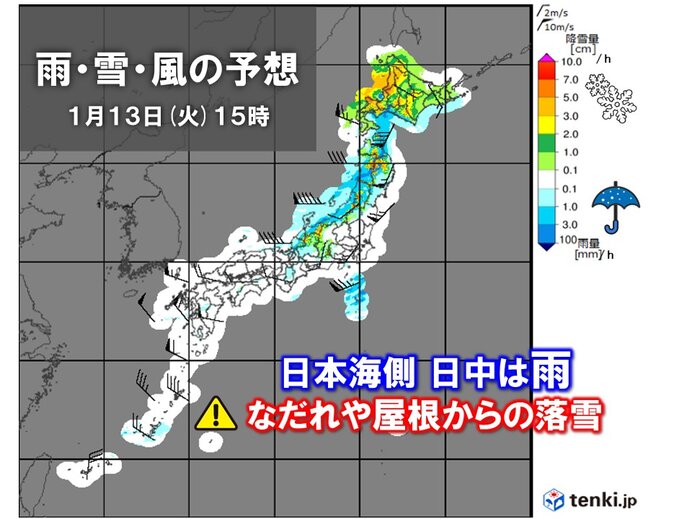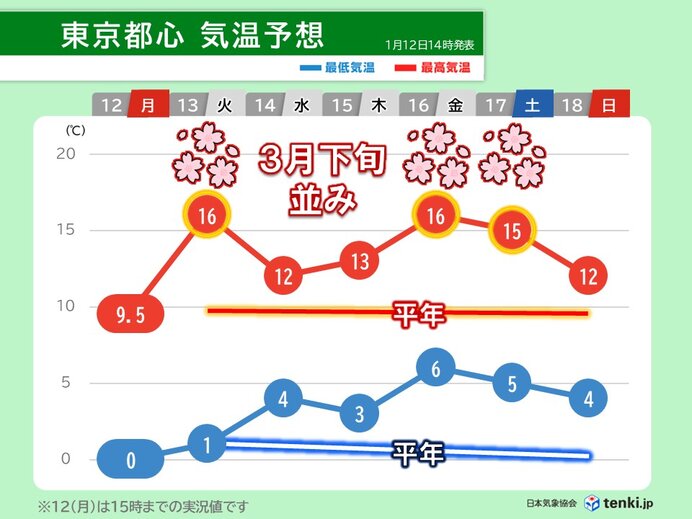「事情聴かず誤認」「教育長への指導は越権行為」…第三者委、斎藤知事の行為を詳細に分析・正当性否定

兵庫県の斎藤元彦知事がパワハラなどの疑惑を内部告発された問題で、19日に調査報告書を公表した県の第三者委員会は、斎藤氏の行為がパワハラに該当するかを詳細に分析して10件を認定し、正当性を訴える斎藤氏の主張を否定した。どのような判断に基づいて結論を出したのか。
■10件認定
2020年6月施行の改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)は、パワハラについて▽優越的な関係を背景とした言動▽業務上必要かつ相当な範囲を超えている▽労働者の就業環境が害される――と定義。厚生労働省の指針では、パワハラに該当する行為を「精神的な攻撃」「過大な要求」など6類型に分類している。
元裁判官ら6人の弁護士で構成する第三者委は、この法律や指針を踏まえた上で、前県西播磨県民局長(昨年7月に死亡)の告発文書などで指摘された斎藤氏の16件の行為について、パワハラに該当するかを検討し、うち10件を認定した。
報告書によると、認定された10件の一つで、告発文にあった「出張先で公用車を降り、20メートル歩かされただけで職員をどなり散らした」行為は、県立考古博物館(播磨町)で23年11月、会議に出席する斎藤氏を職員2人が出迎えた際の出来事だ。
博物館周辺の地下には遺跡があり、埋蔵物を保護するため、玄関に通じる歩行者用通路の車両の通行は禁止され、車止めが置かれていた。斎藤氏の公用車は車止めの前で停車し、降りてきた斎藤氏が「何でこんな所に車止めを置いたままにしているのか」と、2人を激しく 叱責(しっせき) した。
職員の一人は、知事がなぜ怒っているのか理解できずに驚き、自分がうまく会議の場を取り持つことができるか不安になった。
斎藤氏はおおむね事実と認めた上で、「通路が車両通行禁止とは知らされていない当時の認識では、職員の対応が不適切と考えた判断は誤っていない」とし、注意や指導が必要だったと主張した。
これに対し、第三者委は「叱責する前に事情を聞きさえすれば、(車両通行禁止という)前提事実について認識を誤ることはなかったのだから、注意や指導を行うべき客観的な必要はない」と判断。斎藤氏の立場が圧倒的に強いことも指摘した。職員の一人は「パワハラとは思っていない」と話したが、他の職員の勤務環境を害した面もあり、「パワハラ認定が否定されるものではない」とした。
■教育長が謝罪
また、県立美術館(神戸市)が修繕のため23年の夏休み期間中に休館するとの新聞報道について、7月20日夜に知った斎藤氏は「聞いていない」と激怒し、翌日、「発表が急すぎる」などと教育長を叱責した。教育長は25年の大阪・関西万博で美術館を活用するため、最低限の修繕が必要だと説明したが、斎藤氏は納得せず、教育長は「すみません」と繰り返し謝罪した。
第三者委は、県立美術館は知事から独立した県教育委員会の所管で、知事には休館について指導する権限はなく、教育長への指示は「越権行為」だったと指摘。休館期間には合理的な理由があり、「指導の必要性は認められない」とした。
■「司法が判断」疑問
斎藤氏の言動を巡っては、県議会百条委員会も4日に公表した調査報告書で、一部の行為を「パワハラ行為と言っても過言ではない」と指摘していた。
斎藤氏は翌日の記者会見で、「ハラスメントは、最終的には司法の場で判断されるのが一般的」と主張。しかし、実際には、企業や自治体の多くが裁判とは無関係に、厚労省の指針などを参考に社員や職員のパワハラを認定している。兵庫県もパワハラを理由に職員を懲戒処分にしたケースがある。
元大阪高裁判事で、第三者委委員長の藤本久俊弁護士は19日の記者会見で、「裁判に訴えられた件だけがパワハラ(と認定される)ということは、違うのではないか」と述べ、斎藤氏の主張に疑問を呈した。
繰り返す恐れも
労災問題に詳しい上出恭子弁護士(大阪弁護士会)の話 「第三者委は中立的な立場の弁護士が様々な事実を照らし合わせて判断しており、パワハラが認定されたことは重い。斎藤知事に結論を 真摯(しんし) に受け止める姿勢がなければ、同じことが繰り返される恐れがある」