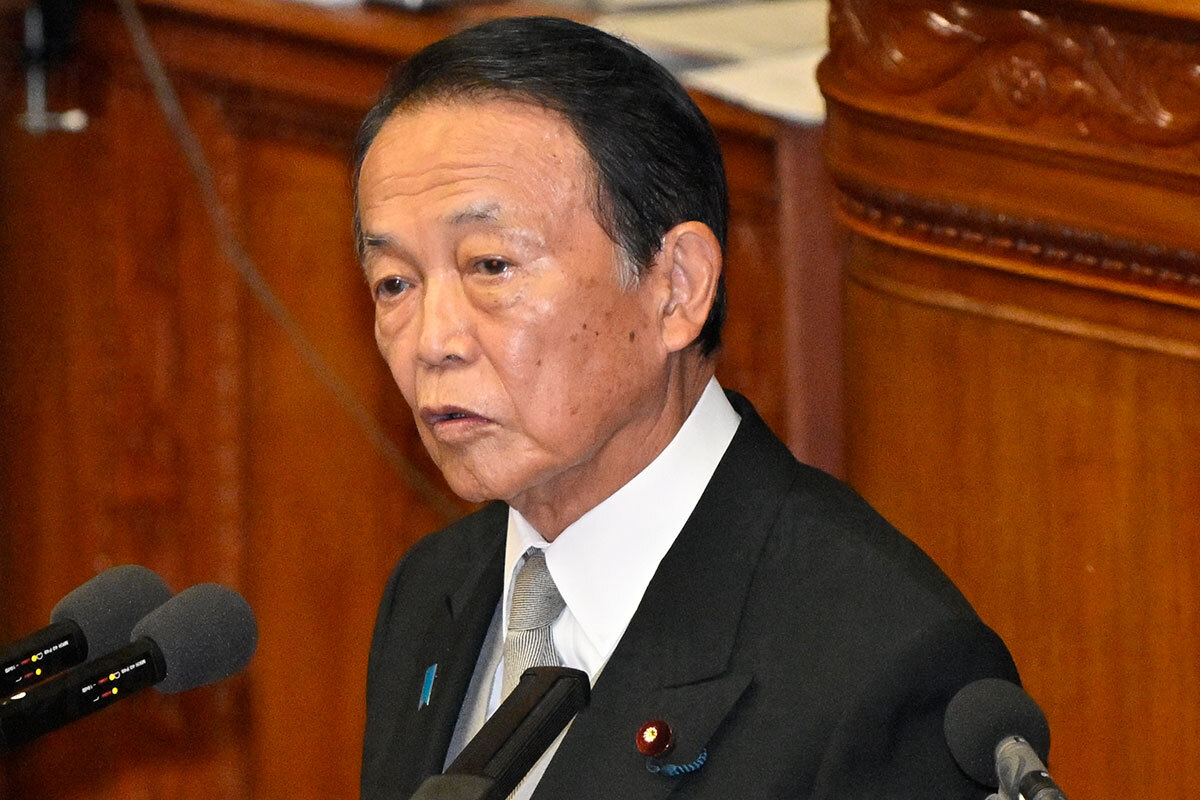京大の「タテカン」 自由と社会性の表現 入試日などに設置

「さあ、みんなで(受験生を)精いっぱい応援しましょう」
京都大学(京都市左京区)の入学試験初日の2月25日早朝。自作した立て看板、通称「タテカン」を設置するため、京大の自治寮「熊野寮」に約30人の学生たちが集まった。サングラスにマスクという物々しい見た目。彼らが顔を隠すのは、設置行為が大学からの処分対象となる可能性があるためだ。
タテカンは学生運動が盛んだった1960年代から目立ち始め、京大の「自由な学風の象徴」として、キャンパス周辺に立てられた。長く続いた光景が一変したのは2018年5月。都市景観保護のため屋外広告物の規制を京都市が厳格化したことを受けて、京大はタテカンに関する「京都大学立看板規程」を作成し、撤去を開始した。その規制に対して大学内外から見直しの声が上がり、21年4月には京大職員組合が「表現の自由」の侵害にあたるなどとして大学当局と京都市を相手に提訴している。
Advertisement規制が始まって約7年、処分の危険を冒してまでタテカンを立て続ける学生たちが今もいる。彼らが所属する大学非公認のタテカンサークル「シン・ゴリラ」は規制を受けて設立。当時の京大学長であった山極寿一・名誉教授の専門分野である霊長類のゴリラをもじって命名された。
主な活動はゲリラ的にタテカンを立てることで、約1カ月に1度のペースで設置を続けている。その中でも、入試日の朝に受験生を鼓舞するためのタテカンは数が多く、今年は大学正門側の東一条通と本部キャンパス北西に位置する百万遍交差点の石垣に約50枚が並んだ。広島市南区から来た受験生は「去年受けた時に見て、自由な雰囲気を知り、ここで学生生活を送りたいと思った」という。
「自分もそうだった」と話すのはシン・ゴリラのメンバー、佐藤一男さん(23歳、仮名)。受験時に「自由の原体験」を目の当たりにした学生が、今度は描く側になって伝えていく「連鎖」がある。しかし、4年で学生のほとんどが入れ替わる大学において、規制前の景色を知る学生が現在ほとんどいないことは大きな問題とも話す。
24年末の12月24日、百万遍交差点の石垣にタテカンが設置された。信号待ちをしていた農学部2年生の男子学生(20)は「経緯は知らないが、大学がダメと言うことをなぜするのかわからない」とつぶやいた。インターネットでタテカンが立ち並ぶ70年代の写真を見たことはあるが「時代錯誤、ノスタルジーの押し売り」と一蹴した。
佐藤さんは「自由を奪われたことに抵抗するという意志は(京大生の中で)薄れている気がする」と嘆く。
また、学生時代にタテカンを制作したことがある京都市北区の会社員男性(37)は「権力を疑うことなく、『お上』が言うことは正しいとうのみにする傾向は学生だけでなく、社会の風潮としてあるように感じる」と案じた。
現在、タテカンを設置できるのは大学敷地内で指定された5カ所のみ。また、公認団体に限られ、氏名や連絡先を明記する必要がある。事故が起きた際、大学に一定の責任が生じることなどが理由だが、一方で大学と学生間で起きている問題などを、氏名を明かして描くことは難しいため、社会に伝える手段を奪われたと語る学生もおり、条例への対応であれば学内にも及ぶ制限は過剰ではないかとの声もある。
景観保護を目的とした規制のためか、設置が許された場所はキャンパス外から、ほぼ見えない。そのことに憤る人たちもいる。
学園祭に来ていた京都市西京区の会社員、山下健さん(65)は、以前は仕事の移動で車からタテカンを眺め、アメフトの試合日や学生が日々考えていることの一端を知れたという。「外の人が大学と交流する窓口がタテカンだった。大学や学生だけでなく、タテカンは地域の人のためでもあるのに」と現状に落胆する。
近隣に30年以上住む主婦(62)は「タテカンが祇園の花街にあれば違和感があるが、京大周辺で何の景観を壊すのか。学生らの主張は営利目的の広告ではない」と市の対応にも疑問を呈した。
タテカンを今でも描く学生の多くは、規程が作られたプロセスにも怒りを持っているという。規程が施行される前の18年2月、反発した学生たちは学内の諸団体と連名で、公開の場での話し合いや説明を求める要求書を提出した。
しかし、京大は「既に決定された」と拒否し、撤去が開始された。対話を重んじる学風とも言われ、「京大らしい」在り方を学生と一緒に模索してきた最高学府だからこそ、「学生が担ってきた文化を、当事者なしに一方的に決めた姿勢は許せない」と佐藤さんは語気を強める。
交流サイト(SNS)が主流の現代において、なぜ、前時代的とも言えるタテカンなのか。そんな問いに、佐藤さんは「タテカンは社会性を持った表現だからこそ、作り手に大きな視点を持たせてくれる」と答えた。
イスラエルによるパレスチナ自治区ガザ地区への武力行使に反対し、2年間毎週飾られているつり看板。過剰な承認欲求が街を壊す様をかわいらしいアニメ調で描いた巨大なタテカン。内容はさまざまだがウイットに富んだ絵や文字で、見る人に訴えかける表現は、タテカンだからこそ生まれるもの。仲間と一緒に作って、立て掛けるという強い主体性を持つことで、その視点は育まれてきた。
「立て続けることは、文化をつなぐこと」。後輩にも、まだ見ぬ未来の京大生にも自由な大学の空気感を残していきたいという。
先述の主婦は学生たちに理解を示す。「京大の学風を守っているのは大人ではなく、学生なのかもしれないね」【山崎一輝】