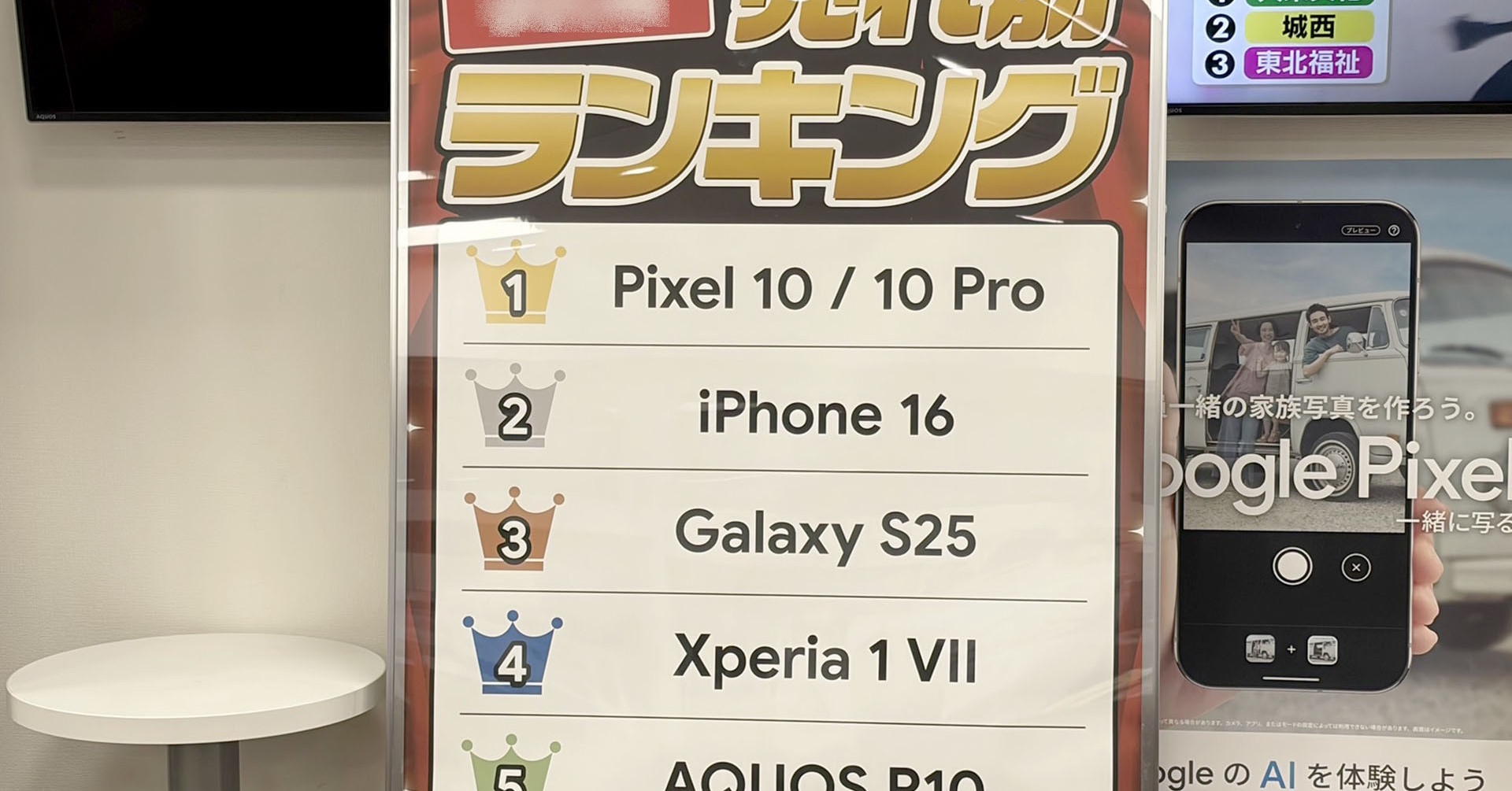M4搭載「MacBook Air」レビュー:M4モデルで“最後発”だった理由が見えた

「M4」チップを搭載したアップルの新しい「MacBook Air」は、昨年の同時期に発表されたM3版の仕様をほぼ完全に踏襲したうえで性能向上を図っている。美しいスカイブルーという新色が用意され(スペースグレイが廃番になった)、カメラが高解像度なものになってセンターフレームやデスクビューなどの機能を搭載したうえで、M3モデルの初期バージョンと比べるとメモリーが倍増となってお値段は据え置きという非常に買い得なモデルだ。
米国の新入学シーズンまでは半年あるが、日本ではちょうど大学に入学すると同時にMacBook Airを購入する学生が多いだろうから、タイミングのいいアップデートといえる(大学生協で大量購入が決まっているところでは、大混乱かもしれないが……)。
そんな人気機種のMacBook Airだが、最初のApple シリコンである「M1」を搭載したモデルとして登場したときはその性能の向上ぶりが大きく注目されたし、「M2」搭載モデルでは冷却ファンをもたない画期的な構造を実現して喝采を浴びた。それなのに、今回のM4搭載に際しては少し遅れてのアップデートとなっている。
なにしろ、M4は昨年5月に「iPad Pro」に搭載され、秋には「iMac」「MacBook Pro」にも搭載されたのだから、MacBook Airの購入を検討していた人は非常に待たされた感じがしたことだろう。いったい、なぜなのだろうか? 今回はこのあたりを少し考察してみたい。
iPad Proへの搭載から10カ月かかって、ようやくMacBook Airに搭載されたM4チップ。なぜ、こんなに時間がかかったのだろうか? PHOTOGRAPH: Apple
MacBook Airが“後回し”になった理由
いちばん売れる花形機種のMacBook Airが、なぜ後回しになってしまったのか? その理由を考えるためのヒントは、同時に発売される「Mac Studio」のチップ構成にある。
今回、Macの頂点となるモデルとして登場したMac Studioの最上位のチップセットは、なんと旧世代チップのM3をベースとした「M3 Ultra」だったのだ。そして、下位モデルに搭載されていたのが「M4 Max」である。高いお金を出してフラッグシップモデルを購入する人が、旧世代チップセットのモデルを買わなければならない状況は釈然としない。
こうなった理由を説明するために、Apple シリコンの事情を少し説明しよう。
アップルは2020年6月、これまで採用してきたインテルの「Core i」シリーズのチップセットの搭載をやめ、独自チップであるApple シリコンへの移行を発表した。そして20年11月に最初のApple シリコンであるM1チップを搭載したMacBook Airが発表された。インテルのチップを使っていては、どうしても製品ラインナップの核心部分をインテルの施策に左右されてしまう。アップルは自社製チップセットを開発することで、自分の好きなタイミングで好きな製品を開発する自由度を得たのだ。
このM1チップの設計はアップルによるものだが、台湾のTSMC(台湾積体電路製造)で生産されている。ご存知のように、TSMCの集積回路の生産技術は現在のところ世界最先端である。微細な集積回路を生産できるということは、つまりは速く、パワフルな処理を、省電力でこなせる集積回路をつくれるということだ。
アップルは、一説には年間2億台ともいわれる世界一の需要をもつiPhone用チップ「A」シリーズの発注を背景に、Mac用チップであるMシリーズをTSMCに生産させることができる。
ボディ形状がくさび形ではなくなった現行MacBook Airの最大の特徴は、ファンレスであること。ご覧のようにヒンジ部分に小さな穴はあるが、排熱は自然の対流のみ。そのくらい発熱が少ないのだ。
M1チップとは非常におおまかに言うと、「iPhone 12」シリーズに搭載されている「A14 Bionic」(「N5」と呼ばれる5nmプロセスで生産されている)のコア数を2倍にしたようなプロセッサーである。CPUや機械学習用の「Neural Engine」はその限りではないが、いちばん大きなスペースを必要とするGPUに関してはほぼ倍になっている。さらに、M1の倍が「M1 Pro」、その倍が「M1 Max」、さらにその倍が「M1 Ultra」という構成で、同じ回路設計を繰り返すことでスケールを大きくする方式がとられている。
同じように、「A15 Bionic」の技術(5nmプロセスの強化版である「N5P」)を利用するM2、「A17 Pro」の技術(3nmプロセスである「N3B」)を利用するM3、そして昨年秋に発売された「iPhone 16」シリーズに搭載された「A18」「A18 Pro」と共通の技術(3nmプロセスの強化版である「N3E」で生産)を搭載するのがM4シリーズということになる。
Apple シリコンの開発は、おおまかにはこのような方針で進んでいる。ところが、実際にはそれほどシンプルにはいかないようだ。
そもそも、iPhoneは毎年9月に新モデルが発表され、Aシリーズのチップセットは毎年アップデートされる。だが、TSMCのチップセット製造技術が足取りを合わせて更新されていくとは限らない。
また、アップルにとってiPhoneは毎年アップデートする必要がある製品だが、Mac、特に上位機種を毎年更新するのは頻繁すぎる。
その顕著な例が、今回のMac Studioの新モデルで、下位モデルはM4 Maxを搭載しているというのに、上位モデルはM3 Ultraの搭載という“逆転現象”が起きてしまう。アップルによると、M4 Maxはチップセット自体の処理能力の高さを期待できるので、音楽制作やビデオ編集、コーディングなどに向いているという。M3 Ultraのほうは最大80コアのGPUと512GBのメモリーを搭載可能なので、大きなデータセットの処理……もっとわかりやすく言うと大規模言語モデル(LLM)の動作に向いていると説明している。
取材したところによると、M4 MaxにはM3世代までに存在した複数のチップを接続する「UltraFusion」と呼ばれるインターコネクト機能は搭載されていない。つまり、基本的には「M4 Ultra」に相当するチップセットは開発できないので、話の筋としては合っている。しかし、購入する側としては複雑な気持ちがする。
Apple シリコン固有の事情
Apple シリコンの開発は各世代において、Aシリーズ→Mシリーズ→Mシリーズの「Pro」→Mシリーズの「Max」→Mシリーズの「Ultra」と進んでいくのだろうが、それぞれただ接合すれば済むという話ではなく、必要な速度でデータをやりとりするために独自の設計が必要になる。また、メディア処理に用いるためにM2で搭載された「メディアエンジン」や、M3でメディアエンジンに搭載されたAV1デコーダー、M4で搭載されたダイナミックキャッシング機能やハードウェアアクセラレーテッドレイトレーシングなど、負荷のかかる処理に特化した専用の回路が追加されることもある。
その結果、M3 Ultraが登場するまで、同世代のチップであるA17 Proが発表されてから1年6カ月もかかってしまっている。このネーミング方式を継続していては、最上位機種が登場したときに、すでにそれが旧型に見えてしまうという問題が発生し続けるというわけだ。
チップセットの名称を気にするのはデバイスに詳しい人であろうから、新しく開発された最新鋭のチップセットはMacBook ProやMac Studioから先に搭載するということになるのだろう。また、生産可能な数の問題もあり、いちばん販売量の多いMacBook Airから搭載するのは難しい側面もあったのかもしれない。
というわけで、M1、M2はそれぞれMacBook Airに最初に搭載されたが、2023年にMacBook Airの15インチモデルを投入して一拍おいたことでM2版のMacBook Airを2年もたせて、MacBook Airの販売を同世代チップセット対応の後半にもってきたわけである。
登場はM4搭載モデルのなかでは遅めになったが、それだけMacBook Airが一般のコンシューマーに受け入れられた“名機”ということだろう。大量に供給しなければならないから年間スケジュールの後半にもってきて、チップセットの供給量が増えてから生産することになったと考えていい。
これが、MacBook AirへのM4チップの搭載が最後になった理由だと思われる。
性能はいかなるものか?
今年のMacBook Airの新色はスカイブルーだ。写真では伝わりにくいと思うが、本当に薄いシルバーに近い青である。iPadのブルーはもちろん、「iPad Air」のブルーよりさらに薄い青みがかったシルバーといったほうがよさそうな色だ。
写真では伝わりにくいと思うが、非常に美しい新色のスカイブルー。限りなくシルバーに近く、薄くブルーが入っている感じだ。
それでは性能はいかなるものか。新しいM4と、M1~M3を加えた計4世代のMacBook Airをベンチマークソフト「Geekbench 6 Pro」にかけてみた。
M4版のMacBook AirをGeekbench 6 Proにかけた。
MacBook AirのM1モデルからM4モデルまで、それぞれGeekbench 6 Proにかけた。驚くほど均等に性能向上しているように見えるが、M2とM3の間だけは2年かかっている。
結果はご覧の通り。きれいな右肩上がりに性能が向上しているように見えるが、途中でCPUやGPUのコア数が増えたり、M2とM3の間は2年あったりすることを考えると、むしろこうやってきれいに性能向上させるために何らかの調整を加えているのかもしれない。
Geekbench AIの結果はもっと激しく、性能差が大きい。Apple Intelligenceの搭載が決まってから、ここに大きく注力してきたのだろうと思われる。
こちらは生成AIに関連する性能を計測できるベンチマークソフト「Geekbench AI」の結果だ。特にApple Intelligenceの利用で重要になると言われている「Quantized(量子化)」の数値が大きく上がっており、M1とM4で比較すればおよそ3.2倍の性能向上となっている。Apple Intelligenceの活用が増えてくれば、M1世代をまだ使ってる人は買い替えを検討してもいいかもしれない。
安心して購入できるスタンダードモデル
チップセット以外の大きな変更点としては、画質が1080pだったFaceTimeカメラが1,200万画素のセンターフレームカメラになったこと。1,200万画素といっても高解像度になったというよりは、iPhoneの超広角カメラのようなワイドのカメラで、そのうち一部を切り取って広角のひずみを修正し、センターフレームカメラ(ユーザーを追跡して映す機能)とデスクビュー(机の上のものを映す機能)を実現している。
あと、非常に細かい点だが、日本語キーボードでは、キートップの「英数」「かな」の印字が、「ABC」「あいう」に変更された。この変更は同じ日に発売されたiPad Air用の「Magic Keyboard」にも適用されているので、今後この仕様に移行していくのだろう。
Photograph: TAKUTA MURAKAMI
新しいモデルにアップデートされるたびに、着実に性能が向上するMacBook Air。いつ買っても、その時点でのベストな性能を得られるという点は、今回のM4版のMacBook Airでも変わらない。安心して購入できる製品だ。
(Edited by Daisuke Takimoto)
※『WIRED』によるアップルの関連記事はこちら。MacBookシリーズの関連記事はこちら。
Related Articles
雑誌『WIRED』日本版 VOL.55「THE WIRED WORLD IN 2025」 発売中!
『WIRED』の「THE WIRED WORLD IN 20XX」シリーズは、未来の可能性を拡張するアイデアやイノベーションのエッセンスが凝縮された毎年恒例の大好評企画だ。ユヴァル・ノア・ハラリやオードリー・タン、安野貴博、九段理江をはじめとする40名以上のビジョナリーが、テクノロジーやビジネス、カルチャーなど全10分野において、2025年を見通す最重要キーワードを掲げている。本特集は、未来を実装する者たちにとって必携の手引きとなるだろう。 詳細はこちら。