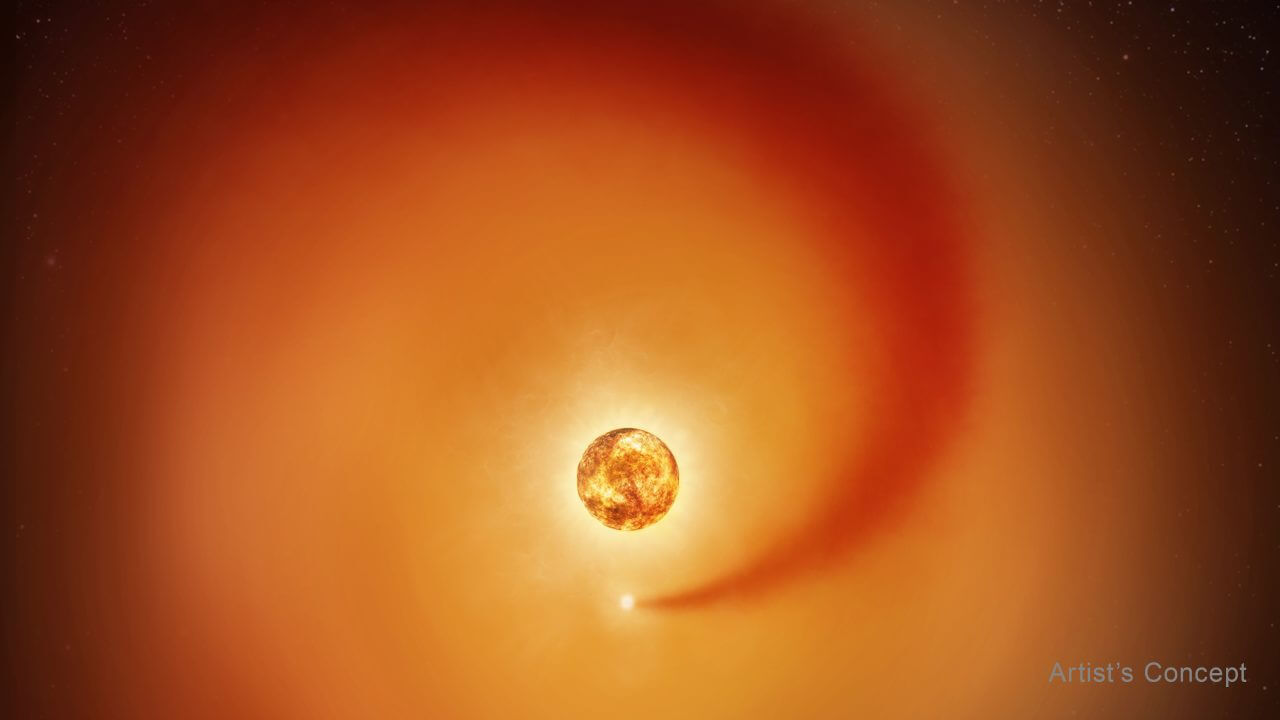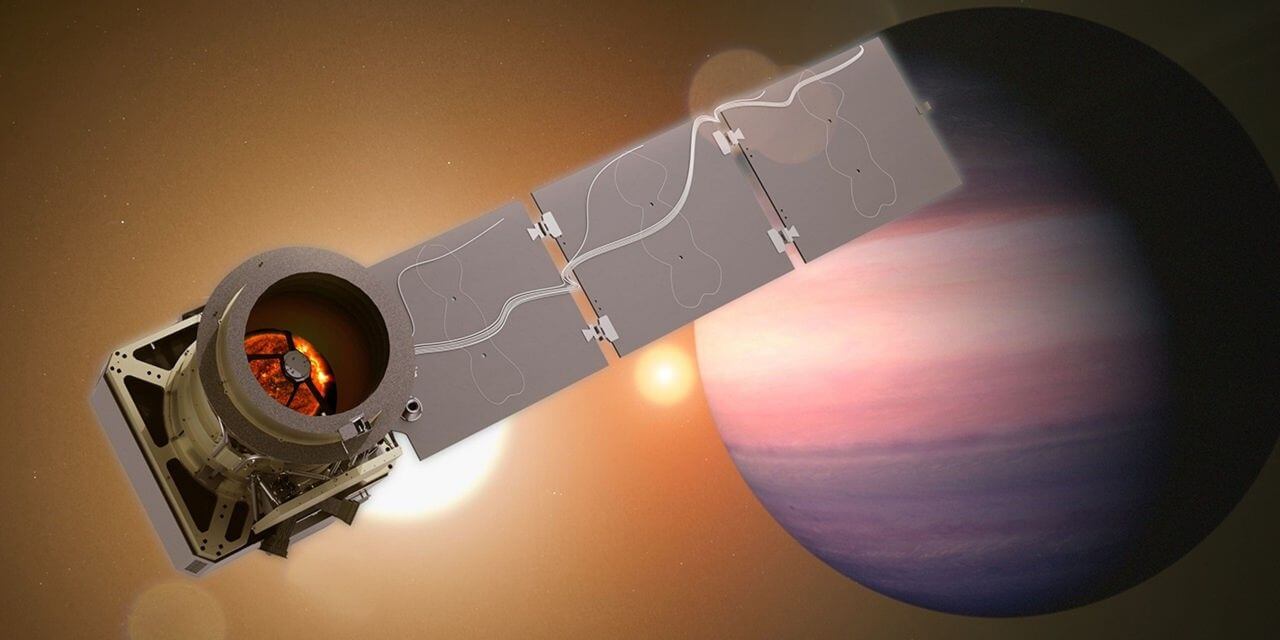東大生《鬼滅の刃》炭治郎が無限城を落下する速度を暗算→水柱・冨岡義勇のヤバさに気付いた 少しだけ数字が好きになる「手抜き」計算とは

9:01 配信
数字に強い人とそうでない人。いったい何が違うのでしょうか? 実は、「数字に強い」というのは、ただ生まれ持ったセンスがあるというものではないのです。計算の仕方を工夫したり、数字の捉え方をほんの少し変えてみるだけで、誰でも「数字に強い」人になれるのです。この記事では、『数字に強くなる30のトレーニング』(TAC出版)を上梓した西岡壱誠さんが、割り算のテクニックをご紹介します。
■“無限”城は実際のところ…
みなさんは『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』をご覧になりましたか? 公開後60日時点で興行収入は330億円を突破。日本映画の金字塔『千と千尋の神隠し』はいまや3位に陥落し、1位2位を『鬼滅の刃』が独占しています(1位は『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』)。日本アニメ映画界の歴史を塗り替えたともいえる本作。ただ、筆者にはどうしても気になる描写がありました。
本作は、テレビアニメ放映された『柱稽古編』の続きが描かれており、主人公の竈門炭治郎ら鬼殺の剣士たちが、みんな「無限城」と呼ばれる鬼たちの総本山へ引っ張り込まれる描写から始まります。鬼たちは「血鬼術」と呼ばれる超常の力を操りますが、その中に強制テレポート能力を持つ鬼がいたのです。
さて、この無限城は、文字通り「無限」の広がりを持つとされる城です。とはいえ、数学的な意味での「無限」の広がりを本当に持つのだとすれば、制御するに足るエネルギーもまた無限大。ほぼ無尽蔵の再生能力を持つ鬼の中で屈指の強さを誇る「上弦」の能力とはいえ、その能力源が文字通り無限とは考えにくいですから、実際のところは「無限(に思えるくらい広大な、たかだか有限の面積・体積を持った)城」なのでしょう。
問題は、この無限城に鬼殺隊士たちが引きずりこまれるシーンです。この無限城は、異空間に異能の力で作り上げられた「城」であり、建築基準法どころか物理法則すら無視して建造されています。一般に「無限城」と言われてイメージできるものは、平面上へ無限に広がる大広間などでしょうが、実際には大量の部屋のブロックが不規則に積み重なっていて、左右どころか上下すらもまた「無限」に続いています。コンテナを不規則に積み上げているようなイメージです。
炭治郎をはじめとする隊士たちは、この「無限」の城へ落とされるように入城しました。運よく部屋部分に落下できた隊士もいたでしょうが、炭治郎は縦穴のように広がる廊下(? )の部分へ落ち込んでしまいます。この時、彼が目にする「無限」の絶景はぜひ劇場で確認してほしいところですが、落下中の彼にそんなことを考える暇はない。
かなりの高さから落とされたのでしょう。映像を見る限り、落ちゆく穴の底は暗闇に閉ざされており、光が届かないほどの深さがあるようでした。薄暗い城内であることを差し引いても、数十メートルはありそう。普通の人間なら明らかに死んでしまいます。
炭治郎の場合には、幸運にも水柱・冨岡義勇の助けを得ることができました。独力で助かるには、どこか建物の縁を掴むか、剣技を繰り出した衝撃で落下ダメージを相殺する必要がありますが、これは非常に困難です。彼の人徳と運が九死に一生を得ました。
ただ、炭治郎の着物を鷲掴みにして助けた冨岡の握力にも注目したい。心の声を吐いている瞬間は時間が流れていないとしても、劇中で見る限りの炭治郎は、少なくとも5秒以上落下しています。それほど落ち続けるなんて、現実ではスカイダイビングくらいでしか体験できません。彼の落下速度は、どれほどだったのでしょうか。
■F1レース並みの落下速度 落下速度vは重力加速度gと時間tの掛け合わせによって計算可能。重力加速度はおよそ9.8m/s²とされますから、仮に落下時間を5秒とするならば、彼の落下速度は 9.8×5=49(m/s)
と推定できます(空気抵抗などを一切無視した場合)。炭治郎の体重は公式設定によれば61kg。冨岡は秒速49mで落下してくる約60kgの物体の軌道を片手で変えたことになります。いくら柱といえども、末恐ろしい身体能力ですね。
ところで、秒速49mと言われても、なんだか速度がピンとこないのは私だけでしょうか。100m走なら2秒ちょっととなり、「人類最速」ウサイン・ボルト選手の9秒58を大幅に更新する大記録です。雑に考えても、ボルトのおよそ4.5倍。なんだかすごく速そうですが、車や電車と比べたらどうでしょうか?
気になってきたので計算してみましょう。分速や時速は、秒速を60倍していくことで求められますが、まずは分速から。炭治郎の瞬間的な落下速度は秒速49mだったので、式は49×60=2,940(m/min.)となります。1kmは1,000mですから、これはだいたい分速3kmくらいです。日常ではお目にかかれない速さですね。
でも、分速なんてやっぱり普段は見慣れません。ここは時速で見てみましょう。2,940×60で時速を求められますが、ちょっぴり面倒くさい。そこで、ここは少し雑に分速3kmと概算してしまいましょう。すると、 3×60=180(km/h)
と求められます。これは、国産自動車のリミッターギリギリの速度であり、実生活上では高速道路ですら拝めません。高速道路を爆走する車の、2倍近い速さで、炭治郎は落下していたのです。これはもう、握力云々だけではなく、反射神経の問題もある気がしてきましたね。
■計算が速くなる「3つのコツ」 さて、ここまで私は無限城を落下する炭治郎の速さを計算で求めてきましたが、実は一切電卓を使っていません。もちろん、フラッシュ暗算とかそろばんとかを習っていたわけでもない。とある「計算のコツ」を知るだけで、誰でも暗算で計算できるようになれるんです。 今回紹介するコツは以下の3つ。①10倍を作る②難しい計算から逃げる③「ざっくり」で求める
まず、「10倍を作る」から。私は最初、炭治郎の落下速度を物理公式「v=gt」にあてはめて、9.8×5の計算をしました。でも、小数点があると、なんだかしり込みしてしまいますよね。そこで、「10倍を作る」が効果を発揮します。
やり方はいたってシンプル。無理やり「×10」を作ってしまうだけ。今回の場合は9.8×5を、9.8×10にしてしまう。でも、これでは計算結果が元の式と違ってしまいますね。2倍も大きな数が出てきてしまうからです。ですから、最後に2で割って、帳尻を合わせましょう。すなわち、 9.8×5=9.8×10÷2
としてしまう。10倍の計算なら、小数点をひとつ右にずらすだけ(もしくは末尾に0を追加するだけ)ですから、簡単です。9.8×10=98を出してから、これを2で割ってあげればいい。
■「めんどくさい」なら問を捻じ曲げる でも、98を2で割るのもちょっとめんどくさい。そんな時、2つ目の「難しい計算から逃げる」が役に立ちます。98÷2や49×60など、「あとちょっとでキリのいい数になるのになぁ」と感じるときは、えいやっとキリのいい数にしてしまいましょう。
例えば、98÷2は100÷2にしてしまう。49×60も50×60にしてみます。これなら、前者は50、後者は3,000と答えやすくなりました。もちろん、ここで計算は終わりません。帳尻を合わせましょう。
98÷2を100÷2にするときには、何をしたでしょうか? 割られる数に、2を足しましたよね。ですから、その分だけ引いてやらないといけません。ただし、2を足しましたが、2を引くわけではないことに注意してください。例えば、2÷2=1ですが、割られる数に2を足した4÷2=2ですよね。同じように、6÷2=3で、8÷2=4と考えると、「割られる数に足した数を、割る数で割った分だけ計算結果からマイナスする」ルールが見えてきます。ですから、50-(2÷2)=50-1=49が答えとなります。
同じように、49×60の方も見ていきましょう。49なんて、とっても惜しい数です。あとちょっとで50になるのに。50になれば、コツ①「10倍を作る」を応用して、×100を作り、楽に計算できます。
それなら、いっそ50にしてしまいましょう。50×60に読み替えてみると、50×60=3,000とかなり計算が楽になりました。ただ、やはりこれでは正確な結果ではない。差し引きプラスマイナスゼロになるよう調整しないといけません。
49×60は、前後逆にして60×49と読み替えても計算結果は変わりません。「49個入りのクッキーが60缶ある」でも「60個入りのクッキーが49缶ある」でも、クッキーの総量は変わらない。
ただ、今回は49缶しかないクッキー缶を「50缶ある」と数え間違えて計算してしまいました。60×50では、ちょうど60個だけ多くなってしまう。なので、60個引き算します。3,000-60=2,940となり、これで正しい計算結果が出てきました。
■暗算のコツは「手を抜く」こと
ここまでいろいろ計算してきましたが、大体は「計算しやすい数を作って、あとから帳尻を合わせる」ことが肝でした。お察しの通り、計算が速くなるコツとは「頑張らないで計算できるフィールドに引っ張り込む」こと。もちろん仕事や研究で必要な計算は正確性が求められますが、スーパーに買い物へ出たとき「298円」とか「1,980円」とかを1円単位で正確に計算しなくても、お財布事情に支障をきたすことはないでしょう。
だからこそ、コツ③「『ざっくり』で求める」が役に立ちます。最後、炭治郎落下速度の時速を求める際には2,940×60を計算する必要がありました。でも、別に私たちには正確な速度は必要ありませんよね。大雑把に、ざっくりでいいから「こんなに速いんだ!」を実感できればそれで十分なはず。なら、2,940×60を3,000×60に読み替えても、そんなに大きな問題はありません。実際に、分速2,940m×60をすると、時速176.4kmとわかりますが、正直日常の感覚で言えば180も176.4も「めちゃくちゃ速い」の範疇であり、大きな違いはないですよね。
このコツを使えば、スーパーで買い物中に財布や電子マネーの中身を確認しなくて済むようになります。298円の商品を買ったとき、重要なのは「298円であるか否か」ではなく、「いくらあれば買えるか」なはず。だったら、298円を300円と読み替えてしまっても、全く問題ありませんよね。
計算のコツは、とにかく楽して手を抜くことです。計算が好きならともかく、苦手だったり嫌いだったりするならば、真正面から付き合ってやる必要はない。計算が好きな人ほど、こういったコツを自力で見つけていることも多いんです。計算自体の速さの前に、楽をする工夫を覚えれば、今日からは少しだけ数字が好きになれるかもしれません。
東洋経済オンライン
最終更新:10/2(木) 9:01