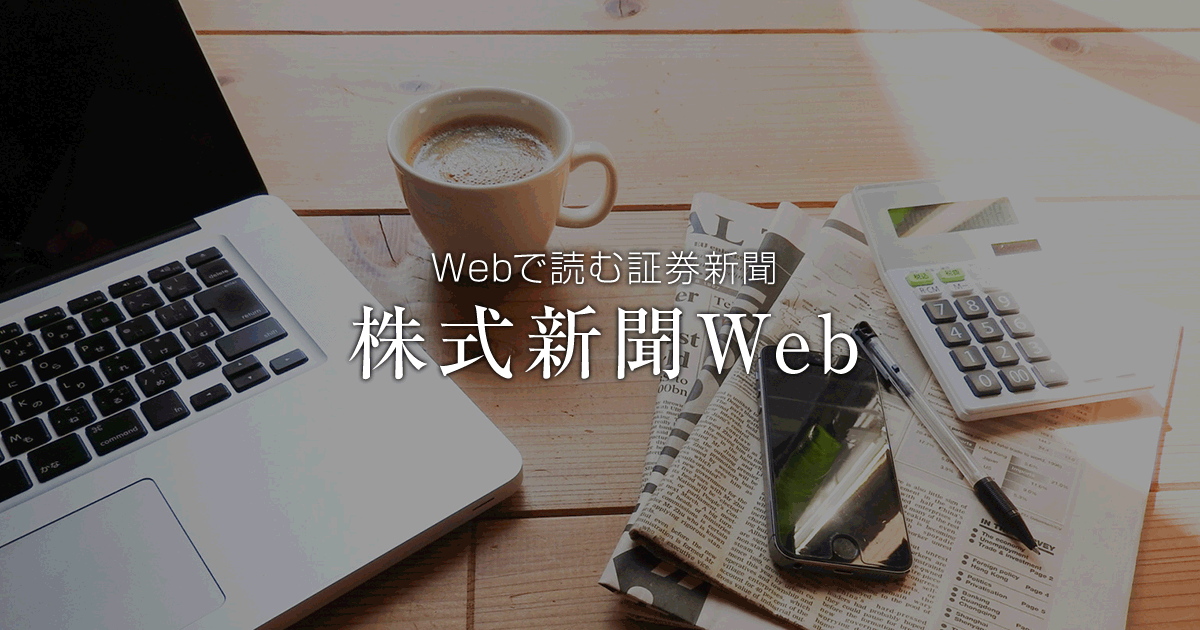コラム:「マールアラーゴ合意」に現実味はあるか、日米交渉の行方を占う=高島修氏

[東京 18日] - 我々は今のところ、いわゆる「マールアラーゴ合意(プラザ合意2.0)」が具体的なリスクだとは考えていない。しかし、トランプ政権が通貨政策において究極的にそうした構想を描いていることには留意すべきだ。
万が一、米政権がその実現に向けてかじを切った場合、日本のように外貨準備保有高が多く、通貨が割安化している国が主なターゲットとなろう。安全保障や経済領域において米国への依存度が高い日本のような国への協力要請はなおさら強いものとなるかもしれない。
とはいえ、我々はその実現を前提に相場シナリオを組み立てている訳ではない。もともとドル/円に弱気な相場見通しだが、現在の基本シナリオとしては当面145円程度で下げ渋った後に、年後半に改めて下落が再開。140円台を割り込み、来年には135円台を下回る下げになっていくと予想している。
<マールアラーゴ合意とは何か>
2カ月前に「プラザ合意2.0」を題材にコラムを寄稿した。1985年のプラザ合意は近代の為替相場の歴史の中でも最重要イベントの一つだが、割高化している米ドルの相場是正のため、トランプ政権の通貨政策が「プラザ合意2.0」のような形で動き出さないか、注意が必要だと指摘した。
ちょうどその頃から欧米市場を中心に「マールアラーゴ合意」という聞きなれないフレーズがささやかれるようになった。マールアラーゴはトランプ大統領がフロリダ州パームビーチに持つ別荘の名前だ。トランプ政権内でその私邸にちなんだ通貨政策の国際的な合意を目指すことが検討されていると言うのだ。
その元となっているのは、米大統領経済諮問委員会(CEA)のスティーブン・ミラン委員長が昨年11月に出した「世界貿易システム再構築のためのユーザーガイド」というレポートだ。戦後の通商秩序の再編を訴えるその論考では、ドル高に強い不満が表明され、特に過去数十年で巨額化してきた世界の外貨準備がそうしたドル高を招き、製造業を衰退させたとして非難している。
そのドル高是正、ひいては製造業復活のため、ミラン氏が提案するのがマールアラーゴ合意である。これは中国や日本、欧州諸国に加え、カナダやメキシコを交えて、プラザ合意のようなドル高是正のための国際間政策協調を目指すものである。これは一種の多国籍間アプローチといえる。
その際、一部の国には外貨準備で保有している米国債を100年債など超長期証券へ乗り換えてもらい、長期金利の抑制を図りながら、それらの国にドル準備のうちの売却資金の一部を売らせるというものだ。
<マールアラーゴ合意の前に来るもの>
とはいえ、マールアラーゴ合意が近い将来に実現する見込みが少ないことはミラン氏自身が認めている。プラザ合意がなされた時に比べると、今日における外貨準備保有国の上位には中国やインド、ロシアなどが軒並み名を連ねる。複雑なこれらの国々との国際政治的、地政学的な利害を調整しながら一つの通貨合意を達成することは至難の業だ。
そこで、ミラン氏は関税政策を優先的に発動させ、関税をその後、通貨政策での譲歩を引き出す交渉カードとして使うことを提唱している。この観点では目下、世界を混乱させているトランプ関税は最初の通過点に過ぎないとの位置づけとなる。
また、ミラン氏には、米国が各国に100年債のような超長期債を発行する際、低金利で行いたいとの考えもあるようだ。規制緩和やエネルギー政策でインフレ圧力を沈静化させ、連邦準備理事会(FRB)の金融緩和で米金利が低下しているような環境がマールアラーゴ合意に先行して実現している方が好ましいと考えている節がうかがえる。
この段階ではドル安よりもまずドル高が黙認される可能性が高かろう。通貨政策においては、中国や日本を対象に通商交渉に絡めながら、米国による単独主義的アプローチ、もしくは二国間アプローチが試みられることになろう。だが、この間にもしドルが大幅に値崩れしてしまうと、関税が物価水準を押し上げる中、インフレが再燃するリスクが高まる。従って、この段階では極端な通貨政策の発動は見送られると考えるのが自然だ。
<日米通貨政策の焦点>
とはいえ、それでもドル/円に関しては、マールアラーゴ合意に至る前のこの二カ国交渉の段階でさえ、政治・政策的には相応に下振れリスクが生じよう。
昨年のドル/円の140円への下落が完全な円安是正には不十分だったことを考えると、日本政府としては、緩やかなペースなら130円ぐらいまでのドル安円高なら黙認。場合によっては歓迎だろう。一方、トランプ政権が為替レートの不均衡の是正を求める場合、100円前後が意識されていると考えるのが自然だろう。あくまでも政治・政策的な議論に過ぎないが、二カ国協議の段階では120円ぐらいが両者の妥協点になってくると考えるのが自然ではなかろうか。
もちろん、トランプ政権が万が一、マールアラーゴ合意のような多国籍間アプローチによるドル高是正を本当に目指すのであれば、日本は他の国よりも深くその枠組みにコミットすることが求められよう。
日本は中国に続く、世界第2位の外貨準備大国であり、しかも、実質実効円相場が半世紀来の低水準にあるように、通貨は極端に割安化している。その円安でドルの実質実効相場はプラザ合意以来の高値圏に押し上げられている。ベッセント米財務長官は円安や日銀の金融正常化の遅れに不満を抱いていると言われるが、そうした不満も理解できなくはない。
加えて、日本は安全保障、経済領域の両面において米国への依存度が高い。従来なら日本や韓国、カナダのようにその双方の領域で米国と深い関係にある国は通商問題上、厳しいターゲットにはなりにくいはずだった。
だがトランプ政権の場合、そこに安全保障とそのコスト負担の問題が絡んでくる。そのため、マールアラーゴ合意のような通貨政策においては、安全保障や経済領域において米国依存度が高い日本のような国にこそ、米国債の利払い軽減や財政事情の改善のための協力が求められることになる。
これはあくまでも政治・政策的な議論であり、相場予測とは異なるが、もしもそのような段階に至った場合には、米国が求める妥協点はドル/円で100円など、二カ国協議の段階での妥協点を下回ってくる恐れがあろう。
<日米交渉の行方を占う>
しかしながら、冒頭で書いたように、我々はそのようなシナリオが最終的に実現するリスクが大きいとは現在のところは考えていない。あくまでも今、顕在化している具体的な問題は日米交渉、つまり二カ国協議の段階でドル/円に加わりうる政治・政策的な調整圧力のリスクである。
日本時間の17日、赤沢亮正経済再生相が訪米し、日米通商交渉が公式に始まったが、その中で為替相場の議論は避けて通れないと見られている。今回は為替相場に関する議論はなかった模様だが、来週には首都ワシントンで世銀・国際通貨基金の春期会合、G20会議が予定されている。
来週、訪米するであろう加藤勝信財務相とベッセント長官の間で日米交渉第2弾が持たれる可能性が高い。そこで通貨政策に関しては、財務省による為替介入のみならず、外貨準備の運用方針や日銀の金融政策までを含めた総合的な政策の枠組みが議論されることになるのではないか。
そこでの円安是正に対するシンプルな選択肢の一つは、もちろん財務省によるドル売り円買い介入である。だが、もしも本当に米国が将来、日本など各国の外貨準備を100年国債など米政府の長期資金調達の原資にしたいという腹案を持つのならば、現段階で日本がドル売り介入することを米国が望むのかは分からない。
最近の米国債を含めた米国市場の不安定さも考慮すると、現段階での現実的な選択肢としてはむしろ、保有する米国債のデュレーション長期化などが議論されてもおかしくないように思われる。
そうなると、円安是正に絡んで思わぬ余波が及びかねないのが日銀の金融政策だ。シティの日本エコノミストはトランプ関税などによる景気減速の可能性を考慮し、次の利上げ時期を従来の今年6月から来年3月へと修正した。
経済分析的には妥当な考えだと思われるが、ドル/円が140円以上に留まっているような場合には、事実上、円安是正を目的に日銀が金融正常化を継続するというシナリオが浮上する。暗にそれが、米国が関税率を引き下げる一つの条件になってくるということも考えられなくもなかろう(もちろん、実際の関税引き下げには貿易不均衡の是正など様々な問題をクリアする必要があるだろう)。
このような通貨政策の観点では、日銀利上げ見通しには前倒しのリスクがくすぶっていると思われる。
編集:宗えりか
*本コラムは、ロイター外国為替フォーラムに掲載されたものです。筆者の個人的見解に基づいて書かれています。
*高島修氏は、シティグループ証券の通貨ストラテジスト。1992年に三菱銀行(現・三菱UFJ銀行)に入行し、2004年以降はチーフアナリストを務め、2010年3月にシティバンク銀行へ移籍。2013年5月以降はシティグループ証券に在籍。
*このドキュメントにおけるニュース、取引価格、データ及びその他の情報などのコンテンツはあくまでも利用者の個人使用のみのためにコラムニストによって提供されているものであって、商用目的のために提供されているものではありません。このドキュメントの当コンテンツは、投資活動を勧誘又は誘引するものではなく、また当コンテンツを取引又は売買を行う際の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。当コンテンツは投資助言となる投資、税金、法律等のいかなる助言も提供せず、また、特定の金融の個別銘柄、金融投資あるいは金融商品に関するいかなる勧告もしません。このドキュメントの使用は、資格のある投資専門家の投資助言に取って代わるものではありません。ロイターはコンテンツの信頼性を確保するよう合理的な努力をしていますが、コラムニストによって提供されたいかなる見解又は意見は当該コラムニスト自身の見解や分析であって、ロイターの見解、分析ではありません。
私たちの行動規範:トムソン・ロイター「信頼の原則」, opens new tab