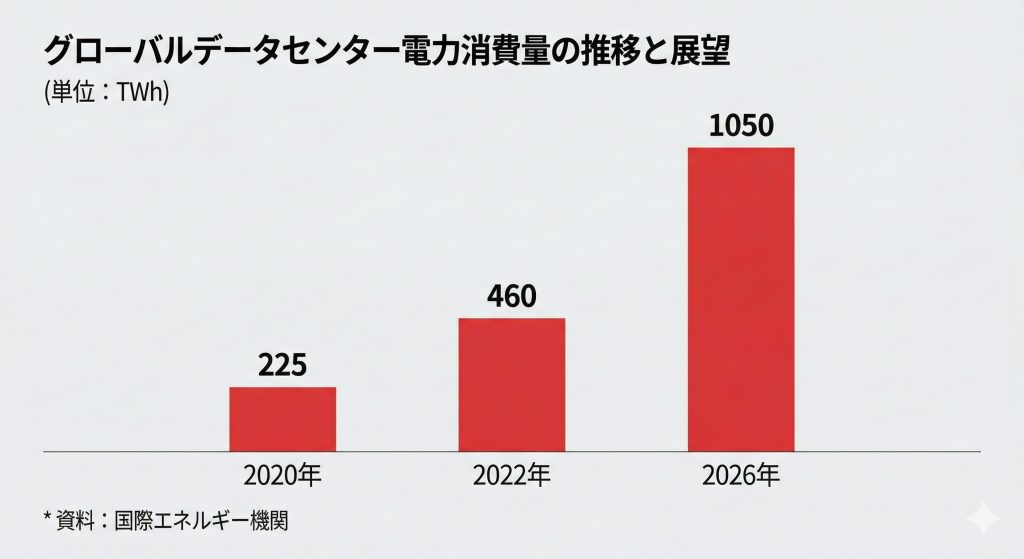「核のゴミ」を“宝物”に変える。放射性廃棄物処理に、新発想

化石燃料と比較すると、排出する温室効果ガスが少ない原子力発電。安全性とともに考えなければいけないのは、原子力発電ででる使用済み燃料、「核のゴミ」と言われる放射性廃棄物。
どこにどう処分すべきかは、国や科学者が常に検討している中、新しいアイデアが出てきました。
核のゴミを「バッテリー」に変える
オハイオ州立大学の科学者チームは、核のゴミから小さなバッテリー(電池)を作る研究をしています。
目を向けたのは、シンチレータ結晶です。シンチレータは、放射線を吸収し光を発する蛍光体材料。これをそのまま使って、発光するエネルギーで充電しようというのです。
バッテリーの試作品では、核のゴミとしてメジャーな存在であるセシウム137とコバルト60で実験。セシウム137では288ナノワット、コバルト60では1.5マイクロワットの電力充電に成功。わずかなエネルギーですが、小さなセンサーを動かすのには十分だといいます。
ただし、一般的な10WのLED電球には1000万マイクロワットが必要なので、電力としてはまだほんとうに微々たるもの。
課題は大型化
ソーラーパネルが大きくなれば集める太陽エネルギーが増えるのと同じように、シンチレータ結晶も大きければ大きいほど吸収する放射線も放出する光も、それによって生成されるエネルギーも大きくなります。
ただ、大型化はコストの問題もあって大きな壁。
オハイオ州立大の原子炉研究所所長を務めるRaymond Cao氏(今回参照した論文の主執筆者)は、大型化は可能だとし、マイクロワットからワット級、将来的にはそれ以上のバッテリーが考えられるといいます。また、こうして得られるバッテリー(エネルギー)は、燃料プールなど核のゴミ関連施設でそのまま使用できると考えているといいます。長期利用が可能でメンテナンスが最小限ですむ可能性もあり、実現すれば大きなメリットとなります。
大学のプレスリリースにて、Cao氏は「(私たちの研究は)そのままではゴミだと考えられているものを集め、宝に変えようとしているのです」と語っています。
オハイオ大学の機械航空宇宙エンジニアのIbrahim Oksuz氏(上記論文の共同執筆者)は次のように語っています。
「核バッテリーのコンセプトは有望なアイディアです。進化すべき余地がまだ多くありますが、将来的には、センサー業界、エネルギー生成業界の両者において重大な役割を担うアプローチだと考えています」
研究論文はOptical Materials: Xにて公開されています。