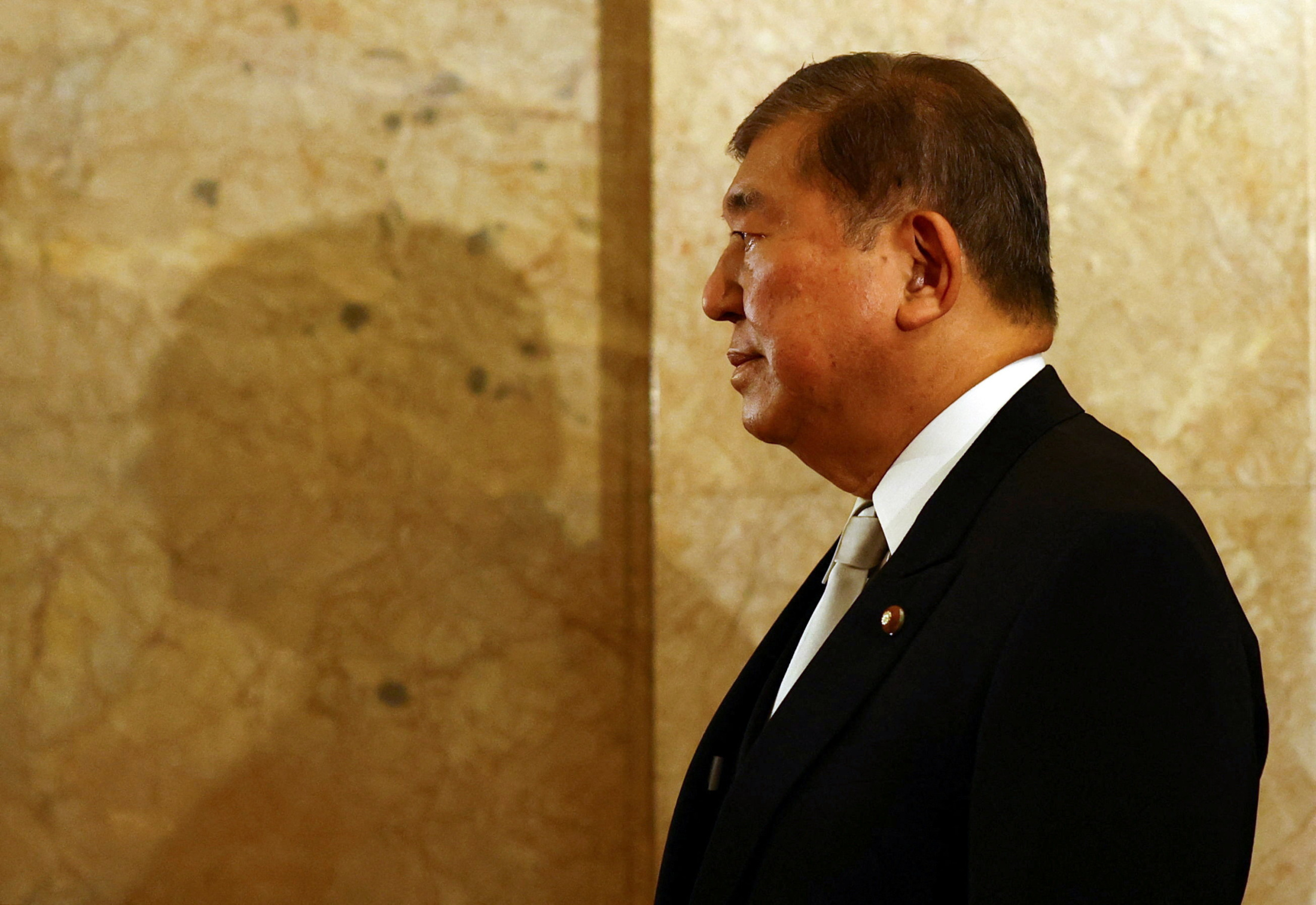なぜ人は宗教に時間とお金を費やすのか…貧しい女性が進んで教会に献金する「意外な動機」(東洋経済オンライン)

11/21 13:30 配信
現代社会において、宗教はすでに巨大な経済活動を伴う「ビッグビジネス」と化しており、その市場規模はマイクロソフトやアップルといった企業の収益を上回るといいます。宗教活動はいかにして強大な力を得たのでしょうか。なぜ、貧しい人もこぞって宗教団体に献金するのでしょうか。一見非合理に見える献金の動機を、ポール・シーブライト『ビジネスとしての宗教』の抜粋から読み解きます。■気前のよい貧者
貧しい人がどうしてわざわざ裕福な人にお金をあげるのだろうか。2015年2月、ガーナの首都アクラで、ある若い女性(ここでは仮にグレイスと呼ぶ)と話をしたとき、わたしの頭を離れなかったのは、この疑問だった。
彼女はわたしの研究チームの経済学の実験に被験者として参加するため、セントラル大学(CUC)の研究室に来てくれていた。年齢は24とのことだった。質素ながら小ぎれいな身なりをしていて、口数は少ないが、物腰に聡明さが感じられた。きっとそれなりの学校を出ていて、今は小企業か行政機関で事務員か何かをしているのだろうとわたしは思った。
これはとんでもない見当外れだった。グレイスは週6日、アクラへと通じる幹線道路に行き、信号待ちをする車列のあいだをひたすら往復している。そうやって歩きながら、小さなビニール袋入りの氷水を、頭に載せたかごの中から取り出して売っている。
1日の稼ぎは、1.5ドルをわずかに超える程度にしかならない。炎天下の路上で12時間、埃と排気ガスにまみれて、へとへとになるまで働いたら、スラム街にある粗末な家に帰る。家では、数年前いっしょに上京してきたおばと2人で暮らしている。 日曜には教会に行く。教会では案内係として、訪れた人を出迎えて席を案内している。それが終わると、聖歌隊の一員として聖歌を歌う。さらに日曜学校の手伝いもしている。
教会への献金も怠っていない。収入の10%を納める伝統的な十分の一税に加え、ミサの最中に求められる献金にも応じている。それらを合わせると、教会に差し出している金額は、ただでさえ少ない収入の12%前後にものぼる。教会に献金すれば、病気がちのおばの治療代など、ほかのことにお金が使えなくなることがわかっていながらだ。
教会の指導者で、献金をおもに受け取っているウィリアム牧師(仮名)は、元気で笑顔を絶やさない、とても感じのいい人物で、たいへんな金持ちでもある。金持ちであることを隠そうとはせず、大きなメルセデスに乗り、ズボンのベルトにはドル記号をあしらった大きな丸いバックルがついている。
完璧に仕立てられたスーツも足りていて、もらっても困るといったところだろう。グレイスからの献金を必要としていないことはひと目でわかる。なのに、グレイスはみずから進んで献金している。なぜそんなことをするのか。
■貧しい信者が裕福な牧師に献金する「合理的な」理由
グレイスが単に愚かだからとか、だまされているからといった答えが正しくないのは確かだ。グレイスは自分がしていることをはっきりと理解している。わたしよりよっぽどしっかりした金銭感覚の持ち主だ。ほかの教会に移ろうと思えば移れることも知っているし、十分の一税を納めなくとも、献金箱にお金を入れずとも、今の教会にいられることも知っている。それでもこの教会に留まって、毎回、きちんとお金を納めている。
有望な答えといえそうなのは、このグレイスの気前のよさは別段めずらしい振る舞いではない、なぜなら貧しい人や中間層はふだんからたえずお金持ちにお金を払っているのだからというものだ。そもそもお金持ちがお金持ちになれるのはそのおかげだ。
もちろん、お金を払っている人たちは自分たちの行為を献金とは思っていないだろう。それでもウォルマートで食品を買ったり、ネットフリックスの契約を更新したり、ルイ・ヴィトンのバッグを購入したり、アマゾンプライムに登録したりするとき、たいていの人は自分がそうすることでお金持ちをさらに富ませるのに貢献していると気づいている。
グレイスの日々の労働をつぶさに思い描いてみなければ、なぜ日曜日に教会に通うことが彼女にとってそんなに重要な意味を持つのかはわからないだろう。日曜日に教会に行くときには、洗い立てのきれいな服を着られる。案内係として、教会に来た人たちと気持ちのよい挨拶を交わすことができる。
日曜学校では自分より若い人や、自分よりもっと弱い立場に置かれた人たちに対して責任を持つことができる。ほかの人といっしょに歌うことができる。平日を露天商としてともに過ごしているいろいろな人たちとおしゃべりができる。友だちをつくることもできる。
この恐ろしい街でなりゆきで選んでしまうかもしれない求婚者よりも、飲んだくれて妻に暴力を振るう可能性が低い未来の夫と出会えるかもしれない。こういうことをすべて、自分のことを受け入れ、敬意を払ってくれるコミュニティの中ですることができる。
教会に通うために収入の8分の1を支払うというのは、むしろ安く感じられるのかもしれない。わたしたちのように外部から見ている者には、大金持ちといってもいいウィリアム牧師が貧しい女性に献金を求めるのは、理不尽なことに思える。
しかしグレイスにとってはそういう問題ではない。コミュニティの一員でいるために十分の一税を納める必要があるなら、彼女は喜んでそれを納めるだろう。■宗教団体が提供する「商品」と「サービス」の対価
そこにはさらに複雑な要素もある。もしネットフリックスの月々の利用料を支払わなければ、あなたはコンテンツを見られなくなるだろう。もしウォルマートのレジで代金を支払わなければ、あなたはかごに詰めた食品を持ち帰ろうとするのを止められるだろう。
しかしグレイスは十分の一税を納めなくとも、教会には喜んで受け入れてもらえるのだ。ただし、以前ほど、心から歓迎されているとは感じられなくなる恐れがある。それまでは温かい微笑みをたたえていた牧師が、いくらかしぶい表情を見せるようになるかもしれない。
路上でどなられたり、蔑まれたりしている日々の生活とは違って、ここでは誰からも大事にしてもらえる。それは単に教会に来ているからではなくて、みずから進んで教会に来て、あり金をはたいて献金しているからこそだった。
そのことはグレイスもウィリアム牧師もわかっている。牧師と教会に集う人々のおかげで、グレイスは自分を誇らしく感じることができる。そのように感じられるのには、グレイスがウィリアム牧師を神と特別な関係を持つ人と信じていることも大きく関係している。
21世紀に入ってからも、世界の何十億という人々が宗教指導者の呼びかけに応えて、時間と労力とお金を宗教団体に費やしている。大半を占めるのは、グレイスと同じように、冷静かつ明晰な判断のもとにそうしている人々だ。
その結果、宗教団体が世界各地で強大な力を手にしている。ときに宗教指導者は単なる精神的な指導者に留まらない。比喩的にではなく、文字どおりの意味で、人々に命を捧げるよう求めることすらある。
(翻訳:黒輪篤嗣)
ポール・シーブライト :トゥールーズ大学経済学部教授
最終更新:11/21(金) 13:30