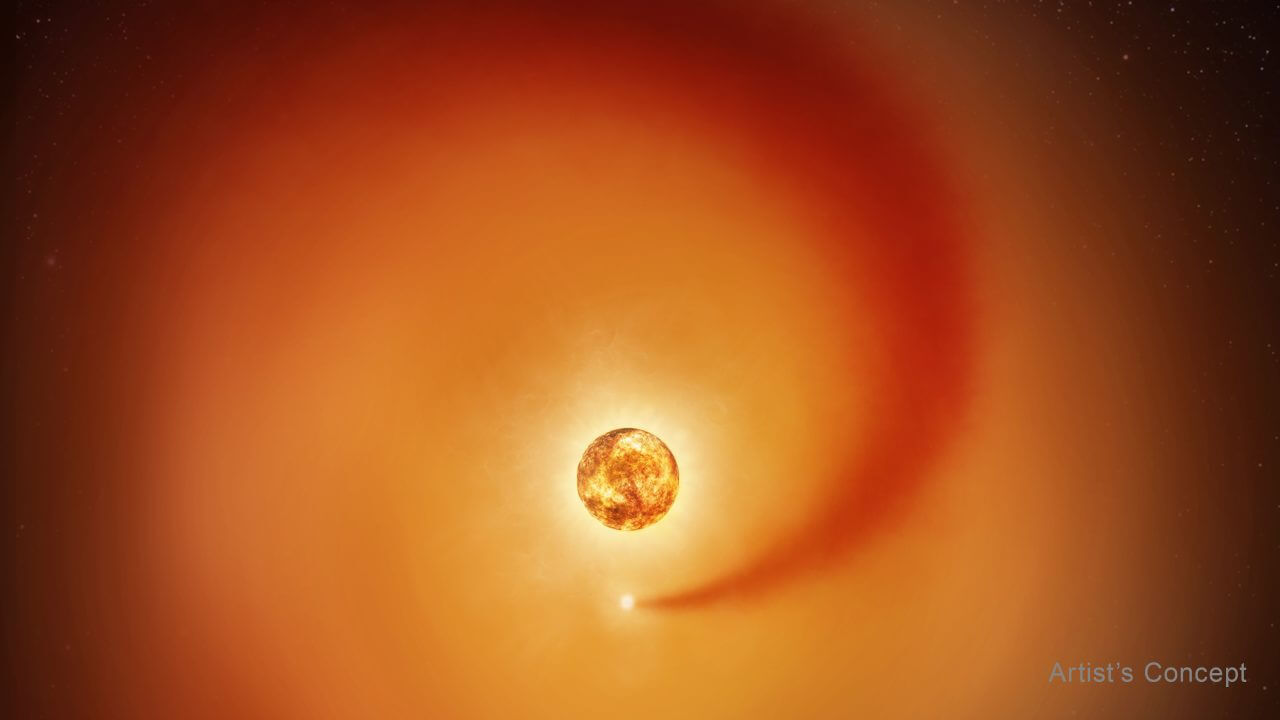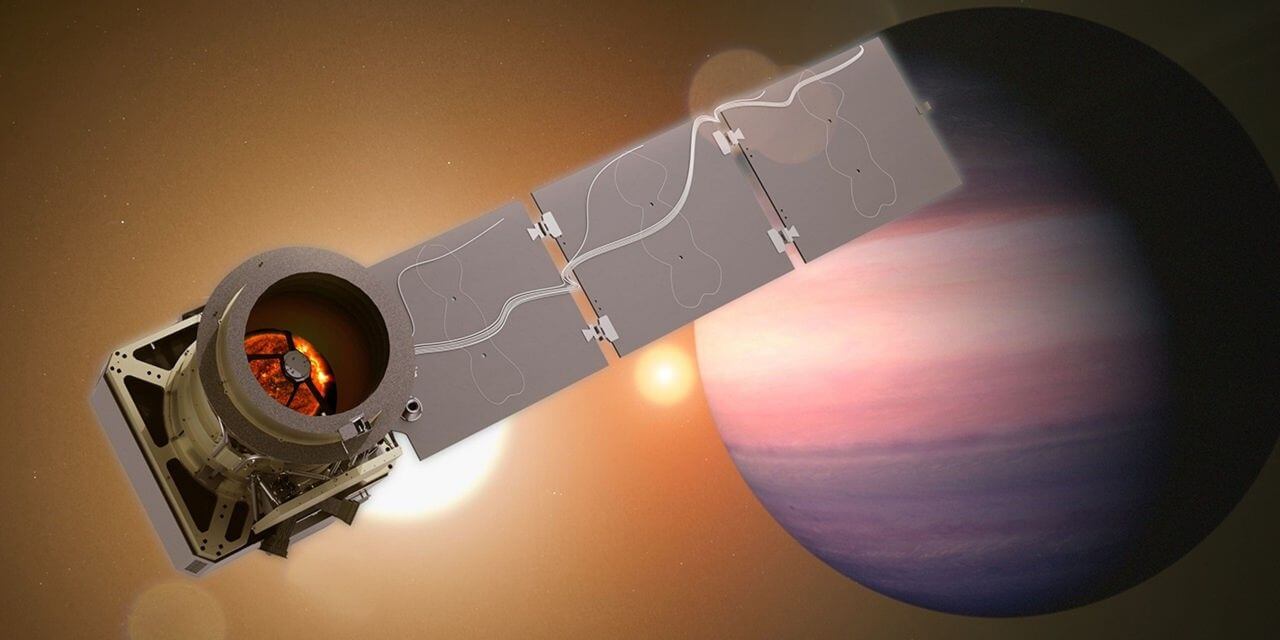でんじろう先生の中学生時代「反応は派手な方が楽しい」…「安全に配慮」しながら続けた“自由な実験”の数々

子どもたちに科学の面白さを伝えるため、全国各地で実験ショーを開催している米村でんじろうさん(70)。最近はYouTubeの実験動画も人気で、チャンネル登録者数は50万人を超える。その原点は、豊かな自然のなかで理科に親しんだ少年時代にあるという。(読売中高生新聞編集室 大前勇)
生まれた場所は「となりのトトロ」のような世界
米村でんじろうさん「生まれは千葉県の房総半島。今はゴルフ場がたくさんありますが、僕が子どもの頃は山間部の寒村でした。道路は砂利道で、バスが1日に何本か通るぐらい。家はかやぶき屋根で、炊事やお風呂にはまきを使ってました。毎日がアウトドアみたいな感じです。映画『となりのトトロ』に出てくるような世界でしたね。
でも、小学校での理科の実験は充実してました。電磁石でベルを作ったり、手押しポンプの模型を作ったり……。夏の夜はグラウンドで天体観測をしました。天の川がきれいに見えてね。毎日見ていると、金星が少しずつ移動しているのがわかって、すごくおもしろかったです。
中学1年生の時のでんじろうさん。後列右端大人になって調べたのですが、旧ソビエト連邦(ソ連)が人類初の人工衛星の打ち上げに成功した『スプートニク・ショック』(1957年)が背景にあったようです。東西冷戦でソ連と激しく対立していたアメリカでは、それまでの科学教育を見直す必要に迫られます。アメリカの同盟国の日本にも影響は及び、僕が子どもの頃は理科がとても重要な科目とされていたのです」
子どもの頃は「科学に興味をもちやすい時代」
中学校では「科学クラブ」に入り、実験漬けの日々を楽しんだ。
日本経済が急速に発展し、社会が大きく変わるなか、科学への興味はますます膨らんでいく。
「東京五輪があった1964年、10歳ぐらいまでは戦前とほとんど変わらないような生活だったのではないでしょうか。それが急速に変わり始め、テレビも見られるようになりました。未来を特集した番組では、車が空を飛んでいるとか、スイッチ一つでご飯がチーンと出てくるとかやってましたね。ロボットが活躍する手塚治虫さんのアニメ『鉄腕アトム』が人気になるなど、科学に興味をもちやすい時代でしたよね。
それでも、日常の全てがすぐに変わるわけではないので、家では毎日、手伝いで火おこしをしてました。だから、学校で勉強している理科と自分の生活とのつながりも感じてました。学校では、物の燃焼には酸素や温度が必要だと教わって、少し理屈がわかるみたいな感じでした」
「理科室で実験の本を見て、薬品を混ぜるとか、バケガク(化学)系が楽しかったですね。先生も自由にさせてくれて、『やりたい実験がある』と言えば、よっぽどのことがない限りやらせてくれました。
中学生だから、実験は派手に反応する方が楽しい。例えば、 硝酸(しょうさん) カリウムと 木炭(もくたん) 、 硫黄(いおう) を混ぜて火をつけると“ブアー”と激しく燃えるんです。調べると、 黒色火薬(こくしょくかやく) はこの成分だったんですよね。花火もどんな仕組みか知りたくて分解しました。
サイエンスショーでの巨大空気砲(米村でんじろうサイエンスプロダクション提供)アメリカのケネディ大統領が1961年に『アポロ計画』で人類を月に送るという目標を掲げ、僕が中学3年生の時にアポロ11号が月面着陸に成功します。学校の教室のテレビで、その映像を見ました。宇宙ブームの時代だったので、自分でロケット花火を作ったりしてましたね。
そんな実験をしていると、やけどやケガをすることもあります。それでも、うるさいことは言われないし、当時はおおらかでしたよね(笑)。2B弾という爆竹のようなおもちゃがあって、僕もよく遊んでいたんですけど、全国的に火事が相次いで製造中止になるような時代でした。
もちろん安全に配慮し、リスクを避ける努力はしないといけませんが、小さな失敗から学びを得れば、大きな事故を防ぐことにもつながります。科学クラブの実験では、失敗をどう次へ生かすかが大事だと学ばせてもらいました」
(つづく。次は「苦悩の大学受験」編です)