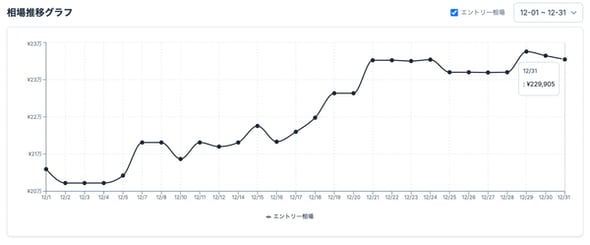ロボット導入で「眠れる人材」に光、人手不足対策で思わぬ波及効果

ファミリーレストラン「ガスト」では、猫型配膳ロボット「ネコロボ」が注文の品を客席まで運ぶ姿は見慣れた光景になりつつある。人手不足解消や生産性向上を目的に導入されたロボットだが、同時に高齢者や外国人ら「眠れる人材」を掘り起こすという想定外の効果をもたらした。
ガストを運営するすかいらーくホールディングスは2021年からグループの飲食店にネコロボの導入を開始。22年までに3000台を設置して以降、フロアスタッフの勤務時間中の歩行数は42%減少した。ハンバーググリル皿や鍋セットなど重い食器を運ばずに済むため体への負担が減り、従来採用が難しかった65歳以上のシニアスタッフの雇用は20年比でほぼ倍増。70歳以上は3.6倍に増えた。
今の仕事の半分は「ロボットに助けられている」と話すのは、東京都港区のガスト三田慶応大学前店で6年ほど前から働く71歳の田川泰子さん。現在は週に最大20時間シフトに入り、テーブルの後片付けのほか、空いた時間には外国人スタッフらにトレーニングを行っている。年齢的に動き回るのは大変だが、「ロボットと一緒なら、今のところ仕事は全然苦になっていない」と語った。
86席ある同店舗では1台のネコロボが料理を出す「上げ膳」を全て担当する。ロボット導入で接客の機会が減り、言葉に不安のある外国人を雇用するハードルも下がった。
ネパール出身で日本語を勉強中のランジト・カワスさん(20)は今年1月から同店舗で働き始めた。当初はネコロボの操作に手こずったものの、田川さんらの指導を受けて今では問題なく使えるようになったという。
企業の存続をも左右しかねない人手不足の解消は喫緊の課題だ。帝国データバンクによると、採用難や人件費高騰などを原因とした「人手不足倒産」は24年に前年比約1.3倍の342件と2年連続で最多を更新。建設と物流で4割を占めるが、飲食店や美容業でも急増したという。すかいらーくの取り組みは、人手不足への対応とともに、高齢化が進む日本で人材の活用を模索する企業にとってヒントとなり得る。
ロボットと人との協業は経営面でもプラスの効果が表れており、同社の売上高人件費率は24年に32.6%と3年前の40.2%から改善した。
ブルームバーグ・インテリジェンスの北浦岳志シニアアナリストらは、ネコロボの1日の稼働時間を8時間、3年で償却と想定すると、3000台の導入で年間約50億円のコスト削減効果があると分析。ネコロボを時給換算すると350円になると試算した。
国内では接客業や介護などの分野で人手不足が目立つ。厚生労働省によれば、1月の有効求人倍率(パート含む)は接客・給仕で2.79倍、介護サービスで4.08倍と全体の1.20倍を大きく上回っている。
人手不足を補うネコロボのようなロボットの販売は世界で伸びている。国際ロボット連盟(IFR)の報告書によると、23年の業務用サービスロボットの販売台数は20万5000台超と前年比30%増加。日本のサービスロボット市場はさらなる拡大が予想され、富士経済の推計では30年の市場規模は4000億円超と、24年の見込み値から約3倍に膨らむ見通しだ。
IFRの伊藤孝幸会長は、サービスロボットは「まだこれからどんどん伸びていく分野だ」と指摘。力仕事は「ロボットに任せる方がいい」だけでなく、ロボット導入が女性や高齢者の雇用拡大にもつながるとの見方を示した。
リクルートワークス研究所の予測によると、高齢化を背景に日本では40年に労働人口が1100万人不足する。国立社会保障・人口問題研究所の推計では、65年には国内人口の約4割が65歳以上になる。
介護や物流の現場でも
40年度までに約57万人の働き手が不足すると予測されている介護の現場では、ロボット導入による負担軽減が期待されている。介護分野で働く人を支援する公益財団法人介護労働安定センターによると、介護職員の29.3%が仕事上の不安として腰痛や体力を挙げた。
特別養護老人ホーム「フロース東糀谷」(東京都大田区)などを運営する善光会は、過去15年間に移動支援ロボットなど300以上の機器を試験的に導入してきた。同施設で働く介護士の田辺麗奈さん(27)は、以前は職員2人の介助が必要な利用者がいたが、体重205キロまで移動可能なロボットなどの導入で職員の体の負担や業務時間が減り、楽になったと話す。
フロース東糀谷では入居者の睡眠や排せつの状態などを見守るセンサーも導入している。職員の負担が減るだけでなく、見守りで減った時間を他の業務に充てることが可能になった。
善光会の宮本隆史理事は、介護者をベッドから車いすに移動するといった「人の移乗などを機械でやっても耐えれるようなオペレーションにしないと、なかなかワークシフトしていかない」と危機感を示す。ロボットなどの導入で先端機器に関心の高い若年層に加え、高齢者や外国人をより多く採用できるようになったという。
佐川急便などを傘下に持つSGホールディングスも、荷積み作業の自動化に向けて人工知能(AI)を搭載したロボットの導入へ動いている。全日本トラック協会によると、トラックドライバーなど輸送・機械運転従事者数の88万人のうち女性はわずか3万人で、全体の3%程度にすぎない。人材の確保には女性や高齢者らが働きやすい環境整備が欠かせない。
もっとも、現状ではサービスロボットが技術やコスト面で企業の要望に応えきれていないとIFRの伊藤氏は課題に言及。「労働力が不足することはもう普遍の事実」であり、今後はロボットの機能開発や導入にかかるコストの削減が重要になると語った。
ガストで働く田川さんは一人暮らし。職場で同僚や客との交流を楽しみにしている。「キッチンもロボットがやってくれるようになればとてもいいかもしれない」と、進化を遂げるロボットとともに長く働き続けることに期待を寄せた。