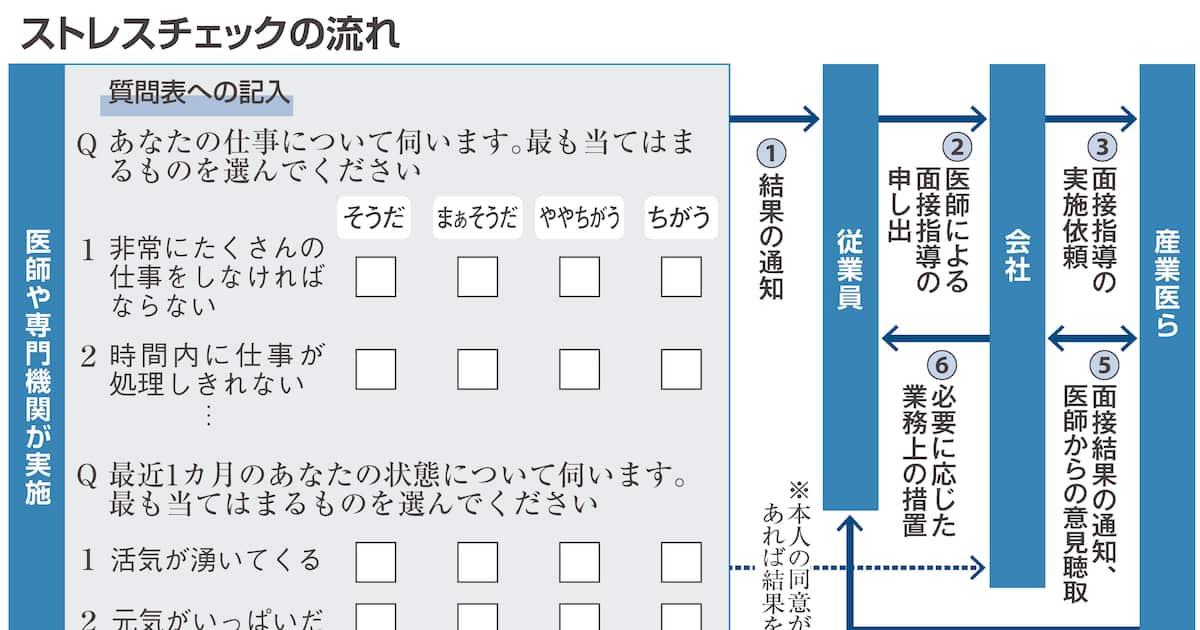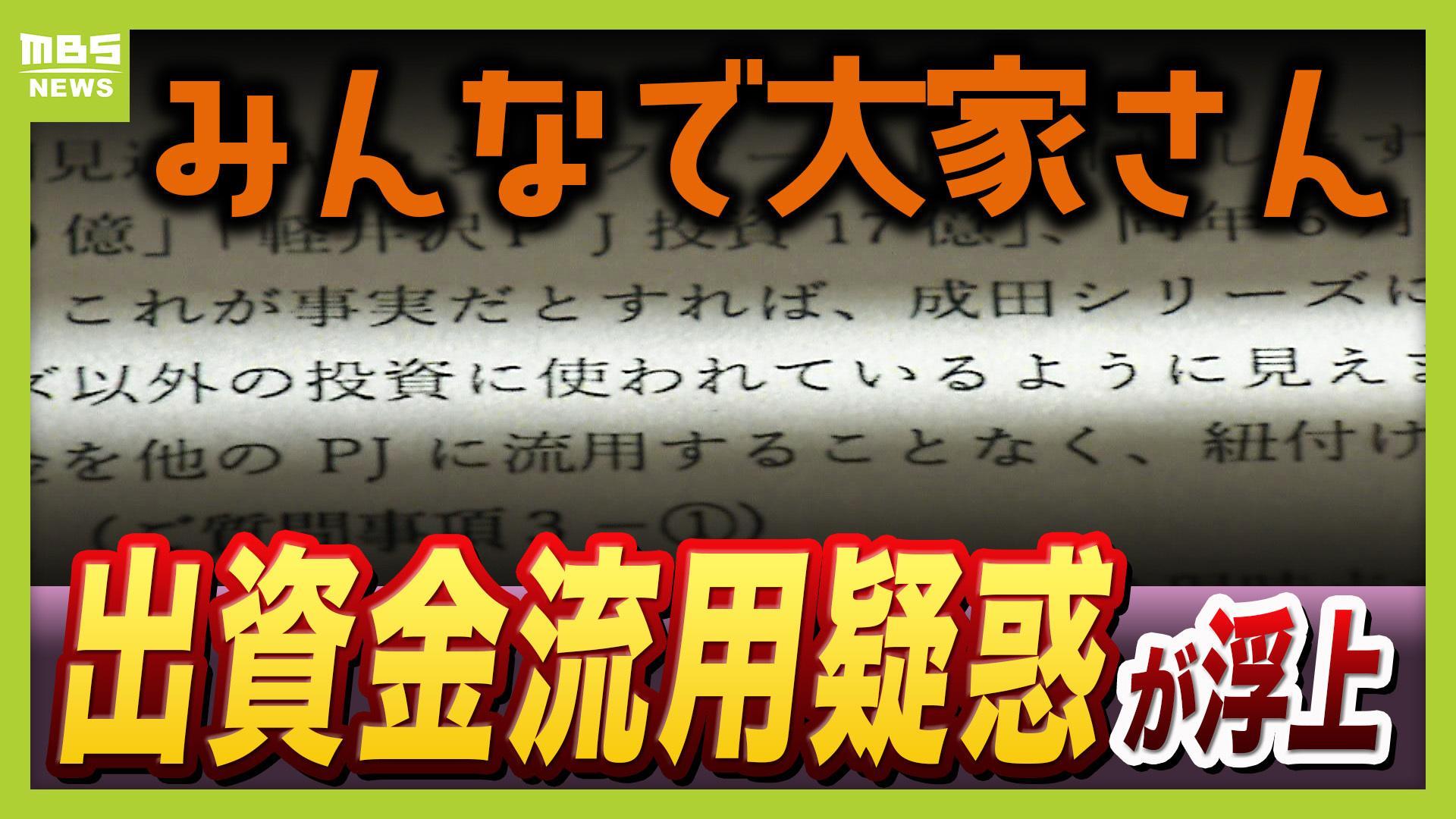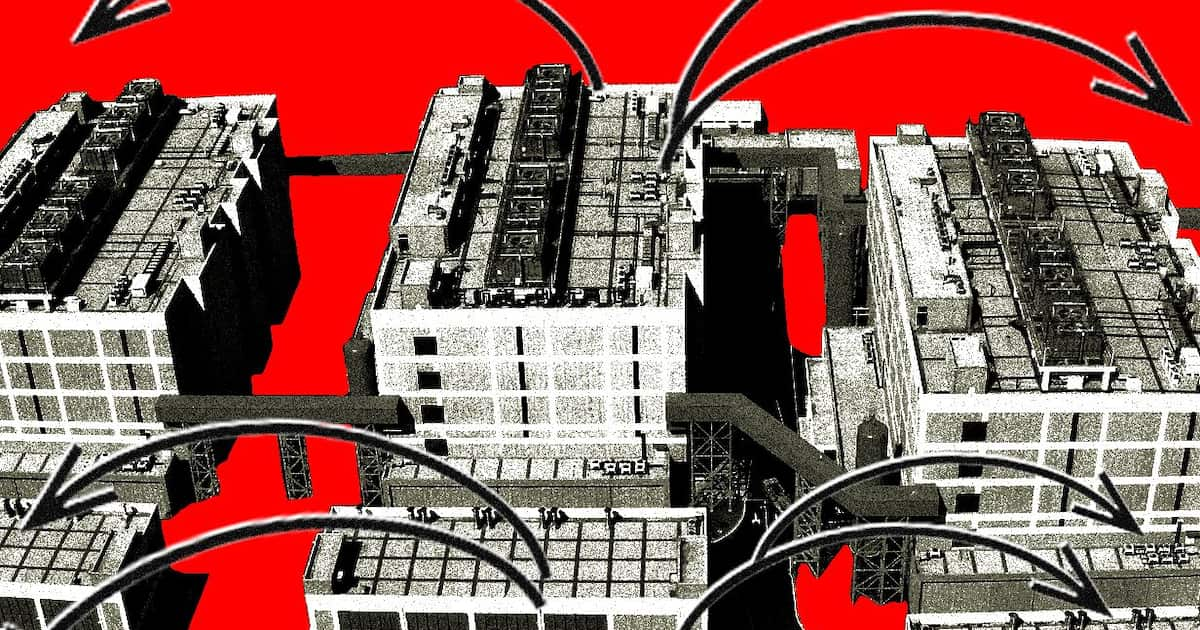iPhoneの「全機種eSIM化」がもたらすもの、Apple Watchの5Gに「楽天が非対応」の理由――Apple新製品から読み解く通信業界の現在地

9月19日に発売となるiPhone 17シリーズとiPhone Airでは「全機種eSIM」が話題となっている。
アップルではiPadに始まり、最近ではアメリカのみ全機種eSIM対応にするなど、10年近くeSIMを手がけてきた。世界中のキャリアにおける対応が広がり、ようやくiPhoneからSIMカードスロットが消えた。ただし、日本は全機種eSIMだが、一部の国や地域で物理SIMカードのモデルが残るとされている。
アップルがeSIMにこだわったのは当然のことながら「本体のスペース確保」が大きい。薄型のiPhone Airを実現させるには、できるだけ余計なものを無くしたい。そこで物理カードスロットを廃し、eSIMにすることで、少しでも薄くすることが可能だ。
一方、iPhone 17 Proと17 Pro Maxでは、eSIMにすることでできたスペースを生かし、電池容量を増やすことに成功した。アップルは電池容量のスペックを公開しないため、どれくらい大きくなったかは不明だが、動画視聴で2時間、伸ばすことに成功したようだ。
ちなみにeSIMのメリットとしてひとつ挙げられるのがクイック転送機能だ。古いiPhone(物理カードで可)から新しいiPhoneにeSIM情報を簡単に移転できる。ただし、見え方として、古いiPhoneから新しいiPhoneに直接、移行しているように見えるが、実際は背後でキャリアのシステムにつながり、新しいiPhoneにeSIM情報を書き込みつつ、古いiPhoneからはeSIM情報が削除されている。
iPhoneでは仕組み上、AndroidからのeSIMクイック転送にも対応しているのだが、残念ながら9月11日現在、日本のキャリアにおいてはNTTドコモは「現時点で対応可否について決まったものはございません」とコメント。KDDIは「異なるOS間でeSIM転送する場合、My auなどで手続き可能です。クイック転送については対応を検討していますが、具体的な時期は未定」、ソフトバンクは「現時点ではできません」とのことだった。
現状、アメリカのキャリアが対応しているものの、Android端末側もグーグル・Pixelなどごく一部しか対応できていない。
iPhone Airではアップルの設計したモデムである「C1X」が搭載されている。実は、iPhoneは出荷する国・地域に応じて、3つのモデルが存在する。周波数ごとに違いがあるため「中国向け」「アメリカなど向け」「その他の地域」といった具合だ。
これまで日本は「その他の地域」に含まれることが多かった。実際、iPhone 17 Proと17 Pro Maxはその他の地域だ。しかし、iPhone Airに限っては「日本専用モデル(A3516)になっている。
この理由は、日本特有のバンドともいえる「Band 11/21」が他のモデルでは対応しておらず、日本で流通させるにはBand 11/21は必須ということで、日本専用モデルが誕生したのだった。
ただ、実は半年近く前に登場したiPhone 16eには「C1」が搭載されており、このときはBand 11/21は非対応であった。当時、「Band 11/21はNTTドコモが使っているが、ネットワーク品質的に不安要素になりはしないか」という声が上がっていた。
iPhone 16e発売以降、特に「Band 11/21が使えないから不便」という指摘が上がっていないようだったが(そもそも、NTTドコモのネットワーク品質がイマイチという話はある)、アップルとしては、Band 11/21対応は避けては通れなかったということなのだろう。
Apple Watch Series 11、SE3、Ultra 3では、セルラー版が「5G」になった。
「Watchで動画やウェブなんて見ないのになぜ5G対応するのか」というのが疑問であったが、5Gに対応することで、電力効率が良くなり、結果、使用時間が延びるのだという。実際、Apple Watch Ultra 2では5Gと組み合わせることで最大36時間であったが、Ultra 3では5Gとバッテリーサイズの大型化で、最大42時間になっている。
アップルのプレゼンで気になったのが、5G対応キャリアだ。日本ではNTTドコモ、au、ソフトバンクのロゴはあったが、楽天モバイルのそれはなかった。「楽天モバイルもApple Watchを扱っているのに、なぜのけ者なのか」と思ったら、今回の5Gは5G SAで接続するため、5G SAネットワークが本格的に稼働していない楽天モバイルは非対応ということになったようだ。
ちなみに、ソフトバンクは5G SA向け次世代IoT通信規格「5G RedCap」で接続する。NTTドコモは「5G RedCap」について「現時点で対応していないが、IoTのユースケースを考慮するとエリアカバレッジも重要であり、デバイスの対応状況も含めて適切なタイミングで検討して参ります」とコメント。KDDIも「現時点では対応していないが、市場動向やユーザーニーズを踏まえて判断する」とのことだった。