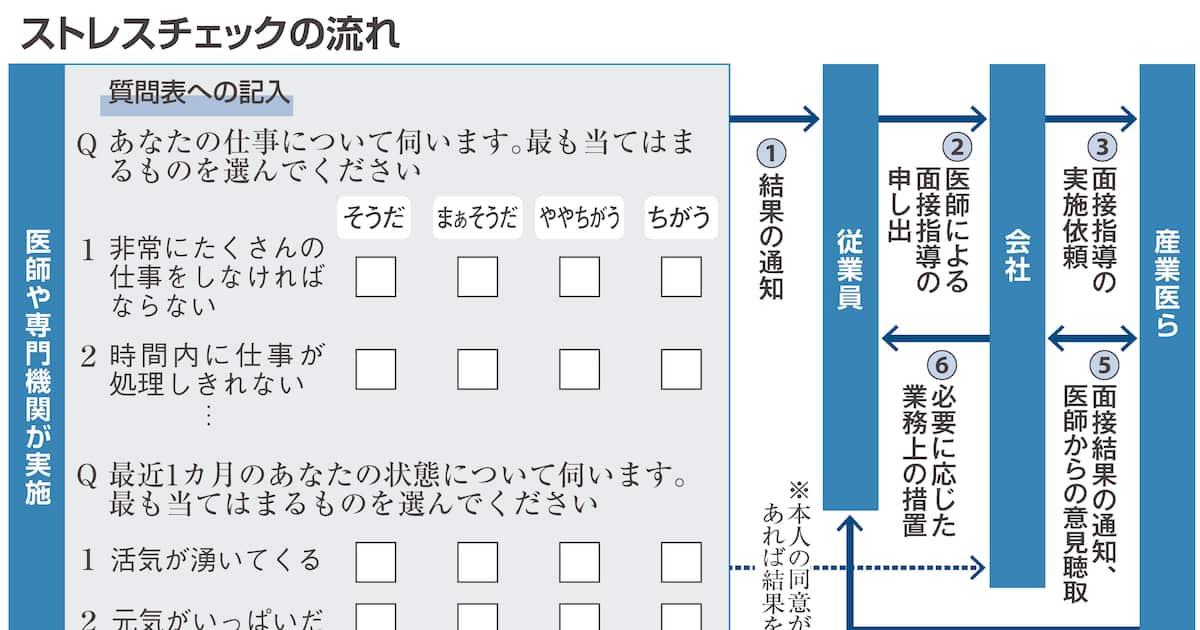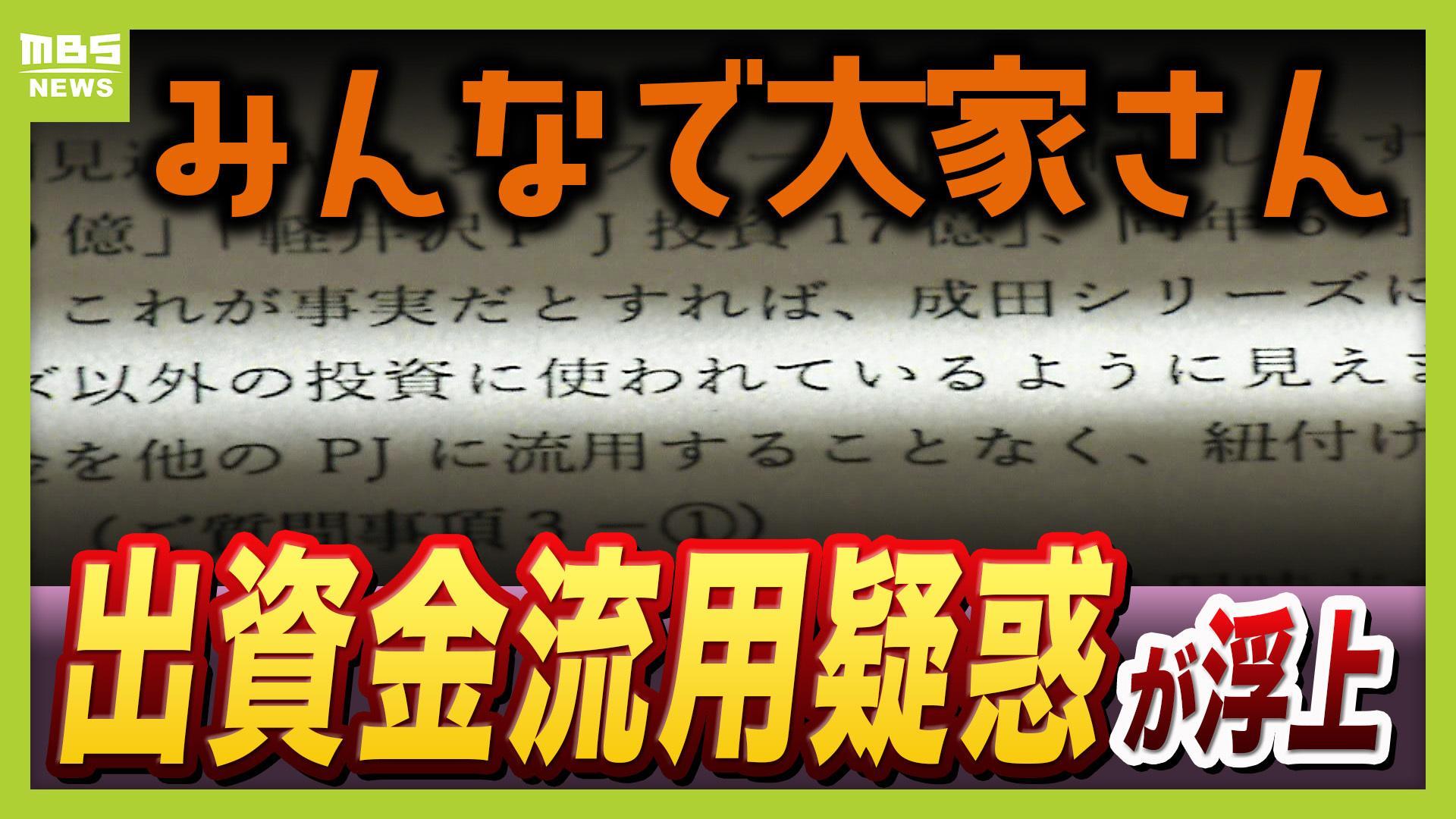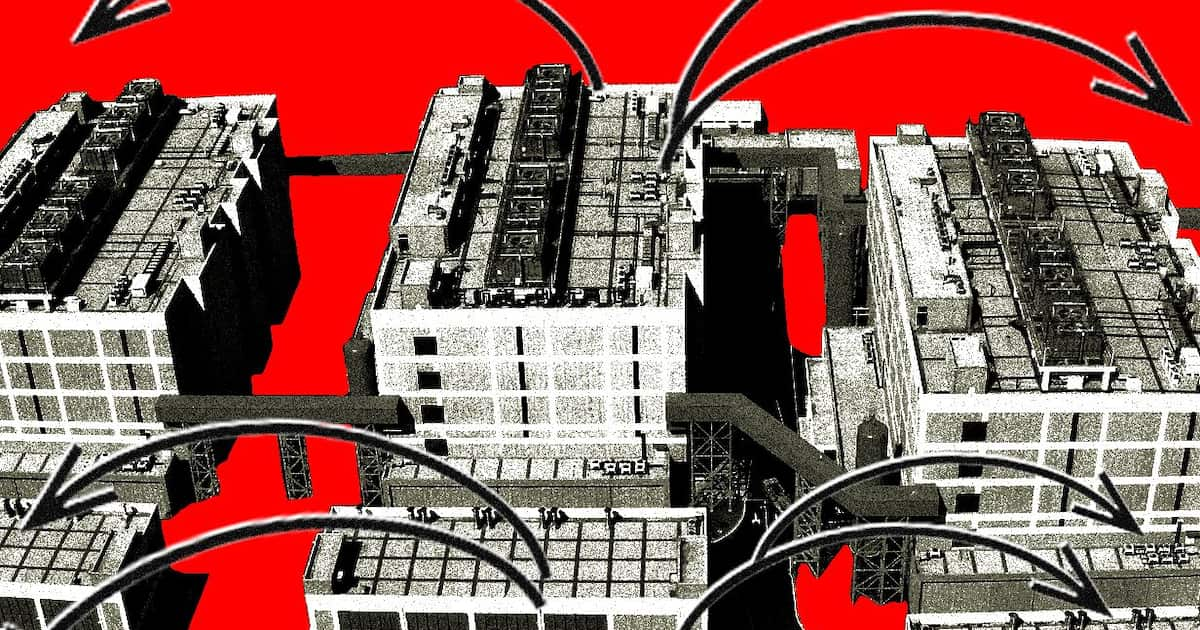マネクリ マネックス証券の投資情報とお金に役立つメディア

プラザ合意とは、1985年9月にG5(先進5ヶ国)の財務相、中央銀行総裁がNYプラザ・ホテルに秘密裏に集合し、米ドルの実質的切り下げを決めたことを言う。これを受けて、G5各国は協調的に米ドル売り・自国通貨買いの介入を行い、米ドル/円のケースでは250円程度から200円割れへ強引な押し下げに動いた(図表参照)。
当時は東西冷戦時代の最終局面で、ソ連との軍拡競争などにより米国は巨額の財政、経常「双子赤字」を抱えていた。「プラザ合意」の狙いは、米ドルを実質的に切り下げることにより、「双子赤字」解消を目指すことだった。
当時はレーガン政権だったが、トランプ大統領の尊敬する人物の1人がレーガン大統領だということもあり、トランプ政権でも巨額の財政、経常赤字解消のために米ドル高是正の「第2のプラザ合意」を目指しているとの見方はある。
「プラザ合意」当時、米国の経常・貿易赤字の最大の相手は日本だった。このため米ドル安・円高への為替調整は米貿易赤字解消の有効策のように見えなくなかった。この観点からすると、今の米国にとって最大の貿易赤字先は中国なので、貿易赤字解消には米ドル安・人民元高への為替調整が不可欠と感じられる。しかし、トランプ政権は今のところ中国と厳しく対立しているようだ。またそもそもトランプ大統領はG7(7ヶ国財務相会議)やG20(20ヶ国財務相会議)といった国際協調に対して否定的のように見える。
以上のように見ると、為替調整を国際協調として行うことで米国の「双子赤字」解消を目指した「プラザ合意」のようなアプローチをトランプ政権が「第2のプラザ合意」として進めるのは、今のところはかなり無理があるのではないだろうか。
日米の円安是正の可能性:クリントン政権時との違い
日米の2国間で米ドル安・円高へ誘導することにより、ポスト冷戦時代における米経済復活を目指したのは1993年に発足したクリントン政権だった。当時125円程度だった米ドル/円は1995年には戦後初めて1米ドル=100円を超える円高、「超円高」が80円まで進むところとなった。トランプ政権は関税政策を巡る日米交渉において、通貨問題も1つの課題に位置づけているようだ。ではこの先、日米2国間で円安是正の為替調整を目指すことになるだろうか。
クリントン政権時代の米ドル安・円高は、「プラザ合意」のような協調介入は使われなかった。それでも米ドル安・円高が広がるきっかけになったのは、クリントン大統領自身を含めた円高要請の明言だった。
例えば政権の要人の1人は、「強い米ドルを望むのか」との記者団からの質問に対して「強い円を望む」と発言した。そしてクリントン大統領は、初の日米首脳会談後に行われた記者会見の冒頭で、「日米間の貿易不均衡是正で第一に有効なのは円高」と発言した。こうして米政権が日本に対して円高を求めていることをはっきり明言するたびに米ドル安・円高は大きく進むところとなった。
もう1つ重要な役割を演じたのは、クリントン政権1期目に進められた財政赤字削減による米長期金利低下だっただろう。米長期金利、10年債利回りはクリントン政権発足前の7%程度から財政赤字削減策を織り込む形で1993年後半には5%を割れるまで低下した。こうした米金利低下は、米ドル/円が下落する実質的な要因になったと思われる。
この点は、トランプ政権においても類似点かもしれない。ベッセント財務長官は政府支出の削減などにより長期金利の低下を目指すと述べてきた。一方で日本政府に対して、金融政策の正常化として早期の利上げを期待しているように見える。以上から、日米2ヶ国が金融・為替政策において緊密に協力し、主に金利差(米ドル優位・円劣位)縮小により円安是正を目指すことには現実性がありそうだ。
ただクリントン政権においても、1994年以降は米金利が上昇に転じたものの米ドル/円の下落は止まらなくなっていった。このように為替調整は途中からコントロール不能に陥るリスクがある。クリントン政権時代は、1995年になりG7が協調介入を繰り返すなど苦労を重ねることでようやく米ドル/円の底入れとなった。
トランプ政権では、相互関税発表以降、一時「米国売り」が拡大した可能性があった。そうした中で米ドル安への為替調整を行うならコントロール不能の米ドル安に陥るリスクがあるだろう。そしてトランプ大統領はアンチ国際協調派のように見える。そうであれば万一米ドル危機のような事態になった時、協調介入など国際的な政策協調が機能するかも甚だ怪しそうだ。