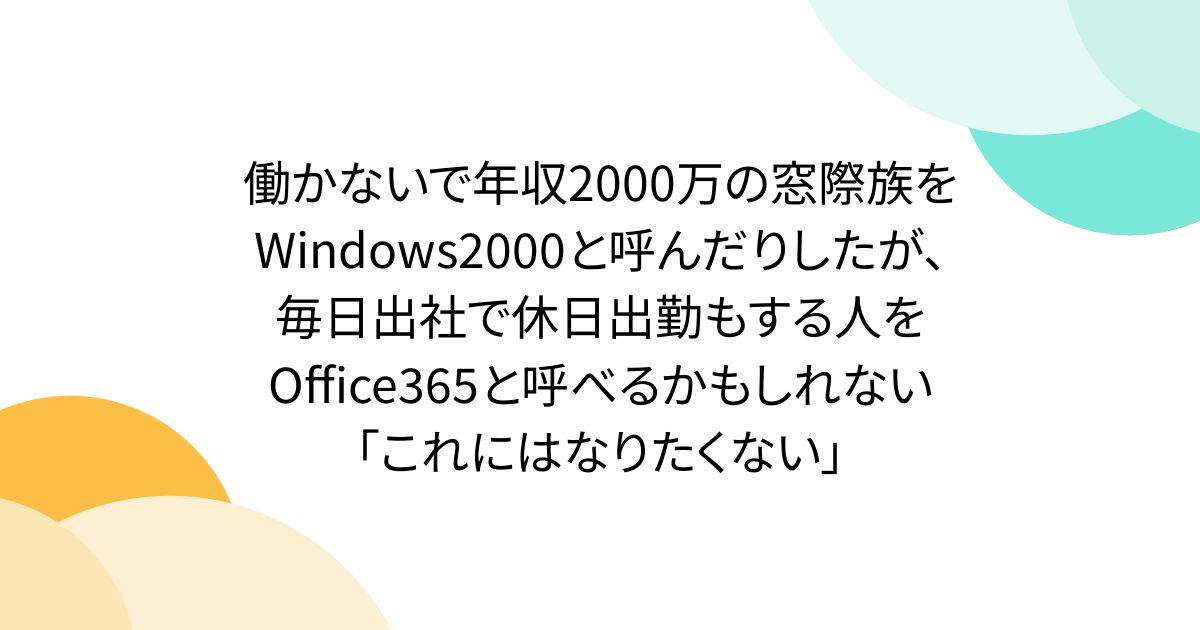【Hothotレビュー】ミニPCの常識が変わる。Ryzen AI Max+ 395搭載「MINISFORUM MS

MINISFORUMから、待望のRyzen AI Max+ 395を搭載したミニPC「MS-S1 MAX」がついに発売となった。価格は35万9,990円だ。発売前に今回いち早く製品サンプルを入手したので、試用レポートをお届けしよう。
ニュース記事からもう想像がついていると思うので、結論から言ってしまうと、MS-S1 MAXはこれまでのミニPCの中で最強の存在であり、特に生成AIやLLM(大規模言語モデル)を比較的リーズナブルに自宅や社内で動かしたいというパワーユーザーにとって、これ以上の選択肢がなく極めて優れた1台であった。
Ryzen AI Maxは2025年1月の発表当初、おそらくほとんどの人にとって「CPUとGPUがちょっと強いプロセッサ」という認識の方が強かっただろう。確かにその際も「GeForce RTX 4090相当のAI性能」だと謳われていて、AIを全面的に押し出していたことには間違いないが、画像生成AIはNVIDIAの方が有利、LLMもローカルで実行できる規模には限度があるという認識がほとんどだったのではないかと思う。
しかしOpenAIが2025年8月に発表した「gpt-oss」でこの状況が一変。モデルのコンテキスト処理をGPUに負担させウェイト自体はCPU側に置くという効率性に優れた構造や、複数小さいモデルからなる“エキスパート”を組み合わせて使うMoE(Mixture of Expert)アーキテクチャにより、「PCのメインメモリが32GBさえあれば20b、96GBあれば大規模な120bがそこそこ動く」というブレイクスルーを実現。さらに日本語対応もほぼ完璧であったので、ローカルLLMが一気に身近になった。
ただ結局のところ、ローカルでLLMを超快適に使いたいのなら、VRAMを96GB以上搭載した、100万円以上するサーバー/ワークステーションビデオカードが必要な状況は変わらないのだが、そこそこの速度で良いのなら、実はRyzen AI Max+ 395は優れたコストパフォーマンスを実現できる選択肢となるため、注目され始めたのだ。
その理由だが、以下の3点に集約できる。
- メモリ128GBの構成では96GBをVRAMとして割り当てることができ、大きなAIモデルが置ける
- メモリはクアッドチャネル(256bit)構成、しかもLPDDR5x-8000で高速
- iGPUはかなり強力なRadeon 8060Sを内蔵
1)については、AMDが公式で謳っているため、改めて言うまでもない特徴の1つだ。これにより、96GBのVRAMを搭載した超高価なビデオカードが不要になる。
実は、Ryzen AI 9 HX 370でも、メモリ128GBを搭載すれば、96GBをVRAMとして割り当てることが可能な環境もあるようだが、挙動的には非公式だ(MINISFORUM AI NAS N5 Proで確認)。また、この環境で筆者が試した限り、Windows版LM StudioのVulkan版llama.cppは、64GB以上を割り当てることができなかった(なぜかモデルウェイトをCPU側に置くこともできなかった)。しかし、Ryzen AI Max+ 395ではAMDが公式で対応を謳っているだけあって当然この問題は発生しないので、今のところAMD環境ではRyzen AI Max+だけの特権となる(GPUを使わず、CPUだけを使うのなら問題ないが)。
2)について、Ryzen AI 9 HX 370でもLPDDR5x-8000対応ではあるのだが、デュアルチャネルでバス幅が128bitであるほか、メモリを増設できるミニPCでは、モジュール型DDR5-5600を採用しているため、帯域幅は89.6GB/sに限定される。一方Ryzen AI Max+ 395はクアッドチャネルでLPDDR5x-8000専用のため、帯域幅は256GB/sとミドルレンジのビデオカード相当だ。LLMではこの帯域幅が“効く”ので、無視できない要素だ。
3)のRadeon 8060Sについてだが、CU(Compute Unit)数が40基と、Ryzen AI HX 370の12基よりかなり多くなっている。このため演算性能が必要とされるコンテキスト処理も高速に行なえるのだ。
IntelのCore Ultra 9 285H搭載ミニPCでも、メモリを128GB搭載すれば、gpt-oss-120bを動作させられる。そのため要件1)自体はRyzen AI Max+ 395の特権というわけではないが、メモリのバス幅やGPU演算性能の点で劣るので、動作はできても速度は遅い。答えが出れば良いという使い方ならアリではあるのだが、「そこそこのレスポンスで」「比較的安価に実行したい」というのであれば、今のところRyzen AI Max+ 395搭載機は唯一無二の存在となるのだ。
それではさっそくMS-S1 MAXを見ていこう。本体の箱はこれまでの同社のミニPCラインナップの中では大きい部類に入る。内容物は本体のほかに電源ケーブル、HDMIケーブル、固定用ネジ類(100mmピッチのVESA、またはラック設置時固定用)、M.2 SSD用ヒートシンク、そしてPCIe拡張カードから基板を保護するための絶縁シートが添付されていた。ACアダプタが付属されていないが、これは本機が電源を内蔵しているためである。
この320Wの電源ユニットを内蔵している点は大きなアドバンテージだ。これにより、多くの高性能ミニPCで必須だった巨大なACアダプタが不要となり、デスク周りの設置スペースを大幅に節約できる。コンセント周りがスッキリするのは、地味ながら非常に嬉しいポイントだ。
筐体は分厚い金属で囲まれており、堅牢性はかなり高い印象を受ける。前面はダイヤモンド状のメッシュとなっているほか、背面および本体上部(横置き時)にも多くの通気孔が用意されており、排熱にかなり気を配っているのが分かる。デザイン的にはシンプルで、特に前面はラックマウントサーバーを彷彿とさせるものがある。
前面インターフェイスはUSB4 2基、USB 3.2 Gen 2、そして音声入出力と電源ボタン。背面にはUSB4 2.0 2基、USB 3.2 Gen 2 2基、USB 2.0 2基、10Gigabit Ethernet(10GbE) 2基(10GBASE-T)、HDMI出力を備えている。ミニPCとしては十分すぎるほどだ。
ちなみにUSB4 2.0は、つまり80Gbps転送が可能なものだが、これはRyzen AI Maxが本来備わっているものではなく、Intelのチップ(JHL9580)によって実現している。MINISFORUMによればRyzen AI MaxとこのJHL9580の組み合わせは初だ。
10GbEを2基搭載する点も本機ならでは。10GbEが2基という特徴自体は、同社初のミニワークステーションで搭載されたが、この際のポートはSFP+で、接続する際にはSFP+モジュールを別途購入する必要があった。もちろん、光ファイバを使う10GBASE-SRや10GBASE-LRといった接続方法が選べるという意味ではSFP+の方が自由度が高いが、一般企業や家庭内においては銅線を使う10GBASE-Tの方が、既存の機器との親和性が高く、ケーブルも一般的な家電量販店で購入しやすい。この10GBASE-TのSFP+モジュールが比較的高価だ。その意味で、本製品は最初から10GBASE-Tの10GbEポートが2基搭載されているので親切だ。
このほか、Wi-Fi 7やBluetooth 5.4も備えており、ミニPCとして実現し得る限りのネットワークが構築できる。
内部的へのアクセスは簡単で、本体背面左右にある2本のネジを外すことで、後ろに引き出せるようになっている。
開けてまず目に付くのがヒートパイプを6本採用した大型のヒートシンクと2基のファンだ。ちなみにCPUとヒートシンクの間の熱伝導には、一般的なグリスよりも高い性能を実現する相変化材料が使われている。こうした工夫により、最大ピークパワーは160Wに達するという。
直近のインタビューで、MINISFORUMはこの最大160Wのピークパワーを特徴として謳っていた。AMD公式のスペックによれば、Ryzen AI Max+ 395のcTDPは120Wまでとなっているのだが、一部メーカーではピーク140Wまで引き出している製品もある。しかし本製品ではそれよりもさらに高い160Wを達成できたのは、開発陣による努力だろう。
動作電力については現状、BIOS上からモード切り替えを行なう仕組みとなっている。標準では「Balance Mode」が設定されていたが、より静音な「Quiet Mode」やこの160Wを引き出すための「Performance Mode」、ファン制御を無効にしてBalance ModeとPerfomance Modeの間の性能を達成する「Rack Mode」が用意されている。
筆者の主観で静音性を評価させてもらうと、「ほぼ仕様値通りかなぁ」という印象。アイドル時はBalance Modeでも「Ryzen AI Maxが入っている」と思えば静かだと思うのだが、同社の「AI X1 Pro」や「M1 Pro-285H」のような静粛性がほしければ、Quite Modeにする必要がある。一方Perfomance Modeはアイドル時でもやや耳につく印象だ。フルロード時はいずれのモードも結構耳に届く。
幸い、不快な軸音ではなく風切り音がメインなので慣れてしまえば気にならない。2m程度離れると届きにくくなるので、離れたところに置く使い方もアリだ。また、ファンの音は主に横置きの際の上部の通気口から聞こえてくるのだが、本製品は縦置きに対応しているため、縦置きにしてファンの音を別方向に逃がすといった工夫をすれば良い。
CPUファンの前側にはM.2スロットが2基用意されている。うち空きの1基はWi-Fiカードとは2階建て構造になり、接続もPCIe 4.0 x1とバス幅が限定される。なお既にSSDが装備されているM.2スロットは4.0 x4接続だ。
また、裏側にPCIe 4.0 x4(x16形状)の拡張スロットを備えている点も本製品ならでは。LowProfileでハーフレングス、なおかつシングルスロットというあたりで、中に収まるカードでは本機の特徴を生かせるものが少ないが、OCuLinkカードを使って外に出すという手段も残されている。
ただここで注意したいのは、このPCIeスロットは今のところ「いかなるdGPUもサポートしない」という点。MINISFORUMによればRyzen AI Max自体の作りがかなり特殊でサポートできないとのことだ。この注意書きは説明書にも記載されているので、改めて喚起しておきたい。
ここで「なぜM.2やPCIeスロットはフルスペックではないのか?」という疑問もあるであろう。実際数えてみると、JHL9580がPCIe 4.0 x4接続、M.2スロット装着済みのSSDがPCIe 4.0 x4接続、2つのRTL8127がPCIe 4.0 x1接続×2、そしてWi-Fi 7カードのMediaTek MT7925がPCIe 2.0 x1接続……といったあたりで、実はRyzen AI Max+ 395が持つPCIeの16レーンのうち11レーンが使用済みなのだ。その残った4レーンがPCIeスロット、1レーンがM.2スロットに割り振られているわけである。
ちなみに、空きM.2スロットの手前にはピンヘッダが用意されているのだが、これは集中制御用とされている。実際、線をどう這わすのか工夫する必要があるのだが、NanoKVMといった拡張カードを使ってリモートで電源投入からBIOS、OS起動までを操作する……といった使い方も考えられよう。
本機の一番の期待は、やはりその性能だろう。筐体サイズが従来のミニPCの枠を超えているので、これまで通りの性能だったら面白くはない。今回はベンチマークとして「PCMark 10」「3DMark」「Cinebench R23」「ファイナルファンタジーXIV」といったお馴染みのベンチマークに加え、いくつかアプリケーションやゲームも実際に実行してみた。
なお先述の通り、4つのモードが選べるのだが、今回はBalance Mode、Perfomance Mode、Quite Modeの3つでテストした。比較用に、ディスクリートGPUとしてRadeon RX 7600M XTを搭載した「AtomMan G7 Pt」の結果(静音モード)を並べてある。
まず一般的なPCとしての性能だが、GPU統合型CPUとしてはさすがに凄まじいの一言。総合的なPC性能を示すPCMark 10では、いずれの動作モードでも8,000を超えるスコアをマークし、日常作業からクリエイティブなタスクまで、あらゆる場面で快適な動作を提供できることが確認できた。
ミニPCで一般的なCore Ultra 9 285HやRyzen AI 9 HX 370では異なる性能のコアが混在しているのだが、Ryzen AI Max+ 395は16コアすべてが高性能コアだ。こうした圧倒的なCPU性能が下支えしているのに加え、ディスクリートGPU級の性能を持つRadeon 8060Sも内蔵しているしているため、Creativity Scoreも高い。
CPU性能を測るCinebench R23では、Perfomance Modeのマルチコアで37,036ptsというスコアを記録。これはAtomMan G7 Ptのスコアはもとより、AtomMan G7 Ptをパフォーマンスモードで動作させたときのスコア(未掲載だが、実際は31,993)や、多くのデスクトップPCをも凌駕する数値だ。正直、“破格”の一言である。
これまで内蔵GPUでは限度があったゲーミング性能においても、MS-S1 MAXは高い性能を発揮。3DMarkテストにおいてはRadeon RX 7600M XTに肉薄する性能を実現していた。
ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー ベンチマークでは、1,920×1,080ドットの最高品質設定では、いずれの性能モードでもスコアが1万に達し、「とても快適」の評価を獲得。Ryzen AI 9 HX 370などではノートPC(標準品質)にしても1万に届かず、同じ最高品質にすると半分以下の4,000台なので、2倍以上の性能を持つ計算になる。
ファイナルファンタジーXIVではRadeon RX 7600M XTに敵わなかったのだが、Cyberpunk 2077(フルHD解像度)では逆にAtomMan G7 Ptを上回った。Radeon 8060SのアーキテクチャであるRDNA 3.5は、Radeon RX 7600M XTのRDNA 3から改善されたものなので、このあたりが効いた可能性が大きいと言えるだろう。
実際のゲームとして「エースコンバット7」「ゼンレスゾーンゼロ」などさまざまなゲームをプレイしてみたが、画質を「高」などにしても、GeForce RTX 4060を搭載したミニPCとまったく遜色なくプレイできた。
最も、本製品でもっとも注目すべき性能は、LLMだろう。LM Studioで大規模モデル「gpt-oss-120b」を動作させたところ、トークン生成速度は30tok/sを超えるという驚異的な結果を叩き出した。これだけの速度が出れば、ローカル環境でありながら、クラウドサービスに肉薄する快適さでAIとの対話が可能になる。
この驚異的な性能の源泉は、強力なRadeon 8060S GPUと、それを支える256GB/sもの広帯域なクアッドチャネルメモリにある。グラフィックスメモリをメインメモリと共有するiGPUにとってメモリ帯域は生命線だ。Ryzen AI Max+ 395を搭載したMS-S1 MAXはこのボトルネックを解消することで、性能のポテンシャルを最大限に引き出すことに成功している。
MS-S1 MAXは、これまでミニPCでは設定を妥協する必要があった高度なグラフィックスを利用する最新の3Dゲームや、ディスクリートGPUの搭載をもってしても実現が難しかった大量のVRAMを消費するLLMの快適運用が可能になる1台だと言える。
MS-S1 MAXは、単に「高性能なミニPC」という言葉で片付けられる製品ではない。ミニPCというカテゴリそのものの可能性を再定義し、新たな時代を切り開くゲームチェンジャーだ。
大量にメモリを消費するオフィスアプリやクリエイティブアプリの快適利用はもちろんのこと、ミドルクラスのゲーミングPCに匹敵するグラフィックス処理能力、ローカル環境で大規模言語モデルを快適に動作させる圧倒的なAI性能……これらすべてが、電源ケーブル1本で完結する、洗練されたコンパクトな筐体に収められている。
MS-S1 MAXは決して安価ではない。しかし、大型のデスクトップPCを組むコストや手間、設置スペースを考えればその価値は十分にある。また、VRAMを32GB以上消費するようなLLMに関しては現状、40万円切りの自作PCでどうにかなるレベルではないので、こうした市場が本製品のようなミニPCによって新たに開拓される。
よって、ミニPCの歴史は、MS-S1 MAXの「登場以前」と「登場以後」で語られることになりそうだ。それほどの衝撃と完成度を、本機は秘めているように思う。