【毎日書評】部下や後輩が驚くほど成長する!科学的に証明された「教える技術」
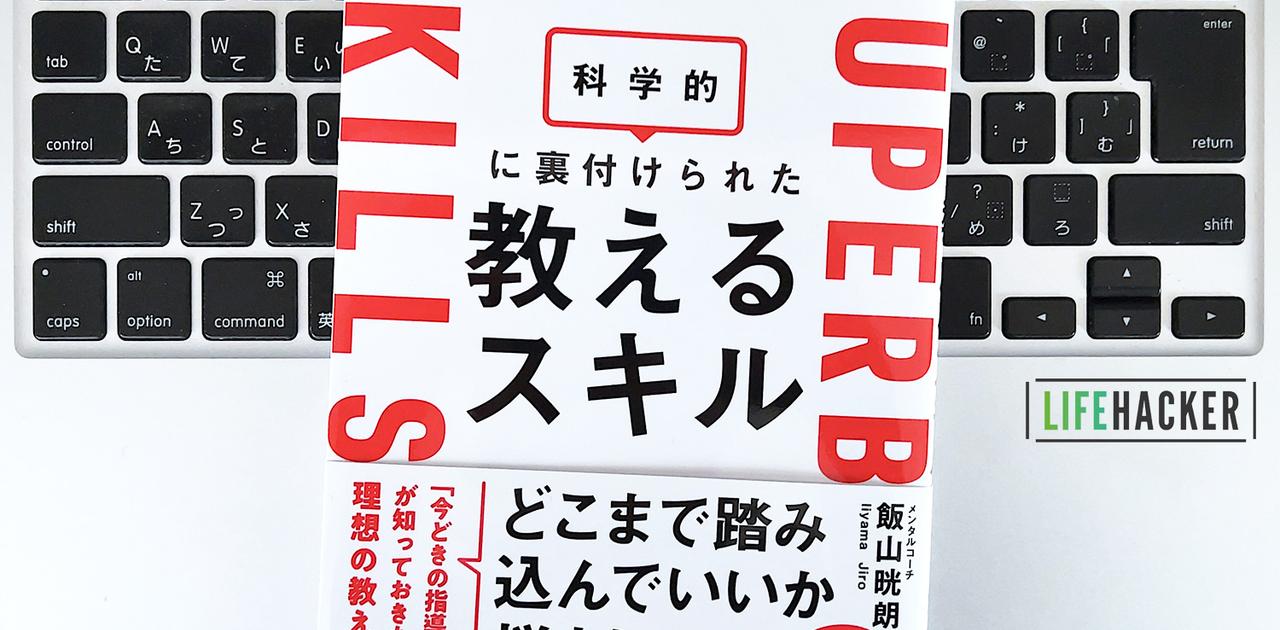
『科学的に裏付けられた教えるスキル』(飯山晄朗 著、KADOKAWA)の著者は、メンタルコーチ/人財教育家として活動する人物。これまで、何万人規模の企業から十数人規模の企業まで、多くの組織やチームに対して人財教育を行ってきたのだそうです。
そんななかで気づいたのは、「その組織やチームに合致した教育をしていく必要がある」こと。そして、「だとすれば組織内で『教える人』をつくればいいのではないか」という思いに至ったことから、個々の組織やチームの実情に合った教育指導を行うインストラクターを育成するための活動をはじめたのだといいます。
なお、そうした活動のなかでよく相談されるのは、次の2つであるようです。
① 「成果をつくるためにはどうしたらいいのか」
② 「どうやって教えたらいいのか」
(「まえがき」より)
そこで本書においては、“成果をつくるための型”や“教え方の型”を中心に、脳科学を用いて、これまで企業を筆頭に多くの分野で効果が出た方法を紹介しているわけです。
ちなみに著者は脳科学を活用した人材マネジメント手法である「科学的マネジメント」を企業や組織で導入しているそう。脳科学によって、脳思考タイプがわかるようになったというのです。
脳思考タイプとはわかりやすく言うと「思考の癖」のことです。
私たちの脳には明確に傾向性、つまり思考の癖があることが立証されています。
この脳思考タイプに合わせた人材教育が効果を発揮するのです。(「まえがき」より)
そうした考え方に基づく本書のなかから、きょうはPart1「『教える』ことの成果ってなに?」内の第2章「実現力を養うために」に焦点を当ててみたいと思います。
どれだけ努力したとしても、報われないことはあるもの。仕方がないことであるようにも思えますが、著者によれば、努力が報われないことには理由があるようです。その努力に「しなければならない」という義務感を抱いているから報われないのだというのです。
当然ながらそれは、脳にとって不快な状態でもあるでしょう。そのため集中することができず、効率も上がらないため、いくら努力してがんばっても報われないのだということ。
しかし、だとすれば、脳が快く感じる努力なら報われるということになるはずです。
例えば、スマホでゲームをやったりYouTubeを見ているときはどうでしょう。楽しくてぜんぜん苦になりませんし、時間を忘れて集中してしまいますよね。
これと同じように仕事に取り組めたら、どうでしょう。必ず成果をあげることができると思いませんか?
「そうは言っても、仕事とゲームは違うから」などという反論がありそうですが、私からしたら同じです。
高得点を出したり、強敵を倒したり、新しいアイテムを手に入れたり…
やっていることは仕事と同じですよね。(62〜63ページより)
著者いわく、そこがポイント。なぜなら、脳は「思っている」ことよりも「やっている」ことを信用するものだから。たとえば、ひとつの仕事を終えたら、笑顔で「できた!」と口にするなど、表情や動作、行動を変える。そうすることで、脳は「このことが楽しい」と認識してくれるわけです。
なるほど、「やりなさい」では義務感になってしまいます。そこで、部下や後輩と一緒に喜びを表現してあげるべきだという考え方なのです。(60ページより)
それに加えて著者は、もっと目標に向けた努力を楽しむために、「お祝い」も用意してみてはいかがだろうかとも述べています。
ミスや失敗に対して通知を出したりすることはあったとしても、よかったこと、できたことについて通知や周知を図ることは少ないはず。ある意味で、できることが“当たり前”になっていることが少なくないからです。
その点について、製造業で考えてみましょう。
現場においては不具合や不適合など“不良に関すること”を周知することはあっても、納期どおりに収めたとか、不良がなかったなど“よかったこと”を発表する機会は少ないのではないでしょうか。しかしそれでは、社員がネガティブになってしまっても無理はありません。
その結果、本来の目的は「不良が出ないこと」であるにもかかわらず、不良が一向に減らないと状況になってしまうことも考えられます。
著者によればそれは、脳が「なにに意識を向けているか」ということに関係しているようです。つまり脳は意識していること、イメージしていることを実現していくということ。そのため不良に意識を向けると“不良を出したイメージ”が湧いてきて、不良を出してしまうことになるわけです。
だとすれば大切なのは、不良をクローズアップすることではなく、いいことやできたことに意識を向け、“できるイメージ”を持てるようにすること。
そこで著者は、できたことに対して「お祝い」をすることをすすめています。具体的に提唱しているのは、ポジティブな事柄を記録する「ポジティブ・スコアリング®︎」。
目標に向けたポジティブな行動を記録するのです。
「できた」を増やすことで、自信をつける効果もあります。(58ページより)
重要なのは、ポジティブなスコアをつけていき、それをフィードバックすること。会社都合の評価とは別に、自分で決めた行動(スコアリング)を評価してあげる――つまりはそれが「お祝い」だというわけです。
「お祝い」の目的は、「望ましい行動」を習慣化することだそう。たしかにそれなら、前向きに仕事を進めていくことができそうです。(64ページより)
本書を活用すれば、教える立場の人や組織のリーダーとしての指導の悩みが解決するはずだと著者は述べています。よりよい教え方を身につけたいのであれば、参考にしてみてはいかがでしょうか。
>>Kindle unlimited、500万冊以上が楽しめる読み放題を体験!
Source: KADOKAWA



