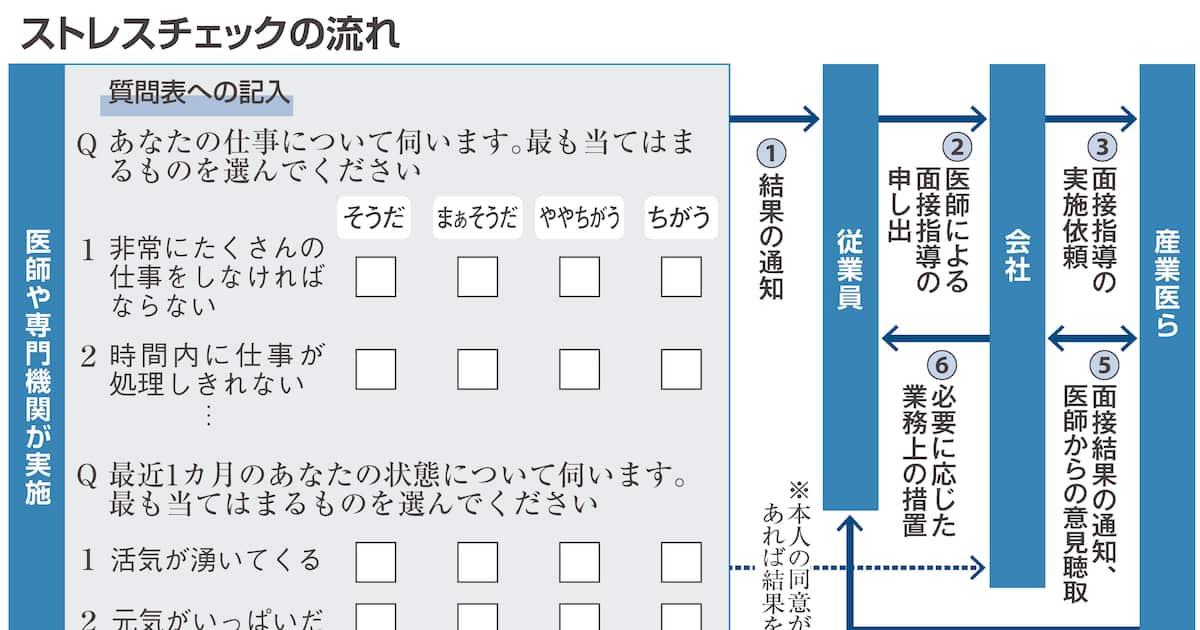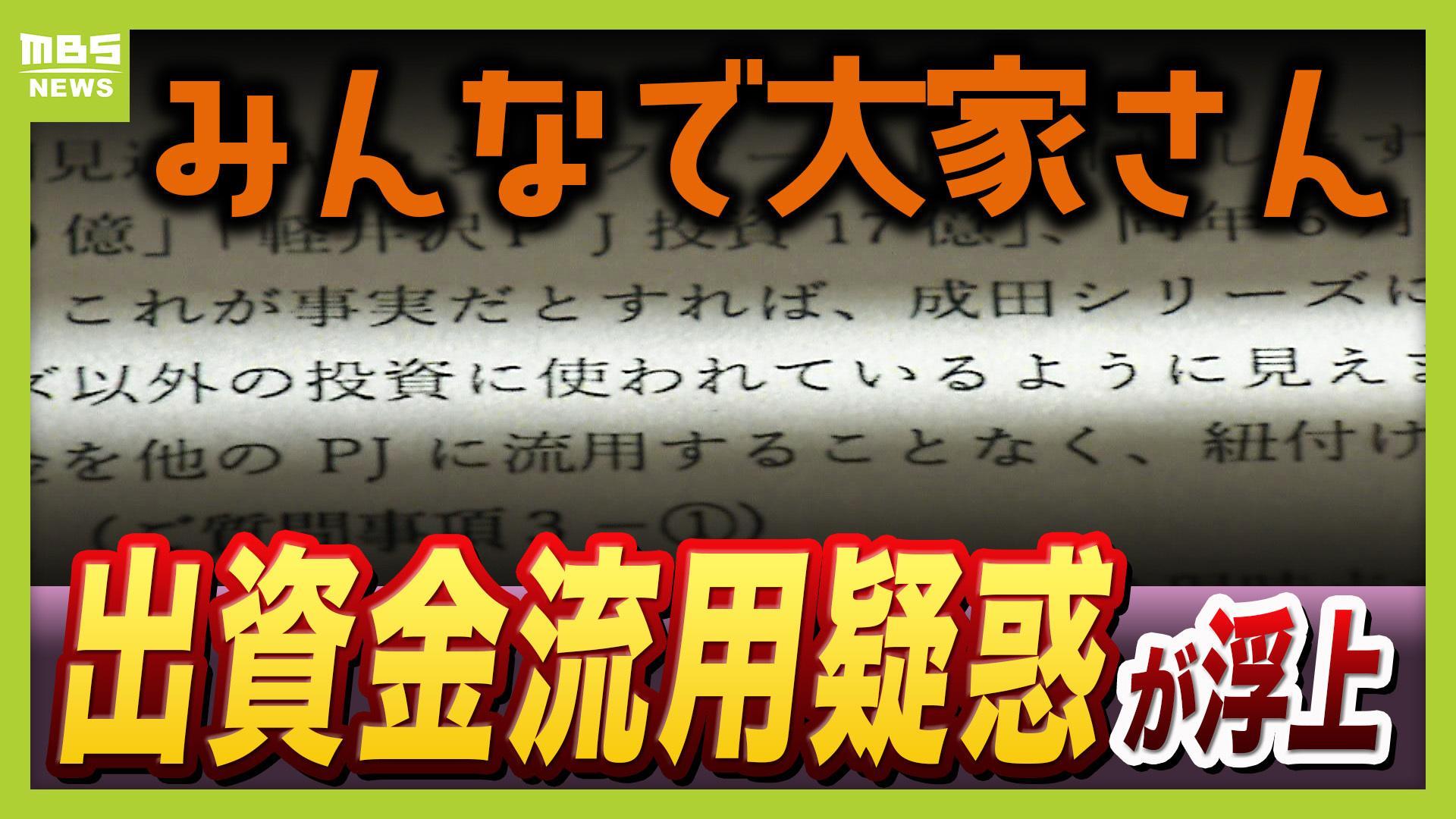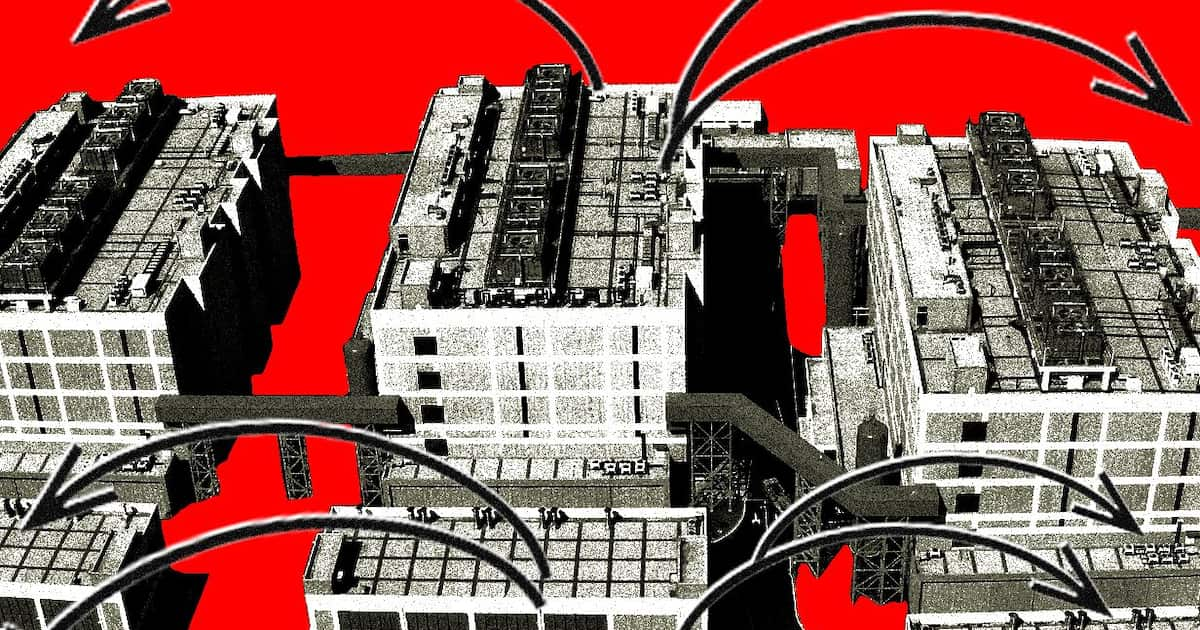新iPhoneの「超量産」がもたらすもの 堅牢・低消費電力、カメラの変化

今年も米・カリフォルニア州クパティーノにあるアップル本社へと赴き、iPhoneを中心とした新製品の発表を取材した。
良くも悪くも、iPhoneは毎年議論を呼ぶ。多くの人が使っているからこそ、誰もがなにか物申したくなるのかもしれない。
今年は薄型に特化した「iPhone Air」を中心に、デザイン変更にフォーカスが当たった年だったと言える。
他社製品はAIにフォーカスするものが少なくないが、アップルは開発の遅れから、そこではまだ強いアピールができない事情もある。
一方で、今年のiPhoneをはじめとした製品の設計思想の背景には、AIをはじめとした変化の影響が見てとれる。
そしてそれ以上に、久々に「超量産という力技」ありきの製品づくりを見た印象が強い。
そのことは、アップルでないと難しい得意技であり、スマホをまた少し変えていく要素ともなっている。今回はその話をしよう。
今回の発表を見ながら、個人的に思わず声を上げた点が3つある。
それを順に説明していこう。
1つ目は「iPhone 17 Proのユニボディ」だ。
最近のiPhoneは、フレームの前後にディスプレイとカバーガラスを挟み、その中にメイン基板とバッテリーを入れるような構造だった。
だが今回のiPhone 17 Proシリーズでは、アルミ合金の一体成形であるユニボディが使われている。全体を1つのアルミ合金製ケースでカバーし、メイン基板は可能な限り本体上部に集めた上で、内部の大半を巨大なバッテリーパック用のスペースにする。背面はワイヤレス充電のためにガラスでカバーするが、その面積はいままでのモデルよりも小さくする。
デザインのバランスが過去のiPhoneとは変更になったので、シンプルに違和感を覚えた人も多いようだ。
とはいえ、実物を見ると不思議と納得がいく。これは、バッテリー動作時間や発熱の低減、堅牢性を重視した、実用性とのバランスを考慮した造りなのだ。
そこでアルミ合金を使うのも、発熱低減が狙いである。チタン合金に比べて放熱が速やかになる。
ではなぜ、これまではチタン合金だったのか?
理由は強度だ。
曲がりにくくするにはフレームの強度が重要。枠の構造をとる場合、アルミ合金では求められる強度に達しづらく、結果としてチタン合金を使うことになったのだろう。
このことは、フレーム構造を採用しつつさらに薄型化を目指した「iPhone Air」はチタン合金フレームを使っていることからもわかる。
ではiPhone 17 Proはどうかというと、アルミ合金を使いつつ「フレームではなく複雑な構造のユニボディで堅牢さを実現する」方向に向かっている。
より厚いアルミ合金で、さらに複雑なバスタブ構造とすることで、「1つのパーツでありながら堅牢なボディ」にしているわけだ。
重要なのは、このユニボディを切削加工でなく「冷間鍛造」で作ったことにある。
冷間鍛造とは、冷たいままの金属に圧力をかけて形状を作る技術のことだ。特徴は、精度の高さと強度・靱性を両立できることであり、欠点は、切削や薄板のプレスに比べ非常にコストがかかることにある。
冷間鍛造は、自動車で言えばギアやシャフトなどの精度と強度が必須な部品で使われている。過去、アップルはステンレスフレームに冷間鍛造を使ったことがあるが、「アルミのユニボディ」は切削加工だった。
スマホのボディは内部形状が複雑であり、切削加工の方がコスト的には圧倒的に有利だ。だが今回iPhone 17 Proでは、あえて強度と放熱特性、そして複雑な形状の3つを実現するため、大規模な冷間鍛造プロセスを採用している。
こうした判断は、とにかく大量に生産するiPhoneのような製品でないと難しい。逆に言えば、スマホの発熱とバッテリー動作時間の問題について、アップルは「それだけのコストをかけてでも解決が必要なものだ」という判断を下した、という話でもある。
iPhone 16 Proシリーズは特に発熱が大きかった。それが不評という話もあるが、今後Apple Intelligenceが進化し、「常時AIが走る」スマホになるとすれば、バッテリー動作時間と発熱低減は、よりクリティカルな要素になってくる。
だからアップルは、ここで一気に製造プロセスに投資したのである。
2つ目の驚きは「フロントカメラのイメージセンサーを正方形にしたこと」だ。
一般的に、イメージセンサーの形状は長方形をしている。人間の視野は横に長く、写真の縦横比も「横長」が多い。
フロントカメラのイメージセンサーも、結局のところ「一般的なセンサーの形状」に合わせて作られている。スマホでの自撮りは本体を縦に持って撮ることが多いので、一般的には「縦長」にイメージセンサーを配置している。
だがiPhone 17シリーズとiPhone Airでは、フロントカメラ用のイメージセンサーを「正方形」にした。縦長で撮る場合も横長で撮る場合にも、同じ「縦持ち」のまま撮影できるようになっている。
別の言い方をすれば、フロントカメラでの写真は「常にイメージセンサーから一部を切り出して撮影する」わけで、贅沢な使い方だと言っていい。
画角をAIで自動的に切り替え、写っている顔の大きさが適切になるよう自動でデジタルズームをする機能も、その延長線上にある発想だ。
今までは「写真」は、イメージセンサーをできる限り広く使い、画素を無駄なく使うのが基本だった。だから正方形のイメージセンサーは業務用で、スマホやデジタルカメラにはあまり使われてこなかった。
だがアップルは、「自撮りはリアカメラでの撮影とは異なる」という姿勢を打ち出した。落ち着いてシャッターを切る「カメラ」とは、撮り方がそもそも違うと考えたわけだ。自撮りで重要なのは「みんなの顔がしっかり映る」こと。スマホを持ちかえるのは面倒だし、カメラの位置は上の方が、皆の目線がずれない写真になりやすい。
アップルによれば、昨年1年で、iPhoneでは5,000億枚もの自撮り(セルフィー)が行なわれたという。ならば、自撮りは「普通の写真とは異なるもの」と捉え、同じようなセンサーを採用するのではなく、独自のものを用意する……という発想はあっていい。
似た発想をしたところは、他にもあったかもしれない。
しかしこれを実現するには、イメージセンサーのメーカーに対し、「正方形のフロントカメラ用センサーを、自社専用に作らせる」必要が出てくる。少量では実現できないことであり、やはりこれも「iPhoneを一気に大量に作る」アップルだから実現しやすかったのだろう。
逆に言えば、これで「正方形のフロントカメラ用センサー」は用意できたことになるので、今後色々なメーカーが「写真を切り出して使うことを前提とした、正方形のフロントカメラ用イメージセンサー」を採用してきても不思議はない、と思う。
3つ目の驚きは「eSIM」だ。
今回は日本で販売するモデルでも、全機種がeSIMのみになった。iPhone本体からSIMカード用のスロットが省かれる。
アメリカでは2022年からすべてのiPhoneでeSIMが採用されている。だからいつかは日本も含む他の国でも……と予想していたので、「まさか」ではない。「ついに」という感覚だ。
これは、今回発表されたiPhone Airが薄型であり、もはやSIMカードスロットを搭載するスペースがない……という事情もあるだろう。
iPhone 17シリーズでは他国の場合eSIM非採用のモデルもあるが、iPhone Airは、eSIMのモデルしかない。eSIMの採用に許認可が必要であり、政府の動きがハードルとなっていた中国向けのモデルですら、iPhone AirだけはeSIMを採用しているくらいだ。
eSIMへの切り替えは、一定の混乱を伴う。「トラブルが起きたら面倒だ」と考え、eSIM化を歓迎しない人もいるだろう。
だが、スマホメーカーも携帯電話事業者も、SIMカードを離れてeSIMへの移行を望んでいる。SIMカードスロットの分、バッテリー容量を増やしたり本体を薄くしたりできる上に、「eSIMだから」というビジネスも増やせるからだ。
例えば観光用のSIM。海外旅行者向けにSIMカードを売るビジネスがあるが、eSIMになれば扱いも課金も簡単になる。特定のライブ配信を見るために課金をセットにしたeSIM……というものも作れる。
メインの通信での機種交換や回線切り替えがオンラインで完結しやすくなる、というメリットもあるが、新しいビジネスの可能性もある。
とはいえ、トラブルも想定されるものなので、各社は「おそるおそる様子見」という部分もあった。そこである種の強制力を持って進められるのは、アップルのようにたくさん売る・たくさん売れるメーカーによる要望だから……という部分があるだろう。
切り替えなどでは携帯電話事業者のアナウンスを確認してほしい。
すでにiPhoneを使っていて、しかも、契約している回線がeSIMの「クイック転送」機能に対応している場合、扱いはとても簡単。新機種への移行途中で自動的にeSIMも移動する。
この機能、利用者側では機種変更なのだが、実質的には「eSIMの再発行」に近いもの。携帯電話事業者側では機種変更手続きが行なわれておらず、「再発行されたeSIMが新しい機種に入った」という扱いになる。大手4社はこのやり方の場合、「当面無料」としている。
店頭での手続きや「機種変更」として行なう場合、事務手数料が発生する可能性もある。その辺も含め、携帯電話事業者での扱いをご確認いただきたい。
なお、AndroidからiOS、iOSからAndroidへのクイック転送は、規格で定められている上に、すでにGoogleのPixelなどでは実装もされている。しかし現状、日本の携帯電話事業者では対応しているところがない。今後、遠くないうちに対応が行なわれると予測している。そうなると、どのスマホとの間でもeSIMでの機種変更が安価かつ簡単に行なえることになりそうだ。
最後に1つ、ボディ設計とeSIMが絡む面倒な話をしておきたい。
日本のiPhone 17 Proシリーズには、上部に「特に使われない樹脂製のパーツ」がある。
これは、ミリ波に対応したアメリカモデルで、ミリ波のアンテナのために用意されたもの。日本ではミリ波未対応なので、この部分は「単に樹脂のパーツが埋め込まれている」だけだ。
本来こうした場合には、
- eSIMとミリ波を採用したアメリカ向けボディ
- SIMカードスロット搭載でミリ波非対応のボディ
- eSIMでミリ波非対応のボディ
の3種を作るべきなのだが、冷間鍛造の加工はコストと手間がかかるので、一番目と二番目だけが作られている。
結果として日本や諸外国などの「ミリ波非対応だがeSIM」という国は、無用な樹脂が入ったボディを使うことになってしまった。
これは、冷間鍛造の持つ「ボディ設計を多数用意しづらい」という課題と、「全モデルでeSIMだけになった国が多い」という話の合わせ技で起きている話だ。
ならば、この機会にアップルは日本でもミリ波に対応してほしいところだ。
しかし、携帯電話事業者(特にVerizon)がミリ波対応を求めるアメリカと、そうではない日本とのギャップが埋められていないのだろう。日本での売価を抑えるには、ミリ波搭載は「まだ難しい」という判断なのかもしれない。