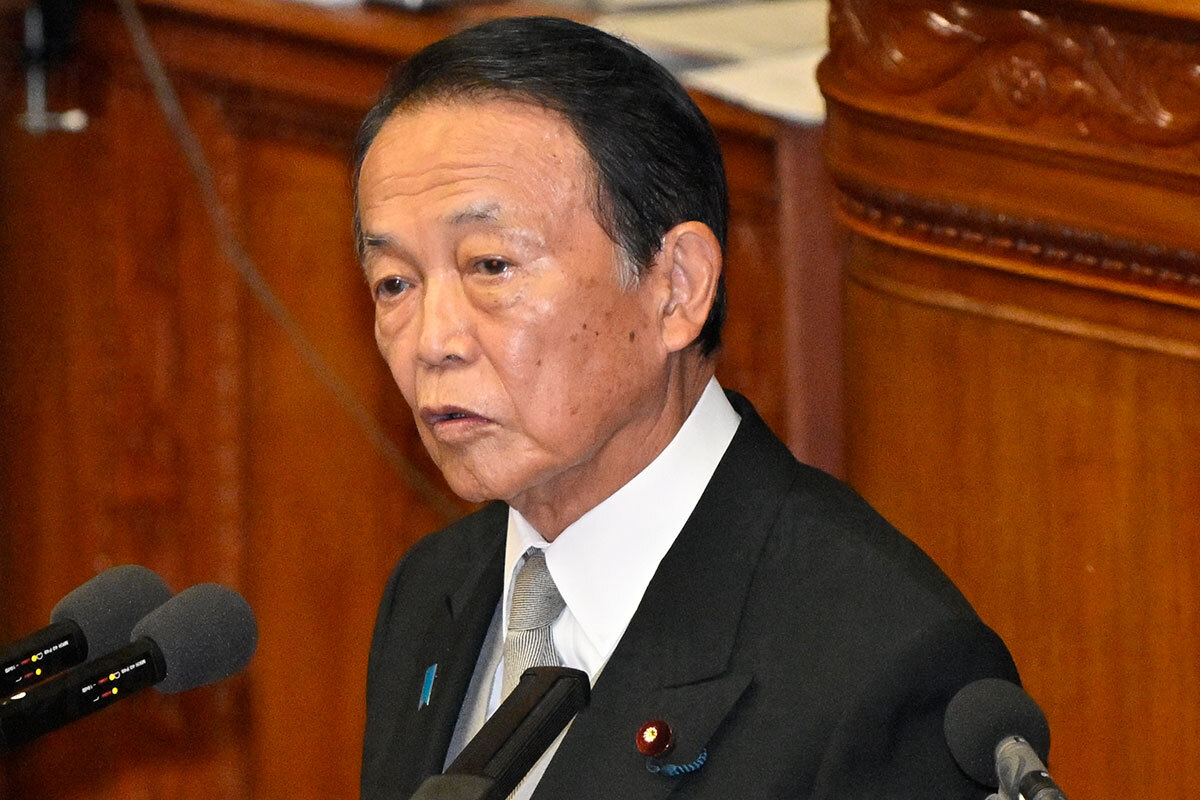“奇跡の生還”の苦しみ乗り越え 9日間生き埋めから命を守る仕事へ

東日本大震災から14年を迎える。小中学生のほとんどが震災後の生まれとなり、高校生もほぼ記憶にない世代となった。震災当時、10~20代だった世代が一つでも多くの命を救うため、語り部など防災活動に取り組んでいる。
「ここまでは来ないだろう」
「この看板の意味が分かりますか」
宮城県石巻市で1月下旬、阿部任(じん)さん(30)は東京から来た高校生らを相手に、大きな声で尋ねた。
Advertisement「津波避難場所を示しています。今住む地域に無くても、旅行先、これから就職する先にはあるかもしれない。覚えておいてほしい」
声を張り上げるのは、自分自身の後悔と、「南海トラフで失われる命を一つでも減らしたい」という思いがあるからだ。
14年前、仙台市内の高校に通っていた阿部さんは、石巻市内の自宅に帰省中だった。自宅に祖母と2人でいたところ、強い揺れに襲われた。
テレビでは大津波警報が発令されていたが、自宅から海まで約900メートルあり、目視もできない。「ここまでは来ないだろう」。自宅2階にとどまっていたところ、黒い津波が一気に押し寄せてきた。
2階部分が切り離され、200メートルも流されていたが、それを知ったのは後のこと。潰れた家の中で奇跡的に上向きに倒れていた冷蔵庫から食べ物を得て飢えをしのぎ、圧縮袋に入っていた布団やタオルで寒さをしのいだ。がれきの下から2人が救出されたのは9日後だった。
今でこそ、伝承活動に積極的に取り組むが、震災直後は違った。「奇跡の生還」という見出しとともに、入院していた病院にまで押し寄せたメディア。「自分の失敗が美談になって、注目されている」と苦しみ、「きっと逃げなかったことを非難される」と恐れた。そのまま県外の大学に進学し、ほとんど地元に帰らなくなった。
東日本大震災と向き合うきっかけとなったのは、同郷から同じ大学に進学した友人だった。酒席で「こいつ、9日間も埋まっていたんだぜ?」と笑い話でいじられる日々。「なんだ、俺の悩みってこんなもんか」と、自身の抱え込んでいた複雑な感情が和らいでいく感じがした。
「自分が背を向けている間に」
大学4年の時、約5年ぶりに石巻に帰った。自宅の跡地を探しに行ったが場所が分からず、たどり着けない事実に衝撃を受けた。「自分が背を向けている間に、見ず知らずの人が、がれきとなった家を片付けてくれた。復興のために。そんなことも知らず、申し訳ない気持ちになった」という。
卒業後は「地元のために」と石巻に戻り、現在は震災の教訓を伝承、他地域とのつながりを目指す「3・11メモリアルネットワーク」で職員として働く。特に今直面している課題は、震災を知らない世代への伝承、そして次世代の語り部の育成だ。
内閣府は南海トラフ地震で東海地方が深夜に被災した場合、約16万人の死者を想定。その一方、全員が発生直後に避難行動を取れば、死者数を9万人減らせると予想している。
震災から14年が経過し、子どもたちのほとんどが、震災の記憶を持たない世代となった。「宮城の小学生でも、東日本大震災が何月何日に起きたか分からない子がいる」と、危機感を抱く。未来に起こりうる有事のため「自分より若い世代にも語り継いでくれる人が必要」と訴える。
一方、伝承活動をする人の多くが、語り部だけでは生計が立てられない現状もある。「この状況で、手放しに次の世代へ『一緒にやろう』と呼びかけるのは無責任にも感じている」という阿部さん。語り部を「方法は違っても、消防士や警察官と並んで命を守る大切な職業」と考えているからこそだ。
昨年、阿部さんの職場に22歳の後輩がやってきた。同じく、東北大学の学生も語り部活動に参加している。「若手の語り部は、学んだことの要点が整理されていてとても聞きやすい」と信頼を寄せる。こうした未来の人材のためにも、確立した職業にするという目標がある。
他の被災地域や南海トラフが想定される地域の人々とも交流して、語り部の在り方の知見も深めている。「語り部が十人十色であるように、聞き手もそれぞれ。聞く人の人生に共感を生める人間でありたい」【北山夏帆】