特集 - 株探ニュース
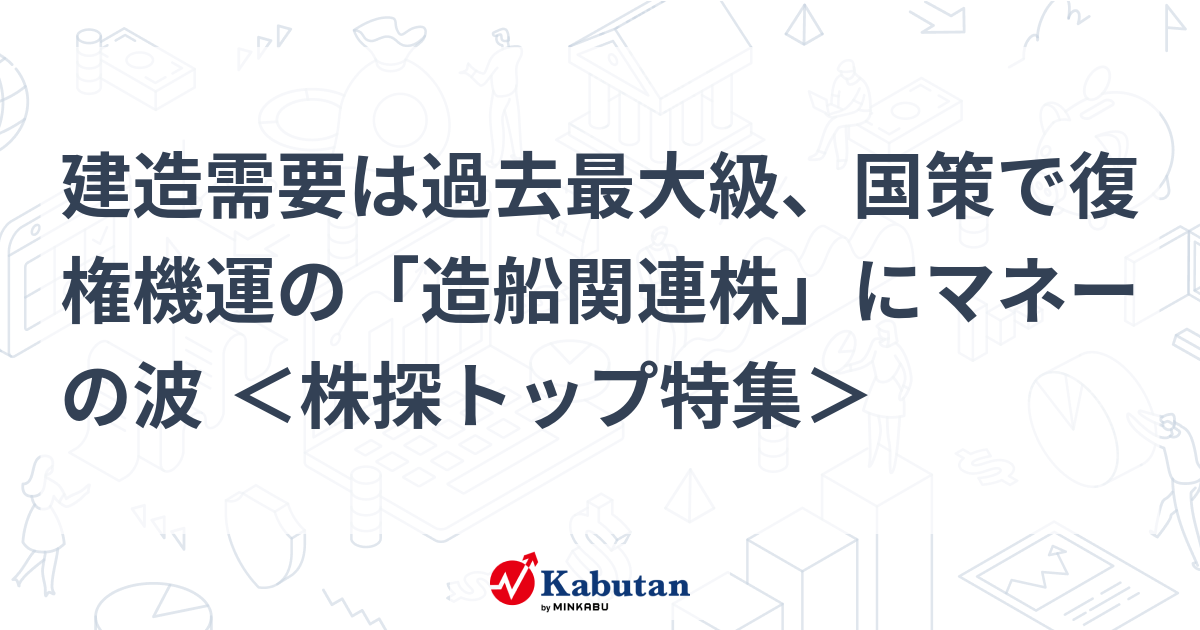
トランプ関税による世界景気の後退リスクが警戒されてはいるものの、 造船業界の強い受注トレンドが覆されるといった悲観が広がるまでには至っていない。中国・韓国勢に押される形で存在感が低下していた日本の造船業界は、国際的な環境規制を背景とした新造船需要にとどまらず、経済安全保障の観点から国策として復活を後押ししようとの機運も高まり、関連各社の事業に強い追い風が吹いている。更に今回の日米関税交渉では、半導体やAI、重要鉱物のほか、造船分野においても米国内で強靱なサプライチェーンを構築すべく両国が連携する方針が示された。好決算を発表する造船会社もあり、株式市場では関連株への物色意欲の高まった状態が続いている。
●「国立造船所」構想も浮上 日本造船工業会の世界の新造船建造需要予測によると、2021年に年間6000万総トン台にあった建造量は拡大基調を続け、30年代初めには1億総トン台に達する見通しだ。その後、50年にかけて1億総トンを上回る水準での推移が続くと考えられている。ゼロエミッション化への対応を背景に、過去最大級の造船需要が到来することとなる。 一方で、日本の造船業界は中国・韓国メーカーとの激しい競争のなかで大手の撤退も相次ぎ、人手不足という供給面での問題も抱えている。造船業の競争力が低下し海外への生産依存度が高まれば、四方を海に囲まれた日本にとって、安全保障上のリスクが高まることとなりかねない。 こうした危機感から、自民党の海運・造船対策特別委員会と経済安全保障推進本部は合同で、造船業の再生に向けた緊急提言をとりまとめ、6月20日に石破茂首相に提出した。商船と艦船の両面を見据えて生産能力の拡大と技術力の向上を実現するため、国主導で1兆円以上の投資を可能とする基金を創設し、国有施設民間操業(GOCO)による設備投資の拡充も検討しつつ、船舶のサプライチェーンの強靱化に臨むべきだと主張。「国立造船所」の建設構想として話題を呼んだ。造船業の現状に危機感を抱くのは米国も同様で、日米貿易協議では造船協力が日本側の交渉カードの一つとなった。対ロシアの観点から北極圏を航行できる砕氷船にスポットライトが当たり、製造能力を落とした米国の造船業を日本がサポートするシナリオが浮上している。防衛協力の観点では、オーストラリアが30年に運用を開始する予定の新型フリゲート艦について、三菱重工業 <7011> [東証P]の「もがみ型」の採用が決まったことも耳目を集めた。
●好反応示した内海造やダイハツイン国内の造船会社は今治造船(愛媛県今治市)が最大手となる。同社はJFEホールディングス <5411> [東証P]、IHI <7013> [東証P]が出資するジャパン マリンユナイテッド(JMU)の子会社化に乗り出しており、規模の拡大を図っている。JMUは砕氷船の建造技術を持つことでも知られる。上場企業では神戸と香川・坂出に造船所を持つ川崎重工業 <7012> [東証P]、三菱造船を傘下に持つ三菱重に加え、ばら積み船やタンカー、LPG船を製造する名村造船所 <7014> [東証S]、フェリーやRORO船、自動車運搬船など幅広い船種を手掛ける内海造船 <7018> [東証S]がある。内海造は造船事業から撤退したカナデビア <7004> [東証P]の持ち分法適用会社だ。
5日に内海造が発表した26年3月期第1四半期(4~6月)の決算は最終利益が前年同期比89%増。受注残高は同51%増の1401億円に膨らんでおり、事業環境は良好との受け止めから翌6日の同社株は急伸した。一方の名村造が7日に発表した25年4~6月期決算は最終利益が同53%減。前年同期との比較で為替が円高に振れたことが響いた。好決算の期待で先回り買いが入っていた同社株は、翌8日は下押しを余儀なくされた。造船関連銘柄といっても業績のモメンタムなどに応じ株価の反応に明暗が分かれている。造船関連企業には、舶用エンジンや機器メーカーも含まれることになる。三井E&S <7003> [東証P]は舶用エンジンやその周辺機器を展開。ディーゼル機関のジャパンエンジンコーポレーション <6016> [東証S]、ディーゼル発電機用補機のダイハツインフィニアース <6023> [東証S]が筆頭格に挙がる。7月30日に25年4~6月期決算を発表したダイハツインは良好な受注状況を示したことが好感され、翌31日の株価には強い上昇圧力が掛かった。
古野電気 <6814> [東証P]はレーダーやオートパイロットシステムなど航海機器や通信機器でグローバルでもトップブランドとなっている。船舶用配電制御システムの寺崎電気産業 <6637> [東証S]、船舶用塗料の世界的企業である中国塗料 <4617> [東証P]もメインプレーヤーだ。エンジン回りに関しては、自動車と技術面で重複する部分もあり、大同メタル工業 <7245> [東証P]は大型船舶用の軸受で世界シェアトップとなっている。もちろん、新造船の中期的な増加トレンドが事業の追い風となると期待される銘柄はこれらにとどまらない。
●化工機やナブテスコも要マーク三菱化工機 <6331> [東証P]はプラント・環境設備の建設やエンジニアリングを展開。オンサイトでの高純度水素ガス製造装置も手掛ける。船舶関連では バラスト水処理装置や船舶用燃料油の清浄に用いる分離板型遠心分離機などを供給。船舶の環境規制対応に向けた潮流は関連事業の追い風となっており、受注残高は積み上がった状況だ。今期は営業・経常ベースで連続最高益更新を計画する。
ナブテスコ <6268> [東証P]は7月31日に鉄道車両機器、精密減速機とともに舶用機器事業の需要が堅調だとして25年12月期の業績予想を引き上げた。産業用ロボットや航空機関連に注目が向かいがちな同社だが、舶用エンジン遠隔制御システムで高いシェアを持ち、中期的に船舶向けは同社の業績を下支えする要因となりそうだ。
荷物用エレベーター大手の守谷輸送機工業 <6226> [東証S]は26年3月期は連続最高益更新を計画。02年にシンドラーエレベータから船舶用エレベーター技術などを取得し、24年には韓国のサムスン重工業から船舶用エレベーター32台を受注した実績を持つ。前期の売上高のエレベーターの製造・販売売上高のうち船舶向けは9%にとどまるものの、需要拡大が期待される分野だけに、攻めの一歩が打ち出されるか注目される。
三浦工業 <6005> [東証P]は米ボイラー大手のM&Aによる海外市場の攻略とともに、舶用機器の拡大も図っている。バラスト水処理装置や造水装置など製品群は幅広く、新造船ラッシュに伴う受注の更なる増加を期待したい。
NITTAN <6493> [東証S]はエンジンバルブの製造を手掛け、自動車とともに船舶用にも展開。26年3月期第1四半期(4~6月)は増収・最終黒字転換を果たした。舶用中速エンジン向けの推定シェアは71%。軽量化が可能で冷却効果を持つ中空エンジンバルブの量産技術の発揮による業績押し上げ効果が生まれるか注目される。
このほか、中北製作所 <6496> [東証S]は自動調節弁を手掛け、船舶向けに手持ち工事量を十分に確保しているもよう。中小型船向けのエンジンメーカーである阪神内燃機工業 <6018> [東証S]は25年4~6月期の売上高の急増に対し営業利益が半減し、株価の下押しを余儀なくされたが、海外での出張据え付け作業の集中による費用増などが原因で、同社としては想定内の状況という。防衛関連株としてもマークされる東京計器 <7721> [東証P]はジャイロコンパスで世界トップシェアだ。
四国化成ホールディングス <4099> [東証P]は外航船向けのバラスト水処理装置や専用薬剤を取り扱う。ポエック <9264> [東証S]はポンプなど水処理機器やスプリンクラー式消火装置に加え、グループ会社の東洋精機産業で舶用エンジン部品の精密加工を手掛ける。高出力・高効率エンジン向けの部品需要が拡大。4月に転換社債型新株予約権付社債(CB)の発行を決議し約20億円を調達してM&Aや既存事業の成長投資に充てる方針を示している。
造船関連株には流動性の低い銘柄も数多く存在する。6月下旬に急騰劇を演じた船舶用エンジンの赤阪鐵工所 <6022> [東証S]は関連株としてマークされながらも、商いの薄い状態が続いていた。売買の活発化が期待される銘柄として、船舶用バルブの拡大期待が強いオーケーエム <6229> [東証S]や韓国での好調な造船業界の恩恵を満喫する作業工具のスーパーツール <5990> [東証S]が候補に挙がる。テクノアルファ <3089> [東証S]はパワー半導体の後工程で用いられるワイヤーボンダーなどの製造装置が主力だが、舶用クレーンや特殊甲板機器、救命艇といった舶用機器を製品群に持つ。ステンレス継ぎ手のMIEコーポレーション <3442> [名証M]は水素やアンモニアなど次世代エネルギー運搬船の配管システムの提供を通じて更なる成長を目指すほか、鉄道車両用機器を主力とする森尾電機 <6647> [東証S]は船舶向けに甲板照明灯や防爆灯を展開。ニッチツ <7021> [東証S]はハッチカバーを供給する。
株探ニュース


