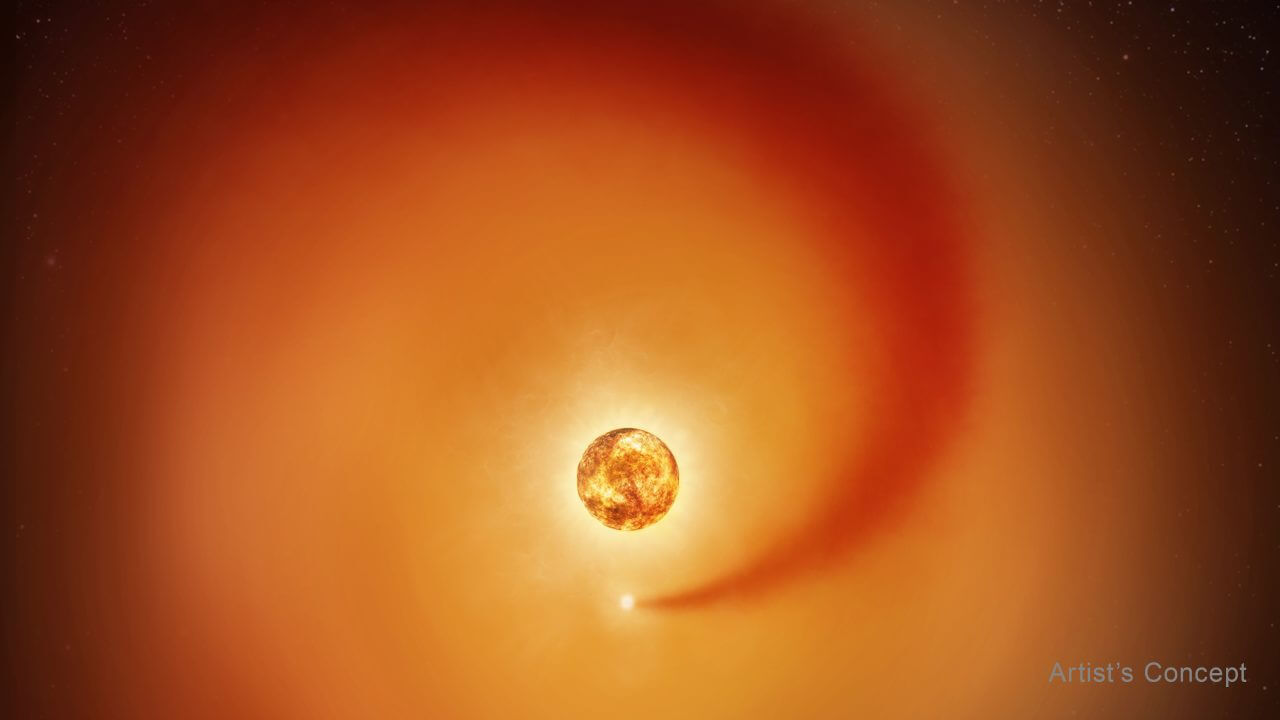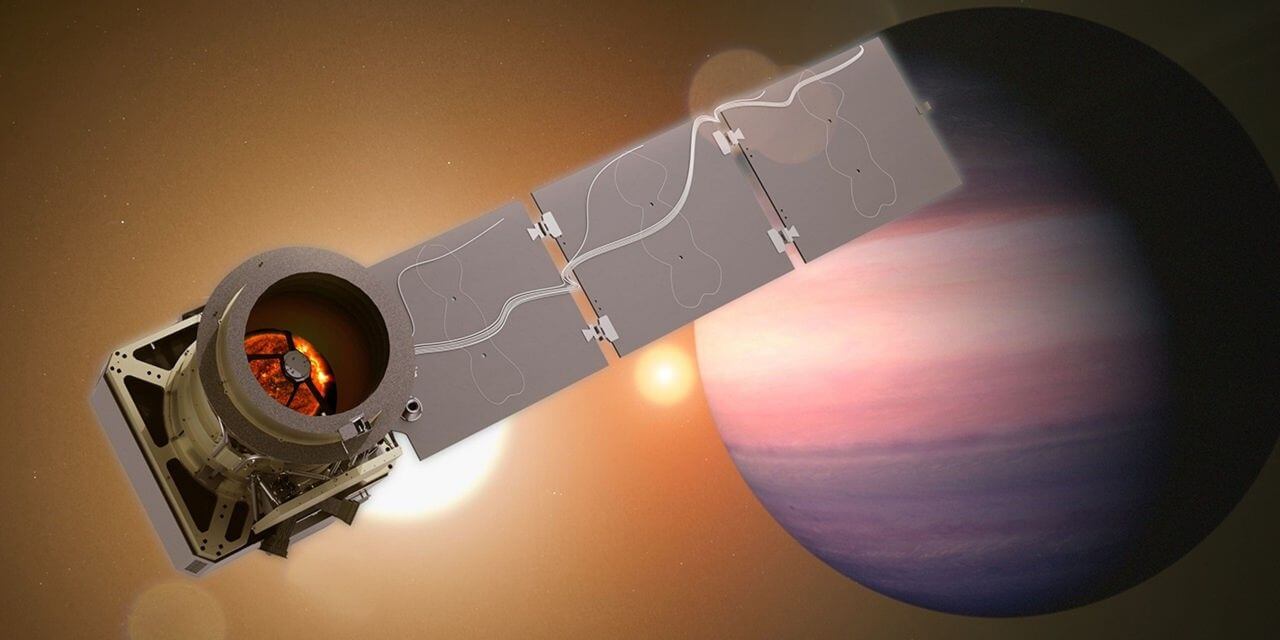奥村大河氏のバイオミネラル(生体鉱物)研究、読売新聞科学記者が取材 : 読売新聞

生物の体にはしばしば、遺伝子の情報をもとに作られるたんぱく質などの有機物だけでなく、骨や歯のように無機質を中心とした硬い組織がある。「バイオミネラル」(生体鉱物)と呼ばれる。
バイオミネラルは、形や構造が精密に制御され、短期間に成長する。一般的な岩石の「鉱物」が高温の作用や長い年月を経て生成されるのと比べると、生物のスマートな営みには驚かされる。
早稲田大学の奥村 大(たい)河(が) 准教授(38)(鉱物学)は、貝やサンゴといった海の生物によく見られる炭酸カルシウムのバイオミネラルに注目し、生成の仕組みを探っている。将来、二酸化炭素の効率的な封じ込めにつながる可能性もはらむ。
有機物に導かれて結晶が育つ
アコヤガイの殻の電子顕微鏡写真。柱状に成長した炭酸カルシウムの結晶がいくつも並び、それらの間には有機物がある。50μmは0.05ミリ・メートル=奥村准教授提供「バイオミネラルの大きな特徴は、有機物の存在です」と、奥村さんは説明する。
たとえば、真珠養殖に使われるアコヤガイの殻を電子顕微鏡で観察すると、柱状などの塊に成長した炭酸カルシウムの結晶がいくつも並び、塊と塊の間を有機物が埋めている。奥村さんは「実際には、まず有機物が鋳型となるフレームワーク(枠組み)を作り、その中を炭酸カルシウムが埋めていって、こうした形になるのではないか」とみている。
カルシウムを集めやすい性質の有機分子もある。それがフレームワークにくっつき、結晶の形成を促すことも考えられる。ほかに、「結晶が成長する方向を制御する」「結晶構造を部分的に乱して割れにくくする」といった働きも、有機物が担っている可能性がある。
成長する様子を電子顕微鏡で捉えたい
奥村さんは「有機物が結晶の成長に影響を与えている現場を、原子レベルで見てみたい」と熱意を抱く。しかし、その手法はまだ確立できていない。
様々な種類の装置を駆使して、バイオミネラルの研究に取り組む奥村さん(早稲田大学で)結晶の材料を用意して、そこに有機物を加え、結晶が成長していく様子を電子顕微鏡で観察すれば、その有機物の働きを突き止めることが期待できる。ただ、炭酸カルシウムが電子線に弱いことなど、観察を阻む技術的ハードルがある。今後、それを乗り越える手法を編み出していきたいという。
こうした実験を目指し、生物系の共同研究者に、貝殻に含まれる有機物を分析してもらっている。結晶が成長する途中の観察はなかなか難しいが、まずは有機物を加えて成長させた結晶を観察し、有機物の働きを推定しようとしている。奥村さんは「全体像を描くまでには、やらねばならないことが多い。地道な作業です」と話す。