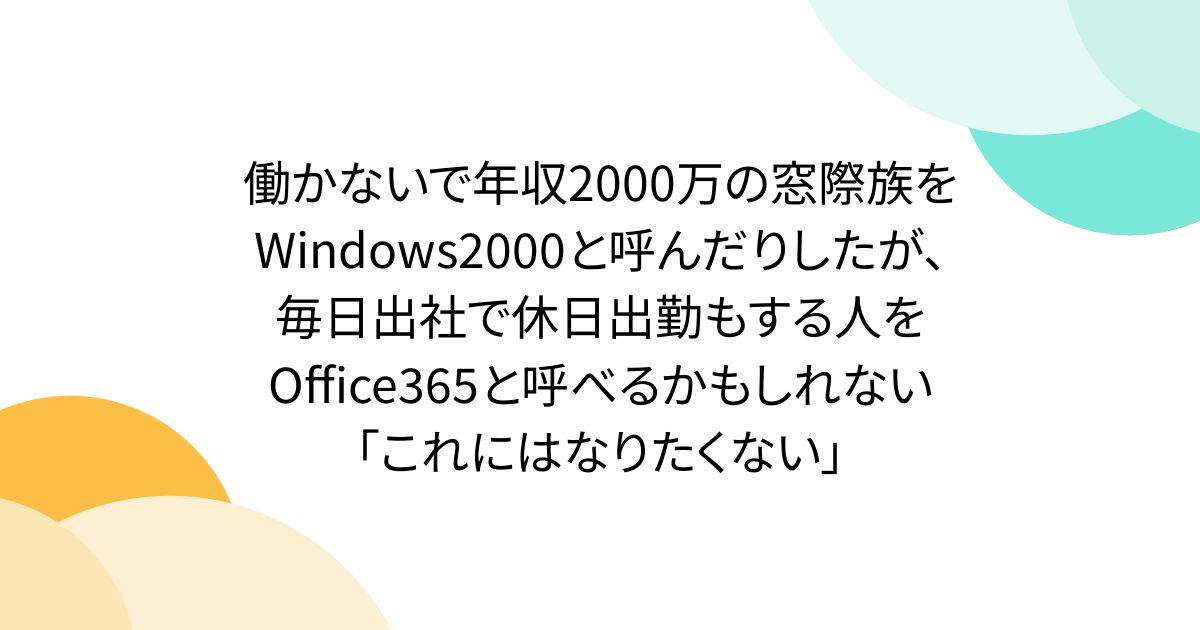「スマホ悪玉論」はホント?学力低下の原因に人口減少?テック×教育の可能性とは(ABEMA TIMES)|dメニューニュース
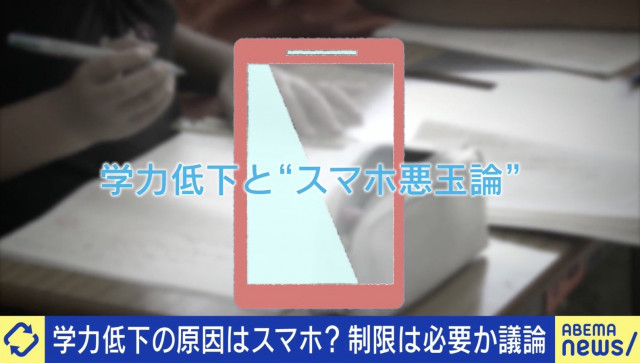
文部科学省が先日、全国学力調査の結果を公表した。小学6年生と中学3年生を対象とするものだが、前回調査と比べて、学力スコアが大幅に低下していた。分析結果について阿部俊子文科大臣は、「データのみからは断定できないが、勉強時間が短く、テレビゲーム、スマートフォンの使用時間が長いことが確認された」と話した。
【映像】勉強時間が低下…学校外での過ごし方(詳細)
さまざまな指摘の中で、注目されたのが「スマホ」の存在だ。Xでは「子どもの学力低下、高確率でスマホが原因だ」「ルールも厳しくして使用時間の制限が必要」といった声も見られる一方、「なんでもスマホのせいにするのはどうか」「うまく使えば勉強に役立つツールでもある」との反論も。『ABEMA Prime』では、識者とともに、子どもの学力低下とスマホの関係を考えた。
■「人口減少により学力が下がるしかない構造に」
学習管理アプリ「スタディプラス」取締役の宮坂直氏は、学力が下がっている原因は、スマホに限らないと話す。「共働きで親子の会話が減り、家庭でやるべき役割が、学校へスライドしている。しかし、学校も長時間労働や、勉強以外の教育が増え、パンクしてきている。高校も大学も倍率が下がり、地域によっては地元唯一の進学校に、勉強しなくても入れる。人口減少により学力が下がるしかない構造になっている」。
作家の乙武洋匡氏は、文科省調査に「『スマホ』『テレビゲーム』『勉強』の選択肢で大丈夫なのか」と問う。「『スマホ』はスマホを使って、何をしている時間かわからない。勉強かもしれないし、ゲームやSNSを見ている可能性もある。分解せずに『スマホ』とくくる問いはアホだなと感じる」。
教育ジャーナリストの松本肇氏は、「スマホは学習に悪影響を及ぼす」と考えている。「昔ならゲーム機を見て、ひと目で『遊んでいる』とわかったが、いまは子どものスマホやタブレットの使い方が達者で、勉強しているのか、遊んでいるのかわからない。勉強にも使えるからと買い与えたのに、結局はショート動画ばかりを見ているケースが散見されるのでは」と問題点を挙げる。
■逆算して将来設計する場合も?
コラムニストの小原ブラス氏は、「“学力”の測り方が前時代的に思える」と疑問を呈する。「いまの学力は結局、暗記などでの記憶や知識で、算数でも計算ミスがない人が高得点を取る。ただ、現代ではExcelを使う能力があった方がいい。昔は情報にアクセスできず、知識を頭に入れている方が役立つ時代もあったのだろうが、いまは『どれだけ早く正確に情報を引き出すか』の方が時代に合っているのではないか」。
乙武氏は「これまでゲームは『大人が作ったものを子どもが消費する』構図だったが、ChatGPTなどの出現で、小さな子どもでも簡単なゲームなら作れる時代になった。享受して消費する立場から、創作する立場への移行が、テクノロジーの進歩で成り立ちやすくなっている」と考察。
バンド「キュウソネコカミ」のヨコタシンノスケは、「音楽の才能にあふれる若い人が増え、スマホなどで集めるデータで、効率よく作っている。学力ではないが、スマホで才能を伸ばしている人もいる」との見方を示す。
宮坂氏は「いまの子たちは、スマホで情報収集することが身近なため、昔よりも社会課題に関心がある。高校生でも『ゴールドマンサックスに就職したい。そのために、いまこういう勉強をして、この大学へ行き……』と逆算して将来設計する場合がある。日頃から情報収集しているからこそ伸びる。生成AIが登場して、将来設計が求められている時代にはいいことだ」と前向きにとらえている。
■「『欲しいものがすぐ来る』スマホの相性が悪い」
リディラバ代表の安部敏樹氏は、「おやつを食べ続ける子と、後に取っておける子では、後者の学力が伸びるという実験がある」と紹介する。「つまり自制心がある。こうした認知能力を身に付けるためには、小中学校でやるべきことがあるが、それと『欲しいものがすぐ来る』スマホの相性が悪い。非認知能力が開発される観点から、中長期で見てもマイナスだろう」と指摘。
宮坂氏は「タブレットが1人1台配られているといっても、アクセスできるドメインが制限されている。民間教育サービスに入れないこともあり、塾でICTを活用しようとしても、学校のタブレットやパソコンからは使えず、スマホでやるしかない状態もある」と明かす。
一方で安部氏は「なんでもアクセスできない機器を配る方がいい」と考えている。「小学生を見ていると、高学年ぐらいで誰かがスマホを持つと、みんなが『LINEしたい』と持ちたがる。完全に禁止するのではなく、『ここまではOK』と制限した機器を、早めに渡してあげた方がいい」とした。
(『ABEMA Prime』より)