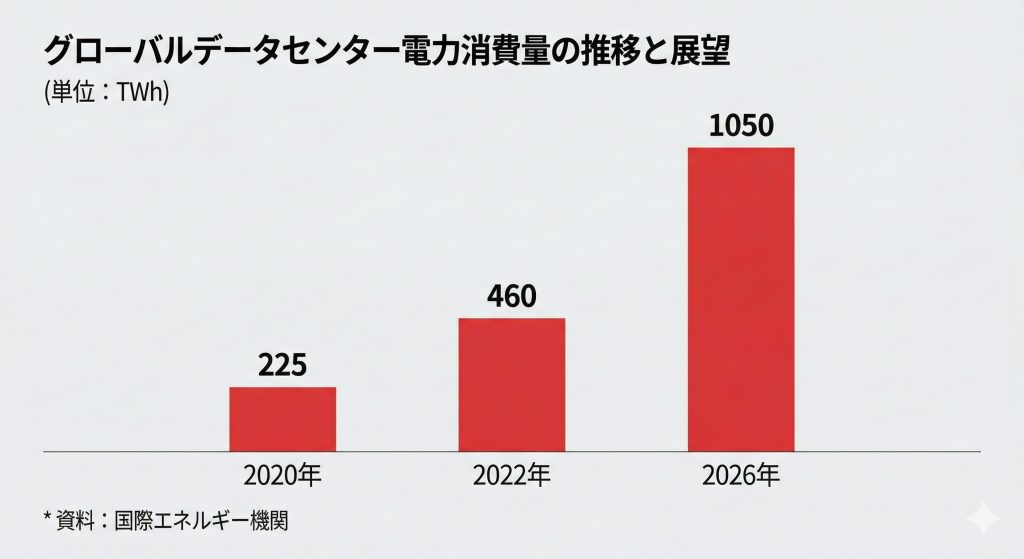アルトコインを保有する上場企業一覧|ETH・SOL・XRPなど主要銘柄別に分析
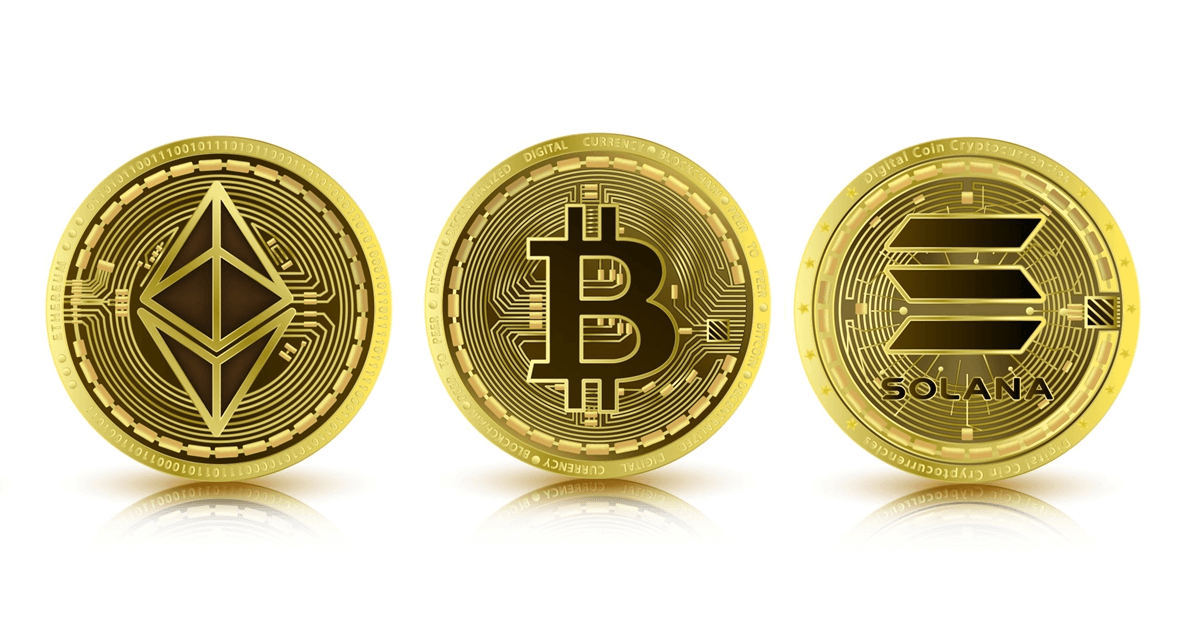
ビットコインと同様、法定通貨の価値下落に備えた分散投資や、資本効率の向上を目的としていますが、アルトコインならではの特徴や利点があります:
- スマートコントラクト市場拡大への期待: イーサリアムやソラナなどは、契約を自動実行できるスマートコントラクト機能を持ち、DeFi(分散型金融)など多様なユースケースに対応。
- ステーキング報酬: 特定のアルトコインを保有・預けることで、ネットワーク運営に参加し報酬を得られる仕組み(例:ETH 3〜4%、SOL 6〜7%)があり、企業収益源としても有力視される。
- 多様性と分散効果: アルトコインは種類が豊富で、複数銘柄を組み合わせることで、単一資産依存のリスクを軽減可能。
- ETF承認や制度整備の進展: イーサリアム現物ETFの承認や、米国でのWeb3政策強化など、制度面での後押しも拡大中。
特に注目されるのが、リスク1単位あたりのリターンを測る指標である「シャープレシオ」です。 ETHには、ステーキング報酬という安定収益が加わることで、この指標が構造的に向上しやすい特性があります。 シャープレシオは、上記のように「リターン ÷ リスク」で計算されるため、分子(リターン)を大きく、分母(リスク)を小さくすることが理想的です。
ETHの場合、リスクを増やさない収益源(ステーキング報酬・優先手数料等)を持つため、「分子だけが増える構造」となり、シャープレシオが上昇します。
- リターン(分子):価格上昇+ステーキングによる安定収益 → 増加
- リスク(分母):価格の標準偏差で決まる → ステーキングによっては変化しない
この特性は、企業の財務戦略においては、以下のような利点もあります:
- 余剰資金の運用先として:中長期で安定した収益が見込める
- 四半期決算への寄与:ステーキング報酬が収益として計上される
- 株主や投資家への説明材料:シャープレシオなどで合理性を説明可能
世界の上場企業によるアルトコイン保有事例を一覧で紹介します。仮想通貨ごとに、枚数や時期、戦略を比較できます。
■ 企業別ランキング表 上場企業の IR・SEC 書類、公式プレスリリース をもとに、 ① 主要アルトコイン と ② 保有(または調達)額が大きい企業 を優先的に掲載した 実績ベース の一覧です。 小規模案件・非上場企業は掲載していません。
■ 銘柄別サマリー表
- ETH:集計サイト StrategicETHReserve.xyz (2025-08-05 時点)の 実保有枚数/企業数 を採用。
- その他通貨(BNB・SOL・XRP・TON・HYPE・TRX・TRUMP 等):各社プレスリリースや アナリストレポートに記載された 発表済み・調達予定額 を合算。
※ 価格変動や追加取得・計画変更により数値は変わる可能性があります。 最新の開示情報を随時ご確認ください。
CM放映中!東証プライム上場 マネックスグループの安心感
入出金・出庫手数料が無料 国内大手SBIグループの総合力
豊富なアルトコインで板取引可 業界最低水準の取引手数料
ここでは、実際にアルトコインを財務資産として活用している企業の中から、代表的な動きを紹介します。
BitMine Immersion|業界最大規模のイーサリアム財務戦略
BitMine Immersion(ビットマイン)は、もともとビットコインマイニング企業でしたが、2025年6月末、戦略的にイーサリアム(ETH)保有に舵を切りました。わずか35日間で833,137 ETH(約45億ドル)を取得し、現在では企業としては世界最大のETH財務資産を保有しています。:
“BitMine moved with lightning speed in its pursuit of the ‘alchemy of 5%’ of ETH, growing our ETH holdings to over 833,000 from zero 35 days ago,” — Tom Lee(Fundstrat会長)
この動きにより、BitMineは企業として最大のETHホルダーに躍り出たのみならず、仮想通貨財務資産では企業全体で世界第3位(ストラテジー、およびマラ・ブロックチェーンに次ぐ形)となりました。
BitMine Immersionの株価は過去2カ月で約4ドル台から40ドル前後まで、10倍に高騰 出典:Yahoo Finance
さらに株式市場においても注目され、日々の平均取引高は16億ドルに達し、米国全上場企業の中で42位にランクされています。また、著名投資家ビル・ミラー3世、ARKインベスト、著名投資家ピーター・ティール系ファンドなど複数の著名投資家からの支援を獲得し、信頼性と戦略の正当性が裏付けられています。
同社は今後、ステーキングによる収益化も計画中であり、ETH保有を単なる資産保有ではなく、企業の資本運用戦略として機能させる意図が明白です。
SharpLink Gaming|イーサリアムを財務資産の中核に
SharpLink Gaming(シャープリンク)は、米ナスダック上場のテクノロジー企業で、スポーツベッティング関連のソフトウェア開発を手がけています。 2025年春から夏にかけて、ETHを財務資産の中核に据える「イーサリアム・トレジャリー戦略」を発表し、世界で最も注目されるETH保有企業の一つとなりました。
同社の戦略は、単なる価格投機ではなく、「ETHを次世代の資本管理・デジタル経済の基盤」として捉える長期的な方針に基づいています。会長にはイーサリアム共同創業者ジョセフ・ルービン氏が就任。
2025年5月〜8月にかけて、私募(約4.25億ドル)とATM調達(約4.13億ドル)を通じて約6.7億ドルを調達し、段階的にETHを買い増し。累計52万ETH以上(約3,000億円相当)を保有し、企業としてのETH保有量では世界第2位(2025年8月3日時点)。
保有ETHの99.7%以上をステーキングまたはリキッドステーキングに活用。2025年6月2日〜7月11日の間に415ETH相当の報酬を獲得し、年率5%以上の利回りを実現しています。
また、ETH保有量と発行済株式数をもとにした独自のKPI「ETH Concentration(1000株あたりETH)」も導入。この指標は6月の2.00から、7月には2.46へと上昇し、投資家にとってのETHベースの企業価値を可視化する役割を果たしています。
この指標の値が高いほど、株価がETH価格の上昇に連動しやすく、仮想通貨市場への間接投資として魅力的になる可能性があります。
この戦略は、BTCを大量に保有するMicroStrategy社になぞらえ、「イーサリアム版マイクロストラテジー」として株式市場でも注目を集めています。
SharpLinkの株価は2025年5月の約3ドルから、7月時点で30ドル前後まで、約10倍に高騰(出典:Yahoo Finance)さらに、Consensysとの提携強化や、ETHのスマートコントラクト技術をiGaming(オンラインギャンブル)分野に応用する構想など、ブロックチェーン活用による事業変革も視野に入れています。
一方で、SharpLinkもリスクについて自認しており、ETH価格の変動リスクや、US GAAP基準での損益反映、仮想通貨・ギャンブル領域の規制対応などに注意を払っています。
関連:米シャープリンク、イーサリアム保有量を52万ETHに拡大
SOL Strategies(ソル・ストラテジーズ)|ソラナを軸にしたバリデータ戦略
もう一つの例は、カナダの投資企業「SOL Strategies」(旧:Cypherpunk Holdings)です。 この企業は、かなり早い段階から仮想通貨に注目しており、2019年にはビットコインを保有しはじめ、のちにイーサリアムやモネロなどを経て、現在はソラナ(SOL)に特化した財務戦略を採用しています。
特徴的なのは、保有だけでなくバリデータとして自社でソラナネットワークに参加し、報酬を得ている点です。2025年6月末時点では、約39万SOLを保有し、その多くをステーキングに活用。報酬利回りは最大で年7%台と、高い資本効率を実現しています。
また、同社は米国SECにForm 40-Fを提出し、NASDAQへの上場準備を進めているなど、株主向けにも「ソラナへの間接的投資手段」としての存在感を高めています。
🛠 加えて、ユーザー向けのウォレット開発(Orangefin)や、エコシステムへの支援活動(JTO保有など)にも力を入れており、「単なる投資保有」以上の役割を担っています。
SOL Strategiesの株価は2025年5月の約3ドルから、7月時点で30ドル前後まで、10倍に高騰 出典:Yahoo Finance
ポイント
3社に共通するのは、「単なる保有」ではなく、以下のような観点でアルトコインを財務戦略に本格的に組み込んでいる点です。
- 収益性: ステーキングやバリデータ運用を通じた継続的な利回り
- 投資効率: シャープレシオや保有集中度といった財務指標で説明可能
- 上場企業としての戦略性: 株主説明やIR資料における明確な位置づけ
特にステーキングやノード運営による安定収益は、企業にとってアルトコインを“運用可能な資産”として扱う時代の到来を象徴しています。
アルトコイントレジャリー企業のリスクと注意点
アルトコインを保有する企業の株式は、価格上昇局面において仮想通貨以上のリターンを生む可能性があります。しかし一方で、その戦略には特有のリスクも存在します。特にETHやSOLといったアルトコインは、BTCと比べて市場成熟度や流動性が低く、価格変動・制度リスク・バリデータ依存など、複合的なリスクを伴います。
アルトコイントレジャリーに内在する主なリスク
- 価格変動性の高さ: ETHやSOLはBTCよりボラティリティが大きく、下落時の影響も深刻になりやすい
- 分散型運用の信頼性: ステーキング報酬はバリデータ依存のため、ネットワーク障害やスラッシングのリスクもある
- 規制リスク: ETHの証券性判断やSOLの規制強化など、政策リスクの影響を受けやすい
- ステーキング報酬の変動: ネットワーク状況や手数料構造によって、収益が想定より低下する可能性
- 評価損益の業績影響: 新会計基準(例:ASU 2023-08)により、仮想通貨の評価損益が業績に即時反映される企業も
- 戦略集中リスク: 特定の通貨(例:ETH)に資産を集中させた企業では、価格下落時の業績インパクトや投資家からの批判が大きくなる可能性
- 産業・規制ダブルリスク: SharpLinkのように、仮想通貨とiGamingといった規制リスクの高い産業を組み合わせた事業では、二重の不確実性が存在する
たとえばSharpLink社は、イーサリアムを財務・収益・事業改革のすべてに活用する積極的な戦略を採っていますが、一方で以下のようなリスクを自ら明示しています:
- ETH価格の下落が、米国会計基準(US GAAP)における未実現損として業績に即時反映される
- 仮想通貨・オンラインギャンブル双方の規制強化リスク(特に米国における動向)
- 資産集中によるボラティリティ上昇や、事業転換期における利益確保の不確実性
アルトコイントレジャリー企業は、将来性や収益性の高さが注目される一方で、事業構造と財務戦略が密接に結びつくため、価格や規制の影響を受けやすいという側面を持ちます。 投資家としては、短期的な成長性だけでなく、これらのリスクにも目を向けたうえで、冷静に判断する必要があります。
ブテリン氏が指摘する「過度なレバレッジ」の危険性
イーサリアム共同創設者のヴィタリック・ブテリン氏は、ETH国庫企業の成長を支持する一方で、「過度にレバレッジされたゲーム」になることへの強い警戒感を示しています。
ブテリン氏が最も懸念するのは、以下のような連鎖的な価格下落シナリオです: ETH価格の下落 → 強制清算の発生 → さらなる価格下落 → 市場の信頼性失墜
「3年後に目が覚めて、国庫企業がETHの破綻につながったと言われたら、その理由は間違いなく過度なレバレッジによるものだろう」と同氏は警告しています。
ただし、ブテリン氏は現在の投資家層への信頼も表明しており、「我々が話しているのは、(2022年に崩壊したTerraブロックチェーンの創設者)Do Kwonの妄信者ではない」として、今回のETH国庫企業に関わる投資家は、過去の投機的な失敗とは異なる、より理性的な判断ができる層であるとの期待を示しています。
仮想通貨が不安な人へ──まずは“関連株”から始める選択肢
本記事では、イーサリアムやソラナといったアルトコインを戦略的に保有する企業について、その背景や株式投資としての魅力、リスクまでを幅広く解説してきました。 マイクロストラテジーやメタプラネット、BitMineなどのように、仮想通貨を財務の中核に据える企業は年々増加しており、株式市場でも新たな評価軸として定着しつつあります。
特に日本では、ビットコインやイーサリアムの現物ETFがまだ承認されていない状況下において、関連企業の株式に投資することが「間接的な仮想通貨エクスポージャー」を得る手段として注目されています。 さらに、株式投資であれば税制面や取引環境においても一定の優位性があり、仮想通貨に不慣れな方でも比較的安心して始めやすいという利点があります。
「仮想通貨には興味があるけれど、直接の投資には少し抵抗がある」 「株式投資の延長(証券会社の口座資金)で、Web3分野にも触れてみたい」
そのような方には、仮想通貨を保有する企業への投資から始めることをお勧めします。段階的なアプローチとして、
基礎段階:日本や米国の時価総額が大きなビットコイン・トレジャリー企業の銘柄分析から開始
発展段階:アルトコインを保有する企業の調査・分析へとステップアップ
このように段階的に進めることで、仮想通貨投資に対する理解が深まり、より適切な投資判断ができるようになるでしょう。
ただし、仮想通貨関連株への投資は投機的な性質から価格変動(ボラティリティ)が非常に大きいため、
①余剰資金での運用に留めたり、分散投資を心がける
②「損切りライン」などリスク許容度をあらかじめ検討する
③相場の過熱感に注意し、短めの時間軸の売買を意識する
ことが推奨されます。
今後、企業による仮想通貨の保有動向や財務戦略は、株式投資における重要な判断材料としてますます注目されることでしょう。
投資で成功するためには、AI(人工知能)やWeb3・仮想通貨業界などの最新トレンドを継続的にキャッチアップし、他の投資家に先駆けて有用な情報を入手・分析することが重要です。そして何より、ご自身のリスク許容度や投資目標に適したアプローチを構築することが欠かせません。
📌 関連株を購入するなら、信頼できる証券口座から
SBI証券は、国内外の株式やETFを幅広く取り扱っており、仮想通貨を保有する企業の株式にも投資が可能です。 情報量の豊富さや取引コストの低さから、初めての証券口座としても高い人気を誇ります。
- ネット証券 総合満足度 第1位(オリコン調査)
- 米国株式の取扱銘柄数:5,400種類以上
- 投資信託も2,700本以上を網羅
- NISA・iDeCoにも対応
- 手数料は業界最安水準
記事の監修
Page 2
- 注目トレンド:
- 1.リップル
- 2.ビットコイン準備金
- 3.アルトコインETF
- 4.BTC保有企業
- 5.米国関連銘柄
Page 3
- 注目トレンド:
- 1.リップル
- 2.ビットコイン準備金
- 3.アルトコインETF
- 4.BTC保有企業
- 5.米国関連銘柄
Page 4
Page 5
レイヤー1ブロックチェーン「Neo(ネオ)」は、2014年に中国で立ち上がり10年以上にわたり開発が続く長い歴史を持つプロジェクトだ。イーサリアムと似た機能を備えることから “中国版イーサリアム” とも呼ばれ、アプリ開発に必要な機能を標準搭載した使いやすい設計が特徴である。
ブロックチェーン開発にありがちなツールの分断や複雑さ、開発環境の制限といった課題に向き合い、「人が自由に経済活動を行える世界」=スマートエコノミーの実現を掲げてきた。 その基盤として、オールインワンで開発可能なNeo N3や、イーサリアム互換を持つNeo Xを整備している。
さらに近年は、AIの進化を背景に「AIが経済活動を担う時代」=センチエントエコノミーを構想し、2025年には中核となる新OS「SpoonOS」を発表した。 加えて、国内仮想通貨取引所の「OKCoin Japan」への上場、日本最大規模のWeb3カンファレンス「webX」への継続出展、日本発Web3投資ファンド「gumi Cryptos」との提携など、日本市場を戦略拠点として位置づけている。
本記事では、Neoの基本構造から最新の技術トレンド、さらには日本市場における取り組みまで、現在のNeoの全体像を解説する。
Neo誕生の背景(これまでの課題点)
ブロックチェーンが登場した当初、多くのプロジェクトは「金融取引の代替」や「通貨発行」に焦点を当てていたが、やがてスマートコントラクト技術の進化によって『アプリケーションの構築』へと活用の幅が広がっていった。
こうした潮流のなかで、より簡単にブロックチェーン上でアプリやサービスを開発できるようにすることを目的として、2014年に中国で誕生したのがNeoだ(当時はAntsharesとして始動)。
技術的な自由度と開発者の使いやすさを両立しながら、スマートコントラクト・デジタルID・資産管理といったブロックチェーンに不可欠な機能を標準で備えるプラットフォームを目指し、Neoは構想・開発を重ねてきた。
Neoとは?
Neoは、ブロックチェーン上でアプリやサービスを作る人たちにとって、使いやすく、整った開発環境を提供することを目的に設計されたレイヤー1のブロックチェーンである。
Neoが掲げるのは「より簡単にブロックチェーン開発ができる世界」であり、その実現のために2つの基盤―「Neo N3」と「Neo X」を開発してきた。
オールインワンで完結する「NEO N3」
ブロックチェーン上でアプリを作るには、スマートコントラクトやストレージ、オラクル、ID管理など多くの機能を組み合わせ、従来の開発環境では、これらを外部ツールから寄せ集めて構築する必要があり、手間もリスクも大きかった。
NEO N3は、そうした課題を解消するために生まれた。アプリ開発に必要な機能をすべてあらかじめ内蔵したオールインワン型のプラットフォームであり、開発がNeo内で完結するのが最大の特徴だ。
また、複数のプログラミング言語に対応し、Web3未経験の開発者にも開かれた、柔軟で親しみやすい開発環境を整え、さらにNeoは、「dBFT」という独自のしくみを使って、ネットワークの安全性とスピードのバランスを取っている。これにより、1秒間に最大1万件の取引を処理できる高性能なブロックチェーンとして、実用性の高い環境を実現している。
開発の幅を広げるサイドチェーン:Neo X
Neo N3は、高速かつ安全なアプリ開発環境を提供する一方で、独自の言語であるNeoVM上で動作するため、Web3で主流のEVM(Ethereum Virtual Machine)と互換性がないという課題があった。
EVMとは
Ethereum Virtual Machine。イーサリアムのスマートコントラクト実行環境。EVMとの互換性を得ることで、ユーザーや資産、dAppsの相互乗り入れが容易になるため、良くも悪くも戦略で重視される。
EVM向けの言語Solidityや既存ツールが使えないことから、開発者の参入や資産の流入にハードルがあり、拡張性の面で限界があった。
そこでNeoは、EVM開発者も柔軟に参加できる土台として、2024年にEVM完全互換の新サイドチェーン「Neo X」を公開した。
Neo Xの登場により、Neo N3が持つオールインワン型の開発環境や高速な処理能力といった強みを活かしながら、SolidityなどEVMベースのツールや資産にも対応できるようになった。これにより、より多くの開発者がNeoエコシステムに参加しやすくなり、既存のEthereum系プロジェクトの展開もスムーズに行えるようになった。
さらに、 取引の先回りや不公平な並び替えを防ぐ設計「MEV耐性」を導入しているため、開発者とユーザー双方にとって公正な取引環境を提供することができる。
Neoの歴史と運営体制
Neoは、2014年に Da Hongfei(ダ・ホンフェイ) と Erik Zhang(エリック・チャン) によって「Antshares」として設立されたブロックチェーンプロジェクトである。当初、中国・上海を拠点に10人足らずのメンバーで始動したが、現在では50人以上の組織へと成長し、Microsoft、Facebook、Amazon、Samsungなどの大手企業出身者も含むグローバルな開発者コミュニティを形成している。
開発実績
2014年 プロジェクト発足(Antsharesとして始動) 2016年 MainNetローンチ 2017年 Neoへリブランディング 2021年 Neo N3ローンチ(最大規模のアップグレード) 2024年 Neo X(EVM互換サイドチェーン)公開 2025年 SpoonOS構想発表(AI × Web3エージェント基盤)経営陣
共同創設者兼Neo Foundation会長: Da Hongfei氏2014年にNeoの前身であるAntsharesをErik Zhang氏と共に設立した共同創設者であり、現在はNeo Foundationの会長およびNeo Global Development(NGD)のCEOとして、エコシステム全体の戦略立案と実行を統括している。
共同創設者兼チーフアーキテクト: Erik Zhang氏Da Hongfei氏と共に設立した共同創設者で、Neoのチーフアーキテクトとして、独自のコンセンサスメカニズムであるdBFTを設計し、プロトコルの設計および開発を担当している。
資金調達
Neoは2016年にICO(トークン販売)を通じて約500万ドルを調達し、開発およびエコシステムの構築を進めてきた。
持続可能なトークンモデル
Neoが外部資金に依存せずにプロジェクトを継続できた背景には、独自の「デュアルトークンモデル(NEOとGAS)」の存在がある。
この2つのトークンが、Neoのネットワーク運営と経済的持続性を支える基盤となっている。
デュアルトークンモデル
NEOでは、「NEO」と「GAS」という2種類のトークンが存在する。これは、ネットワークの運営(NEO)と利用(GAS)を分離することで、シンプルかつ持続的な設計を実現するためのものだ。
NEO:ネットワークの根幹を支えるガバナンストークン
NEOはジェネシス段階で総供給量1億枚を発行し、このうち5,000万枚をICOで販売、残る5,000万枚はNeo Foundationがロックアップした、主に開発費やエコシステム拡充の資金源として活用されている。
NEOは、ノード選出やネットワークの意思決定など、ガバナンスに関わる機能を担う基軸トークンだ。分割ができない設計となっており、1単位ごとにGASを生成する仕組みが組み込まれている。保有者は、トークンを保有しているだけでGASを得ることができるため、ネットワーク参加のインセンティブとしても機能している。
NEOトークン基本情報 総発行量 1億枚 時価総額 約550億円 市場ランク 130位 流通チェーン Neo N3 主な取引市場 Binance, Upbit, OKX *2025年7月8日時点 時価はコインマーケットキャップ参照GAS:ネットワークの利用を支えるユーティリティトークン
GASは、スマートコントラクトの実行やトランザクション処理といったネットワーク利用に必要な手数料として用いられる。GASは、ブロック生成ごとに発行され分配される仕組みとなっており、10%がNEO保有者に、80%が投票参加者に、残りの10%がネットワーク運営を担うNeo Councilメンバーに配分される。単なる保有だけでなく、ガバナンスやノード運営への参加に応じて報酬が得られる、インセンティブ設計が特徴となっている。
GASトークン基本情報 総発行量 6,500万枚 時価総額 約270億円 市場ランク 186位 流通チェーン NEO N3 主な取引市場 Binance, Upbit, OKX *2025年7月8日時点 時価はコインマーケットキャップ参照持続可能な運営のための経済モデル
Neo Foundationなどの主要な保有者は、NEOの保有→GASの生成→市場での売却→資金化という流れにより、継続的な運営資金を確保してきた。このモデルによって、VC資金や頻繁な外部調達に頼らず、ネットワークの経済活動そのものが運営基盤となる仕組みが構築されている。
日本市場への展開
NEOは2019年以降、gumi Cryptosとの提携、国内取引所上場、WebX参加を通じて日本市場での展開を強化。NEOは日本を戦略的重要市場と捉え、Web3エコシステムの拡大を目指している。
gumi Cryptosとの提携
2019年8月、NEOはgumi Cryptos Inc.と戦略的パートナーシップを締結した。gumi Cryptosは日本市場でのマーケティングとコミュニティ形成を支援し、NEOのブロックチェーン技術を活用したゲームなどのWeb3アプリケーションの展開を促進。両社は日本の開発者がNEOエコシステムに参加しやすい環境を構築し、ワークショップやイベントを通じて技術普及を目指している。
WebXへの展開
Neoは2023年のWebX初開催から、3年連続でスポンサーとして参加。2023年はシルバースポンサー、2024年はプラチナ、そして2025年はゴールドスポンサーとして名を連ねている。
この継続的な支援は、日本の開発者・企業・コミュニティとの関係構築を重視し、長期的な協力体制を築く意向を示すものとなっている。