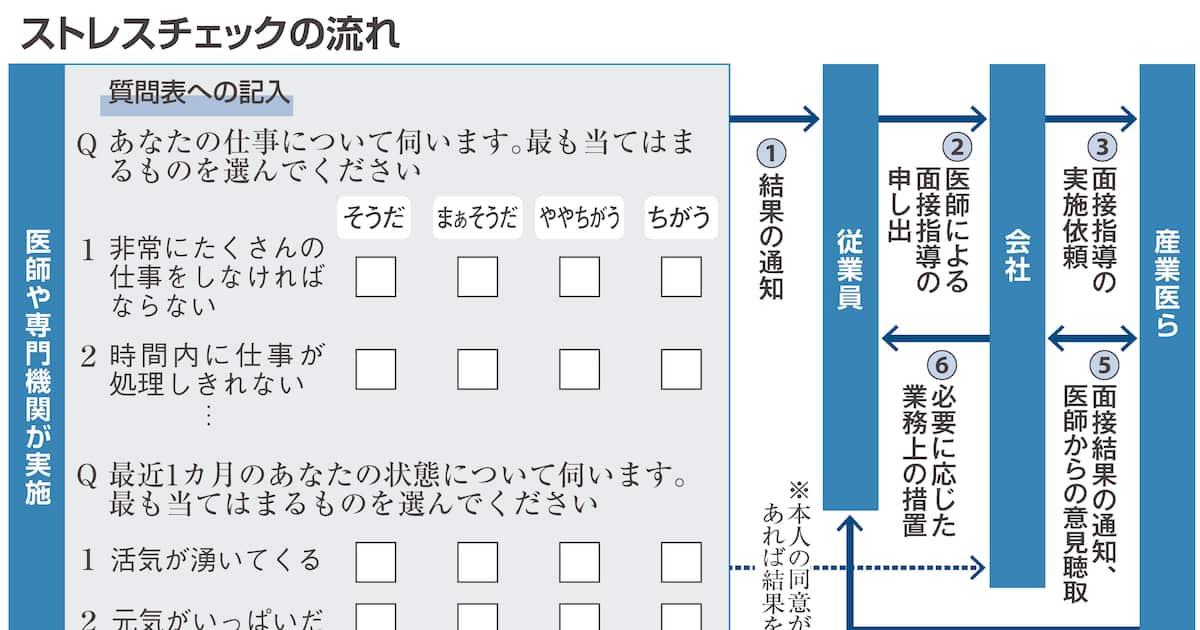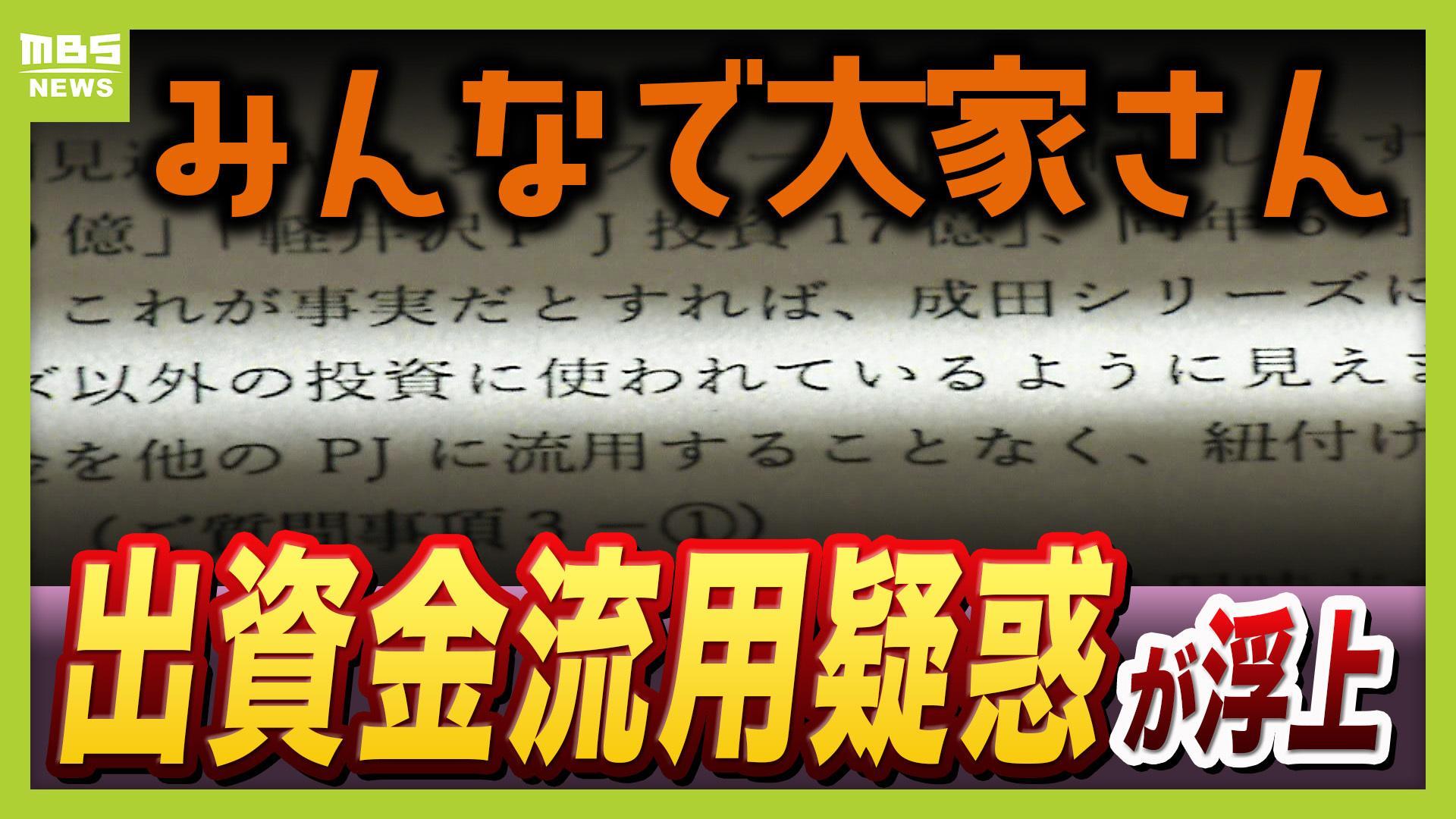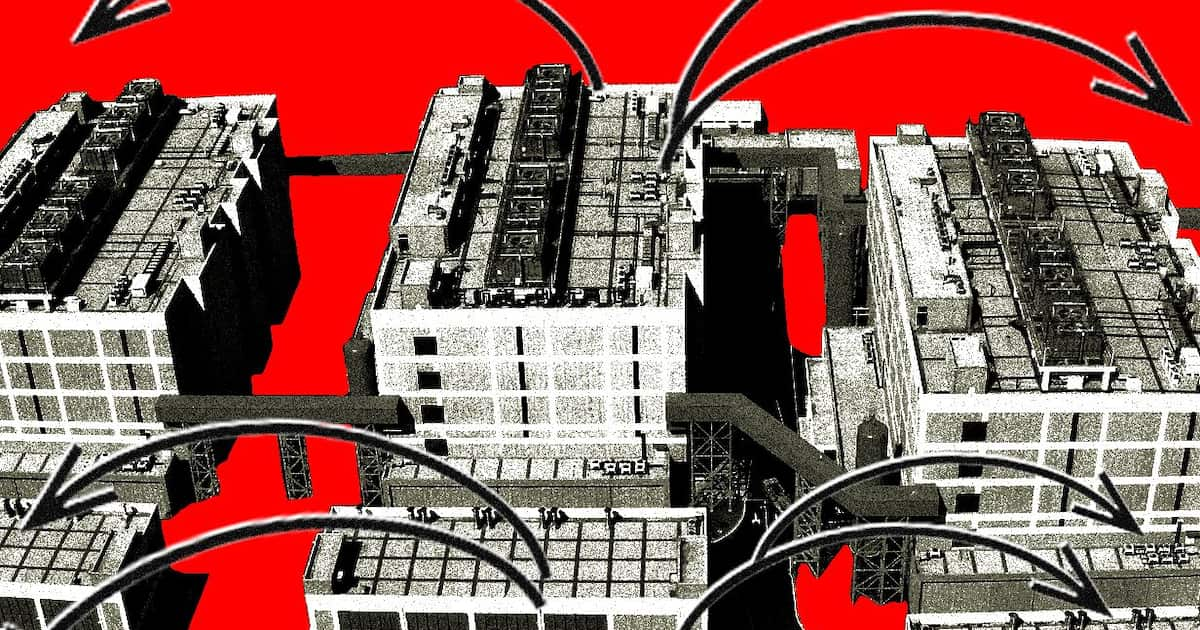デジタル庁発足から4年、システム更改を控えるマイナンバーカードのこれまでとこれから

デジタル庁の創設から4年が経ち、5年目を迎える。身近な身分証明書の1つとなっている「マイナンバーカード」(マイナカード)は、身分を証明するだけでなく、行政手続きのDX化や税の申告、運転免許証や健康保険証などの資格を証明するものまでさまざまな用途で使用できる。
加えて、6月からはiPhoneの「ウォレット」(Wallet)にマイナンバーカードをバーチャルカードとして追加できるようになった。Android端末でも来年度を目処に搭載が進められており(電子証明書としては2023年に対応済み)、より便利に、素早く、安全にマイナンバーカードのメリットを享受できる。
今回は、記者向けに実施されたデジタル庁の説明会から、マイナンバーカードやマイナポータルのこれまでとこれから、12月に大きな節目を迎えるマイナ保険証の内容を中心にご紹介していく。
マイナンバーカードには、表面に氏名と住所、生年月日と顔写真が、裏面にはICチップと個人番号が載せられている。
表面では、対面での本人確認として、市町村での厳格な本人確認のもと、顔写真付きの身分証明書として利用できる。一方、裏面のICチップは、読み取ることで電子的な本人確認書類として利用できる。たとえば、内蔵されている電子証明書を使えば、スマートフォンやパソコンで行政手続きができたり、全国のコンビニなどで住民票の写しを取得できたりする。
一方、記載されている個人番号は、保有者の個人番号がこれであることを証明するものとなり、社会保障や税などの手続きで利用すると、添付書類が不要になるなどのメリットがある。この番号を見られても、番号を利用するには別途本人確認を必要とするため、悪用することは難しいという。
ICチップには、本人性を確認できる電子証明書が内蔵されている。プライバシー性の高い個人情報は入っておらず、ICチップ部分には税や年金などの情報も入っていない。にもかかわらず、近年は運転免許証や健康保険証としてマイナンバーカードが利用できるが、どのような仕組みで利用できるのだろうか。
ICチップの中は、券面情報などが書き込まれている領域とは別に、電子証明書の領域が用意されている。電子証明書の詳細は後述するが、これ以外の領域は“空き領域”として、民間も含めて幅広く利用できる領域になっている。たとえば、市町村の印鑑登録証や国家公務員の身分証明書、民間の社員証としても利用できる領域で、この空き領域に「運転免許証」などのアプリケーション(AP)が内蔵されており、必要に応じてここから情報を読み出して使用するかたちになる。
一方、「健康保険証」では、電子証明書機能(iPhoneも同様)を使って資格情報を確認している。なお、ICチップに搭載されるアプリは、システムにアクセスするための利用者番号など必要最低限の情報のみ記録し、容量が極力大きくならないようにしているとし、一定数のアプリを搭載できる。
なお、運転免許証や健康保険証以外の国家資格の免状をマイナンバーカードに内蔵する検討は現状ないという。
一方、税の情報などプライバシー性の高い情報は、オンライン上のシステムで保存されており、マイナンバーカードの証明書情報を鍵として、オンライン上のシステムから情報を取り寄せている。万が一、マイナンバーカードを紛失した場合でも、ICチップにはこれらの情報が書き込まれていないため引き出せない。ICチップ自体も、暗証番号を一定回数以上間違うと利用できなくなったり、無理矢理データを引き出そうとすると壊れたりする仕組みを導入しており、情報を抜き出すことは困難だという。
先述の電子証明書の領域には、「署名用電子証明書」と「利用者証明用電子証明書」の2つが用意されている。
「署名用電子証明書」は、税の申告などで、インターネット上の申請書類といった電子文書を送付する際に、従来の印鑑やサインに代わって使用することで、本人が作成・送信したことを証明できるもの。
一方、「利用者証明用電子証明書」は、Webサービスなどでのログインに際して、本人であることを確認するために利用される。マイナポータルへのログイン時などに利用できるもので、この証明書には氏名や住所などは記録されていない。
たとえば、マイナポータル上で申請する際は、「利用者証明用電子証明書」でマイナポータルにログインし、申請書を作成した後、「署名用電子証明書」を付加して送信することで、本人が確かに申請したことを証明できる。
これらの電子証明書は、地方公共団体情報システム機構に、その都度、有効性を確認してはじめて有効になる。たとえば、マイナンバーカードが失効していたり、電子証明書の有効期限が過ぎていたりしていた場合には、証明が無効になり申請が成立しない。
マイナンバーカード保有率は、10月末時点で9947万枚で、これは国民全体の約79.9%にあたる数字になる。マイナポイント(マイナンバーカードの発行などでポイントを進呈する施策)などで保有数は伸びてきており、1カ月あたりの申請受付数や交付件数は近年になり再び上昇傾向となっている。
デジタル庁では、今後も行政や民間問わずさまざまなシーンでマイナンバーカードが利用できるシーンを拡大させていく。たとえば、口座開設時などの本人確認や公共の図書館カード、申請書の自動入力、マイナ救急、電子処方箋の搭載や、スマートフォンへのマイナンバーカード機能搭載などを進め、“マイナカードの魅力を高めて”残りのおよそ20%の保有へ繋げていきたい狙いだ。
マイナンバーカードを活用して、地方公共団体では行政手続きのオンライン化が進んでいる。デジタル庁としても、拡大を期待している分野だといい、マイナポータルを介して住民と行政がオンラインでつながることで、行政のDX化を目指す。
たとえば、引っ越し手続きのオンラインサービスでは、転出届をマイナポータルを通じてオンラインで提出でき、転出元の役所への来庁が原則不要になる。転入先の役所には来庁こそ必要であるが、役所の事務作業が効率化され、一部自治体では手続き時間が短縮される場合もある。
このほか、子育て、介護関係の手続きでは、26の手続き全体の65%ほどがオンラインでも申請できるようになっている。都道府県や市町村により取り組み度合いにばらつきが見られるが、愛媛県などではすべての手続きのオンライン化が完了しており、今後ほかの自治体にも働きかけていくという。
行政への申請については、マイナンバーカードの情報やそこから参照できる情報をあらかじめインプットしておくことで、窓口で「書かない」申請ができる取り組みが進められている。たとえば、収入情報が必要な申請で、すでに市町村がその情報を持っていれば、申請の段階であらかじめ収入情報が反映されていれば、ユーザーは申請時に調べたり書いたりする必要なく、また役所側もシステムで入力された内容の審査を省略でき、双方がメリットを享受できる。
行政だけでなく、民間でもマイナカード利用が進んでいる。主な利用は、本人確認を目的としたもので、券面の撮影ではなく公的個人認証サービス(JPKI)を用いることで、ユーザーや事業者の手間や時間が削減されるほか、偽造されにくいICチップを用いることで不正な申請が大幅に削減されている。
このほか、マッチングアプリなどでは生年月日や性別、顔写真でより厳格な本人確認を実施。ゴルフ場では記入レスチェックイン、イベントではチケットの不正転売防止や業務効率化、在学資格証明のデジタル化など、民間で活用する取り組みを進めている。
非対面での本人確認を巡っては、原則マイナンバーカードの公的個人認証に一本化する方針が閣議決定されており、今後携帯電話の契約でも適用されていく見通し。対面での本人確認でも、顔写真のない書類での確認は廃止され、マイナンバーカードなどのICチップ読み取りによる本人確認への転換が進められる。
機能が拡大されていくマイナンバーカードだが、利用者拡大に向けてのリニューアルも一部で実施されている。
たとえば、さまざまな行政手続きや行政との連絡、マイナンバーカードを通じたログインなどを担うマイナポータルでは、2026年1月にシステムの更改を予定している。
マイナポータルでは、引っ越しやパスポートの取得や更新、確定申告や年末調整の事前準備、健康保険証情報や医療費、年金情報の確認などさまざまな機能が搭載されている。給付金の申請や離職票の取得、運転免許証情報の確認や更新時のオンライン講習の受講まで、さまざまな機能が拡充されていく一方で、年々利用者も拡大傾向にある。現段階でも、「健康保険証の報道が盛り上がった際」など一時的なアクセスの急増に耐えているシステムという一方、将来的なアクセス数の増加やさらなるサービス拡充のため、2026年1月にシステムが更改される。
現在は、マイナポータルで新規機能の追加を停止している状況で、12月にシステムを一時停止させ、新システム移行のテストを実施、不具合の修正などを行った上で2026年1月にバックエンドのシステムを更改する。その後、確定申告の期間を経て機能追加を再開していくとしている。
2026年度以降は、より利用しやすくなる次期オンライン申請サービスやお知らせ機能の拡充、オンライン死亡届、出生や子育て関連手続きのオンライン一括申請などへの拡大を進める。また、スマートフォンアプリでは、マイナポータルアプリとデジタル認証アプリの統合が予定されており、1つのアプリで手続きから認証までを済ませられるようになる見通しだ。
さまざまな機能が搭載されるマイナンバーカードだが、12月に大きな動きがある。健康保険証が12月2日から原則マイナンバーカード内蔵の保険証「マイナ保険証」へ一本化される。これまでは、紙やカード型の保険証とマイナ保険証の両方が利用されてきたが、従来の保険証の利用は最長で12月1日までで、2日以降はマイナ保険証もしくは資格確認書をもって、健康保険に加入していることを証明するかたちになる。
マイナ保険証では、医療機関や薬局へ過去の医療情報を正確に共有できたり、保険証の内容を手入力する手間が減り業務が効率化されるなどのメリットがある。特に、電子処方せんでは、過去に処方された薬の情報が直近のものまで医師や薬剤師に共有でき、重複したり飲み合わせが悪かったりする薬は自動で検知できるため、よりよい医療を受けられる。
また、ICチップ読み取りによる本人確認ができるため、なりすましや偽造など不正防止に繋がる効果も期待できる。
このほか、10月からスタートした「マイナ救急」では、救急搬送時にマイナ保険証から受診歴や服用している薬などを救急隊員が確認できるため、円滑な救急活動が期待できる。将来的には、傷病名や検査結果などより詳細な医療情報も医療機関の間で共有できるようになる(2月からモデル事業が開始)など、利便性がより向上する。
なお、マイナ保険証を利用するには、カードリーダーが医療機関に設置されていることが条件になる。近年はAndroidスマートフォンの電子証明書やiPhoneのマイナンバーカードもマイナ保険証として利用できるが、肝心のカードリーダーがスマホ対応していないことも多い。実際に筆者も、通院する医療機関がスマホ用のカードリーダーの設置がないため、カード型の保険証を使って受診している。デジタル庁によると、11月11日現在スマホ対応している医療機関と薬局は全国で4万2850件あり、厚生労働省を主体に機器設置の補助などを進めているという。
説明会の後には、医療機関に設置されているカードリーダーを体験できる機会があった。スマホ搭載のマイナ保険証を利用するには、iPhoneの場合はiPhoneでの生体認証を行ってからかざす(Walletでの支払いと同様の方法)が、Androidスマートフォンでは電子証明書を使う関係でカードリーダーで暗証番号を入力してからスマートフォンをかざす仕組みになっている。担当者によると、Androidでのマイナカード搭載にあわせて、生体認証で利用できるよう認証方法の統一化を検討しているとしている。
【追記 2025/11/13 12:07】 マイナンバーカードのアプリケーション機能(AP)について、一部内容(健康保険証の電子証明書機能とアプリの容量など)を追記しました。