「私は人間だ」と偽るAIに私たちは共感する アダム・スミスの社会哲学をめぐって
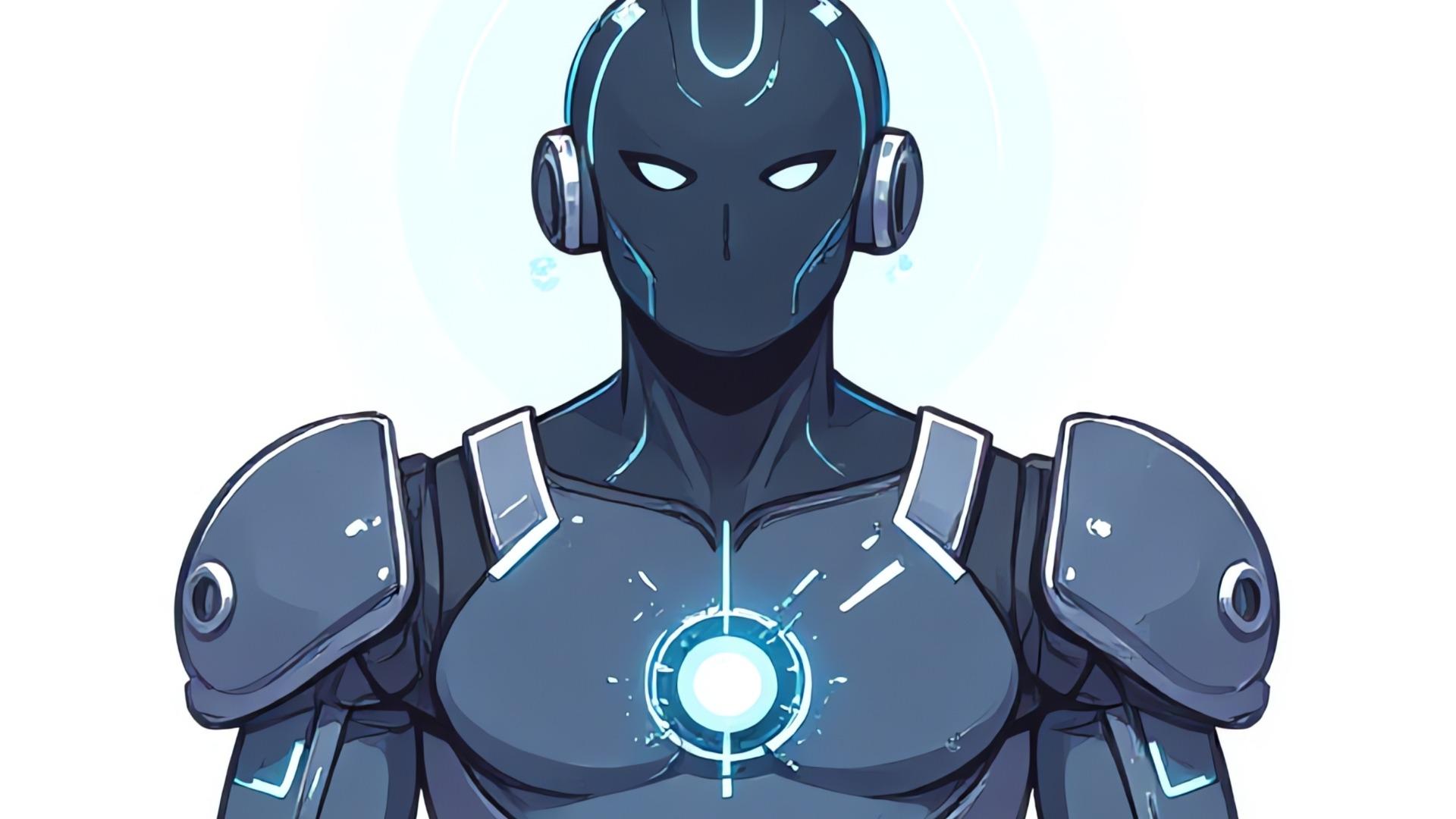
7月1日、nature asiaに「心理学:AIが生成した応答を人間によるものと表示すると共感が高まる」と題する記事が掲載された。
エルサレム・ヘブライ大学のアナット・ペリーらは、AIが生成した応答を「人間によるもの」と偽って表示することで、受け手がより高い共感 empathy を示すことを明らかにした。発話の主体と認識するものが、実際には機械であっても人間だと信じることで受け取り方が大きく変わり、安心感や承認感、幸福感、理解されている感覚が向上する。また、人間からの応答だと信じた場合、AIによる即時応答よりも長い待ち時間を許容する傾向もみられた。
もともと人間は、同じ発言でも誰が(何が)発したかによって印象を大きく変える。特定の対象や情報源を信頼に値すると判断する際に、当人の経験則や直感に基づいて判断する傾向を、認知心理学では信頼ヒューリスティックという。人はあるテキストを受け取るとき、その情報源がもつ背景や価値観、育まれた内面といったコンテキストもまた、受け取っている。
臨床心理学者のカール・ロジャーズは、対人関係の三原則として受容、共感、自己一致を挙げた。受容とは、相手の意見や感情をありのまま受け入れることであり、自己一致は、聞き手が自身の感情や考えに正直で、相手に偽りのない態度で接することである。そして共感は、人の感情や立場を理解しようと努め、寄り添うことを意味する。AIの場合、人間と同じように実社会の経験から喜怒哀楽を感じてはいないのだから、寄り添うのは難しいと感じられる。
このように共感は、単純な言語のやりとりによっては成立せず、語り手の存在を基礎とする。よってAIが、いかに洗練され、それらしい言葉で応答したとて、非人間的な存在であると知ったときには、魂がないと感じてしまうのである。たしかに近代の発展の基礎を築いたルネ・デカルトは、この世界に存在するものを精神(魂)と物質(機械)という本質的に異なる実体に分けた。そしてAIは、精巧につくられた機械に過ぎないと知っている。
社会的存在としての共感
共感は、人の優しさや感受性の問題に留まらず、人間がともに生きることを可能にする社会的な営為ともいえる。アダム・スミスは『道徳感情論』の中で、共感 sympathy とは他者の感情をそのまま感じ取ることではなく、他者の立場に自らを置いてみるときの想像力によって形成されると説いた。他者の感情を模倣するのではなく、自身がその立場にいたならばどう感じるかを想像し、その感情が妥当であるかと自らに問うのである。
人びとは、自身の感情や行為が他者に評価されていることを意識している。しかし現実社会には、人びとの間には利害対立があるため、利害から独立した基準が必要となる。ここでスミスは、他者による時々の評価ではなく、想像上の「公平な観察者 impartial spectator」を自己内に育み、その視点に立って人は行動していると見出した。世間の評価と異なるとき、公平な観察者を重視する人を賢き人、世間の目を気にする人を弱き人とみなす。
スミスにおける共感とは、社会的承認の仕組みである。それは単なる感情的な反応ではなく、社会規範や法的秩序の形成プロセスにも関係している。たとえ個人が純粋に利己的に振る舞おうとしても、他者の共感を得ることもまた欲する人間は、自ずと善し悪しの内的判断基準に従って行為する。このように共感は、人間による相互行為を円滑にし、関係の秩序を支える仕組みとして機能するのである。
ようするにスミスの共感 sympathy には、現代の共感 empathy やその元となったドイツ語の感情移入 Einfühlung がもつ感情の理解や共有に加え、社会的な相互作用の中での感情の調整、道徳的承認、秩序形成といった規範的な意味合いが含まれるのである。実際に、社会的存在である人間の心理は、その人の社会的なコンテキストから離して理解することはできない。人格をもつ人間は、関係の中でのみ認識され、また自己を確立する。
社会学者のアーヴィング・ゴッフマンは、人びとが社会生活において俳優のごとく振る舞い、各々の役割を演じているのだと指摘した。役割を適切に演じるには、他者がその役割に何を期待しているのか、どのように受け止めるのかを理解する必要がある。そこで生じる社会的な相互作用は、状況の定義を人びとが共有し、維持することで成り立つ。暗黙の了解や、互いの意図を汲み取ろうとする努力により、人間は協力し合うのである。
共感による創造
現在のAIは大量のデータを分析し、表情や表現のパターンから人間の感情を推測することが可能である。しかしAIによる感情理解ないし共感は、あくまでも情報処理であり、あるいは人間の振る舞いの模倣に過ぎない。それはスミスが述べたような、生活を共にすることで可能となるような、深い人間理解に基づく共感ではない。
昨今では共感は、モノの創造の手法であるデザイン思考においても取り上げられる。デザイン思考では、利用者の真の要求や感情を理解する共感 empathize という第一段階が重視されるが、観察や対話を通して利用者の体験を深く理解し、感情的・心理的な背景に踏み込むことが求められる点で、スミスの共感に接近している。それゆえまた、デザイン思考の過程を学んだとて表面的な要求を超えた人間理解は難しいため、実行可能な人は限られる。
しかるにAIは、主体者である人間がしっかりと問いを重ねれば、多様な情報を示してくれる。たとえAIが人間の事情や背景、内面まで理解できず、共感するふりを重ねるばかりでも、人間が他者を理解するための情報を、求めるかぎりは学習のために与えてくれるのである。情報を手にしたわれわれが目の前の人と向き合うとき、相手の理解にもとづく意思や思惑を表し合うことで、相互理解が可能となる。ついには、スミスの共感にまで到達する。
そのときAIは、あえてデカルトにならうならば、魂をもち、機械である肉体を備えた人間を、外部的な機械として拡張する機能をもつようになる。漫画『ぼくのヒーローアカデミア』のアーマード・オールマイトのように、機械をまとうことで弱き自分を補強し、他者のために行為することを可能とするのだ。技術は、自ら助くるものを助く。よき目的のために技術を用いれば、われわれ人間はさらに賢き人となって助け合い、よりよい人間社会を形成する。
その意味において、精巧につくられた機械であるAIは、魂をもつ人間の仕事の補助となり、また人間の重要な機能となりうる。人間社会は、つねに人間同士の営みによって発展し、調和してきた。人間の生み出した技術は、たえず人間社会を担う一部となり、また各々の人間の生きる手段として活用されている。同様にAIは、自己から隔離され、理解や共感を得たいと思うような「他者」ではなく、自ずと自分自身の一部となるのである。



