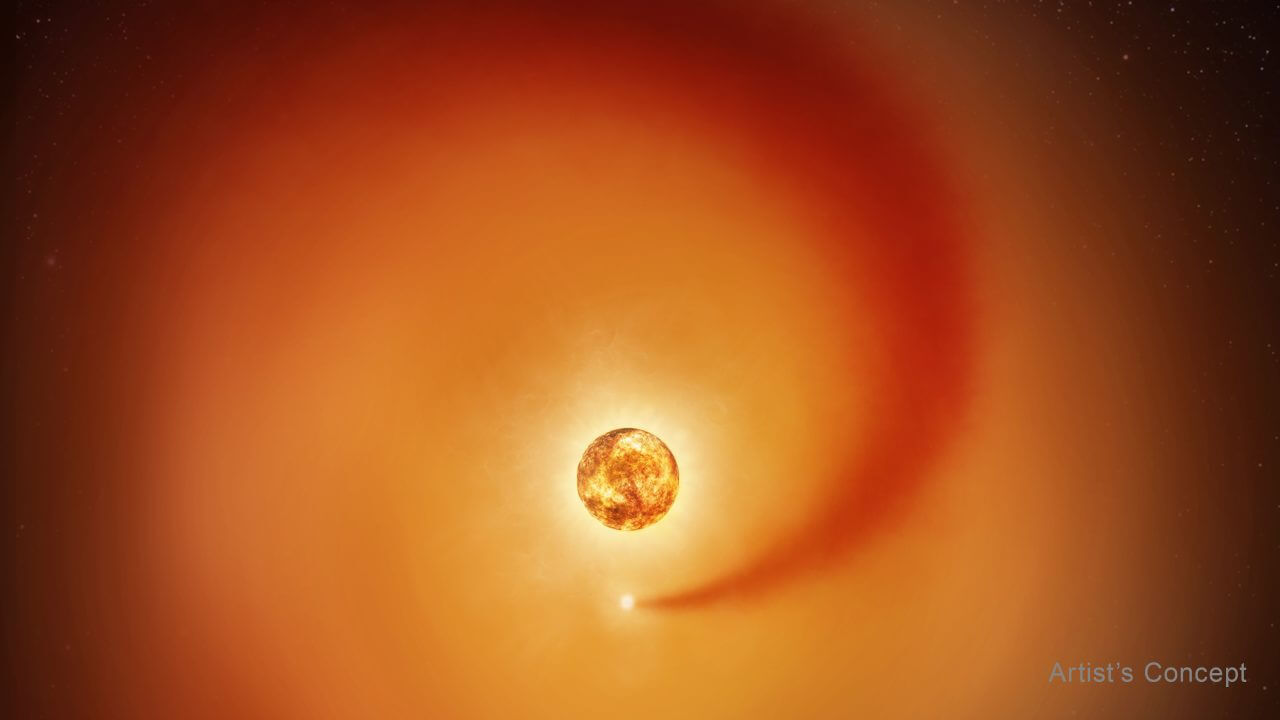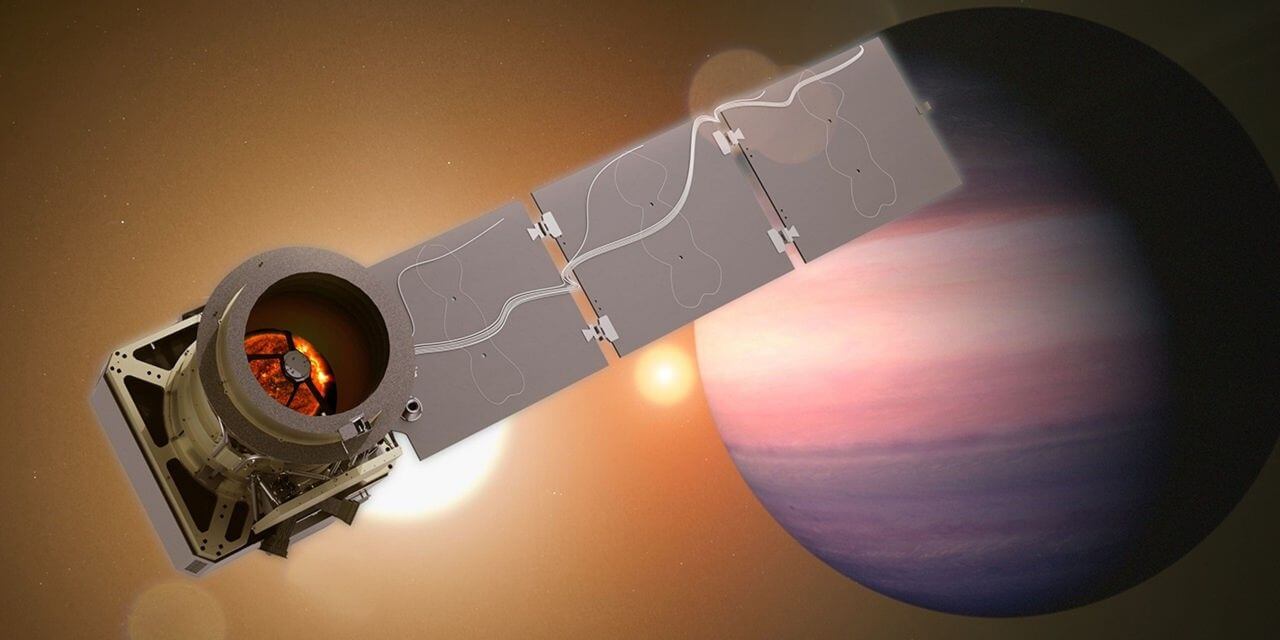「勝手な思い込み」「偏った見方」は人間の特質 今井むつみさんが新刊で向き合い方示す

言語や教育など、様々な分野で発言する認知科学者、心理学者の今井むつみさんの著書が、話題を呼び続けている。新刊『人生の大問題と正しく向き合うための認知心理学』(日経プレミアシリーズ)は、慶応大を定年退職するにあたって行った講義をもとにした。物の見方が偏りがちな人間の特質と向き合う大切さを唱える。
認知心理の基礎
「大学で教えた初めの頃は、米国で学んだ認知科学の最先端を伝えたいと考えていました。でも、何か違うと思うようになったんです。SFC(慶応大湘南藤沢キャンパス)の一般向けの講義でもあり、授業を通して学生たちに人間とは何かを考えてほしかった」
同著は、認知心理学の基礎が分かりやすく学べる構成だ。人間の錯覚や記憶のもろさ、論理的な思考の苦手さなどを紹介し、いかに思考バイアス(偏り)にとらわれる存在かを明かす。
鍵になる一つが、人間特有の物の考え方である「アブダクション推論」だ。「母親に花束を渡したら喜ばれた」→「母親はきっと花が(なんでも)好きだ」といった、論理に跳躍がある非論理的な推論を人間はするのだという。
「人間は、生成AIのように膨大な『点』の情報を集めて処理することはできません。少ない『点』から、『面』になる知識を作るしかない。そこで、アブダクション推論が必要になります。勝手な思い込みになる恐れもあり、人間の推論とはどんなものかを理解し、良質な推論ができるようになることが大切ではないでしょうか」
その過程で、重要な役割を果たすのが言葉だという。「言葉は自分の思考を整理して、抽象化する役割がある。情報をそぎ落とし、つないでいくアブダクション推論のやり方を、子供の頃から学んでいく。言葉がなければ、人間は情報の海に溺れてしまうでしょうね」
感覚とひもづけ
大学の学部時代の専門は、西洋史だった。やがて文献ではなく、「今、生きている人の心の仕組みを知りたい」と、心理学に興味を持った。米国留学を経て1997年に慶応大の教員となり、SFCで28年間、講義を続けた。「自分の中で常に新たな発掘をして熟成させる体験だった」と振り返る。
2024年、オノマトペや子供の言語習得過程に着目した秋田喜美さんとの共著『言語の本質』(中公新書)が、新書大賞1位に選ばれた。『学力喪失』(岩波新書)など、子供が「生きた学び」を得ることについても知見を深めている。
大学を退職する以前は、「やめたら1年は何もしないようにしたい」と言っていた。だが現在は、今井むつみ教育研究所を設立し、認知科学に基づいた子供の教育の調査、研究や執筆、講演などに追われている。
子供たちの教育については、ある物事を身体や感覚とひもづけて理解する「記号接地」の大切さを訴える。意味を理解していないある記号を、別の記号に置き換えているだけの生成AIの文章と人間の違いは、例えばこの点にあるという。
「今までの教育は、いかに分かりやすく教えるかを考えてきました。でも発達心理学や言語習得を研究した立場からいえば、子供がいかに『記号接地』をできるようになり、自走できるか、足掛かりを作るかではないでしょうか」
教育の話になると、一層言葉が止まらなくなった。「だから、全国学力テストで県別平均がいいの悪いのってどうなのでしょうか……。子供たちのそれぞれの個性に応じ、どんな体験や足場の掛け方が適しているか見極めていくことがもっと大切だと思います」