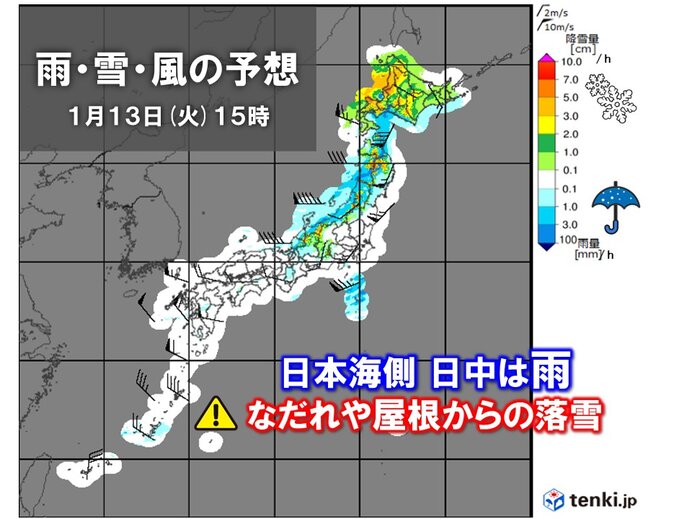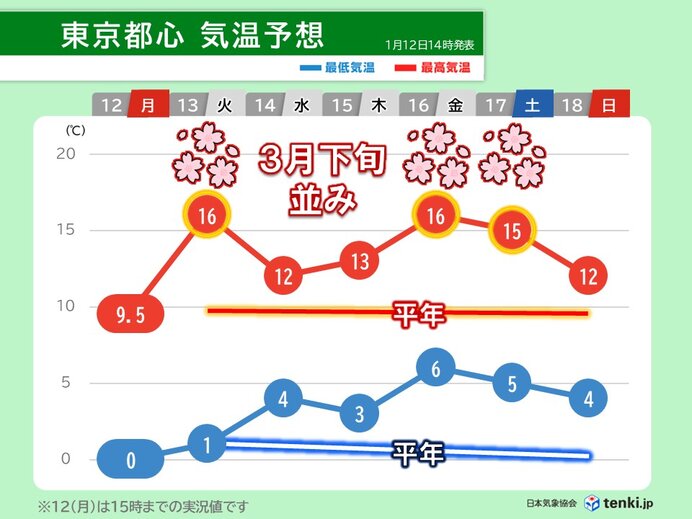「そろそろ戦死してほしいか」、戦艦「大和」と沈んだ父の忘れられない言葉…80年考え続けた父の思い

太平洋戦争末期の1945年4月7日、米軍が上陸を開始した沖縄に向かった戦艦「大和」が九州南西沖で撃沈された。乗組員だった父を失った藤本 黎時(れいじ) さん(93)(広島市)は、父との最後の食事で聞いた言葉が忘れられない。「そろそろ戦死してほしいか」――。その意味を考え、戦後を生きてきた。大和の撃沈から80年となる今月、父と大和への思いを講演で語る。(川畑仁志)
「日本は勝てない」
父との思い出を語る藤本黎時さん=加藤学撮影火鉢の上の鍋で豆腐が煮えていた。その周りで父・弥作さん(当時44歳)と母、弟と妹が笑顔を浮かべている。80年前の夜、13歳だった藤本さんは、広島県呉市の自宅で夕食をとっていた。
ゆったりと酒を飲んでいた父は「日本は勝てないな」とぽつり。そして、突然、「黎時もお父さんに戦死してほしいと思っているんじゃないか?」と問いかけてきた。
ぎくりとした。父に死んでほしい子どもなんているはずがない。食卓は数分の間、静まりかえった。
その夜、父は停泊中だった世界最大の戦艦大和に戻り、そのまま帰らなかった。
1億総特攻の先駆け
3月28日、大和は呉を出港。巡洋艦「 矢矧(やはぎ) 」や駆逐艦「雪風」など9隻とともに沖縄に向かった。海軍の首脳に「1億総特攻の先駆けになってもらいたい」と求められ、戦闘機の十分な護衛がないまま、米艦隊への突入を目指した。
「大和」の沈没地点動きはすぐに米軍に探知された。4月7日、東シナ海に出た直後に、米軍機の集中攻撃が始まる。魚雷や爆弾が次々に命中し、沖縄本島の北方約500キロの海域で沈んだ。
大和に装備を取り付ける 艤装(ぎそう) の段階から関わってきた弥作さん。艦の構造を熟知し、戦闘時は火災を消し、バランスを保つため艦内の区画に注排水をする配置に着いていたという。約3300人の乗組員のうち、駆逐艦などに救助されたのはわずか約280人とされる。その中に弥作さんの姿はなかった。
戦死公報が届いたのは5か月後。空の遺骨箱に父のシャツと爪を納めて供養した。葬儀を終え、「父にもう二度と会えないんだ」と胸を締め付けられ、一人になってから泣いた。
Page 2
平和崩れる危機感
戦後、藤本さんはアイルランド文学の研究者となり、広島大で教授を務めた。退官後に広島市立大の学長に就任。原爆被害を学ぶ講座を設け、平和の大切さを訴えてきた。
大和の乗組員だった藤本弥作さんの家族写真。手前左が黎時さん(黎時さん提供)この80年間、父の記憶をたどると、いつも頭に浮かぶのはあの言葉。「戦死してほしいか」――。
多くの軍人が住んでいた呉では戦時中、一家の大黒柱が次々に亡くなっていた。ある日、剣道仲間と帰宅していたとき、友達の家からその母親が飛び出してきた。「お父さんが戦死した。電報が届いた」。いたたまれない気持ちになった。
藤本さんが勤労動員で働いていた工場の一角には、特攻兵器の人間魚雷「回天」が置かれていた。その話題になったとき父は「上官に乗りたいと伝えたんだ」と漏らした。
父が帰宅するのは、人目に付かないように暗くなってから。藤本さんは「近所でも多くの人が戦死していた。あの言葉は『生きていて申し訳ない』という思いから出たのでは」と推し量る。父が平和な戦後を生きられなかったことが悔しい。
今月6日、慰霊に取り組む「戦艦大和会」が呉市内で開催する講演に出席し、父と大和への思いを語る。世界を見渡せば侵略や紛争が続き、平和がいつ崩れるかと危機感を募らせる。「理不尽な特攻で父を失った経験は伝え続ける」と力を込めた。