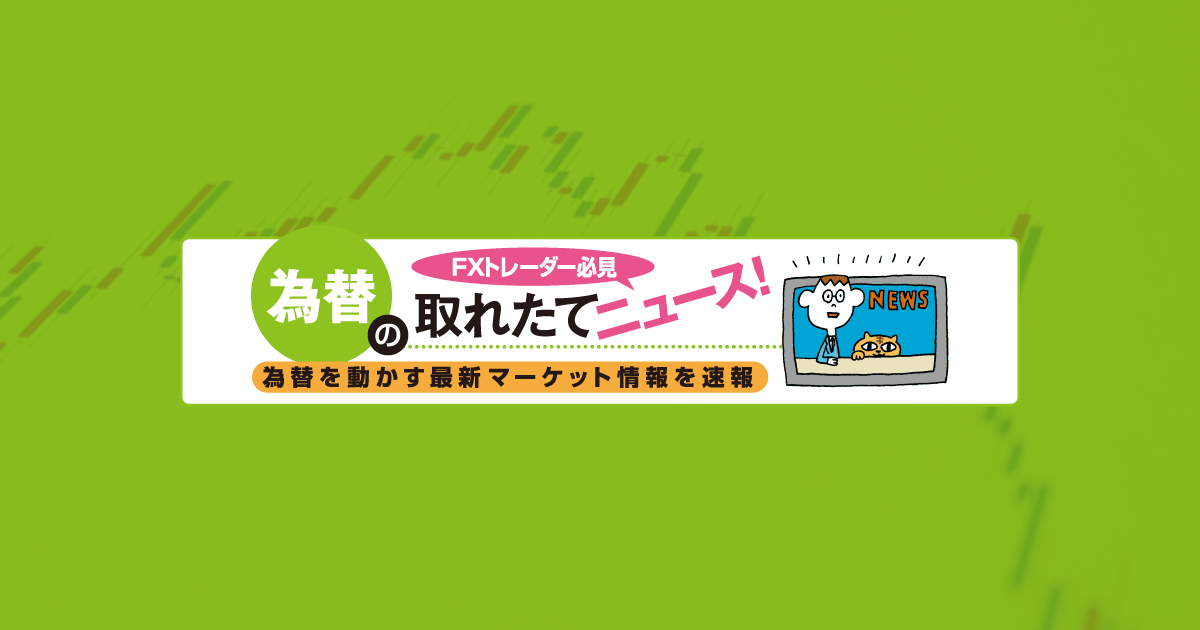日銀会合注目点:不確実性増す中での植田総裁会見、政策維持の見通し

日本銀行が18、19日に開く金融政策決定会合では、金融政策の維持が決まる見通しだ。日銀が目標とする2%を上回る物価上昇率と好調な賃上げが続く一方、世界経済の先行き不確実性は増している。難しい政策運営の中で、植田和男総裁の記者会見に注目が集まる。
複数の関係者によると、トランプ政権による関税措置などの政策が、米国をはじめとした世界経済や日本の経済・物価、金融市場に及ぼすリスクはこれまでよりも高まっていると日銀は認識している。前回の1月会合で決めた利上げの影響を点検する段階にあり、会合では政策金利を0.5%程度に据え置くことが決まる公算が大きい。
BNPパリバ証券の河野龍太郎チーフエコノミストは、植田総裁会見について「不確実性が高いことを指摘した上で、今後も経済・物価が想定通りに推移していけば、徐々に利上げを進めていくという従来の方針を繰り返す」と予想する。利上げは半年に1回程度という市場のコンセンサスを崩すものにはならず、ペースの加速を示唆することもないとみている。
ブルームバーグが4-10日に実施したエコノミスト調査では、今週会合での追加利上げ予想はゼロだった。利上げのタイミングは7月の48%が最多で、次いで6月が15%、5月と9月が13%。一部で時期を前倒しする動きはあるものの、引き続き半年に1回程度の利上げペースが想定されている。
一方、連合が14日に公表した今春闘の第1回回答集計の平均賃上げ率は5.46%と前年の初回集計の5.28%を上回り、1991年の最終集計の5.66%以来の高水準となった。日銀の想定内だが、利上げ路線をサポートする内容と言える。世界経済の不透明感が強まる中で、日銀が重視する基調的な物価上昇率への影響や変化も注目される。
長期金利の上昇
堅調な賃金・物価のデータや日銀政策委員の情報発信などを踏まえ、市場が想定する今利上げ局面での政策金利の最終到達点(ターミナルレート)は徐々に切り上がっており、先の調査では1.25%に上昇した。こうした動きを踏まえて長期金利も上昇基調にあり、足元では約16年ぶりの1.5%超での取引となっている。
三井住友信託銀行の岩橋淳樹シニアエコノミストは、急ピッチな長期金利の上昇を日銀も注視していると考えられるとし、今会合では「植田総裁から長期金利の上昇に関するコメントがあるか注目している」という。
植田総裁は12日の国会で、将来の短期金利に対する市場予想を反映して長期金利が変動することは「自然な姿」と発言。その上で「通常の市場の動きとは異なる形で、長期金利が急激に上昇するといった例外的な状況」になれば、機動的に国債買い入れの増額を臨時に実施すると語った。
複数の関係者によると、日銀は最近の長期金利について、堅調な賃金・物価に関する指標や情報、それに基づく日銀の金融政策に対する見通しの変化、米欧金利の変動などを反映した動きで、国債買い入れの増額などで直ちに対応する必要性は乏しいと認識している。もっとも、急激な変動で景気や金融面に悪影響が出ないか引き続き注視していく方針だという。
商品券配布問題を受けて石破茂政権の支持率が急落しており、今夏の参院選を控えて政局流動化への懸念が高まっている。みずほ証券の松尾勇佑シニアマーケットエコノミストは17日付リポートで、支持率低下を踏まえて「内外の政治動向の不確実性から、日銀が追加利上げ時期を半年に 1度程度のペースから速める意欲が徐々に弱まりつつあるのかもしれない」と指摘した。
他のポイント
- 日銀は引き続き、見通しに沿って経済・物価が推移していると認識。見通しが実現していけば、引き続き利上げで金融緩和の度合いを調整していく方針も維持
- 5月1日に公表する新たな経済・物価情勢の展望(展望リポート)に向けて経済・物価・金融情勢を入念に点検。今回から展望リポートを議論する会合以外を含めて全会合に金融機構局が出席
- 生鮮食品の価格高騰が続く中、消費者物価は総合指数の伸びが生鮮食品を除くコア指数を上回る状況が続いている。コメ価格も高止まりしており、物価の基調を重視する日銀のコミュニケーションは一段と難しくなっている