マツダ、2026年3月期上期決算 売上高は6.5%減の2兆2385億円ながら営業損失539億円、純損失453億円で赤字化 通期見通しは前回公表値を維持
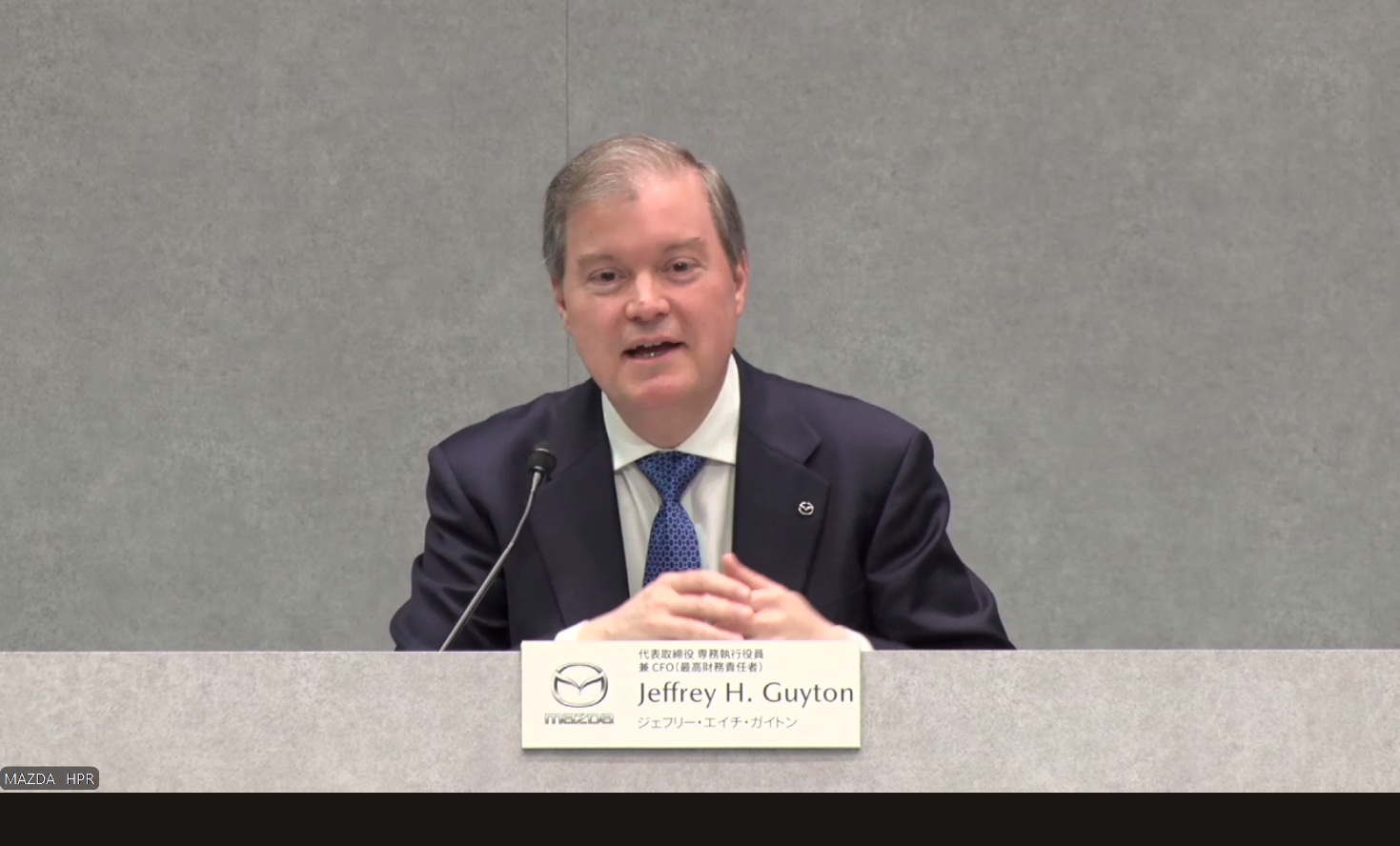
マツダは11月7日、2026年3月期上期(2025年4月1日~9月30日)の決算を発表した。
2026年3月期上期6か月累計の売上高は前年同期(2兆3939億1900万円)から6.5%減の2兆2384億6300万円、営業利益は前年同期(1030億4800万円)から赤字化して-538億7900万円、営業利益率は-2.4%、経常利益は前年同期(835億1300万円)から赤字化して-212億9400万円、当期純利益は前年同期(353億3400万円)から赤字化して-452億8400万円となった。
また、連結出荷台数は前年同期(59万台)から4万7000台減の54万3000台、グローバル販売台数は前年同期(63万台)から2万1000台減の60万9000台。
決算説明会で登壇したマツダ 代表取締役 専務執行役員 兼 CFO ジェフリー・H・ガイトン氏は上期決算の結果について、米国で行なわれている関税措置の引き下げ実施が想定していたよりも遅くなり、8月1日に実施されるとの予測が実際には9月16日になったことで決算にも大きく影響していると説明。
グローバル販売では日本と北米で販売を伸ばした一方、そのほかの市場で販売が減少。とくに欧州では「MAZDA2」の販売終了、モデル切り替えを控えた「CX-5」の販売減などが大きく影響して対前年比17%減という結果となった。しかし、欧州では9月から新型BEV(バッテリ電気自動車)「MAZDA6e」の販売がスタートしており、さらにジャパンモビリティショー2025の会場でも一般公開を行なった新型「CX-5」を2025年末から市場投入する計画で、これらの新型車によって販売を巻き返していくという。
2026年3月期の通期見通しは販売台数、財務指標ともに、8月に開催した第1四半期決算説明会で公表した数値を基本的に踏襲しているが、円安の進行したことで為替差益が発生し、ドル建て資産の金利収入が増えたことを受け、経常利益を150億円上方修正して680億円とした。一方で米国による排出ガス規制の緩和に伴う購入済みクレジットの評価損、海外で行なう調達計画の変更で発生する負担金が通期見通しに計上され、これらの費用によって経常利益の上方修正が相殺する形になる。
通期見通しの説明後、ガイトンCFOは赤字となった上期の決算を通期で黒字に戻す収益構造の施策について説明。
全体で営業利益を1500億円レベルで引き上げる改善計画では、その大半となる1300億円を「台数・構成」で改善。上期は関税の影響を見極めるため米国市場における販売を慎重に進めていたが、想定を上まわる需要を受けて販売見通しの計画を引き上げ。また、2026年のイヤーモデルを導入するタイミングで400ドル~700ドル程度の価格引き上げを実施して、利益率を改善しながら主要セグメントでの競争力も維持していく。これに加え、新型CX-5の市場投入、欧州向けとなるMAZDA6eの本格展開で下期の販売台数を伸ばしていく。
このほか、継続的に進めている変動費の改善と固定費の効率化は順調に進んでいるが、固定費については下期は増加する予定となっている。
個別の施策では、主要市場である米国での販売環境をあらためて説明。四半期ごとの販売台数は、全体需要の増減とリンクする形で堅調に推移しており、一方で競争の激化を受けて高騰しているインセンティブについては業界平均を下まわる数値に抑制して、結果的に上期販売は対前年比2%の減少に留めた。
また、北米市場での販売では米国・アラバマ州にあるMTM(Mazda Toyota Manufacturing, U.S.A.,Inc.)での生産を最大限に活用。ハイブリッドモデルを含めて「CX-50」のさらなる販売拡大を図って行く。
欧州では好調なラージ商品に加えて「CX-30」の販売に注力。さらにマツダ初のBEVセダンであるMAZDA6eは現地メディアからの評価も高く、計画どおり受注が進んでいる。さらに新型CX-5の市場投入を控えるなど、明るい兆しが見えているとした。
日本では首都圏への集中投資を行なって販売網を再構築。ユーザーのブランド体験拡大、利便性向上といった施策を進めている。販売面では利益率の高いSUVシリーズのマーケティング強化を進め、2026年中を予定する新型CX-5導入に備える。
中国では長安汽車との協業で9月末に発売した「MAZDA EZ-60」が順調なスタートを切り、すでに市場導入が進んでいる「MAZDA EZ-6」と合わせて重要な新エネルギー車市場でシェアを拡大していく。
発売を控える新型CX-5についても解説を実施。2012年の発売からこれまでに累計450万台を販売する現行ラインアップの最量販車種のモデルチェンジにあたり、新型CX-5では誰でもCX-5だと分かるデザインを備えつつ、室内空間の広さや快適な乗り心地、走行性能やテクノロジーの領域などでさらなる進化を果たしている。
テクノロジー面では電子プラットフォーム「MAZDA E/E ARCHITECTURE+」を採用して大型ディスプレイの搭載、高度な音声認識などに対応。進化したHMIやADAS(先進運転支援システム)によって新しい運転体験をユーザーに提供する。
さらに「2030経営方針」で掲げている原価低減とサプライチェーン強靱化の一環として、取引先とも開発初期の段階からサプライチェーン全体で合理的、かつ効率的なもの作りを実現する「共創活動」に取り組んだモデルとなっており、一例としては日本製鉄との共創活動で鋼材重量を前モデル比で10%削減するといった成果を挙げていることを紹介。これによって車体剛性や衝突安全性能を確保しながら、原価低減とCO2排出量の削減などを実現しているという。
このほかに将来的な展開として、「SKYACTIV-Z」と組み合わせたマツダ独自のハイブリッドシステムを搭載したCX-5も発売すると述べている。
最後にガイトンCFOは「第2四半期を終えて、当社は依然として厳しい経営状況にあります。低減されたとはいえ、米国の関税動向は非常に大きな影響を及ぼしており、米国やそのほかの国のさまざまな経済領域における不透明な要因となっております。インフレや雇用環境など、経済状況と通商環境の状況を引き続き注視して、素早く必要な対応を講じていきます。ネクスペリア製品の影響については、現時点で当社の生産に影響は出ておりませんが、部品メーカーさまと緊密に連絡を取り合って影響を調査中です」。
「構造改革と変化に対する素早い対応を全社を挙げて進めております。通期営業利益500億円の達成を目指すことに変更はありません。中間配当は25円、未定としてきた期末配当予想は30円と定め、中間配当と合わせた年間配当予想は前年同額の55円とさせていただきます。下期での黒字回復と来期以降の土台ができたことを踏まえ、安定配当の方針に基づいて計画するものとなります」。
「現在の経営環境の変化を機会と位置付け、全社一丸となってさらに強い会社・ブランドを目指してまいります」と締めくくった。



