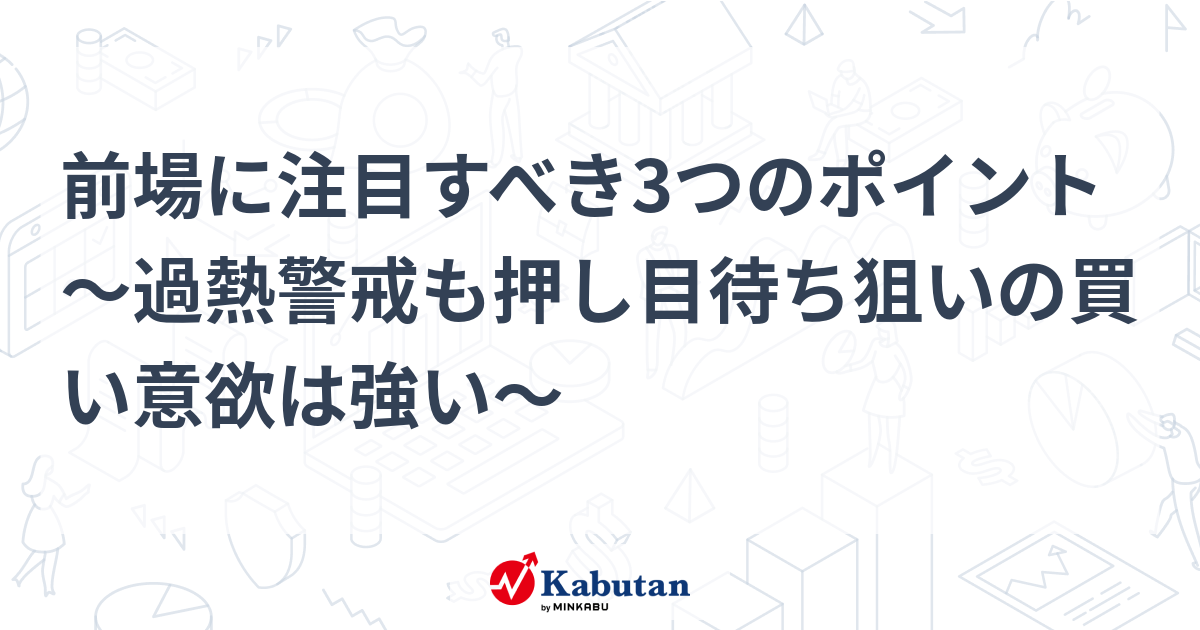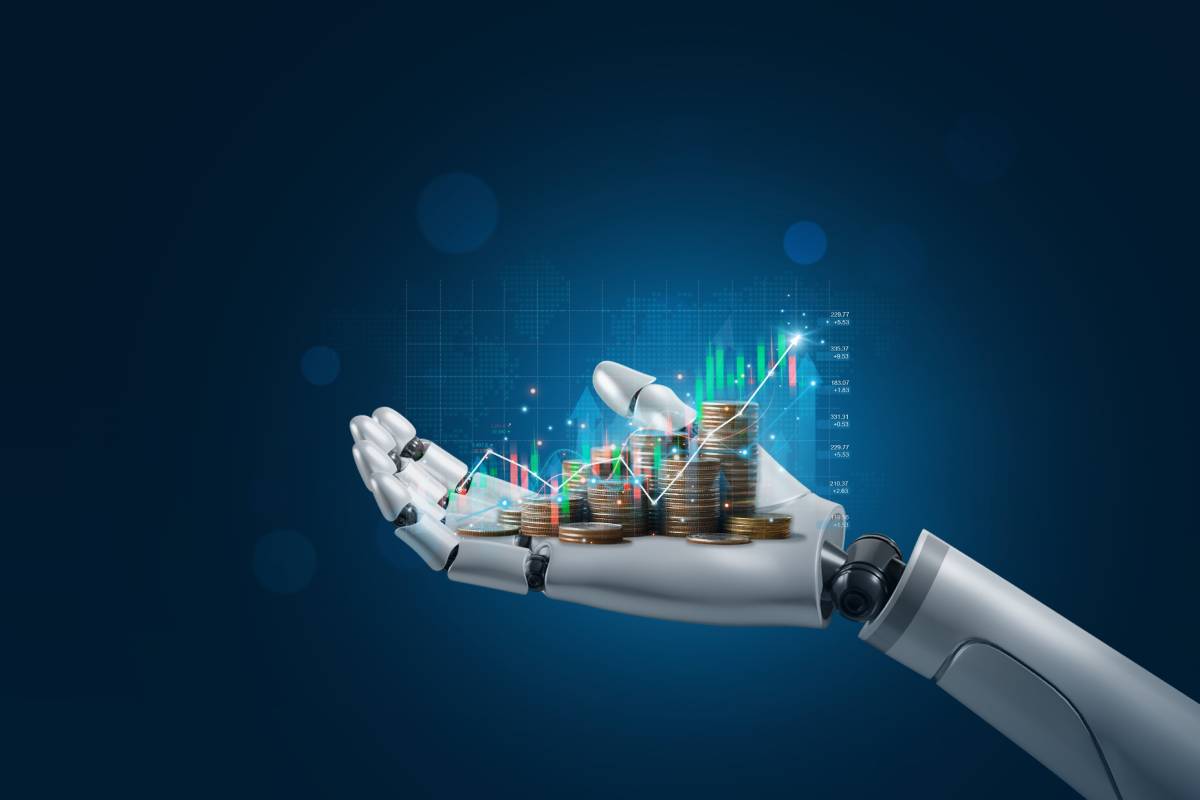日本車メーカーの大逆転がここから始まる…モータージャーナリスト・清水和夫が語る「知られざる切り札」 復活の鍵は「EVを作った後」にある

テスラやBYDとなどの新興自動車メーカーが台頭している。日本車メーカーは生き残ることができるのか。経済ジャーナリストの安井孝之さんが、モータージャーナリストの清水和夫さんに日本の自動車産業が抱える課題と展望を聞いた――。
撮影=プレジデントオンライン編集部
モータージャーナリストの清水和夫さん
50年間、ドライバーとしてモータースポーツに関わってきたモータージャーナリストの清水和夫さんへのインタビューは、大量生産・大量販売にひた走る自動車産業のあり方にも話が及んだ。電動化・知能化の進展が自動車産業の進化を促すチャンスになるかもしれない。
――世界を見渡すとヨーロッパではEVの販売の伸びはスローダウンし、ある意味で踊り場に来ていると思うのですが、どう見ていますか?
【清水】僕が見る限りスローダウンとは思えません。ただ2020年以降、EV販売は行き過ぎの状態でした。そのため事業の足元が危うくなったので、もう1回しっかり事業を見直し、足元を固めているという状況に陥ったのでしょう。
今のお客さんは全員がEVを求めているわけではないので、HEVもつくろうとしていますが、EVの本格的な普及期がいずれやってくるでしょう。
「EV導入にブレーキがかかっているとは思えない」
――トヨタ自動車の豊田章男さんがかつて「意志ある踊り場」と言い、成長を急がず、足場固めをした時期がありましたが、欧州のEVも意志ある踊り場ですね。
【清水】そうです。今も欧州はEV導入に積極的です。少し前にスイスのツェルマットに行きました。マッターホルンの麓の町ですが、温暖化で氷河がどんどん溶けています。その街の中はEVか馬車しか入れません。町の手前で車を置いて、馬車かEVで迎えに来てもらうわけです。
僕がびっくりしたのは、雪が汚れてないのです。PM(粒子状物質)が出てないからです。だから空気が綺麗なだけじゃなくて、街が静かで綺麗なのです。欧州ではそういった規制はベルリンなどでもやっているので、EV導入にブレーキがかかっているとは思えません。
――そういう意味では着実にEV化が進んでいるとみていいですね。
【清水】最近の動きとしてはトルコなど東ヨーロッパでは2万ユーロ、つまり300万円台のEVが出てきています。ドイツなどでつくった高性能なEVはいらない、道が狭い街並みを走るにはコンパクトな車の方がいい、というニーズを掴んでいるのです。
スズキはそこに目をつけています。そのマーケットに火つけたのは、ルーマニアのルノー系のDacia(ダチア)です。安いコンパクトなEVをつくったのです。
――日本の軽自動車のような存在ですね。東ヨーロッパだと、ドイツのようにアウトバーンをぶっ飛ばせないと車じゃない、というわけでもないのですか。
【清水】ドイツ人のような考え方は少数派でしょう。ヨーロッパの人はドライバビリティ優先だからコンパクトでもEVの加速性能などに魅力を感じているのだと思います。
Page 2
――家電製品に使われている金などは「都市鉱山」といわれて回収されていますが、自動車の場合はそうではないということですね。
【清水】特にモーターの永久磁石の回収は技術的にも難しい。日本製鉄とかJX金属などが必死に研究しているのですが、回収技術は確立していません。このままでは技術が確立しても、国内に車がない、ということになりかねません。毎年150万台つくっているHVが中古で海外に売られちゃう。行き先はモンゴルが多く、第一世代のプリウスもたくさん走っています。
写真=iStock.com/tanukiphoto
中古の日本車が流れ着くモンゴル・ウランバートル(※写真はイメージです)
――レアアースの回収技術が確立されていないとなると、モンゴルで走っている中古車は、最後は捨てられるだけですね。それではもったいないですね。
【清水】国内に静脈のバリューチェーンをつくれていないことが大問題です。年間何百万台も車をつくっているのに動脈のことばかり考えてきた結果です。
――産業界はSDGs(持続可能な開発目標)を実現しようと言ってはいますが、まだまだですね。
【清水】すでにお話ししましたが〈インタビュー(上)参照〉、カーボンニュートラルの視点で考えていたら見えてこないことがあるのです。SDGsの視点で考えると、大量消費社会から脱却して循環型社会にしていかなきゃいけないのです。
「エンジン vs. EV」で考えるのは時代遅れ
――車が電動化していくというのは化石燃料を燃やしておしまいのワンウエイの内燃機関から、再生可能な電気エネルギーを使って、車を動かす循環型のEVに進化すると認識するべきですね。そう考えると大量生産・大量販売モデルから循環型モデルに転換できるのではないかと思います。いつまでも内燃機関にこだわっていると循環型社会にはシフトできないのではないかと思いますが。
【清水】世界の人口は70億人を超えました。こんなに人口が増えなければ、化石燃料を燃やしても世界の人口を養えると思います。しかし、このまま行くと人口は100億人になり、車は25億台ぐらいに増える。そのとき宇宙船、地球号は持たなくなる。洞窟の中で火を焚いて生きていたホモサピエンスと同じままでは、もう生きていけません。僕の口から言いにくいことではありますが、内燃機関の進化はそろそろ厳しくなりそうです。ただ航空機など電気で飛ばすことができないような乗り物はe-fuel(合成燃料)を燃やして飛ぶ必要はあると思いますが。
撮影=プレジデントオンライン編集部
モータージャーナリストの清水和夫さん
――「内燃機関は敵ではない」という言葉を自動車メーカーの人からよく聞きます。その度に、誰もこれまで「敵」とは言っていないと反論したくなります。これまで100年間は、人類の暮らしのためには必要な仕組みだったのですが、これから先を睨むと電気にそろそろその座を譲っていっていいのではないか、と言っているだけなのですが。
【清水】「エンジン vs. EV」「EV vs. HV」といった二項対立の形で、メディアではよく議論されます。内燃機関は敵じゃない、という言葉も二項対立を煽っているように思いますが、そろそろ二項対立で物事を考えるのではなく、持続可能性を目指してどのような仕組みがいいのかを考えなければいけないところに来ていると思います。
Page 3
――それに対して日本メーカーのEVへの動きは少し鈍くないでしょうか。開催中のJapan Mobility Show 2025では電動車両の展示が増えてきましたが、日本勢の動きをどうご覧になっていますか。
【清水】トヨタはグループのブランドをみると、「レクサス」で大きくEV化に舵を切っています。「TOYOTA」はPHV、HV、「GR」はスポーツ系なので水素エンジンも含めてエンジンかな。「ダイハツ」は軽ですが、EVをやるだろうなと思っています。
一番上の「センチュリー」は、EVとは言いませんが、先進的な電動車に行かない限り、100年先を見定めた1番ハイエンドなブランドにはなり得ないのではないかと見ています。トヨタはEV化に向けて着々と手を打ってきていると思っています。小さくコンパクトにつくるのは日本が一番長けていますし、日本が得意とするものづくり技術をEVに振り向けたら、世界と戦えるでしょう。トヨタは多分、ちゃんとわかっています。
――ホンダはEV化の目標を少し先延ばししたけれども、EV化を積極的に進めています。でも、それを支える経営力に関して少し心配です。日産自動車はホンダとの統合計画が頓挫しました。そのほかの自動車メーカーは電動化と電脳化が融合したEV2.0の時代をしっかり生き抜くことができるのか。いろいろ心配の種はありますね。
【清水】そういう心配もあるのですが、僕が今、一番問題だと思うのは日本の自動車産業がいまだに大量生産・大量販売のモデルから抜け出していないことです。つまり自動車メーカーは車を売って、終わりで、その次にある保有オーナーへのサービス、そして最後のリサイクルをあまり考えていないことです。動物の体でいうと、老廃物を処理して浄化する「静脈」をあまり見ていないのです。みているのは新しいモノをつくり、販売する「動脈」のことばかりです。
撮影=プレジデントオンライン編集部
クルマを作った後のサービス、リサイクルの基盤整備が重要だと指摘する
年150万台の中古車が海外に流出
――でも最近はシートにリサイクル品を使うなどリサイクルを進めていませんか?
【清水】例えばHVに使っている電池などはほとんどリサイクルされていません。一番問題だと思うのはモーターです。統計をみると、日本は乗用車を毎年400万台販売し、150万台の中古車を輸出しています。HVは人気ですから、その中古車のほとんどが海外に輸出されているのが実態です。そうするとHVに搭載されていたバッテリーもモーターもどんどん海外に出ています。モーターの永久磁石はレアアース(希土類、レアメタルの一種)の塊ですので、貴重なレアアースが国内で使用された後、みんな海外に出ているのです。
――レアアースの確保が重要なのに、それも中古車となって海外に出ているとは驚きです。
【清水】海外に中古車で売った方が儲かるのでしょう。国内で回収・再生するよりも儲かるとなると、中古車は海外に向かいます。それに円安ですから海外の業者はどんどん買っていきます。モーターの永久磁石に使われているレアアースのネオジウムは中国が90%のシェアを握っています。中国はレアアースの輸出管理を強めようとしていますので、このままでは日本は枕を高くして寝られません。
Page 4
――電動化が進むと日本の自動車産業は競争力を失い、日本経済も弱くなるという悲観論が多いですが、電動化は自動車産業が新しい成長分野を取り込むチャンスではないかと思います。新しいバリューチェーンの創造というチャレンジをしてほしいと思っています。
【清水】まさに「静脈」のビジネスは新しいバリューチェーンづくりだと思います。間違いなくトヨタはよくわかっているので、いろんな要素技術をしっかり育て、新しいバリューチェーンをつくろうとする部署ができています。
――電動化は新しいビジネスの宝庫です。EVを買うと戸建てなら充電器を新設します。場合によっては屋根に太陽光パネルを設置して、自給自足のシステムをつくることもできる。そう考えると、車1台売って終わりではなくて、充電器やエネルギーマネジメントサービスまでを自動車メーカーが手掛けてもいいのです。自動車産業は「クルマだけを売る人」ではなくて、EVに必要な電気設備、サービスも含めて生産、販売する業界に大転換するチャンスだと思います。トヨタはようやくEV用の家庭充電器の販売を始めましたが、テスラは充電器だけではなくPowerwallという蓄電器も販売しています。もちろん電池の回収・再利用、清水さんのご指摘されたモーターのリサイクルもバリューチェーンとして育てればいいですね。
【清水】イーロン・マスクは南アフリカ生まれです。南アフリカはアパルトヘイト政策をとっていたので、1970年代から94年まで石油を禁輸された国際的な制裁を受けました。彼の自叙伝によると、小さい頃にその制裁を経験しています。石油は20世紀の富を生んだのは確かだけれど、格差を生むこともマスクは知っている。石油が敵だと思う彼の根拠は石油が格差を生むからです。彼には電気で世界を民主化しようという崇高な哲学があるのだと思います。
実はテスラ社の関係者と話すと、テスラは中国車のような派手なEVではなく、「安全性・ユーザー体験・自動化」という3つのコンセプトを重視し、中国車と戦うようなEVではないと言っています。CO2を減らすだけではなくて、SDGs的な発想を持ち、持続的に社会は豊かになるために電動化、電脳化に向けて積極的に自動車業界が進んでほしいですね。
撮影=プレジデントオンライン編集部
清水和夫さん(左)と安井孝之さん