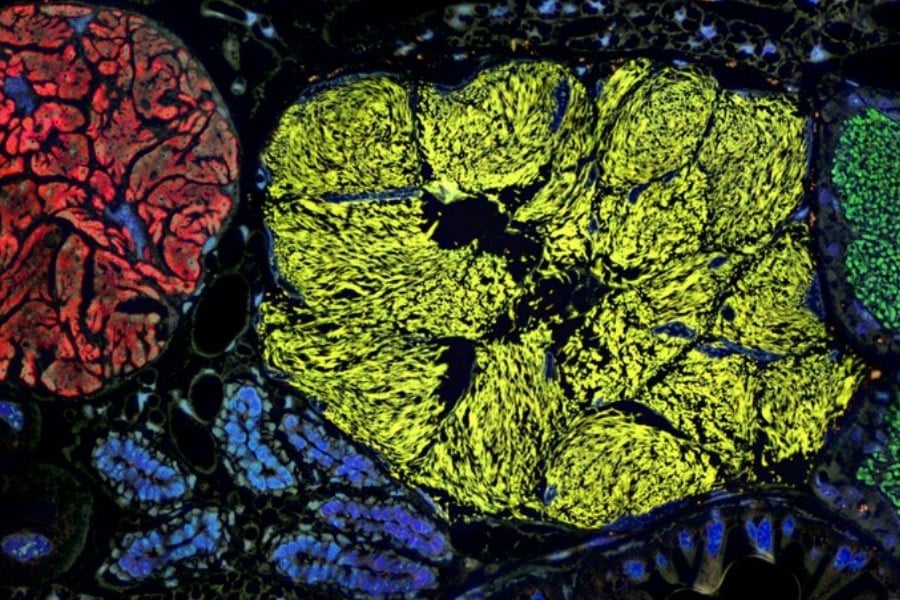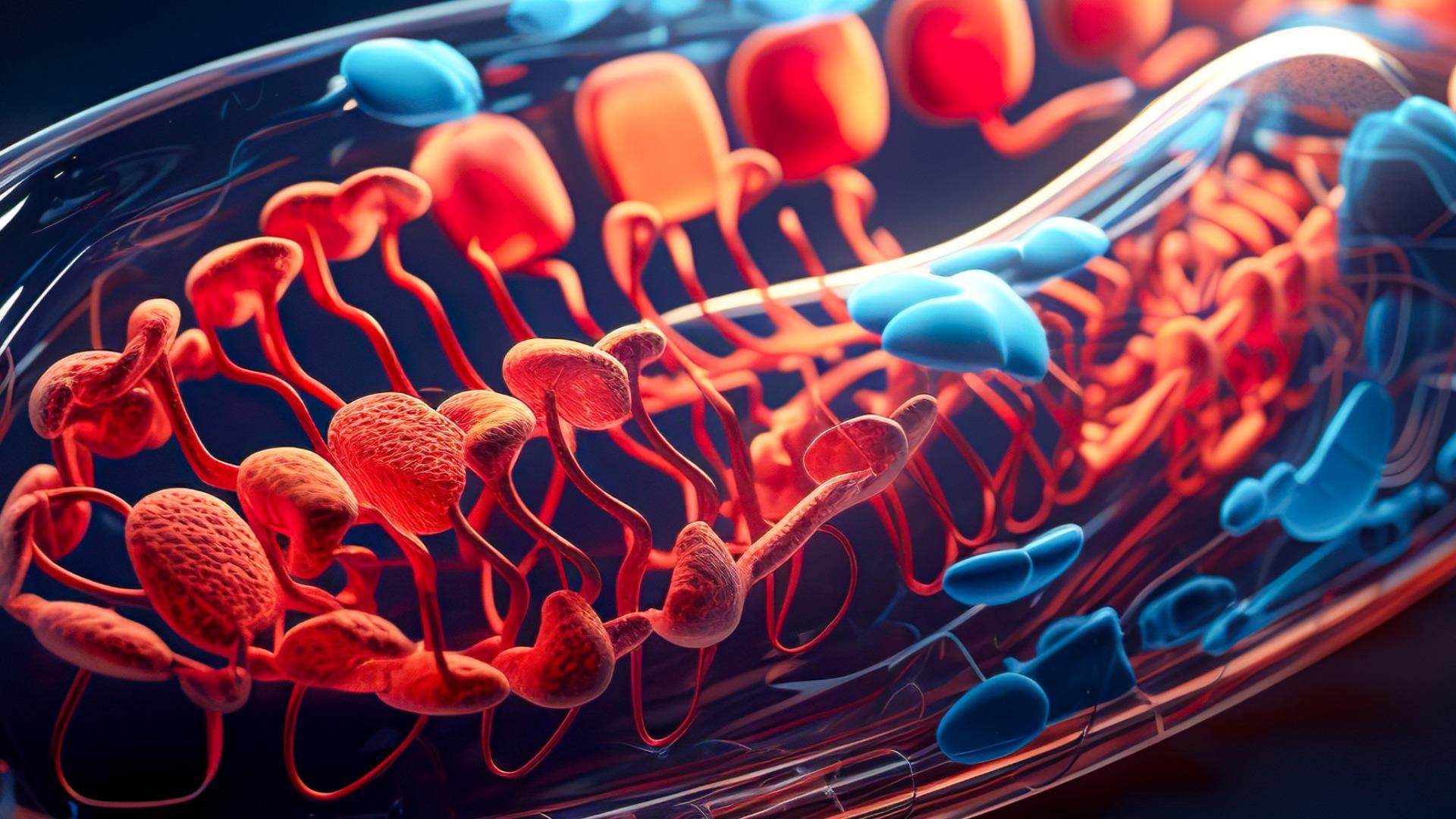ロシア人初の女性大学教授、ポアンカレ予想、村上春樹の名訳。意志強く、自分らしく生きるには? 今月読みたい本(第19回)

綿々と続く男性優位主義、自国第一主義にひた走る世界、移民排斥や海外留学生・学者の受け入れ中止、人権活動の縮小……人々はよりよい未来の実現に向けて歩み続けてきたはずなのに、世界は変わらず、さらに混迷のなかにある。そんな時代をYESかNOか、善か悪かではなく、意志強く、自分らしく生きるには? ノーベル文学賞作家が描いた19世紀の女性学者、彼女に連なる天才の人生、村上春樹による名訳短編を今こそ読みたい。
カナダの女性ノーベル文学賞作家が描く、19世紀ロシアの女性数学者の恋と人生
価格:1,540円(税込)
【概要】 その小説に描かれていたのは、若き日のわたしと、どこか面影のある少女(表題作)。ページをめくるにつれ、過去が新たな景色を見せる──ノーベル文学賞に輝く短編小説の女王、初の文庫化。
短編の名手が日常から切り出す「Too Much Happiness」の不吉さ
アリス・マンローはカナダのノーベル文学賞作家。80歳を過ぎた2013年に断筆宣言をし、2024年に92歳で亡くなった。ノーベル賞作家と聞くと敷居が高いが、短編の名手とされる彼女の作品には、日常から切り出す“地味な閃光”とでも言いたくなるものがあって、どれも味わい深い。
この短編集に収められている「あまりに幸せ」は、19世紀の実在の女性数学者ソフィア・コワレフスカヤ(1850年モスクワ生まれ~1891年ストックホルム没)を主人公にした特異な1編である。原題を「Too Much Happiness」という。史実を小説にするのはマンロー作品の中でも非常に珍しい。
「あまりに幸せ」は1891年、ソフィアがジェノヴァの墓地を恋人で熊のように大きい男と散歩しているシーンから始まる。男性はマクシム・マクシモヴィッチ・コワレフスキーと言って、行政法が専門の教授。ロシア語、フランス語、イタリア語で講義することができ、古典ラテン語も中世ラテン語も理解する桁外れの知識人だ。
ソフィアはマクシムに会うために、彼が滞在していた南仏にやって来て、二人でジェノヴァへの小旅行を楽しんでいる。共に40歳くらい。
ソフィアはマクシムの遠縁にあたる男性と偽装結婚し、やがて真の結婚に至って女児を出産した。しかし夫はビジネスの失敗で自死。墓地を散歩しているこの時点では、魅力的な独身男と魅力的な未亡人である。
ソフィアは墓地を歩きながらマクシムにこう話しかける。今年のうちにわたしたちのどちらかが死ぬわ。マクシムは問い返す。どうして? ソフィアは言う。だって新年の第一日目に墓地を歩いちゃったもの。
続けてソフィアはからかいぎみに言う。あなたは何でも知っているのに、そんなことも知らないの? 私は8歳になる前に知っていたわ。マクシムは彼女にこう応戦する。「女の子は台所女中と過ごす時間が多くて、男の子は馬小屋で過ごす。そのせいじゃないかな」
なんと濃縮されたトップシーンであることか。恋人同士のじゃれ合いが、幼児の頃から刷り込まれるジェンダー問題の領域に手をかけ、かつ、迷信のような俗諺から不用意に引っ張ってきた「死」という単語が、「Too Much Happiness」という原題に潜む不吉さを増幅させる。
フランス最大の科学賞受賞。女の脚光に嫉妬する男の自尊心
遡ること1888年、ソフィアはマクシムと出会って恋に落ちたが、同年ソフィアがフランス最大の科学賞「ボルダン賞」を受賞してから、二人の仲はぎくしゃくし始める。マクシムは受賞パーティの同伴者にはなってくれたものの、祝宴が続く途中でぷいと姿を消し、滞在中の英国の小村に戻ってしまう。
どこにいっても場を支配していた男の自尊心が傷つき、ソフィアが脚光を浴びていることに嫉妬したのだ。マクシムにぞっこんだったソフィアはうろたえるが、そのそぶりは見せないようにして、ストックホルムから乗馬を楽しんだなどとお気楽な手紙を出し続ける。
マクシムと結婚できるかどうか、彼の気分次第のところがあった。そしてマクシムは冒頭のお正月の南仏で、この春に結婚式を挙げると約束する。
ソフィアは幸せだった。この上なく。カンヌ駅まで送ってくれたマクシムと別れ、ソフィアは娘と仕事が待つストックホルムへの一人旅を始める。途中、パリやベルリンに立ち寄りながら。
パリではポアンカレの訪問を受け、彼の愚痴を聞かされる。亡き姉が愛したパリコミューンの闘士ジャクラールと、遺児である甥を訪ねるが、ジャクラールの虚勢と、学問の道には進みそうにもない甥の姿に落胆する
ベルリンでは、病に伏せっていた恩師のヴァイエルシュトラスを訪ねる。ソフィアは回想する。二十歳で欧州数学界の重鎮ヴァイエルシュトラス教授の私邸の門を叩いたときのことを。教授はむげに追い返すことをせず、大学院生級の数学の問題を出した。ソフィアが1週間後に解答を持って訪れると、ヴァイエルシュトラス教授は驚愕する。
自分とは異なった鮮やかな解法、加えて独創性。のちに教授はこう述懐する。こんな学生が現れるのをずっと待っていた。自分を追えるだけでなく、自分に挑んで、その先に飛翔できる学生を、と。
ソフィアは恩師に姉や夫がすでに亡くなっていることを報告し、自分はもうすぐ結婚して、研究に専念するのだと幸せそうに語る。恩師と会うのはこれが最後になるだろうとソフィアは覚悟したが、史実は恩師がソフィアより6年長く生きたことを伝える。
恋愛や結婚相手に関する葛藤は、現代に続く正解のない難問
冷たい雨や雪、みぞれまで降る北上の旅。ソフィアの体を直撃したのは、天然痘が秘かに蔓延している首都コペンハーゲンを避け、デンマークの島々づたいに、列車とフェリーを乗り継いでストックホルムに向かう鈍行の旅の悪環境だった。
寒い、喉が痛い、体を動かすのも億劫。夜汽車に揺られながら、ソフィアは自分の人生に登場した男達のことを思い浮かべる。
間もなく夫になるマクシムのことはこうだ。彼は自由主義者で反体制派として故国を追われているが、男らしい(とされている)行動規範を持っている。危険や意図的な欺瞞があったとしても、その行動規範に従う。女性達はその行動規範から利益を得ることもあれば不利益を被ることもある。
その点、ロシアから出て数学を学びたいとするソフィアを応援して、偽装結婚(親権が親から夫に変わる)してくれたウラジミール。彼は男らしさという価値観には無関心だった。だからこそ、他の男達なら女に与えてくれない平等を与えてくれた。そのかわり、包み込まれるような温もりや安心感をもらうことはできなかったが。
姉のアニュータが愛したジャクラールのことはこうだ。姉は美貌で知られたうえ、投稿した小説でトルストイに文才を認められ、求愛までされた。が、なびかなかった。ジャクラールは「自己中心的で無慈悲で不実」な男だったが、姉は「彼を憎んでいるときでさえ彼に夢中だった」と。
「保守的な男」との恋愛、「リベラルな男」との恋愛、「同志愛で結ばれた男」との恋愛。女性達の恋愛や結婚相手に関する葛藤は、現代にも続く正解のない難問のように見える。
ソフィアはロシア人女性初の大学教授としてストックホルム大学で教えていたが、外国語を話す生活に疲れ果て、望郷の念を募らせていた。しかしロシアに帰ることはできない。女性は大学教授になれないからだ。
そんなとき同国人のマクシムに出会い、“思想は自由主義、行動規範は保守”という彼の中に、安心や安堵、庇護される喜びを見いだした。彼女は結婚に憧れていたのではない。結婚によって得られる果実を欲していたのだと思う。
ストックッホルムに戻った彼女は幸福の絶頂で死を迎えた。原題の一部「Too Much」には、皮肉な響きがある。やり過ぎ、でき過ぎ、食べ過ぎ、持ち過ぎ。過剰さの中には、なにか不吉な種が宿っている。
ソフィア・コワレフスカは小説や回想録、ルポルタージュなどでも高く評価されていた。理系と文系、両方の頭脳を持っていたと言うなかれ。両者は区別なく繋がっている。
ソフィア自身がこう言っている。「数学は無味乾燥な自然科学と思われているが、数学という自然科学の学問には大いなるファンタジーが要求される」と。
アリス・マンローは「数学者」と「小説家」という組み合わせに魅了され、あらゆる資料を読み込んでこれを書いた。女性が学問などするものではないとされた時代に、いくつもの壁を乗り越え、己の天分を無駄にしなかった天才ソフィア・コワレフスカヤ。
この短編は、マンローが異国に散ったソフィア・コワレスカのお墓に供えた香華のように見える。墓地でのマクシムの献辞は、型どおりで素っ気なかった。