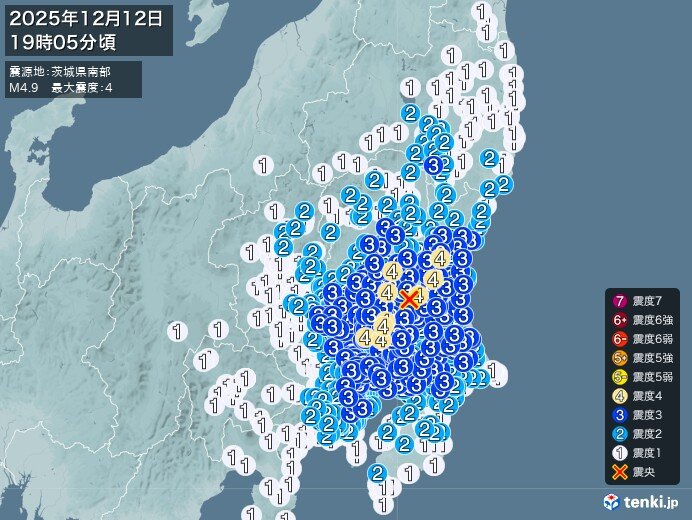だから82歳になっても脳がヨボヨボにならない…認知症研究者が50年間、本気で続けている「趣味」 定年後も脳に楽をさせず、しっかり働かせる

いつまでも元気な高齢者は何をしているのか。薬学者・脳科学者の杉本八郎さんは「筋力と同じで脳も使わなければ衰えてしまい、その分認知症になるリスクが高まる。定年後はのんびり過ごすより、働き続けたほうが脳のためになる」という――。
※本稿は、杉本八郎『82歳の認知症研究の第一人者が毎日していること』(扶桑社新書)の一部を再編集したものです。
写真=iStock.com/Ekaterina Chizhevskaya
※写真はイメージです
認知症研究に人生を費やした82歳の日常
私は人生の大半をかけ、認知症治療薬の開発や研究に徹底的にかかわってきました。その過程において、認知症を予防するために何が必要なのかについても、たくさん勉強してきました。
じゃあ、自分自身も認知症予防のための対策を徹底して行っているのかというと、正直なところ、実はそうでもないのです。
もちろん基本的には早寝早起きですし、毎日のウオーキングを欠かさないなど、生活習慣病を寄せつけないような生活習慣は身についているとは思いますが、「認知症を防ぐためにやれることはすべてやる!」みたいな気負いはいっさいありません。
例えばポリフェノールが認知症予防に効果があるからといって毎日赤ワインを飲んでいるわけではありませんし、ビールはほぼ毎日飲んでいますが、それもホップの認知症予防効果を期待しているからではなく、一日の骨休みとしてお酒を飲むのが好きだからです。
それでも私は、82歳になった今も認知症とは無縁ですし、これから先もその心配はないと思っています。
認知症を遠ざける「生き方」「考え方」
何を根拠にそんなことが言えるのかというと、私の「生き方」や「考え方」が、結果として認知症を遠ざけているという自負があるからです。
「生き方」や「考え方」などというのは数値で測るようなものではないので、一見、非科学的な尺度であるように感じるかもしれません。「そんなの勝手な思い込みでしょ?」と言いたくなった方もいるでしょう。
けれども、どう生きるか、あるいは、どういう考え方をするかによって、脳の使い方はまったく違ってきます。だとしたらそれが認知症の発症リスクに違いをもたらしているとしても、決して不思議なことではありません。
実際それを裏付けるエビデンスも数多く出されており、認知症予防のためには、食事や運動などの「生理的アプローチ」だけでなく、知的活動や社会参加、そしてメンタルヘルスといった「認知的アプローチ」を合わせて行うことが非常に大事だというのが、認知症にかかわる研究者たちの一致した意見なのです。
Page 2
今や人生100年時代といわれているのですから、60~65歳なんて人生の折り返し地点を少し過ぎただけです。脳だってまだまだ元気なのに、早々に楽をさせようとするのは、認知症になりやすい状況をわざわざ自分でつくるようなものです。
私が教えている学生たちにも、「定年で引退ではなく、定年を機に自分で会社を起こせるような人生プランを立てておきなさい」と指導しています。
今の日本は、年金だけで悠々自適に暮らしていけるような状況ではないので、いやでも仕事をせざるを得ないという部分もあろうかと思います。こんなはずじゃなかったと文句の一つも言いたくなるかもしれませんが、認知症予防のつもりでもうひと息、ふた息頑張ってみてはどうでしょうか。
もちろん起業にこだわる必要はないですが、脳のためにも「定年後も働き続ける」という選択はぜひ前向きに検討していただきたいと思います。
毎日自分に課している「俳句10句」ノルマ
このように趣味をもつことが認知症予防に有効であることはさまざまな調査で明らかになっています。
ただ、私の個人的な意見としては、何事も、なんとなくやるのではなく、「とことん極めてやろう!」くらいの意欲をもってやることも、脳をたくさん働かせるためには大事なのではないかと思っています。
私は趣味の俳句をかれこれ50年続けていますが、今も毎日必ず10句作ることをノルマにしています。五七五というわずか17字で、季語も含んで季節感を表現するわけですが、10句も作るとなるとかなり大変です。それでも、よほどのことがない限りこのノルマを欠かしたことはありません。
写真=iStock.com/paylessimages
※写真はイメージです
月に1回は、俳句の雑誌に投句して、2カ月に1回は東京で私が主催するフォーラムに参加します。この会の一部は俳句の会で、二部は研究会という仕立てです。
毎回20人ほどが集まるその会合では、自分の俳句5句を作者がわからないように無記名で提出し、それが全部記載された用紙が回覧されます。参加者はその中から自分が良いと思う句を7句選びます。なお、主催である私は7句のほかに特選4句も選びます。
ちなみに私の俳号は「薬王子」といいます。
選句が終わると一人ひとりが自分が選んだ俳句を披講しますが、自分の俳句が選ばれた作者は名乗り出て、それが1ポイントになります。そのポイントをたくさん取った人がその会のウィナー(勝者)になります。
Page 3
「認知的アプローチ」などというと、少し難しそうに感じるかもしれませんが、わかりやすく言えば、「脳をしっかりと働かせる」ということです。
定年後はのんびり過ごそうなどと言ってただ暇を持て余すような生活をするのは、脳に「もう働かなくていいよ」と言っているようなものです。
すっかりお休みモードになっている脳には、優先的に栄養や酸素を運ぶ必要はありませんから、送られる血液の量もだんだん少なくなります。よくも悪くも、そのような調整作用が私たちの体には備わっているのです。
もちろん一時的なものであれば大きな問題にはならないでしょうが、その状態がずっと続くと血流はどんどん悪くなり、脳の活性が失われて、ただでさえ加齢とともに弱まっていくアミロイドβなどのゴミを排出する力がより速いスピードで弱まっていきます。
また、十分な栄養や酸素が供給されなくなれば、神経細胞が瀕死の状態になる危険性もあります。これらが認知症の引き金になることは本書で繰り返しお話ししています。
運動不足が続くと筋力はどんどん衰えて、転びやすくなったりもすることで骨折などのリスクも高まります。
脳もそれと同じで、使わなければ衰えてしまい、その分認知症になるリスクも高まるのです。
定年後も「脳に楽をさせないこと」が大事
私は2003年にエーザイを定年退職しましたが、その後も、京都大学大学院薬学研究科寄附講座教授、京都大学大学院薬学研究科最先端創薬研究センター客員教授、同志社大学生命医科学研究科客員教授などを歴任しながら研究を続け、2014年には認知症の根本治療を実現する新薬開発のためのベンチャー企業「グリーン・テック株式会社」の代表取締役に就任しました。2025年4月からは名古屋葵大学の学長に就任します。
82歳の杉本八郎さん(写真提供=扶桑社)
「認知症によって苦しむ人々を救いたい」という思いがすべての活動の原動力になっているのですが、この信念のもとに私の脳はサボることなく働き続け、巡り巡って結果的に、私自身を認知症から遠ざけてくれているのです。
私の場合はちょっと働きすぎなのかもしれませんが(笑)、定年を迎えたからといって、60~65歳で社会の一線から退き、あとは楽をしようなどというのは、あまりにもったいないことだと思います。
Page 4
その後、居酒屋に移って懇親会になります。ここではその日に発表した互いの句について言いたいことを言い合います。私はみなさんの句を酷評しまくるのですが(笑)、なんとその酷評が意外にもおおいにウケて、この俳句の会は30年も続いています。
同じ趣味をもつ気心の知れた仲間たちと遠慮のいらない交流は本当に楽しくて、私の活力のもとになっているのは間違いありません。
また毎月投稿している俳誌では一番からビリまで優劣がつけられ、年間を通じて最も優秀だと認められると大きな賞ももらえます。趣味レベルでそんなプレッシャーを負うのは嫌だという人も中にはいるかもしれませんが、私は自分の句がどういう評価を受けるのかを、いつも楽しみにしています。
もちろん、自分の句の順位が下のほうだったり、知り合いの句が高評価を受けていたりするとものすごく悔しいですが、そのぶん、次はもっといい句を作ろうという意欲を掻き立てられます。いくつになっても、このような「競争心」を失わないことも、脳を衰えさせないための秘訣になっているのかもしれません。
俳句は認知症予防にいいことずくめ
もちろん私は好きでやっているのですが、俳句には認知症予防につながる要素がたくさん含まれています。
そもそも俳句が脳の活性化につながるという話はよく聞かれ、「俳句と脳の研究会」なる研究グループが、松山市の支援のもとで、脳科学者である川島隆太教授の協力を得て実験を行ったところ、四則計算などよりも、俳句を作るときのほうが、脳がより活性化することがわかったそうです。
私の場合は、一日に60分くらい俳句を考えるのに費やしていますので、これだけで脳の血流がかなり活性化されているに違いありません。
杉本八郎『82歳の認知症研究の第一人者が毎日していること』(扶桑社新書)
また、いい俳句を作るために、自然の中や名所旧跡に「吟行ぎんこう」に出かければ、たくさん歩くことになり、よい運動にもなります。私の場合は京都御所がすぐ近くなので、毎日御所の美しい自然に触れながら俳句を作っています。
また、俳句を作る上では、季語や自然についてたくさん知っていなければなりませんが、いろいろと観察しながら自然の中を歩いていると、名前を知らない花や草、虫や鳥などによく出会います。その度に本で調べたり知ることは、まさに認知症予防のキーポイントである、「豊富な知的活動(認知機能を使用する活動)」であり、「新しい学習」です。
俳人協会に入って会合に参加したり、俳誌に投稿したりするほうが、より深く楽しめると私は思いますが、個人的な趣味として一人で楽しむだけでも、俳句の認知症予防効果は十分期待できるでしょう。