【3I/ATLAS】太陽系外から彗星が猛スピードで接近中!「太陽に最接近!?いまどこ?」"恒星間天体"としては3例目(RSK山陽放送)
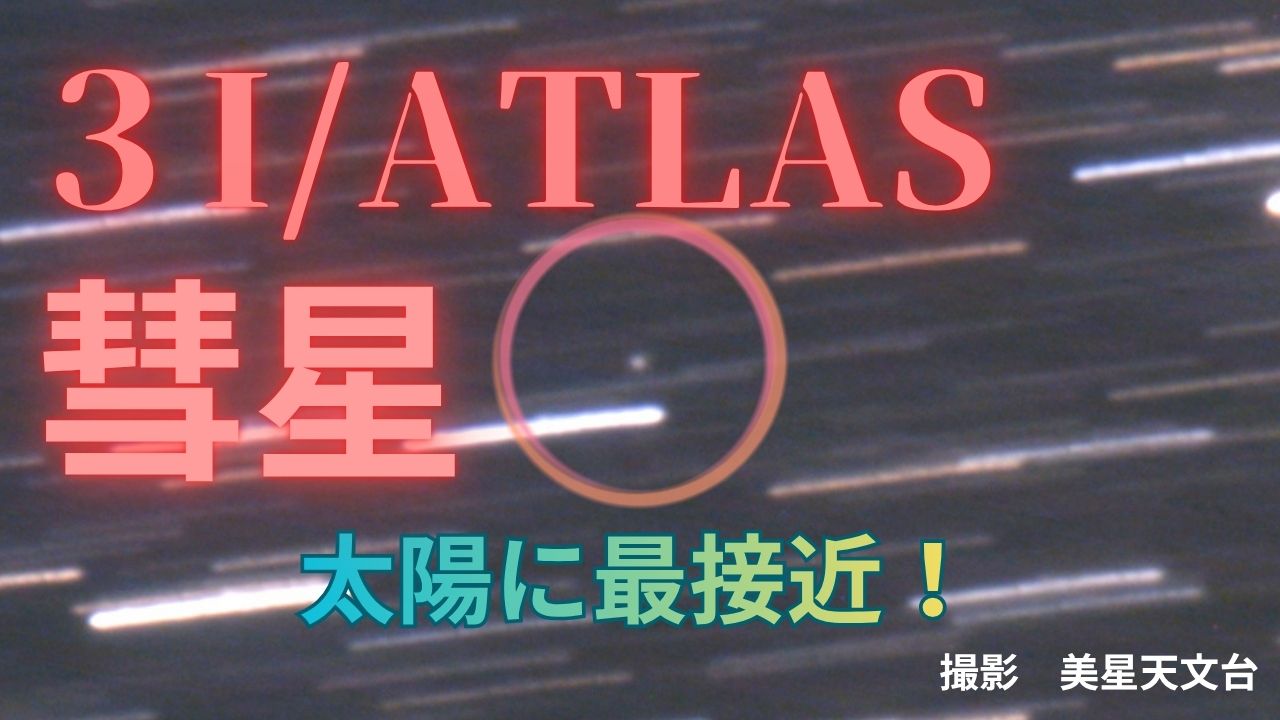
■彗星は宇宙の謎を解く「鍵」 天文に詳しい山陽学園大学地域マネジメント学部講師の米田瑞生さんは、彗星は宇宙の謎を解き明かす鍵となると話します。 ー太陽系外から彗星「3I/ATLAS」が近づいているのですね。 山陽学園大学 米田瑞生さん 「太陽系の中には太陽系の仲間たちしかいないと思ったんだけども、よその天体がたまに訪ねてきてまた出ていくというような、ちょっとダイナミックな様子が分かってきたんですね。 彗星観測は、目に見えない宇宙の謎を解き明かす重要な鍵となっているのです」 ■彗星観測の科学的意義 ー彗星の発見にはどのような意義があるのでしょうか。 米田瑞生さん 「彗星を発見して研究することには、重要な意義があります。 彗星の正体は『水の氷や二酸化炭素の氷、つまり氷やドライアイスの塊のようなもの』であり、太陽に近づくにつれて熱せられ、その本体が溶け落ちてガスや塵を放出することで特徴的な尾を形成するということです。【画像(6)】 氷であるということは他にも意味があって、冷たいものでできている、ドライアイスとか水の氷でできているということは太陽圏の遠いところ、そこで形成された太陽の熱が届かないようなところでできたということは推測できます」 ■彗星から見えてきた太陽系の外縁部 ー彗星の観測でどんなことが分かるのでしょうか? 米田瑞生さん 「彗星の観測を通して、太陽系の外縁部には二つの主要な領域があることが判明しました。 まず『エッジワース・カイパーベルト(EKB)』と呼ばれる領域があり、ここは『短周期彗星』(周期が200年以内の彗星)の故郷です。 そして、さらに遠方には『オールトの雲』【画像(8)】があり、こちらは『長周期彗星』(周期が200年以上の彗星)の発生源となっています」 「近年では、太陽系外から飛来し、また太陽系を去っていく『恒星間天体』の存在も確認されるようになりました。 3I/ATLASもその一つです」 ■「恒星間天体」が初めて発見されたのは2017年 ーこれまでに発見された「恒星間天体」は? 米田瑞生さん 「2000年以降は、プロの天文学者が、大型の望遠鏡やデジタルの力を駆使して、さらに多くの彗星を発見するようになります。そして2017年、驚くべき発見がなされました。 オウムアムアと呼ばれるその天体は、太陽系外からやってきたことが初めて確認された天体、つまり人類が初めて目撃した恒星間天体です。 彗星のようにガスやダストを放出している様子がなく、小惑星のような天体だろうとされています」 ー3I/ATLASの特徴は? 米田瑞生さん 「今回見つかった3I/ATLASは、恒星間天体としては3例目です。太陽からまだまだ遠い段階で秒速60kmを超える猛スピードで、太陽に近づいていました。 そして、この3I/ATLASには、彗星のように、尾があります。太陽系外の恒星(太陽のように、自ら核融合によりエネルギーを生成し、輝く天体)の周りにも惑星があることは、30年前から知られていますが、彗星や小惑星に相当する小天体も存在していることを、強く示唆しています。 それらが、もともといた恒星系のオールトの雲や、エッジワースカイパーベルト領域から、何らかの原因で弾き出されて、太陽系にやってきたのではないでしょうか。 暗黒の空間を、何十万年かそれ以上の時間をかけて太陽系にたまたまやってきたと思うと、ロマン溢れる瞬間を我々は目撃しているようです」
RSK山陽放送



