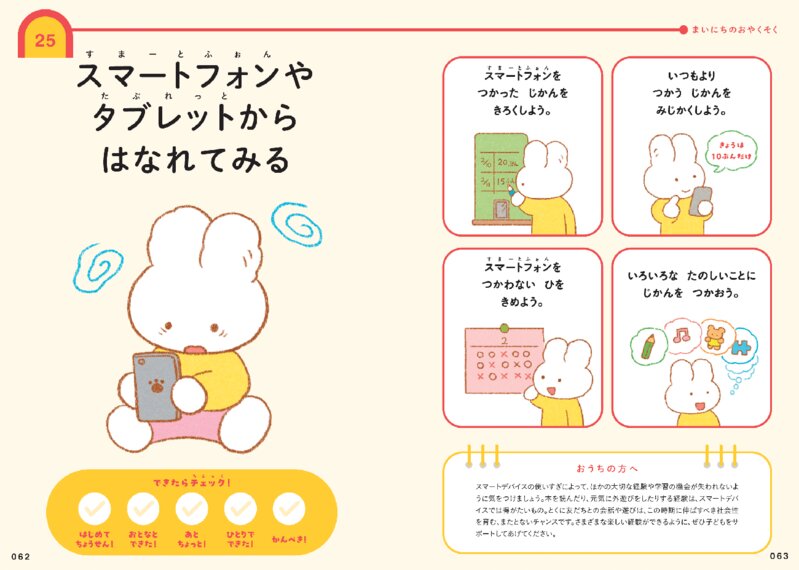「デジタル化で学力低下」は本当か? スウェーデンの“教育アナログ回帰”政策を読み解く

2024年秋以降、一部週刊誌やテレビ特集などで、スウェーデンやフィンランドでアナログ回帰政策が進むという報道があり、これをきっかけに多くのマスコミが教育のデジタル化の弊害を指摘するようになった。しかし学力の低下は、デジタル化が本当に主な要因なのだろうか。 【結果を見る】PISAの点数と、学校でのICT端末利用時間の関連 まず、スウェーデンがアナログ回帰に至った背景を調査整理する北欧教育研究会・教科書研究センターが主催した「教科書の未来を考える~北欧諸国の事例から~」が、客観的な調査結果などをまとめている。これを参考に、特に北欧と日本の教育制度の違いを意識しながら、歴史的な背景を整理してみたい。
スウェーデンでは、1990年代から学校教育にICTを積極的に導入し、デジタル化の歴史は長い。しかし、2022年10月の政権交代で、教育方針はデジタル重視からアナログ重視へと大きく転換した。 1990年代初頭、スウェーデンでは教育現場の自主性を高める運動が起こった。その結果、教科書検定制度が廃止され、教材の選定や授業方法は教員の裁量に委ねられるようになった。 デジタル化が進むにつれて、教材の質にばらつきが生じるようになった。 校長が予算削減のために、質が低い教科書や無料のデジタル教材を選ぶケースもあった。これにより学校間の教育水準に格差が生まれ、全体的な学力低下を招いたのではないかという指摘もある。 こうした状況を受け、2023年11月、スウェーデン政府は教科書の定義を「デジタル要素の有無に関わらず、印刷されたもの」とした。 内容が体系的に網羅された教科書を使うことで、学校間の格差を是正しようという意図によるものだ。コンテンツが多様化しやすいデジタル教材よりも、アウトプットが一つである紙の教科書を教育の軸に据えようとしたとも読める。 そんな中、政権交代により就任したエドホルム学校大臣は「デジタル化は実験だった」と述べた。生徒の読解力や教員の負担軽減などデジタル教材に代替できない利点があるとし、紙媒体教材への投資を増やす方針を示す。当時、学校教育庁が発表していたデジタル化に関する新戦略も差し止めた。教科書の購入補助金を増額するなど、紙媒体教材の普及を促す施策を進める。 「今回の政策に、スウェーデンの教育現場では賛否両論がある。子どものスマホ使いすぎやデジタル教材の効果を疑問視する声もある。一方、多くの教員は、教材の選択は教員が決めるべきことであり、上からの指示によって禁止されるべきではないと考える。デジタルと紙の両方が必要であり、適切な時に適切な教材を使えることが重要だという意見が多い」と信州大学大学院教育学研究科の林寛平准教授は指摘する。 スウェーデンの政策転換を受け、日本国内では「教育におけるICTの活用が学力低下の原因だ」という意見がメディアを通じて出ている。その多くは、2022年のPISA(OECD生徒の学習到達度調査)で、2018年の調査よりも大幅に点数を落としたことを引用する。しかし、これだけでICTが学力低下を引き起こしたと断言できるだろうか。 国内メディアがアナログ回帰の根拠としているPISAの点数を詳しく見る。家庭の経済状況別の読解力の点数を比較すると、経済状況が最も高い層では、2018年から2022年の間に3点しか低下していない。一方、最も低い層では26点も低下している。 この下位層の点数低下が、全体の平均点を押し下げている。 つまり、経済格差による学力格差の拡大が背景にあると考えられる。 また、2020年からのコロナ禍や2022年初頭からのロシア・ウクライナ戦争など、欧州の社会情勢を大きく揺るがす出来事が相次いだ。 これらの情勢悪化は、特に低所得層の生活に影響を与え、子どもの学習にも悪影響を及ぼしたと考えられる。 PISAの点数低下の背景には、このような社会情勢の影響も考慮する必要があり、ICTが学力低下の原因だと単純に結論づけることはできない。 OECDのPISA分析レポートでは、数学の点数とICT利用の関係について分析している。 学習に関係のない使い方、例えば学校でSNSを見ることや、芸能人やアニメに関する内容を検索することは、点数と負の相関があると指摘している。 スウェーデンに見られるように、欧米ではICT利用における課題として、子どもが授業に関係のないことにICTを使ってしまうことが問題視されている。 学習目的のICT利用は、一定の効果があることが示されている。端末を 1日あたり1~5時間利用している生徒は、全く利用していない生徒よりも20点以上点数が高いという結果が出ている。 一方で、5時間以上の利用では点数が低下する傾向があり、7時間以上の利用では全く利用していない生徒と同程度の点数となり、使いすぎはICT活用の効果を弱める可能性が示唆されている。 日本では、1日に5時間以上も授業でICT端末を活用している学校はごく一部であろう。文部科学省などの調査でも、週に何回活用しているかを調べている状況だ。ICTの学力への影響に関する議論は重要だが、このような日本の現状を考えると、バランスを取りながら適切にICT活用を進めることが、学力の維持・向上においては得策ではないか。 次回は、OECDへのインタビューを通して、国際的に見た教育ICTの動向を議論する。 (MM総研の中村成希、MM総研の正置彩花)
ITmedia ビジネスオンライン