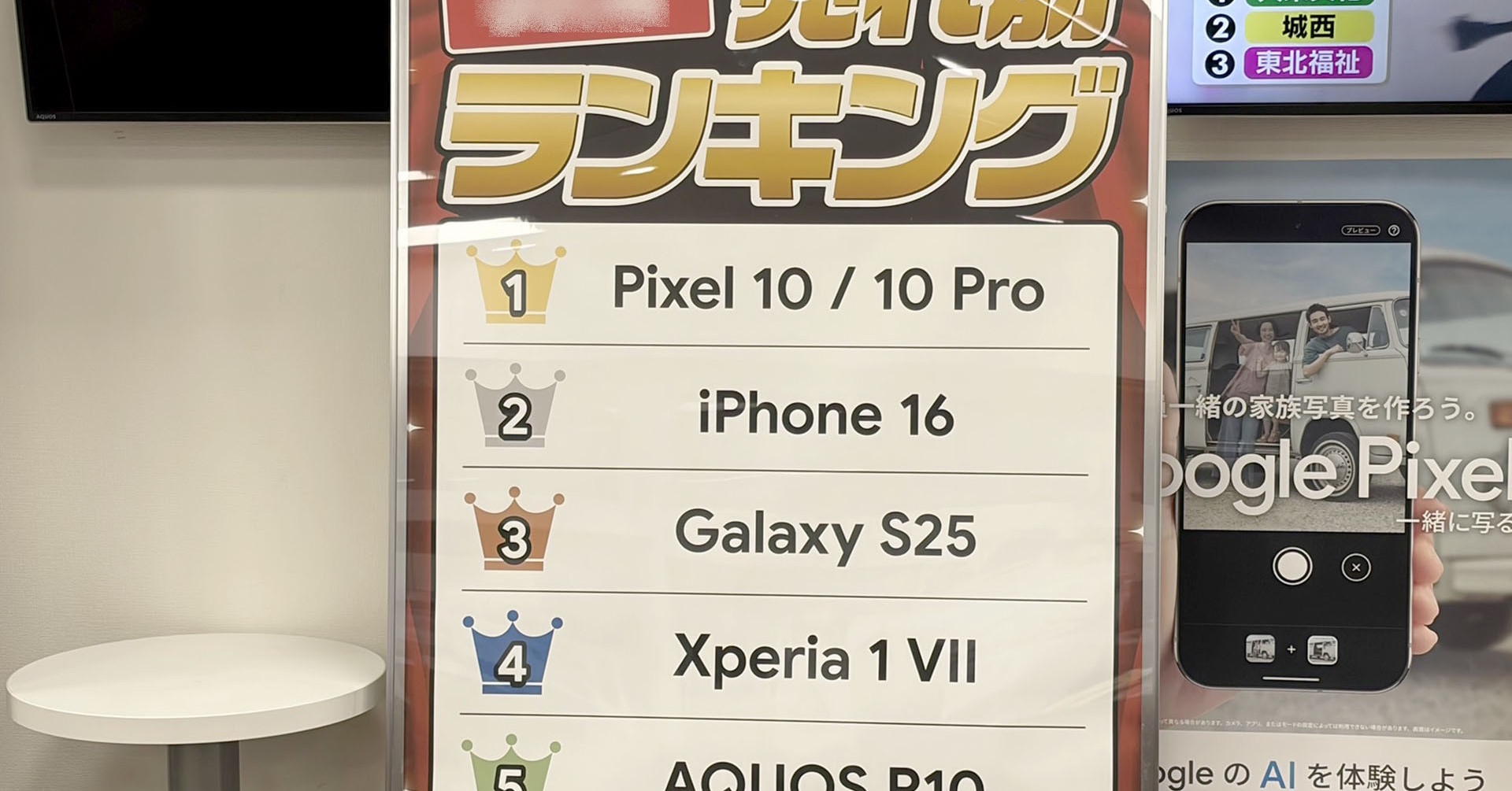ついに出合えた!タイピングを極めたくなる高級キーボード「Keychron Q15 MAX」沼にハマり中 #これ買ってよかった

最初に結論を書いておきましょう。
「Keychron Q15 MAX」を購入して環境を整えた私は、もう30年くらい不完全にしかタッチタイピングができなかったのに、1週間足らずで完全に習得することに成功しています。
信頼性の高い市販品であることも考慮すれば、これは本当に究極のキーボードだと言っていいと思います。
※タイピング速度に関しては、指が覚えるレベルまで相応の習熟期間が必要になります
なぜタッチタイピングは難しいのか
パームレストは私物。記事中に出てくる「Keychron Q15 MAX」は筆者がカスタマイズを施しているので、購入時のものとは異なっていますPhoto: 田中宏和ところで読者の皆さん、キーボードのタッチタイピング(キー印字を見ないでタイピング)はできていますか?
私が調べた限りだと、一般の人で2~3割、IT系やオフィスワーカーでも6~8割程度の人しか完全なタッチタイピングはできないようです。
キーボードに視線を落とすのが非効率的だとわかっていても、指が覚えている頻出文字列以外は、ついキーボードを見てしまう問題。実はそれ、決してユーザーの努力不足だと切り捨てていい話ではないのです。
さて、そもそもタッチタイピングが難しい原因は2つ。現在の標準配列であるロウスタッガード配列(物理的配列)と、QWERTY配列(論理的配列)にあります。
できるだけ手短に説明してみます。
ロウスタッガード(横ズレ)配列の問題点
Image: Wikipedia上の画像は、おなじみ日本語配列のフルキーボードを図示したものです。
もうすっかり見慣れていると思いますが、右側のテンキーやカーソルキーが上下左右整然と配列されているのと違い、アルファベット(ひらがな)キーは各列が左右にズレていて奇妙な配置になっていますね。
Image: Wikipediaこの配列は、コンピュータ登場以前のタイプライターに源流があります。
上の画像を見てのとおり、機械的に活字を用紙に押し付ける必要があったタイプライターには、上下段のキーがそれぞれズレた配列になっていないと、お互いのアームが干渉してしまうという問題がありました。
ロウスタッガード(横ズレ)配列は、せっかく身についている配列を変えたくないという当時のタイプライターユーザーの求めに応じてコンピュータ(ワープロ)にも積極的に採用されたために、現在に至るまでの間に圧倒的多数派を形成、実質的な標準配列となっているのです。
実際のところ、一般的なキーボードに奇妙なズレがあるのは、これだけの理由しかありません。
もちろん、ロウスタッガード配列に合理性がまったく無いということはないと思います。でも横ズレにメリットがあるのなら、テンキーも横方向にズラしておくべきだと思うのですが、そうはなっていませんね。
Photo: 田中宏和一方、「Keychron Q15 MAX」が採用しているオーソリニア(格子)配列では、分割されたSpaceバーの左右でサイズが違う点のみを除き、すべてのキーが格子状に整然と配置されています。
水色=人差し指 紫色=中指 赤色=薬指 緑色=小指Photo: 田中宏和上の比較図でもお分かりのとおり、オーソリニア配列は各キーの位置関係が直感的に把握しやすく、指の役割分担が明確になっています。このため、タッチタイピングを覚えるのにとても都合がいいレイアウトだと言えるのです。
Bキーを左右どちらの人差し指で押すか、などといった混乱を生むことはありません。
QWERTY配列の問題点
Photo: 田中宏和もうひとつ、アルファベットキーの左上から右に向かってQWERTYとキーが並んでいることからQWERTY配列と呼ばれる現在の標準的な論理配列にも、見逃せない問題点があります。
QWERTY配列の問題点が何かといえば、タイピング頻度の高いキーが押しにくい場所に配置されているところ。
日本語をローマ字入力する際、入力頻度が高いAキーを使いにくい左手小指で押さないといけないなど、細かい問題点はいくつもあげられますが、Enterキー、特にBackspaceキーに至っては、ホームポジションのまま小指を頑張って伸ばしても届かないレベルでキーが遠いのです。キートップがテカテカになるくらい頻繁に押すキーなのに……。
結果、ホームポジションから手を動かしてタイピングすることが常態化し、基本運指が崩壊、使用頻度が低い遠めのキーについては指の感覚だけでは配置を覚えられず、いつまで経っても目で見て確認するクセが抜けないというわけです。
ちなみに私は現在、タッチタイピングを覚えるのに大いに役立った大西配列という論理配列に移行していますが、「Keychron Q15 MAX」の紹介という本稿の趣旨から外れてしまうので詳細には触れていません。興味のある人はぜひチェックしてみてください。